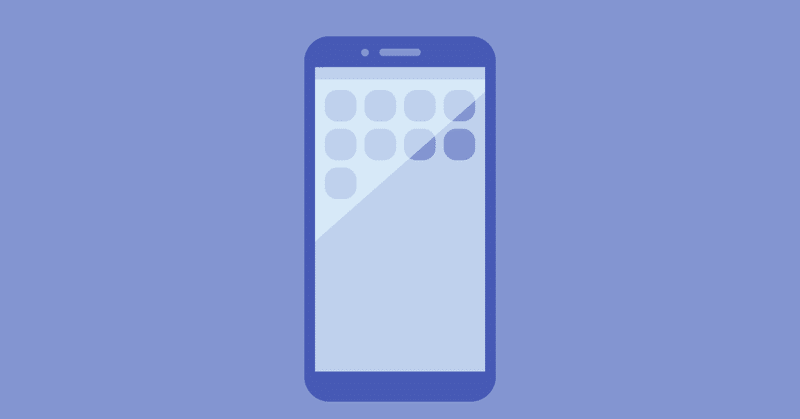
SNSで許せない女
「なあ、どうだった?」
「えっ?」
「だから式場のことだよ。あそこで決める?」
「う~ん……もう一か所だけ見てみていい?」
そう言うと、彼は「仕方ねーなあ」と言って肩を軽く抱き寄せた。
彼は高校の頃の先輩で、付き合い始めてもう7年になる。先月彼が私にプロポーズをして、私たちは式場の下見に来ていたのだった。
私は今、きっと幸せなんだと思う。
ただ、それはそれとして許せないことがある。
それはインターネットでやたらと女性を慰み物にする男たちのことだ。私はいわゆる「フェミニスト」ではないけれど、そういった風潮には抗議の声を上げていきたいと心に決めている。
そういった風潮を擁護する男たちはしきりに「表現には何の悪影響もない」と言うけれど、全くもってそんな筈はない。現に私は傷ついた。これは錯覚じゃない。かつて私自身が実際に被害を受けてきたし、その原因とこの風潮は論理的に繋がっている。私のような被害者を世の中からなくすため、女性を慰み物にする男たちは決して許してはならないのだ。
彼は明日から数日間の出張らしく、夕食を一緒に食べたら泊まらずに帰った。寝支度をしてスマホを見ると、SNSでは今日もまた嫌な男たちの投稿が流れてきていた。
私の投稿に対し馴れ馴れしいリプライを飛ばしてくる男を見て、今いる職場の上司のことを思い浮かべていた。彼は私が新人の頃から馴れ馴れしくて、そのくせ女だからといって見下している。同期の男は彼から仕事に役立つことを教わったと言っているのに、私には下らない世間話しかしていないのだ。
そんなことを考えているうちにだんだんと腹が立ってきて、私はリプライを3通ほど返し、そのアカウントをブロックした。
その夜、私は夢を見た。
夢の中で私はその上司をこれでもかと捲くし立て、上司はとても悔しそうな顔をしていた。
いい気味だ。
夢のおかげで翌日は良い気分だった。
「ナナミン、何か良いことあった?」
仲の良い同期の同僚にそんなことを言われてしまうほどだ。私はとっさに「別に」と答えたが、同僚がしつこく聞いてくるので彼と式場の下見に行ったことを話した。すると同僚は大げさに驚いて見せ「何が別にだよ~この幸せ者め~」と茶化してきた。
「そんなことより、今日竹田主任は?まさか休み?」
「えっ?」
同僚は顔に水でもかけられたかのように動きを止めて、驚いていた。 「竹田主任、まだ休職してるよね。戻ってくるんだっけ?」
「いや……えっ?休職?竹田主任が?」
同僚が何も答えなかったので、私は課長に確認をしにに行くと、あからさまに怪訝な顔をしながら教えてくれた。どうやら2か月前から休んでおり、心療内科に通っているらしい。
そんなバカな。私は金曜日にも彼から仕事を押し付けられていて――。
しかしPCとデスクを隅から隅まで探しても、その痕跡は見つからなかった。
仕事を終えて家に着いても、私はまだ夢でも見ているかのような気分だった。机の上には昨日の下見でもらったパンフレットや見積書が乗っている。
布団の中でスマホをつけて、SNSを眺めると、そこでは変わらず不届きな男たちが暴れていた。
異様に胸の大きい女子高生が新聞の広告に載せられていて、フェミニストの人たちがそのことに抗議していた。調べてみると、電車の中にその女子高生がいて周りの男たちが色めき立っている様子の漫画のコマがでてきて、私は怒りが込み上げてきた。許せなかった。
高校時代の嫌な記憶がよみがえる。私は朝の電車で痴漢をされたのだ。怖くて声を上げられず、相手の顔をまともに見ることもできなかった。悔しくて悔しくて、今でもその時の気持ちを鮮明に思い出せる。あの時少しでも大声が出せれば――。
突如、揺れる電車の音がリアルに聞こえた。走る景色が朝日に照らされている。後ろにいた男は確か――そう、眼鏡をかけた短髪の男だった。私は背後の手を掴んでひねり上げ、叫んだ。
――痴漢してんじゃねえよ!このクソ男!!
夢だった。
あの上司は翌日も、その翌日も休みだった。そしてそれ以外にも変化があった。始業前でも休み時間でも、私に話しかけてくるのは女の同僚だけだった。前はたまに話しかけてきた男の同僚が今は目を合わせようともしない。それもまた翌日になってもそのままだった。
私は何か大きな思い違いをしていたのか。大きなモヤモヤが晴れないまま、そんなふうにも思い始めてきた。
SNSでは論争がまだ続いていた。「大人が女子高生を性的な目で見ていいわけがない!」とフェミニストの方々がたくさんの声を上げている。それに対し、卑劣にも揚げ足取りや論点のすり替えをして嘲笑う男たちが目に飛び込んできて私はまたしても許せなかった。
その日の夜も私は夢を見た。
高校一年生の冬、私は2歳年上の先輩に告白した。先輩は少し照れながらもそれを受け入れてくれた。その前に既に泣きそうだった私は、返事を聞いて嬉しいのか安心したのか、とにかく顔を真っ赤にして泣いていた。その後先輩が遠方に進学することになって、引越しをするその最後の日も私は泣いていた。
それから数か月が経って夏休みになった。帰ってきていた先輩は、なんというか大人だった。髪を染めて服装も垢抜けていて、話し方も大人びてみえた。私は高校デビューするようなタイプでなかったから、この頃はまだ中学生と変わらないような恰好をしていたように思う。
再会したその日の夕方、先輩はホテルに行こうと言った。私は戸惑いながら先輩とタクシーに乗って、気が付けばラブホテルの部屋にいた。先輩は私を優しくベットに押し倒してキスをした。そして手をまさぐるように服の中に入れてきて―――、
――私はそれが許せなかった。
覆いかぶさる先輩を押し返し、カバンを持ってホテルを飛び出していた。理由もわからず涙が止まらなかった。
「ねえ、ナナミ聞いてる?」
翌日、同僚が少しぼんやりしていた私を呼んだ。
「な……何?」
「何?じゃないでしょ。竹田主任、昨日自殺未遂で病院に運ばれたんだよ?」
「じ……じさ……」
目がちかちかして脳が理解を拒む。
昨日帰った後、同僚はそのことを私にラインで知らせたらしい。私はSNSを見ていて確認していなかった。
「いや……なんで、それを私に?知らないんだけど……」
やっとの思いでそう言うと、同僚は眉をひそめ、侮蔑するような目で私を見た。
「流石に酷いんじゃない?だってナナミのせいでしょ。毎日毎日文句言ってさ、竹田主任だって上手じゃなかったかもしれないけど、なんとか私らをまとめようとしてたんだよ」
「待って待って!私が主任に?いつそんなことした?」
「いつって……アンタね……」
同僚の顔が侮蔑から怒りに変わっていた。私は耐えられずその場から逃げ出した。後ろで誰かが何か言っていたが聞き取れなかった。動悸と耳鳴りがしてどうにかなりそうだった。
気が付けば私は自分の部屋にいた。呆然としているうちに日が落ちていた。
どうしてこんなことになってしまったのか皆目見当もつかない。不安と恐怖で振えが止まらなかった。
ふと時計の日付を見て、今日は先輩が出張から帰ってくる日だと思い出した。
私は急いでスマホを取り出しラインを立ち上げるが―――
そこに先輩との会話の履歴は無かった。
あり得ない!なんで!悲鳴に近い声を上げながら履歴を遡り、やっとの思いでその名前を見つけた。最後の履歴は数年前だった。
私は部屋を飛び出した。先輩の家の前まで来て電話をかける。数コールの後先輩は応答した。
「急にどうしたんだよ?」
「今どこにいるの?もう帰ってきたの?」
「どこって、家だけど……」
「出てきてよ!会いたいの!」
「お前、まさか……」
外から私の声が聞こえたのか戸の奥から足音が近づいてきた。カギを開ける音がして、ドアが開く。
「何でお前がウチ知ってんだよ」
「リク助けて……おかしいんだよ何もかも……」
「おかしいのはお前だろ……。助けてって今更何言って――」
「リクトー?」
奥から女の声がした。
「ねえ誰?そのヒト?」
「……元カノだよ、一応。あっいや本当に全然連絡も取ってないんだってホラ!」
先輩が奥の女にスマホの画面を見せている。
「許せない……」
私は静かに、手に持った包丁を前に向けていた。
先輩は私に背を向けてヘラヘラと何かを言っている。女の方が何かに気が付いたような顔をしたが関係なかった。
私は――――
目を覚ますと、私は狭い部屋にいた。硬いベッドと机と椅子、トイレと窓が一つずつある。
独房だった。
フィクションです。流行りに乗じてやりました。
投げ銭方式なので下には何もありません。面白いと思ったら or 睡眠時間を削ってこんなの描いてたのを哀れに思ったら恵んでください。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
