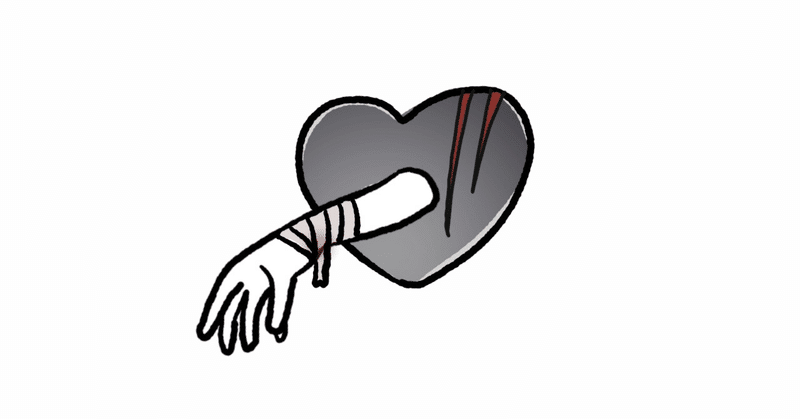
痛い生活
パシャッ
あの男はびっくりした顔をしていた。私は全力で走って逃げた。なぜ立ち向かえず、写真を撮るという中途半端なことしかできなかったのか。それは未だに分からない。
「高橋さん佐田大学なの?犯罪者の大学じゃん。」
コンビニのアルバイト先の主婦の太田さんに言われた。私は笑顔を浮かべて心の中で舌打ちした。
佐田大学は私の入学した大学だ。偏差値は55くらい。馬鹿ではないだろう。でも超エリートではない。私の第一志望は佐田大学ではなかった。悔しい気持ちで入学したが、楽しい大学生活を送って無念を晴らそうといた。
しかし、私の心はさらに打ち砕かれた。文系だからなのかクソ汚い校舎、教授達の学生を見下す態度、自信のない学生達。それらの要素に耐えながら私は必死に自分の居場所を探した。でも見つけられなかった。
挙げ句大学1年の秋。佐田大学の医学部の学生のレイプ事件が起きた。優秀な学生がなぜ?と世間では話題になった。中途半端な学力の立ち位置だからではないかというネットの記事を読んで私は悪態をついた。てめーまじ死ねと。
なぜ?なぜ?なぜ?登下校しながら思った。なんの誇りももてない。救いがない。私は生きている価値があるのか。「あの子死んだ魚の眼をしてる。」笑い声が聞こえて遠くなっていった。いっそ罪を犯してしまったら。こんなふうに退屈で惰性の日々を送るくらいなら激情で犯罪を犯す方がよいのではないか?私は半年でやめた服飾サークルで使ったビーズと布とリボンで飾りを作ってクソ汚い教室の掲示板にそっと貼った。貼ってすぐは悪戯をしてやったことに満足していた。でも教室はその飾りから魔法が広がって美しくなるなんてことはなかった。
あーあ、何やってんだろ。ただの痛い人じゃん。
大学二年になって社会学部の私は法学コースを選択した。友達は相変わらずできない。駅に一人で立っているようなそんな孤独感だった。これは地元の田舎の山に一人でいる時には感じたことのないひりひりと体に染みてくるような寂しさだった。大学はこんなに人がたくさんいるのにその誰とも関係がない。ただその場にいるだけの関係。田舎出身の私にはどうにも慣れなかった。
ああ誰かと一緒に犯罪がしたい。それができたら私の心は幾分軽くなる気がする。私が犯した犯罪が芸術になるのではないだろうか。なんの才能もない私がクリエーターになれるのは犯罪をした時だけなんじゃないだろうか。
刑事政策の授業で、犯罪者を責めるのではなく、犯罪者が再犯しないような仕組み作りが大切、という講義を受けた。つまり、犯罪者が増えない環境をみんなで作ろう、らしい。じゃあさ、私がこんな思いをしないために私に誰か才能をください。それでなくても私のために何かしてよ。私の心を癒やしてよ。そうだとしたら、私はこんな企て思いつくはずもないのに。でもね、みんな結局自分が一番かわいい。誰か辛い思いをしていたって自分の幸せと天秤にかけたら自分をとるでしょ。そもそも誰かの苦しみなんて気づこうともしないでしょ。
なんて自分は自分勝手なんだろうと思い、講義中一人でクスッと笑った。その時、階段教室の二列前の席、私から斜め右の席、カップル風の男女の男の方が振り返った。
一瞬、何かえぐりとられたような気持ちがした。その感覚がなぜなのか意識に上りかけた時、再び男が前を向き、私は気にしないことにした。
「ねえ、本当に君佐田大学なの?」
おまんじゅうみたいな顔のコンビニ店長田口に言われた。
「君、本当に使えないよね。」
アメリカンドッグとフランクフルトを間違えて客に渡してから永遠と怒られている。
おまんじゅうのくせに。お前に私の何が分かるんだよ。
「やっぱりさ、本当は君佐田大学じゃないんじゃないの?だって馬鹿すぎるよ。」
は?店長はバックヤードへと引っ込んだ。
「確かに私はダメなところがあるかもしれないです。だけど、私は血の滲むような努力をしてやっと佐田大学に入ったんです。」
コンビニの店中に聞こえる声で私は怒鳴った。今度こそ男になめられてたまるか。近くで立っていた太田さんはびっくりした顔をしていた。そんなことをするような女ではないと思われていたらしい。
おまんじゅう田口は小走りでやってきて、「高橋さん、お客さんいるでしょ。それに俺は優秀なバイトの佐田大生を見てきたわけ。言いたくもなるよ。」とぶちぶち言って、またバックヤードにひっこんだ。
「お前だって客の前でバイト怒ってんじゃん。」ぽそっと私は呟いた。
あの時とは違う。私は立ち向かえた。それが心の救いだった。
コンビニのアルバイトでは先輩の女子高校生がいた。彼女の名前は山口さん。見た瞬間気が強そうだと分かった。とにかく私のことが嫌いらしい。私がびびって週一しかアルバイトをせず、仕事も大してできないところがおおよその理由だろうと思った。
ある時、ガラの悪いヤンキーの男女が来店した。彼らは普通に買い物をしていったが、山口さんは彼らが退店した時、「あの子達、私のかわいいかわいい後輩ちゃんです。」と言った。生意気な高校生だと私は思った。しかし、彼女は仕事がよくできた。それは動かしようのない事実。反面、私はコミュ障で、気が利かないコンプレックスを勉強だけで埋めようとしていたかつてガリ勉だった女。そして命を削って勉強したにも関わらず、微妙な立ち位置の大学に入ったやつ。ただそれだけ。そんな自分が嫌でコンビニ人間にならなれると思ったのになれなかった。
何者でもない。朝起きるとその事実が私に突きつけられる。鳥の鳴き声が全世界からの私への攻撃に聞こえた。全身の痛みで起きることは稀ではない。
その日も背中に矢がたくさん刺さった夢をみて、痛みとともに目を覚ました。
生きていくのはしんどい。何一つ不自由なく育てられ、四年制大学にも入れ、アルバイトだってわざわざしなくても贅沢をしなければ生きていける。だけど辛い。それはきっと他人によって攻撃されているのではなく、自分で自分を傷つけようとしているのだ。なぜこんなに自分が嫌いなのか自分でも分からない。
部屋の壁に貼ってある時間割表を見た。時間割は十月からの後期のものに昨日変えた。正直大学の勉強は辛い。私は要領が悪いから。だからいつも講義に行く時は戦いに行く気持ちで受けている。大して講義が多いわけではないけれど、全力で勉強しないとついていけない。想像していた大学生活とは全然違った。
「刑事政策の演習、難しくないといいな。」
私は呟いた。
演習の部屋は校舎の二階にある狭い部屋だった。一番先に私が来ていた。
席は四角く囲んで配置されていた。私はホワイトボードに近い、四角の四隅の席に座った。
今日の私のコーディネートはサイケデリックな柄がプリントされたスウェットに黒いスキニー。アイシャドウはオレンジピンクの単色塗り。耳には大きなフープピアス。主にストリート系やモード系を意識したコーディネートを組んでいる。なるべく派手な格好をしているので、今朝大学に登校した時も通りすがりの男子大学生から「あの格好はないわ。」と言われた。そういうことを通りすがりに言われると傷つきもするが、少し思惑通りになって満足した気持ちにもなる。
演習の講義が始まるまで席でスマホを見ていたら、部屋の扉が開いた。どこにでもいそうな大人しそうな男子大学生が入ってきた。
私の背中に寒気が走った。階段教室で、以前目が合った男だった。もしかしてと思って大学受験の時の写真をスマホで探した。
あいつだ。
あの時のままの黒縁眼鏡。短髪でも長髪でもない髪型。青白い顔。やや細く、中くらいの背丈の体。
私は手が震えた。そして憎しみを感じた。
あいつが私をずっと苦しめたんだ。
私は高校3年生の受験の時、痴漢に遭った。
受験の時、母と一緒に大学の最寄り駅から2駅離れた駅の近くのホテルに泊まっていた。
一人で集中したいからと受験会場までの電車は一人で乗ることにした。英語の単語帳を見ていたら尻を誰かが触っているのに気づいた。寒気がした。「痴漢です。」と声を出すことができなかった。だから私は単語帳の一点を見つめたまま固まっていた。
私は痴漢しても騒がないやつだと思われたんだ。その思いはずっとこびりついて離れなかった。それ以来派手な服が趣味になった。
受験会場の最寄り駅になって降りた時、私は振り返って痴漢した男の写真を撮った。
それっきりだった。ただそれだけ。なんてことない。どこにでもある話。痴漢されるなんてことは。こんななんてことないこと、レイプされたわけでもないことがすごく悲しかった。
親にも高校のただ一人の友達にも話せなかった。
「なんだ、そんなこと?」
「そんなの気にしなくてもいいよ。」
「忘れなよ。」
「なんで、抵抗しなかったの?」
そんな反応をされたら自分が壊れてしまいそうだったから。
痴漢男は何気なく私の向かい側に座った。
男は林裕太と自己紹介で名乗った。その日から何回か刑事政策の演習を受けた。
刑事政策の演習は難しかった。難しいと感じると気が紛れるのか、林に対する怒りを束の間忘れた。でも完全に忘れることはできなかった。
もしかしてこれは復讐するチャンスなんじゃないだろうか。私の美しい犯罪にあいつを加担させてやればいいのではないか。
具体的には林を恐喝するということ。
しかし、なかなかきっかけがつかめなかった。
ある日、演習で飲み会をする話が出た。私も参加することにした。
飲み会には林も参加した。
林は全く悪目立ちしない男だった。そこそこ優秀でそこそこ喋り、とにかく全てが普通で、誰でも次の日には忘れてしまいそうな男だった。そして、茶髪ピアスが「林君、いつも一緒にいる子って彼女だよね?」と聞いた時、「そうだよ。」と答えていた。彼女ができるような男なのになぜこいつは痴漢なんかしたんだ、と一瞬頭をよぎったがすぐ忘れた。
私は静かにレモンサワーを飲んでいた。飲み会がだれてきた時、林は「僕、ちょっと用事あるから先に帰る。」と言って店を出て行った。
私は飲んでいたから気が大きくなっていた。チャンスだと思い、私もお金を置いて、店を出た。
「林君。」
林は振り向いた。
「あんたさ、痴漢してたよね。」
「え?」
林はさーっと青ざめていた。
「私受験生の時、あんたから痴漢されたんだよね。そのことマジで恨んでるから。」
林は懇願した。
「お願い。俺が痴漢してたなんてこと誰にも話さないで。なんでもするから。」
私はサディスティックな気持ちになった。占めた。
「私の言うこと聞いてくれたら黙っといてあげる。」私は笑っていた。
退屈で惰性な日々がその日から変わった。
私は毎月林から林のバイト代をもらった。週一のコンビニバイトよりはるかに多い金額だった。コンビニバイトはその収入があるからやめた。私の受けている講義全ての過去問を林からもらった。
私は自由な時間と潤沢な資金を手に入れた。
モード系やストリート系の服を値段を気にせず買うようになり、都会の美術館に足繁く通うようになった。旅行に行った。緑溢れる古都に行った。緑の渦の中に私がいる。自分が生きている実感がした。生きている、生きている、私は生きているんだと叫びたくなった。
幸せだった。
「あんた、まだ痴漢やってんの?」文字が細かすぎて写真では判別できない過去問をもらって図書館のコピー機でコピーしているときに林に言った。
「高橋さんに脅されてからは一回もやってないよ。ちょっと高橋さんに感謝してる。結構要求が辛いけど。」
「は?私に感謝?」
「僕、浪人して佐田大入ったけど、浪人時代のやるせない気持ちをどこに向けたらいいか分からなかった。ある日電車に乗ってた時、満員電車だったからたまたま女の人のお尻に手が当たってその時体に電流が流れた。何か女の人に抗議されるかと思ったけど、別にその人も普通で。なんだ、こういうことしてもいいんだ、と思って。痴漢が止められなくなった。痴漢せずに生きていけないと思うようになって。高橋さんを痴漢したのははっきり覚えてないけど、そういえば、受験の緊張を紛らわすために痴漢をしたような気がする。彼女できてからも別に孤独感とかやるせない気持ちとか消えるわけじゃなかったから、痴漢やめられなくてさ。高橋さんが脅してくれてやっと一時的にだけど止められたってわけ。」
私は涙が出てきた。
「うるさい。あんたなんかの役に立ってたまるか。何それ、あんたが辛かったって?孤独だったって?そんなの知らない。あんたは悪者なの。」
「高橋さんは悪者じゃないの?僕と同じだよ。自分の鬱憤のはけ口を犯罪に使ってるだけ。」
その通りだった。私は被害者だったが、もう加害者だった。
「・・・・。」
林は遠くを見て何回か瞬きをした。
「誰かにさ、こういう痴漢してた自分をどこかで知ってほしかった。こんだけ苦しかったって誰かに分かってほしかった。だから、高橋さんに知ってもらえてよかった。」
林と私はその場に佇んでいた。換気をするために司書が窓を開けていた。そして窓から風が吹いてきて私の頬をなでた。それは優しく、少し冷たく肌に染みて。
「もういい。もう脅したりしないから。許してないけど、共感はした。じゃあ彼女と元気でな。」
私は小走りに駆けていった。
図書館から出ると夕方の優しい光が私を包んだ。孤独で辛い誰かの救いになることが私のできることだ、と思った。それが私のできる償い、私を救う方法だと思った。
だけど、歩くと、外は寒くて校舎を見上げると汚かった。何かが変わった。でも、大きくは変われてない。私は情けない自分がつくづく嫌になった。
私は相変わらず自信がもてなかった。不安と後悔は毎日あり、それを取り除こうと瞑想をしたり、運動をしたり、ヨガに行ったり、カウンセリングを受けたりした。確かにそれらをしているときは気分がマシになりはした。でも私は根本的には孤独で自信がなく、不安で日々は退屈で惰性だった。林から金をもらわなくなったので、今度はピッキングのバイトを始めた。そこでも使えないやつと怒鳴られたりした。
大学三年生になって服が少し地味になった。西洋経済史の授業で初めて友達が出きた。
由香ちゃんだった。由香ちゃんは巡(めぐり)という私の下の名前を少し略してめぐちゃんと呼んでくれた。
由香ちゃんの顔は日本政治史の授業で見たことがあり、なぜか印象に残っていた。いろんな人と大学で出会い、うまく関われないことに絶望してからは友達を作るのは諦めていたが、西洋経済史の授業で由香ちゃんを見た時、何も考えずに彼女に声をかけていた。
「何年生ですか?」
由香ちゃんは特に驚きもせず、極めてナチュラルに答えてくれた。そして、二言、三言会話した後に由香ちゃんの後輩が由香ちゃんの隣の席に座り、私と由香ちゃんの会話は途切れた。
もう、それっきりだと思っていた。何日か経って大学の書店で本を眺めていると、由香ちゃんが、「こんにちは。西洋経済史受けてるよね。名前なんていうの?私は由香っていいます。」と言った。
「高橋巡っていいます。呼び方はなんでもいいよ。」
「巡って珍しい名前だね。よろしくね。めぐちゃん。」
由香ちゃんは面白い子だった。ある時、ピカソの絵の「人生」の画像を二人で見た。裸で寄り添っている男女の男の方が、服を着て赤ちゃんを抱えている女性を指さしている絵だったのだが、私が「これなんて言ってるのかな。」と言うと由香ちゃんは「お前がヤらせてくれねーから浮気したんだよ、って言ってんじゃない。」と言い爆笑の渦が起きた。
由香ちゃんと制服で遊園地に行ったりもした。遊園地の近くに制服をレンタルできる店があったので、そこで二人で一人5千円で制服をレンタルした。写真をたくさん撮りまくった。私が言い出しっぺだったのだが、制服を着ている最中は落ち着かなくて、楽しいけれど、早く私服に着替えたいような複雑な気分だった。そのことは由香ちゃんには言わなかったけれど。私はその制服遊園地が楽しすぎて、自分が死ぬ時、走馬灯のように馬鹿みたいに制服着て遊園地行っていたことを思い出すだろうと思った。私は由香ちゃんと出会えてよかったと思った。と同時に由香ちゃんには私の秘密を知られてはいけないと思った。由香ちゃんを私の人生から失いたくなかった。
いつまでも遊んでいたかったけれど、私達は大学三年生だったので、二人ともぽつぽつとインターンに行き始めた。
「本当さあ、なんで就活なんてしなくちゃいけないんだろうね。就活なんて奴隷になりますって言いにいくようなもんじゃん。ほんといや。」
由香ちゃんは言った。
「奴隷って・・・。」私はケラケラ笑った。
「本当由香ちゃんて面白いよね。」
「めぐちゃんの前だとなんだか思いつくんだよね。面白いこと。めぐちゃんと西洋経済史で出会えたこと本当によかったと思ってるからね。」
由香ちゃんのことが大好きで、佐田大学に入ってよかったと少し思えた。けれど、由香ちゃんと楽しい日々を過ごせば過ごす程、由香ちゃんに自分の過ちを知ってもらって許してもらいたいと思い、それはできないと苦しむようになった。そして、日々を過ごしていくなかで、自分の無力感、情けなさからは逃げられなかった。突然不安になった。由香ちゃんと出会ってからも、むしろ出会ってから消えてしまいたくなるようになった。
「ポプラの会」のボランテイアが大学の掲示板に貼り出された。非行に走ってしまった少年とその親達と、一緒に街頭清掃をしたり、花を植えたりするボランティアだった。私は林のことを思い出した。傷ついている誰かに寄り添えば、自分を癒やすことにもつながるのではないか、そう思った。それに就活の自己PRにも使えるのではないかと思って少し迷ったが参加してみることにした。
ポプラの会では最初に練習会があった。非行をしてしまった少年達を責めたりするのではなく、寄り添えるような会話の仕方の練習をした。その練習会には学生と初老の男女達が参加していた。自己紹介では肩書きを言わない約束になっていたが、一人の初老の男性は有名新聞社に勤めていたと自己紹介で発言し、周りから顰蹙を買っていた。
その後、私は街頭清掃に参加した。少年達とその親達は真剣にゴミを拾っていた。その姿に親子が必死で社会とつながろうとしていることを感じた。少年の一人と話をしたが、何か犯罪をしたようには思えなかった。漫画にハマっていると嬉しそうに話していた。犯罪者が自分と全く関係ないなんて思うのはおかしいのかもしれない。そういう私がすでに犯罪をしているのだが。
すみれさんは四十代の主婦でポプラの会で知り合った。穏やかで優しい人だった。会ったのは練習会と街頭清掃の二回きりだった。私は勝手に足が向かなくなり、ポプラの会には練習会と街頭清掃の二回しか参加しなかったのだ。なぜなのかは自分でも分からないが、あまりに内容が濃く、それ以上はお腹いっぱいだったのかもしれない。その後の私の人生ですみれさんと会うことは二度とないだろう。けれど、私は彼女のことを一生忘れない気がした。
すみれさんは一人だけ、若くも老いてもいないボランティアで、少し目立っていた。
「今日のお月様きれいだね。」
最初そう話しかけてくれた。
「そうですね。」
私は言った。確かに綺麗だった。煌々と輝いてはいないがひっそりと見守るように月が空にあった。私はこの人とは気が合う気がすると思った。
街頭清掃が終わった時、すみれさんは私をお茶に誘った。すみれさんは自分の話をしてくれた。
すみれさんは中学生の一人息子がいた。息子さんは同級生からいじめられていて、いじめで暴力を受けて殺された。息子さんはすみれさんの人生からいなくなった。すみれさんは息子さんくらいの少年が歩いていると、つい目で追ってしまう。すみれさんは息子さんがいじめられているのになんとなく気づいていた。けれど、自分ではどうしてあげることもできなかった。いじめっ子達を恨んで殺したくなったりもした。憎い、憎い、地獄に落ちれば良いのに、そんなことを毎日すみれさんは考えていた。それを考えていることにも自己嫌悪を感じた。また、自分が何もできなかったせいで息子さんを殺してしまったのではないかと後悔の念に駆られた。生きるのが辛くて、絶望していた。
当てもなく、夜の街をさまよっていたら、「ポプラの会」が街頭清掃をしているのを見た。参加者に声をかけると、詳しくは教えてくれなかったが街頭清掃をするボランティアだと教えてくれた。それがポプラの会で、非行をした少年とボランティアをする会だと後から知った。
気づいたらすみれさんはポプラの会でボランティアをするようになった。ただ何も考えず、非行少年達とボランティア活動をする。生きているとか死んでいるとかいちいち考えずにただその活動をしていると悲しみが薄らいでいった。だから、自分は死ぬまでこの活動を続けると思う、すみれさんはそう言った。
私は少し言葉を失った。自分は恵まれているのにも関わらず、どうしてこんなに生きるのが辛いのか。どうして普通に生きていたすみれさんが不幸の底に落とされてしまったのか。そしてすみれさんが今こうして生き延びているのはなぜなのか。もしかしたら、何か生きるヒントをくれるのではないのか。
「私、恵まれているのにとても生きるのが辛いんです。すみれさんみたいにとても悲しいことがあったわけでもないけれど、辛いんです。普通にしていても辛いけれど、誰にも言えない秘密があってそのことを隠して生きていくのも辛いんです。すみれさんからしたら私なんて馬鹿みたいですよね。図々しいけれど何か私に教えてくれませんか。」
すみれさんは微笑んだ。
「辛いのはどうしようもないよ。」
「え?」
「辛い気持ちを、どうにかしようともがくと、余計苦しくなっちゃうよ。だから辛いのは当たり前のことだと思って目の前の行動に集中する。それだけだね。」
時計は9時になっていた。
しばらくすみれさんと何か話していたような気もするし、黙っていたような気もするが、どうだったかはよく覚えていない。私達は解散した。たまたま偶然出会って共鳴しあっていき、そして離れていく。それが人生なのかもしれない。
私はすみれさんの言った通り、辛いのをなくそうとするのを諦めた。就活の不安、自分の理想通りの大学に入れなかった辛さ、要領
が悪くて何かと苦労する辛さ、恐喝をしていたことがバレて信頼をなくす不安、それらをなくすことを全部諦めた。そして、自分がだめであることを受け入れた。私は私以上にも私以下にもならない。それが私だと思うことにした。それらを実行したからと言って、世界が変わるなんてことはない。むしろ辛さは当たり前にある。
ただ、ある日銀杏の木が卵色になっていた時、ああ季節が秋になったんだ、とぽつんと思えた。少し、生きるのが楽になった気がした。
私は大学3年の春休みに遅い就職活動を始めた。
就職活動は孤独だった。由香ちゃんともしばらく連絡は取り合わなかった。大学の就活講座にはほぼ全部参加した。身だしなみを教えてもらう講座に参加し、使われていたメイク道具を自分のメイク道具があったのにも関わらず買い足した。自己分析講座で、自分を棚卸ししてみたりもしたが、自分のことなんてどうしてそんな簡単に分かるのだろう。自分の長所なんて全く分からない。長所なんてないのではないか。自分のやりたいことだって、孤独で辛い誰かを救う、それができる会社なんてどこにあるのだろう。そんなことを思いながら受講した。グループディスカッションの講座では、会話のテンポについていけず、今どういう話の流れになっているか全く分からなかった。辛いのは当たり前、辛いのは当たり前、手が震える中、自分に言い聞かせ、私は痛むお腹をなでた。集団模擬面接の講座で、緊張しすぎて、文字が書けなくなった。自分が意図した方向にペンを動かすことができないのだ。これで、もうだめだ、と思い、実家に少しだけ帰省することにした。
帰省すると、子供部屋が待っていた。ここで私は大きくなっていったのだと帰省するたびに思う。
実家で両親に会うと、母は頭をなでてくれ、父は私にピースした。
両親が仕事に言っている間、居間にまだ残されている炬燵に入っていたが、余計な思考がぐるぐる渦巻きだした。このままどこからも内定をもらえないんじゃないだろうか、そしたらどうしよう、死んでしまおうか、そんなことを考え出して、すみれさんを思い出した。考えるのはなくそうとせず、気持ちをもったまま、何か行動をしよう、体を動かす、そうだ、散歩をしようと思った。
ジャージに着替え、日焼け止めを塗って帽子を被り、家を出た。
天気がよかった。近所のスーパーを横切って、河原まで歩いた。孤独だった。孤独だ、でもみんな孤独だ。だから私は孤独だけどみんなと同じで孤独だ、だから孤独じゃない、歩いているとそんな気持ちが湧いてきた。堤防につくと、大きな川が流れていた。鳥がゆっくりと旋回して、上へ上へと上がっていた。こんな風に私の人生も上がっていけたらいい、そう思った。実際は一歩進んで二歩下がることの方が多くて今もそうだけれど、一歩進んでいたことには意味があるかもしれない。だってただ二歩下がっているよりは前に進んでいるから。
河原の向こうには緑の壁、山脈があり、いつか自分はこんな山だらけのところから、山を越えて都会で暮らすんだと思っていたことを思い出した。田舎で人間とうまく関われない自分が都会で人間とうまく関われるようにはならないということを今になって悟ったけれど。
歩いているうちに未来を生きたいと思うようになってきた。一時間程歩いて家に帰った。その後はずっと眠っていた。
起きて、母の手作りのクッキーを食べていると父が母より先に帰ってきた。
「おかえり。」
「おう、ただいまめぐり元気か?」
「元気ない。」少し構ってもらいたかったので、私はそう答えた。
「就活大変かもしれないけどな、とりあえず一日を終わらせればいいんだ、それで、また次の日も一日終わらせる。その繰り返しだ。がんばれよ。・・・いや、がんばるな、もう十分がんばってるからな、普通に過ごせ、そしたらそのうち光が見えてくるぞ。」
父は私にグッドラックの指をした。
私はまた住んでいたアパートに戻った。先が見えないのは変わらないけれど、実家に戻って少しやる気が戻った。内定もどこか一つはもらえるんじゃないか、そう思った。
エントリーシートを書くのは大変だった。自分をよく見せるようにプレゼンするのはしんどい。何度も大学の就職カウンセラーに添削してもらった。
履歴書の字をほんの少し歪んで書いてしまった時は、就職支援課の人にこれは大丈夫か確認した。
面接も地獄だった。
受けた会社と一文字違いの会社のホームページを見て志望動機を言ってしまい、落ちたことがあった。自分は本当に馬鹿なんじゃないかと思った。
私は7月になって初めて内定がもらえた。でも志望度は低いSEの仕事で、就活はまだ続けることにした。もうその頃には由香ちゃんが、就活が終わったと連絡をくれた。とても焦った。
悪戦苦闘しているうちに時間が勝手に過ぎていき、私は10月になってやっと納得のいく会社から内定をもらい、就職活動を終えることができた。輸送貨物の検査をする会社の経理だった。嬉しかった。
由香ちゃんと居酒屋でお祝いの会をした。
「めぐちゃんよかったね。」
「由香ちゃんもおめでとう。」
私達は彼氏欲しいだの、脱毛したいだの、お金が欲しいだの楽しくお話していた。
私は浮かれてお酒を飲みすぎていた。
「あのさあ、私痴漢してきた男脅してお金もらってた時があったんだよね。」
「え?」
由香ちゃんの目が尖った。私は一瞬で酔いが覚めた。
「私、そんな人と友達でいたくない。」由香ちゃんは毅然として言って、お金を置いて居酒屋を出て行った。
私は少しの間何が起きたか自覚できず、混乱していたが、急いで会計を済ませ、由香ちゃんを追いかけた。
由香ちゃんは早足で外を歩いていた。
「待って。」
「もう話したくない。あっち行ってよ。」
由香ちゃんに冷たくあしらわれた。
私はまた独りぼっちになってしまった。寂しさを感じたがどこか冷静だった。どうにもならないことをなんとかしようと悩んでも無駄だ。できることは何か考えて淡々と行動していこう。
私ができることといえば残っている大学の単位をとり、日々生活して生きていくことだ。決して死ぬことではない。由香ちゃんがいつか許してくれるかは由香ちゃんの課題であって、自分がなんとかできることではない。ただ淡々と日々を過ごす。そして由香ちゃんと大学で会ったら、挨拶をする。それだけだ。あわよくば仲直りしたいところだが、無理かもしれない。そうなったらそうなったで諦めるしかない。
私は朝6時に起きて散歩をし、鯖と味噌汁と米の朝ご飯を食べ、大学でわずかに必要な単位の講義に加え、暇を埋めるためにそれ以外の講義にも出席し、あとはバイトをしたり、図書館で読書をするような生活を続けた。そして一度由香ちゃんと大学ですれ違った時、「こんにちは。」と言ってみたりした。もちろん無視されたが。
余分に受けている教養展開の講義で「アートと心のケア」という講義があった。アートを通じて精神疾患を抱えた患者を癒やす活動についての講義だった。私は絵を描くのが好きだったことを思い出した。しかし同時に高校の美術の授業で周りと比べて自分が一番下手で、近くに座っていた女子二人から馬鹿にされて以来絵を描くのが嫌いになったことも思い出した。
今更絵を描いても意味ないかも。しかし、やはり私の心のどこかに絵が引っかかっていた。もう一度描いてみようかな、そう思って1ヶ月が経ったころ、林からラインが来た。
「痴漢またやってしまって迷惑防止条例違反で捕まってしまいました。」既読
「あんたなんで刑務所にいないの?」既読
「在宅事件になったから。」
私はしばらく考えて、ラインのメッセージを送った。
「一度会わない?林の話聞きたい。」既読
林と、大学の近くのカフェで待ち合わせした。
林は髭が伸び放題で服は黒ずくめだった。痩せ型の身体がさらにガリガリに痩せていた。
「彼女にもばれちゃってさ、別れることになった。食欲もなくて、最近食べてない。もう人生終わりだ。」
「終わってないよ。林はまだ生きてるしまだ若い。できることをやってけよ。そんな甘ったれたこと言うなよ。」
「ははは。」
林は力なく笑った。
「私、林にひどいことした。だから私もあんたと同罪。でもできることしてくって決めた。私、あんたのために絵を描く。」
え?今私は何を言ったのだろうか。なぜ、絵を描くのだろうか。
「絵を描く?」
「林がこれからできることをして生きていきたくなるような絵を描く。」
この言葉も口から勝手に出てきた。まるで、操られているかのようにするすると。
「ありがとう、楽しみにしてる。」
林は弱々しい笑顔で言った。
「あ、そういえば、脅してもらってたお金、ちゃんと返すから。」
「利子もつけてよね。」
「なんだ、図々しいな、そんだけ図々しければ生きていけるよ。」
私達は笑った。
私は公園で林をモデルにデッサンをした。普通よりは上手いが、パーツの比率が崩れていた。こんなので、林の人生の役に立つのか?自信はなかったが、一生懸命描いた。大体はそのままで描いたが、一つだけ変えたのは、林の表情を暗い顔から笑顔にしたことだ。ちょうど、カフェの図々しい話で笑った時の顔に変えた。
林は絵を見て、喜んでくれた。
「ありがとう、ちょっと下手だけど、僕ってまだ笑えるって思い出せた。少し勇気もらった。」
「下手とは余計な。ま、本当だけどさ。林、お前痴漢だったってこと忘れんなよ。」
「高橋さん僕を元気づけたいのか奈落に落としたいのかよく分からないね。」
「人間てのはよく分からないんだよ。善人でもあり、悪人でもある。それが人間だよ。」
偉そうに言ってみた。
林は略式罰金で済んだそうだ。大学側にも特にバレなかったようで、除籍にはならなかった。それでも林はこのままではいけないと思ったようで、クリニックで痴漢依存をケアすることにしたそうだ。認知行動療法や同じ痴漢依存者同士のミーティング、芸術行動療法などの治療を受けているらしい。林からカフェで報告を受けた。
治療を受けているうちに少しの安心感と再犯の危機感を感じるようになったらしい。林は芸術行動療法でギターを弾いた時、気持ちが少し安らぐ感じがあったそうだ。
それを聞いて私は軽い気持ちでこう言った。
「林さ、音楽やればいいじゃん。私、絵で誰かを救おうと思ってるけど、林は音楽で人を救って償いなよ。」
「あー、いいかも。なんかちょっとわくわくしてきた。」
林は嬉しそうに言った。
私は絵を描くことを林はギターを弾くことを始めた。お互い進捗を報告しあった。私も林もお金をケチって独学でがんばっていた。
そして気づいたらもう大学を卒業する頃になった。けれど、新型コロナウイルスがもう流行っていて、卒業式は行われなかった。
卒業証書を見て私は自分の4年間を思った。痛い4年間だった。痛すぎて目もあてられない。それだけ痛いのが、生きた証拠のような気がした。
もし佐田大学に入らなかったら、私はどうなっていたのだろうか。もっといい大学に入っていたら、人の痛みなんて分からなかったかもしれない。もっと馬鹿な大学に入っていたらくすぶりすぎておかしくなってしまったかもしれない。いや、もっといい大学に入っていたらただ単に素直に幸せに生きていたかもしれない。もっと馬鹿な大学に入っていたら毎日馬鹿みたいに遊んで悩みなんかなかったかもしれない。たらればしてみても答えなんてでない。
ただ一つ言えること、佐田大学に入ったら今の私になった。それは佐田大学に入ったからかどうかではなく、私がどう動いたかである。大学で私は変わらない。私が大学の意味づけを変える。それだけだ。
大学4年の春休み、私はひたすら絵を描いた。ペットボトルの絵、好きなバンドのバンドメンバーの肖像画、青空の絵、佐田大学のクソ汚い校舎の絵、夕焼けの絵、星空の絵、小学校の頃一番の友達だった女の子の絵、虹の絵、暇さえあれば描いていた。それをSNSに投稿した。いいねはなかなかつかない。
林はギターを毎日弾いていた。たまにラインでギターの音声を送ってきた。それは心がにじみ出たような音色だった。最初は下手だったけれど、だんだん林のギターの音声は磨きがかかっていった。
林のことは完全に許してはいなかった。たまに殴りたくなる。でも友達がいるのは心強い。林とは仲が良くなったが、恋人には絶対にしたくなかった。なぜなら気持ち悪いから。自分を性的なモノとしてみた人間なんかとキスしたり、セックスなんてしたくない。そもそも愛せない。
「林、あんたのこと私全く恋愛対象じゃねーからな。」
カフェで話している時、林のふとした表情が、自分が受験生だった時の気持ちをフラッシュバックさせたので、私は怒りを覚え、そう口走った。
「大丈夫、僕も人のこと脅してくるような女性は恋愛対象じゃないから。」
「ふん、生意気な。」
しばらく険悪な雰囲気が立ちこめたが、すぐにお互いの芸術の趣味、絵と音楽の話になった。楽しいとか、いつか成り上がれたらとか、夢想を語った。それは夢だから楽しかった。坂の上の虹を渡りに行こうと子供になって誓いあっているように。そして、今まで話してなかったお互いの友達の話になった。
「林は友達いるの?まあ、彼女いたくらいだからいるよな。」
「まあそこそこいるよ。その時々で3人くらい。」
「その時々って何?そんなにころころ変わるの。」
「そりゃあそうだよ。お互い変わっていくでしょ。環境も、自分自身も。いつも同じじゃない。そのうち、合わなくなって疎遠になっていく。でも次の出会いが必ずある。」
「寂しくないの?」
「少し寂しい時もあるけど、居場所なんていつだって流動的だろ。仕方ないよ。それに縁があったら、疎遠になった人とまた繋がるかもしれない。過去や未来じゃなくて、今が一番大切だよ。今の友達と繋がっていればそれで十分。」
「林って痴漢してたわりに大人なんだね。」
「痴漢痴漢うるさいな、傷つくから、あんまり冗談でも言われたくないよ。」
「ごめん。でも言う。」
「言うのかよ。まあ仕方ないな。」
「私、自分の分身、それ以上に大好きな女の子の友達が大学にいたんだけどさ、酔っ払った時にその子に林を恐喝してたこと喋っちゃって、絶交されちゃったんだよね。まあどうしようもないから仲直りするの半ば諦めてるけど、たまに楽しかった思い出を思い出すんだよね。」
林は腕を組んで少し考えた。
「うーん。きっと仲直りできるよ、みたいな甘いだけの言葉は言いたくないな。仲直りはかなり難しいね。まあ僕に言えることは楽しい日々が過ごせてよかった、と思っておくことだね。その友達に執着してもしょうがないよ。さっきも言った通り、縁があったらまた繋がることもある。今のことだけ考えなよ。」
「それたぶん私もうすでに思ってた。でも形にならなくて誰かに言語化してもらいたかった。ありがとう林。」
「ガクッ、なんだそれ。」
一笑い起きた。それでも、私はやっぱりどこかで由香ちゃんとまた友達になりたいと思っていた。夢と執着の違いはあまりない気がした。
私は新入社員になった。電話応対が怖すぎて最初の1ヶ月は全く電話に出なかった。分からない単語が多すぎて、上司が何を言っているのか全く分からなかった。上司の話を聞いているだけで、気持ち悪くなったこともある。挨拶をしても絶対に返してくれない人がいて、気に病んだり、上司と雑談がうまくできなくて落ち込んだりもした。そんな風に悩んだり苦しんだりしていくうちになんだかんだ日々は過ぎていった。
社会人一年目の秋になって由香ちゃんからラインが来た。
「上司と不倫してたら、上司の奥さんのことが憎くて憎くて仕方なくなっちゃった。このままだと私おかしくなりそう。」既読
「話聞くよ。電話しない?」既読
電話がかかってきた。
「もしもし、めぐちゃん?」
「由香ちゃん、どうしたの?」
「大好きな上司がいて、奥さんいるから好きにならないようにしていたけど、上司すごい優しくしてくれて、純愛だけど不倫しちゃった。」
純愛・・・。恋は盲目。少し笑ってしまいそうになったが我慢した。
「奥さんが憎くてたまらないの。私が彼と会えない間に彼と一緒に奥さんが過ごしているのかと思うと気がおかしくなりそうなの。いっそのこと殺してしまいたい。めぐちゃんならこの気持ち分かってくれると思って。私、自分のこと健全で、悪いことなんてしようと思わないと思っていたのに、こんな自分が出てくるなんて信じられない。」
泣きながら由香ちゃんは言った。
私はどんな理由であれ、由香ちゃんがまた再び私と連絡をとってくれることが嬉しかった。
「由香ちゃん、自分が悪い感情をもったからって自分のこと責めなくてもいいよ。責めるともっと感情が大きくなっちゃうから。そういう感情を抱えながら日々を淡々と過ごしていくのがいいよ。上司との恋愛は、私恋愛のことよく分かんないから何もアドバイスできない。どっちにせよ何かしたら後悔するから完全な正解を選ぼうとしないことだね。」
自分の思っている素直な気持ちを伝えた。
「ありがとう、めぐちゃんが悪いことしちゃった気持ち、完全ではないけれど今なら分かる気がする。冷たくしてごめんね。また友達になってくれる?」
「もちろんだよ。」
由香ちゃんとバーでお酒を飲んだ。
最近描いた絵の写真を由香ちゃんに見せた。由香ちゃんが星を眺めてる絵だった。由香ちゃんの恋を表現したつもりだった。
「わあ、うまいじゃん。」
「下手だよ。でも、ありがとう。」
「本当だよ。私よりずっとうまいもん。」
「私、他人の孤独と辛さを癒やすのが夢なんだよね。できれば画家になって。でも全然手が届かないけど。」
「夢、もう叶えてるじゃん。」
「えっ、叶えてないじゃん。」
「私はこの絵を見て孤独と辛さが癒やされたよ。それに画家って何?定義ないじゃん。私にとって由香ちゃんはもう画家だよ。」
「ありがとう。」
涙が出たのでそっぽを向いてこそこそ涙をふいた。
話題は林の話になった。最初、由香ちゃんは林のことを気持ち悪がっていたが、話を聞いているうちに林も人間なのだと納得した。
「めぐちゃん、林から痴漢されたのによく仲良くしているね。」
「なんでだろ。林と過ごしていると憎しみも湧いてくるけど、もう一人の自分を見ているような気がして、放っておけないんだ。もしかしたら私は林に友達になってもらっているのかもしれない。」
「なるほど。それっていろんなことでもそうかもしれないね。親切とかってしている方が何かしているようで、されてもらっている方は親切させてあげているのかもしれないね。」
確かに、と思った。誰かへ施すことは施しをするものの傷を癒やすことになって、施されるものは癒やしを施しているのかもしれない。
「じゃあ、もしかして寝たきりになった人も誰かに施しているのかもしれないね。」
私は言った。
「確かに、じゃあやっぱりこの世の中で生きている価値がない人なんていないのかもしれないね。」
私達はしばらく余韻に浸った。
明日からも生きていこう。絶望する日は必ずあるけれど、私はどんな時でも生きている価値がある。私はその価値を証明するために生きている。私は私以上でも私以下でもない。そして私は生きているだけで痛々しい。痛々しいのは生きている証拠だ。最後の私が私じゃなくなって意識がなくなる時まで、私は私の人生を歩み続けようと思う。
林が社会人の軽音サークルに入ったらしい。由香ちゃんと林のライブを見に行った。
林はボーカルとギターをやっていた。
シンプルにうまかった。プロ並みではないけれど素人に毛が生えたくらいにうまかった。林は活き活きとギターを弾き、歌を歌っていた。
普通に抵抗するという内容の歌詞だった。「普通ってなんだよ。」というフレーズが頻繁に出てくる。歌っている林はすぐに忘れてしまいそうなどこにでもいそうな男ではなかった。戦っているという表現がふさわしかった。
林は普通に溶け込もうとしていたけれど、それがもしかしたら苦しかったのかもしれない。大丈夫、林あんたはあんただ。あんた以上でもあんた以下でもない。
私はスマホのカメラで林の写真を撮った。パシャッ
林裕太はびっくりした顔をしていた。そして笑顔で私にピースをしてきた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
