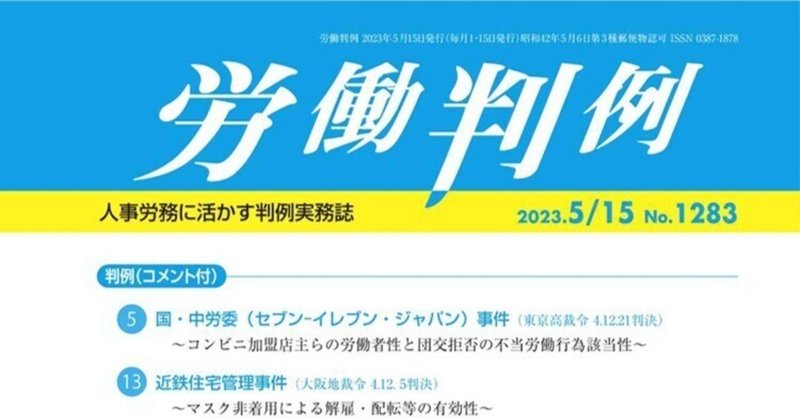
労働判例を読む#489
※ 司法試験考査委員(労働法)
今日の労働判例
【国・中労委(セブン‐イレブン・ジャパン)事件】(東京高判R4.12.21労判1283.5)
この事案は、セブンイレブン店舗の経営者たちXらが、自分たちは労働者であるとして、セブンイレブンに対して労使交渉を求めたところ、それが拒絶されたので、これが不当労働行為に該当するとして労働委員会に救済命令(労使交渉に応じる旨の命令)を求めた事案です。都労委は不当労働行為と認定しました(Xらが労働者であると認定しました)が、中労委Yは認定しませんでした。
そこでXは、裁判所でYの判断を争いましたが、1審2審いずれもYの判断を維持しました。
1.労働者性と経営者性
2審は1審の判断の多くをそのまま維持しています。
そこで特に共通して注目されるのは、「労働者性」の判断方法です。詳細は、1審の解説をご覧いただければ、と思いますが、その概要は以下のとおりです。
まず、判断枠組みとしては、①事業組織への組入れ、事業の依頼に応ずべき関係、②報酬の労務対価性、③契約内容の一方的・定型的決定、④時間的場所的拘束、指揮命令関係、⑤独立した事業者としての実態、の5つが示されました。
けれども特に注目されるのは、⑤について、さらに詳細な判断枠組み(❶加盟店の損益の帰属等、❷加盟者の経営判断、❸加盟者自身の稼働状況)が設定され、しかも①~④より先に、再願書の判断の冒頭で検討されている点です。これは、「労働者性」というよりも「経営者性」があるかどうかを検証するものです。
この判断枠組みを見ると、「労働者性」に対立する概念として「経営者性」を設定し、その「経営者性」を「労働者性」に先立って詳細に検討し、「経営者性」が相当程度高いことを認定したうえで(⑤)、①~⑤の総合的な評価を行っています。
すなわち、「労働者性」は、拘束性や指揮命令などの強制の要素だけで絶対的な評価をするのではなく、ここでの「経営者性」のように、労働者性が否定されるとした場合の関係性(本事案では「経営者」ですが、「役員」や「家族」等もあるでしょう)の程度との比較による相対的な評価をしたのです(相対的評価)。
2.フランチャイザーとフランチャイズ・チェーン
2審では、1審での議論に加え、控訴の際に追加された議論についても裁判所が判断を示しましたが、その中でも注目されるのは、セブンイレブンとフランチャイズ・チェーンの関係です。
Xらは、フランチャイズ・チェーンとXらの関係を見れば「労働者性」が認められる、と主張したのですが、2審は、フランチャイズ・チェーンとXらの関係を検討することなく、Xらの請求を否定しました。すなわち、(a)Xらが「団体交渉を求める相手は、フランチャイザーである参加人であって、セブンイレブンのフランチャイズ・チェーンではない」という点と、(b)Xらが「セブンイレブンのフランチャイズ・チェーンに組み込まれているからといって、直ちに(Xら)が参加人の事業に組み込まれていることと同視することはできない」という点が、その根拠とされています。
労使交渉を求めた相手が、フランチャイザー(セブンイレブン)でなく、その運営するフランチャイズ・チェーンであれば、(a)を見る限り、労働者性が認められる可能性があるようにも見えます。
けれども、(b)を見れば、これが上記判断枠組みの①についての判断にすぎず、その他の事情(②~⑤、❶~❸)についての判断にまで踏み込んでいないことがわかります。その他の事情について、判決の他の部分でいずれもXらにとって消極的な評価がされていることを見れば、仮に(a)でフランチャイズ・チェーンを相手に労使交渉を申し入れ、さらに仮に、その結果、①事業への組み入れが認められたとしても、結論に違いは生じなかったように思われます。
とは言うものの、フランチャイザーとフランチャイズ・チェーンのどちらを交渉相手にするかによって、少なくとも①について差が生じる可能性はありそうであり、技術的にフランチャイズ・チェーンが交渉相手になり得るのか(使用者性があるのか)という点も含め、今後、議論が深められるべき問題でしょう。
3.実務上のポイント
上記1のような「相対的」な判断方法ではなく、「労働者性」の有無だけを「絶対的」に評価し、判断する方法もあり、そのような方法で判断した裁判例も存在します。
けれども、「絶対的」な判断方法は、通常の取引先にも要求される強制の契機、例えば事業遂行の際に指定した制服を着用するなどの約束について、取引先であっても事業のブランド政策の観点から、契約によって制服の着用が求められる場合もあるでしょうが、指示に従わなければならない、という意味で強制の契機ですから、例えば「指揮命令」の要素と評価されかねません。すなわち、本来は事業者性を肯定すべき、事業契約に基づく約束が、逆に「労働者性」を肯定すべき事情の1つとしてカウントされかねない可能性があり、実態に合わない評価がされる原因になりかねないのです。
このように、「相対的」な評価は、本事案のような団体交渉における「労働者性」だけでなく、労基法上の「労働者性」についても、同様に基本的な判断方法とされるべきです。
※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
