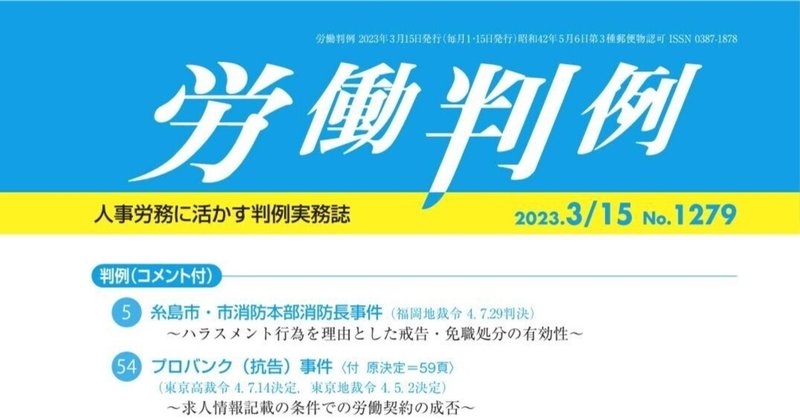
労働判例を読む#477
※ 司法試験考査委員(労働法)
今日の労働判例
【プロバンク(抗告)事件】(東京高決R4.7.14労判1279.54)
この事案は、求人情報に記載された給与を期待していたのに、会社Yからの内定通知書にはそれよりも低い金額の給与が示されていたため、給与額を訂正した内定通知書を返送するなどして、給与額について争っていた採用予定者Xが、内定通知書記載の条件での給与の支払いを求めた事案です。
裁判所は、Xの請求を否定しました。
1.契約の成否
1審2審いずれも、契約の成立を否定しました。すなわち、求人情報記載の条件はおろか、内定通知書記載の条件ですら、契約は成立していない、と判断しました。
この判断のポイントは2つあるように思います。
1つ目は、会社が、求人情報記載の条件と異なる条件を提案することが許されている、という点です。もちろん、「つり広告」のように、実際にそのような条件で採用するつもりが無いのに過大な条件で抗告するようなことは、許されるわけがありません。
けれども、そのような悪質な場合でなければ、むしろ、採用予定者の能力や経験に応じた条件が設定されることは当然であり、特に採用のプロセスから見ると、期待した能力や経験に及ぶ候補者がいない場合でも、それで誰も採用しない場合があれば、他に当てはまる業務があるので異なる条件での採用を再提案する場合もあるでしょう。
この事案では、Yからの再提案について、1審・2審は、新たな契約の申込みとして有効であるとし、これに対応するXの承諾がない、したがって契約は成立していない、と評価しました。Xは、会社からの再提案(内定通知書)について、わざわざ金額を訂正して返送しており、再提案を拒絶する意思が極めて明確に示されていますので、内定通知書の条件での契約成立が否定されるのは当然でしょう。また、今度は逆に、会社からの内定通知書の記載が明らかに求人情報の条件と異なり、求人情報とは別の契約交渉であることが明らかですから、求人情報の条件での契約成立も否定されたのです。
このように、会社が求人情報の条件と異なる条件を提示することが可能である、という点が、その後のプロセスの評価につながるのです。
2つ目は、求人情報の条件がそのまま労働契約の内容とされたこれまでの裁判例との違いです。
たしかに、求人情報で示された条件が労働契約の内容になるから、求人情報の情報どおり処遇することを命じられた裁判例は、相当数見かけます。
けれども、それらは労働条件が明確に定められていない事案など、会社と従業員の合意内容が明確でないような場合に適用されるルールです。たしかに、上記の「つり広告」に象徴されるような悪質な採用活動は許されませんが、かといって、募集から選考などのプロセスを通して、候補者に合った労働条件を定めていくことを否定するわけにもいかないでしょう。なぜなら、会社と従業員の労働条件は、「労働契約」を基本にしており、すなわち、当事者の意思に基づく合意が前提になっているからです。
その観点から本事案を見ると、XとYの意思が(結果的に合意に至りませんでしたが)明確に示されており、不明確な意思の内容を求人情報の条件によって補充する必要が無く、本来の原則どおり両当事者が明確に示した意思に従って処理されるべき事案です。
2.実務上のポイント
この事案では、XからYに対して損害賠償請求がされていません。
そのため、求人情報の記載が実際に後に再提案される内定通知書の条件と違う点を中心とする、募集活動の合理性について、何ら判断が示されませんでした。
しかし、雇用条件や労働契約の成否、という上記の問題の他に、このような募集活動の合理性自体も争われる可能性がありますので、最終的に雇用条件を明確に示しさえすればそれで良い、という安易な判断をしないように注意しましょう。
※ JILA・社労士の研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
※ この連載が、書籍になりました!しかも、『労働判例』の出版元から!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
