
死を鏡として尊厳ある生の追究
彼らの苦しみ、悩みは、どこまで行っても彼らにしか分からない。ぼくらは、彼らの話を聞くことしかできない。そして、彼らの決断を受け止めることしかできない。決して行動の主体にはなれない。そこに、断絶があると感じた。
生き死にとは、法も倫理も関係のない、究極的にプライベートな議題なのかもしれない。
だからこそ、一般論で語られるべきものではない類のはなし。
当事者が何を思い、家族が何を思ったか。
論点があるとすればそこにしかなく、決して「安楽死」の是非にはない。

「だから、もう眠らせてほしい」を読み始めた。
看護師からの内線を受ける西先生を自分に置き換えて、
(えっ安楽死。そんなぁ…。またまた何言ってるのさ…。話していくうちに、きっと生きる希望はどこかに見出せるはず。何とかなる。まずは辛さや苦しみに共感そして傾聴だ。)
吉田ユカのバックグラウンドをみる。
度重なる身体的な虐待、家族間での差別、蔑みの言葉、冷酷な関係、性的な虐待、複雑性PTSD。
(いや…。掌返す、そりゃ死にたくなる。)
安らかに死を迎えることは、誰もが望むと思う。長期間苦しめられたり、痛みが延々と続くなか延命処置されることに何の希望を見出すことができるのか。それなら雪山のロッジなどで安らかに眠りにつきたい。パトラッシュみたく天使に運ばれて逝きたい。
医療技術の飛躍的な進歩によって、多くの命が救われる半面、安らかな死を妨げる過剰な医療や延命措置に対する問題は前から気になっていた。
高負担高福祉国家として知られる北欧諸国では、寝たきりの高齢者や胃瘻患者がほとんどおらず、誤嚥性肺炎治療などもあまり行われない
という医師が書いた記事を読んだことがある。
点滴もしないことに驚く日本人医師に対し、「ベッドの上で、点滴で生きている人生なんて、何の意味があるのですか」と、逆に質問されたところが印象的だった。
スウェーデンで終末期高齢者に濃厚医療を行わない最も大きな理由は、このようなQOLを重視した人生観が形成されているためだ。また、終末期高齢者に人工栄養を行うのは、非倫理的(老人虐待)という考えもあるらしい。
まぁ、これは海外の価値観であって、日本は日本なりに制度というオプションを付けるか否か。薬を飲んで安らかな死を迎えるというオプションを選択肢として与えるべきかどうか…
吉田ユカが最期に述べた「民主的」というワード
症状が悪化した時に、苦しまずに安らかに死ぬことができるというオプションがあることは、患者に心の安寧を与えるのかもしれない。患者は、万一の時はこの薬があると思えることで、安心を得られるのかもしれない。
これが伝家の宝刀、この制度がガバガバになった未来を想像すると恐ろしいので正しい正しくない、あったほうが善い悪いは、多様な考え方を持っていない自分では何ともハッキリ判断し難い。
患者の自己決定が尊重されるべきであることと、患者の利益が守られるべきであることの二点が悩ませる。
終末期の病気にともなう苦痛から(死期を早めることによって)解放されることにある患者の利益は、どれだけ大きいのだろうか。
また、命の尊さには、死にたいという本人の意向や、苦痛から逃れることにある本人の利益を守ることよりももっと大きい価値があるといえるのか。
死にかたや死ぬタイミングに関する個人の自己決定については、必ずしも常に尊重されるべきなのだろうか。
死ぬ権利は存在するのか…。
自らの意思で死を選ぶことは許容されていいことなのか。自殺OKな世の中なのか。
死に至る過程についての選択権はあると思うが。
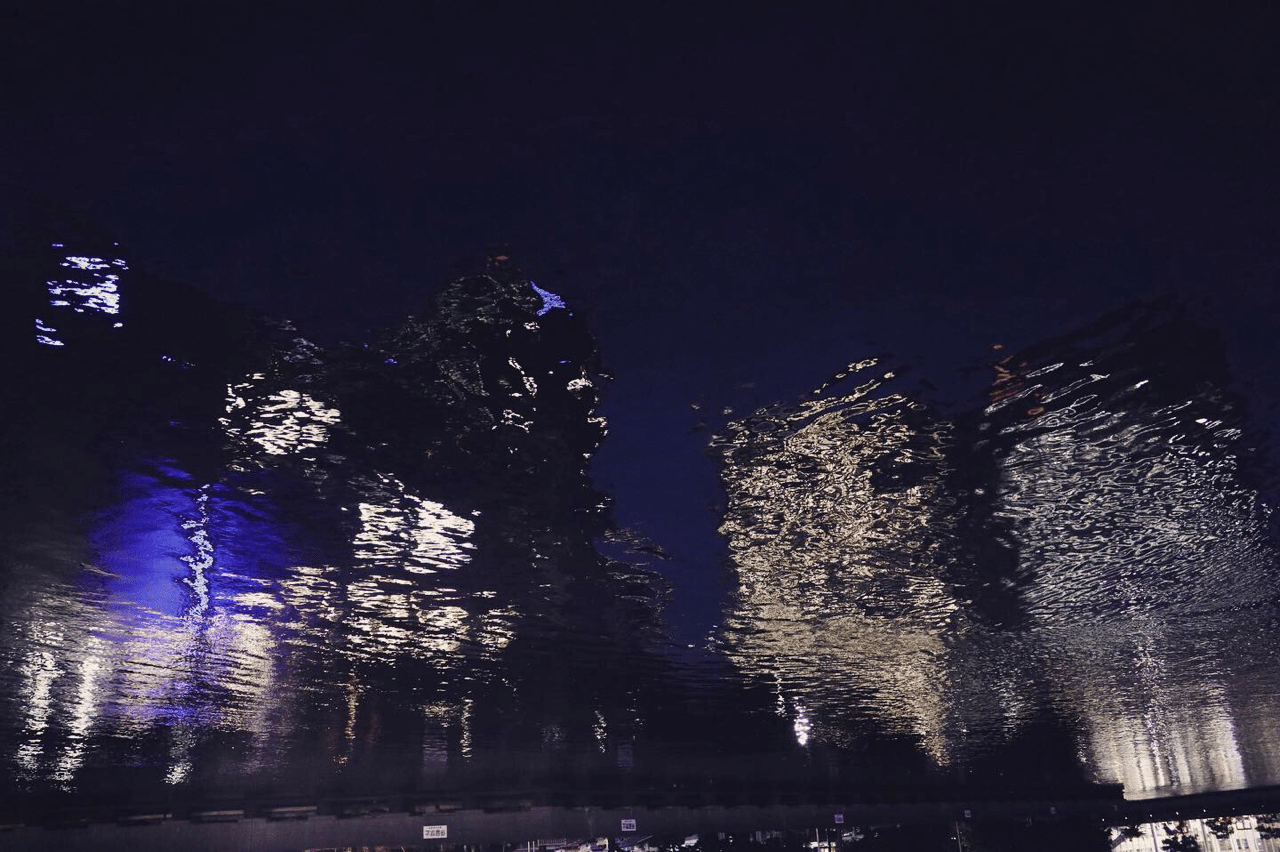
もう一人の主要人物Yくん
彼は周囲にすべてを委ね、死の直前まで普通に生活ができ、世界とのつながりを感じながら生きていた。
「今」は「今」しか生きられない。
そんな感じだ。
だからこそ、「今」のありがたさを噛み締めている。自分の命という単位ではなく、一瞬で過ぎていくこの「今」が大事なわけで。
こういう思想を仏教的に説明するならば、確か「諸行無常」と言っただろうか。
この世のすべての存在は一瞬一瞬で変化し続けていて、不変のものなんて存在しない。だからこその「今を見つめる」
これこそ尊厳のある生なのかもしれない。
ぼくたちは親を選べず、時代を選べず、「偶然」に生を受けた。そして、いつ病に倒れるか死ぬかもわからず、どんな境遇に出会うかも知らず、「偶然」の流れに身を委ねている。
身を委ねる行為
偶然に支配されつつ、どう意志を持って生きるのか。死に至るまでに道を選んでいく権利は存在するはずだ。
自分にも今まで生きてきて少なからず死にたくなるような日は何度かあった(やはり人間関係や格差が原因)
けど、首に手をあてたり、駅のホーム黄色い線の外側まで気持ちがはみ出した経験はない。
明日死のう、とも思わない。
それに、まだやり残したことはいっぱいある。満たせてはいないことだらけだ。
かと言って、"死ぬまでにやりたいことリスト100"を全て達成したところで「よしじゃあ満足!さてどうやって死のう」となるわけでもない。
でも、そうじゃない人たちがいる。
『早く死んでしまいたい』
そうは絶対に思いたくない
そこは紛れもなく自分の中の真実。
自分は、どこまでいっても自分。そんな恐ろしい環境を経験してきたわけでもなければ、重篤な病気を抱えているわけでもないので「人それぞれ」なんだと思う。
けど、この本を読んで到達した感情を「人それぞれ」の一言で片付けてたまるかよという気持ち。
社会的孤立から抑うつや不安がやってくる。地域における社会的孤立を解消し、癌を抱えながらでもその生を全うできるような社会を育てていくべきと問題提起して、それに対するアンサーであるよりよい生への「社会的処方」、「死にたくなくなる手立て」を体現している西智弘先生であったり、社会的孤立、精神的&社会的&肉体的死に対してアクションを起こしている人たちは、ほんとうに優しい。
理想像だ。そういう世界で生きていたい。そういう人でありたい。そういう人たちに囲まれていたい。そして願わくば自分の周りだけでも「早く死にたい」そんな風には思ってほしくない。これは自分のエゴだが、「もうちょっと生きていたい」と思える世の中であってほしい。
決して崇高な思想を持って毎日仕事しているわけではないですし、ごくごく平均的な医療従事者(理学療法士)のうちの一人なのですが、やはり本書を読み進めていくうちに苦しくなるし、できれば何とかしてあげたいと思ってしまう。
そんな現実の出来事に対して、自分の理を持って周りに流されず自分自身に身を委ねている先生の轍に出来るだけ近づきたい。そんな想いも湧いてくる。

生き死にについて語るにあたり、思い出したのはBUMP OF CHICKENのユグドラシルというアルバム。生まれて初めて買ったCDだ。
BUMP OF CHICKENが唄うテーマは、生と死。存在と喪失。出会いと別れ。
彼らの音楽は決して「がんばれ」とは言わない。ただそばに居てくれるだけだ。そんな音楽は初めてだった。
人生は喪失の連続だ。家族、友人、夢、絆、健康、仕事、記憶、、、
生まれた瞬間から喪失の日々が始まる。容赦なく死へと向かう。得るもの、出会いがあるということは、それを失う時が必ずやって来る。自らの意志で手放すこともある。今、自分のこの命があるということは、必ず終わりの時が来るということ。
生まれた事を恨むのなら ちゃんと生きてからにしろ
これは「レム」という曲の歌詞の一節。
「甘ったれ」に対するド正論がこれでもかというくらい歌われるが、この「ユグドラシル」というアルバムは、通してこの「甘ったれ」に対するメッセージが込められているように感じる。
「オンリーロンリーグローリー」も「乗車権」も、「ギルド」も、「Sailing Day」にも、共通したもの。「生きることから逃げるな」というメッセージだ。
これは失礼にあたるかもしれないが
ぶっちゃけて言うと、劣等感にまみれたひねくれたぼくからすれば、医療者や心理士という地位を持ってる側の人間からの説法なんかより、BUMP OF CHICKENの曲を聴いた方が、何万倍も心が救われるし、なんだか対話してる気分になる。"この世で生きていく無常さ"ってこともよくわかると思う。
自分が死にたいなぁ…ってほど悩んだり落ち込んだりしたときに心に響いて軌道修正できたのはまぎれもなくBUMP OF CHICKENだ。彼らに命を繋ぎ止めてもらった人が多いという話はネット上でよく聞く。
つまり彼らはもはや「野生の医療者」だ。
自分も大物アーティストとまではなれなくとも、地域のコミュニティを把握していてそれを繋げることができる人(リンクワーカー)には行動次第じゃなれるんじゃないかなと思う。
医者という肩書きをあえて出さずに地域でコーヒーを配り地域の方々と対話をする守本陽一先生率いるYATAI CAFE然り、
私も「野生の医療者」になりたい。
川の下流に流れてきた人を病院で診ているのであれば、川の上流で川に落ちた理由を突き詰めていきたい。
せめて自分の大切な人たちが住んでいる範囲だけでも、何か熱中、没頭できる取り組みをしたい。
西先生の足元にも及ばないが、自分だってホスピタリティや利他精神は少なからず持っている。
他者をコントロールしようだなんて、おこがましいことは考えていないが、
自分の残機一機しかない人生を賭して、何か自分もみんなもワクワクするような取り組みはできないかな〜とこの本を読み終わってさらに深く決意する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
