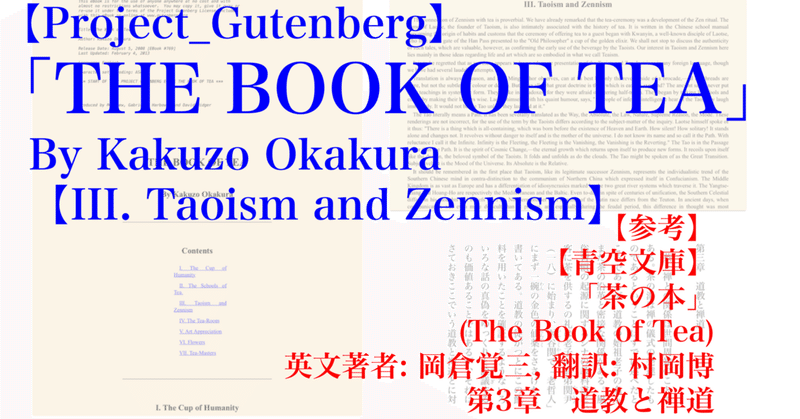
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」その3【III. Taoism and Zennism】
〜〜【Project_Gutenberg】→Web翻訳版→【Project_Gutenberg_200im】
〜
THE BOOK OF TEA
By Kakuzo Okakura
〜
【Contents】
I. The Cup of Humanity
II. The Schools of Tea
III. Taoism and Zennism. ←今回の紹介
IV. The Tea-Room
V. Art Appreciation
VI. Flowers
VII. Tea-Masters
〜
〜〜
〜〜[上記【Project_Gutenberg】の翻訳は以下の通り。翻訳にはアプリ「DeepL」を使用。]
〜
茶の本
岡倉覚三著
〜
内容
I.人類の杯
II.お茶の学校
III.道教と禅教 ←今回の紹介
IV.茶室
V.芸術鑑賞
VI.花
VII.茶人
〜
〜〜
【出所】URL> https://www.gutenberg.org/files/769/769-h/769-h.htm
〜〜【Project_Gutenberg】THE BOOK OF TEA
〜
III. Taoism and Zennism
The connection of Zennism with tea is proverbial. We have already remarked that the tea-ceremony was a development of the Zen ritual. The name of Laotse, the founder of Taoism, is also intimately associated with the history of tea. It is written in the Chinese school manual concerning the origin of habits and customs that the ceremony of offering tea to a guest began with Kwanyin, a well-known disciple of Laotse, who first at the gate of the Han Pass presented to the "Old Philosopher" a cup of the golden elixir. We shall not stop to discuss the authenticity of such tales, which are valuable, however, as confirming the early use of the beverage by the Taoists. Our interest in Taoism and Zennism here lies mainly in those ideas regarding life and art which are so embodied in what we call Teaism.
It is to be regretted that as yet there appears to be no adequate presentation of the Taoists and Zen doctrines in any foreign language, though we have had several laudable attempts.
Translation is always a treason, and as a Ming author observes, can at its best be only the reverse side of a brocade,—all the threads are there, but not the subtlety of colour or design. But, after all, what great doctrine is there which is easy to expound? The ancient sages never put their teachings in systematic form. They spoke in paradoxes, for they were afraid of uttering half-truths. They began by talking like fools and ended by making their hearers wise. Laotse himself, with his quaint humour, says, "If people of inferior intelligence hear of the Tao, they laugh immensely. It would not be the Tao unless they laughed at it."
The Tao literally means a Path. It has been severally translated as the Way, the Absolute, the Law, Nature, Supreme Reason, the Mode. These renderings are not incorrect, for the use of the term by the Taoists differs according to the subject-matter of the inquiry. Laotse himself spoke of it thus: "There is a thing which is all-containing, which was born before the existence of Heaven and Earth. How silent! How solitary! It stands alone and changes not. It revolves without danger to itself and is the mother of the universe. I do not know its name and so call it the Path. With reluctance I call it the Infinite. Infinity is the Fleeting, the Fleeting is the Vanishing, the Vanishing is the Reverting." The Tao is in the Passage rather than the Path. It is the spirit of Cosmic Change,—the eternal growth which returns upon itself to produce new forms. It recoils upon itself like the dragon, the beloved symbol of the Taoists. It folds and unfolds as do the clouds. The Tao might be spoken of as the Great Transition. Subjectively it is the Mood of the Universe. Its Absolute is the Relative.
It should be remembered in the first place that Taoism, like its legitimate successor Zennism, represents the individualistic trend of the Southern Chinese mind in contra-distinction to the communism of Northern China which expressed itself in Confucianism. The Middle Kingdom is as vast as Europe and has a differentiation of idiosyncrasies marked by the two great river systems which traverse it. The Yangtse-Kiang and Hoang-Ho are respectively the Mediterranean and the Baltic. Even to-day, in spite of centuries of unification, the Southern Celestial differs in his thoughts and beliefs from his Northern brother as a member of the Latin race differs from the Teuton. In ancient days, when communication was even more difficult than at present, and especially during the feudal period, this difference in thought was most pronounced. The art and poetry of the one breathes an atmosphere entirely distinct from that of the other. In Laotse and his followers and in Kutsugen, the forerunner of the Yangtse-Kiang nature-poets, we find an idealism quite inconsistent with the prosaic ethical notions of their contemporary northern writers. Laotse lived five centuries before the Christian Era.
The germ of Taoist speculation may be found long before the advent of Laotse, surnamed the Long-Eared. The archaic records of China, especially the Book of Changes, foreshadow his thought. But the great respect paid to the laws and customs of that classic period of Chinese civilisation which culminated with the establishment of the Chow dynasty in the sixteenth century B.C., kept the development of individualism in check for a long while, so that it was not until after the disintegration of the Chow dynasty and the establishment of innumerable independent kingdoms that it was able to blossom forth in the luxuriance of free-thought. Laotse and Soshi (Chuangtse) were both Southerners and the greatest exponents of the New School. On the other hand, Confucius with his numerous disciples aimed at retaining ancestral conventions. Taoism cannot be understood without some knowledge of Confucianism and vice versa.
We have said that the Taoist Absolute was the Relative. In ethics the Taoist railed at the laws and the moral codes of society, for to them right and wrong were but relative terms. Definition is always limitation—the "fixed" and "unchangeless" are but terms expressive of a stoppage of growth. Said Kuzugen,—"The Sages move the world." Our standards of morality are begotten of the past needs of society, but is society to remain always the same? The observance of communal traditions involves a constant sacrifice of the individual to the state. Education, in order to keep up the mighty delusion, encourages a species of ignorance. People are not taught to be really virtuous, but to behave properly. We are wicked because we are frightfully self-conscious. We nurse a conscience because we are afraid to tell the truth to others; we take refuge in pride because we are afraid to tell the truth to ourselves. How can one be serious with the world when the world itself is so ridiculous! The spirit of barter is everywhere. Honour and Chastity! Behold the complacent salesman retailing the Good and True. One can even buy a so-called Religion, which is really but common morality sanctified with flowers and music. Rob the Church of her accessories and what remains behind? Yet the trusts thrive marvelously, for the prices are absurdly cheap,—a prayer for a ticket to heaven, a diploma for an honourable citizenship. Hide yourself under a bushel quickly, for if your real usefulness were known to the world you would soon be knocked down to the highest bidder by the public auctioneer. Why do men and women like to advertise themselves so much? Is it not but an instinct derived from the days of slavery?
The virility of the idea lies not less in its power of breaking through contemporary thought than in its capacity for dominating subsequent movements. Taoism was an active power during the Shin dynasty, that epoch of Chinese unification from which we derive the name China. It would be interesting had we time to note its influence on contemporary thinkers, the mathematicians, writers on law and war, the mystics and alchemists and the later nature-poets of the Yangtse-Kiang. We should not even ignore those speculators on Reality who doubted whether a white horse was real because he was white, or because he was solid, nor the Conversationalists of the Six dynasties who, like the Zen philosophers, revelled in discussions concerning the Pure and the Abstract. Above all we should pay homage to Taoism for what it has done toward the formation of the Celestial character, giving to it a certain capacity for reserve and refinement as "warm as jade." Chinese history is full of instances in which the votaries of Taoism, princes and hermits alike, followed with varied and interesting results the teachings of their creed. The tale will not be without its quota of instruction and amusement. It will be rich in anecdotes, allegories, and aphorisms. We would fain be on speaking terms with the delightful emperor who never died because he had never lived. We may ride the wind with Liehtse and find it absolutely quiet because we ourselves are the wind, or dwell in mid-air with the Aged one of the Hoang-Ho, who lived betwixt Heaven and Earth because he was subject to neither the one nor the other. Even in that grotesque apology for Taoism which we find in China at the present day, we can revel in a wealth of imagery impossible to find in any other cult.
But the chief contribution of Taoism to Asiatic life has been in the realm of aesthetics. Chinese historians have always spoken of Taoism as the "art of being in the world," for it deals with the present—ourselves. It is in us that God meets with Nature, and yesterday parts from to-morrow. The Present is the moving Infinity, the legitimate sphere of the Relative. Relativity seeks Adjustment; Adjustment is Art. The art of life lies in a constant readjustment to our surroundings. Taoism accepts the mundane as it is and, unlike the Confucians or the Buddhists, tries to find beauty in our world of woe and worry. The Sung allegory of the Three Vinegar Tasters explains admirably the trend of the three doctrines. Sakyamuni, Confucius, and Laotse once stood before a jar of vinegar—the emblem of life—and each dipped in his finger to taste the brew. The matter-of-fact Confucius found it sour, the Buddha called it bitter, and Laotse pronounced it sweet.
The Taoists claimed that the comedy of life could be made more interesting if everyone would preserve the unities. To keep the proportion of things and give place to others without losing one's own position was the secret of success in the mundane drama. We must know the whole play in order to properly act our parts; the conception of totality must never be lost in that of the individual. This Laotse illustrates by his favourite metaphor of the Vacuum. He claimed that only in vacuum lay the truly essential. The reality of a room, for instance, was to be found in the vacant space enclosed by the roof and the walls, not in the roof and walls themselves. The usefulness of a water pitcher dwelt in the emptiness where water might be put, not in the form of the pitcher or the material of which it was made. Vacuum is all potent because all containing. In vacuum alone motion becomes possible. One who could make of himself a vacuum into which others might freely enter would become master of all situations. The whole can always dominate the part.
These Taoists' ideas have greatly influenced all our theories of action, even to those of fencing and wrestling. Jiu-jitsu, the Japanese art of self-defence, owes its name to a passage in the Tao-teking. In jiu-jitsu one seeks to draw out and exhaust the enemy's strength by non-resistance, vacuum, while conserving one's own strength for victory in the final struggle. In art the importance of the same principle is illustrated by the value of suggestion. In leaving something unsaid the beholder is given a chance to complete the idea and thus a great masterpiece irresistibly rivets your attention until you seem to become actually a part of it. A vacuum is there for you to enter and fill up the full measure of your aesthetic emotion.
He who had made himself master of the art of living was the Real man of the Taoist. At birth he enters the realm of dreams only to awaken to reality at death. He tempers his own brightness in order to merge himself into the obscurity of others. He is "reluctant, as one who crosses a stream in winter; hesitating as one who fears the neighbourhood; respectful, like a guest; trembling, like ice that is about to melt; unassuming, like a piece of wood not yet carved; vacant, like a valley; formless, like troubled waters." To him the three jewels of life were Pity, Economy, and Modesty.
If now we turn our attention to Zennism we shall find that it emphasises the teachings of Taoism. Zen is a name derived from the Sanscrit word Dhyana, which signifies meditation. It claims that through consecrated meditation may be attained supreme self-realisation. Meditation is one of the six ways through which Buddhahood may be reached, and the Zen sectarians affirm that Sakyamuni laid special stress on this method in his later teachings, handing down the rules to his chief disciple Kashiapa. According to their tradition Kashiapa, the first Zen patriarch, imparted the secret to Ananda, who in turn passed it on to successive patriarchs until it reached Bodhi-Dharma, the twenty-eighth. Bodhi-Dharma came to Northern China in the early half of the sixth century and was the first patriarch of Chinese Zen. There is much uncertainty about the history of these patriarchs and their doctrines. In its philosophical aspect early Zennism seems to have affinity on one hand to the Indian Negativism of Nagarjuna and on the other to the Gnan philosophy formulated by Sancharacharya. The first teaching of Zen as we know it at the present day must be attributed to the sixth Chinese patriarch Yeno(637-713), founder of Southern Zen, so-called from the fact of its predominance in Southern China. He is closely followed by the great Baso(died 788) who made of Zen a living influence in Celestial life. Hiakujo(719-814) the pupil of Baso, first instituted the Zen monastery and established a ritual and regulations for its government. In the discussions of the Zen school after the time of Baso we find the play of the Yangtse-Kiang mind causing an accession of native modes of thought in contrast to the former Indian idealism. Whatever sectarian pride may assert to the contrary one cannot help being impressed by the similarity of Southern Zen to the teachings of Laotse and the Taoist Conversationalists. In the Tao-teking we already find allusions to the importance of self-concentration and the need of properly regulating the breath—essential points in the practice of Zen meditation. Some of the best commentaries on the Book of Laotse have been written by Zen scholars.
Zennism, like Taoism, is the worship of Relativity. One master defines Zen as the art of feeling the polar star in the southern sky. Truth can be reached only through the comprehension of opposites. Again, Zennism, like Taoism, is a strong advocate of individualism. Nothing is real except that which concerns the working of our own minds. Yeno, the sixth patriarch, once saw two monks watching the flag of a pagoda fluttering in the wind. One said "It is the wind that moves," the other said "It is the flag that moves"; but Yeno explained to them that the real movement was neither of the wind nor the flag, but of something within their own minds. Hiakujo was walking in the forest with a disciple when a hare scurried off at their approach. "Why does the hare fly from you?" asked Hiakujo. "Because he is afraid of me," was the answer. "No," said the master, "it is because you have murderous instinct." The dialogue recalls that of Soshi (Chaungtse), the Taoist. One day Soshi was walking on the bank of a river with a friend. "How delightfully the fishes are enjoying themselves in the water!" exclaimed Soshi. His friend spake to him thus: "You are not a fish; how do you know that the fishes are enjoying themselves?" "You are not myself," returned Soshi; "how do you know that I do not know that the fishes are enjoying themselves?"
Zen was often opposed to the precepts of orthodox Buddhism even as Taoism was opposed to Confucianism. To the transcendental insight of the Zen, words were but an incumbrance to thought; the whole sway of Buddhist scriptures only commentaries on personal speculation. The followers of Zen aimed at direct communion with the inner nature of things, regarding their outward accessories only as impediments to a clear perception of Truth. It was this love of the Abstract that led the Zen to prefer black and white sketches to the elaborately coloured paintings of the classic Buddhist School. Some of the Zen even became iconoclastic as a result of their endeavor to recognise the Buddha in themselves rather than through images and symbolism. We find Tankawosho breaking up a wooden statue of Buddha on a wintry day to make a fire. "What sacrilege!" said the horror-stricken bystander. "I wish to get the Shali out of the ashes," calmly rejoined the Zen. "But you certainly will not get Shali from this image!" was the angry retort, to which Tanka replied, "If I do not, this is certainly not a Buddha and I am committing no sacrilege." Then he turned to warm himself over the kindling fire.
A special contribution of Zen to Eastern thought was its recognition of the mundane as of equal importance with the spiritual. It held that in the great relation of things there was no distinction of small and great, an atom possessing equal possibilities with the universe. The seeker for perfection must discover in his own life the reflection of the inner light. The organisation of the Zen monastery was very significant of this point of view. To every member, except the abbot, was assigned some special work in the caretaking of the monastery, and curiously enough, to the novices was committed the lighter duties, while to the most respected and advanced monks were given the more irksome and menial tasks. Such services formed a part of the Zen discipline and every least action must be done absolutely perfectly. Thus many a weighty discussion ensued while weeding the garden, paring a turnip, or serving tea. The whole ideal of Teaism is a result of this Zen conception of greatness in the smallest incidents of life. Taoism furnished the basis for aesthetic ideals, Zennism made them practical.
〜
〜
IV. The Tea-Room ←次回紹介予定
〜
〜〜
〜〜【Project_Gutenberg】“THE BOOK OF TEA”「茶の本」
〜〜 翻訳はアプリ「DeepL」を使用。
〜
III. 道教と禅
禅と茶の結びつきは格言的である。 茶道が禅の儀式を発展させたものであることはすでに述べた。 道教の創始者である老子の名前もまた、茶の歴史と密接に結びついている。 習慣や風習の起源に関する中国の教典には、客人に茶を供える儀式は、老荘の有名な弟子である観音から始まったと書かれている。 しかし、道家が早くから茶を愛飲していたことを裏付ける貴重なものである。 ここでの道教と禅宗への関心は、主に私たちが茶主義と呼ぶものの中に具現化されている、生活と芸術に関する考え方にある。
道家と禅の教義を外国語で十分に紹介する試みはいくつかあるが、いまだにないのは残念なことである。
翻訳は常に反逆であり、明の作家が述べているように、せいぜい錦の裏返しでしかありえない。 しかし、結局のところ、説き明かすのが簡単な偉大な教義などあるのだろうか? 古代の賢人たちは、自分たちの教えを体系的な形には決してまとめなかった。 彼らは逆説で語り、中途半端な真実を口にすることを恐れた。 彼らは愚か者のように話し始め、聴衆を賢くすることで終わった。 ラオッツェ自身、風変わりなユーモアを交えてこう語っている。 彼らがそれを笑わない限り、それはタオではないだろう」。
タオとは文字通り「道」を意味する。 この言葉は、「道」、「絶対」、「法」、「自然」、「至高の理性」、「モード」などと訳されてきた。 道家のこの言葉の使い方は、探求の対象によって異なるからである。 ラオッツェ自身、このように語っている: 「天地が存在する以前に生まれた、すべてを含むものがある。 なんと静かだろう! いかに孤独か! それは単独で存在し、変化しない。 自らを危険にさらすことなく回転し、宇宙の母である。 私はその名を知らないので、それを道と呼ぶ。 不本意ながら、私はそれを無限と呼ぶ。 無限は儚く、儚さは消え、消えは回帰する」。 タオは道よりもむしろ通路にある。 それは宇宙の変化の精神であり、新たな形を生み出すために自らに回帰する永遠の成長である。 道家のシンボルとして愛されている龍のように、それはそれ自体に反発している。 雲のように折り重なり、広がる。 タオは大いなる移行として語られるかもしれない。 主観的には宇宙の気分である。 その絶対的なものは相対的なものである。
第一に、道教はその正当な後継者である禅教と同様、儒教で表現された華北の共産主義とは対照的に、華南の個人主義的傾向を表していることを忘れてはならない。 中王国はヨーロッパに匹敵するほど広大で、それを横断する2つの大河系によって特徴づけられる特異性の分化がある。 揚子江と黄河はそれぞれ地中海とバルト海である。 何世紀にもわたって統一されてきたにもかかわらず、今日でさえ、南方天人はその思想と信念において、ラテン民族の一員がチュートン人と異なるように、北方兄弟と異なっている。 現在よりもさらにコミュニケーションが困難だった古代、とりわけ封建時代には、この思想の違いが最も顕著だった。 一方の芸術と詩は、他方のそれとはまったく異なる雰囲気を漂わせている。 ラオツェとその信奉者たち、そしてヤンツェ・キアン自然詩人の先駆者であるクツゲンには、同時代の北方作家たちの散文的な倫理観とはまったく矛盾する観念論が見られる。 老子はキリスト教時代の5世紀前に生きていた。
道教の思索の萌芽は、長耳の姓を持つ老子(ラオッツェ)の登場よりずっと前に見出されるかもしれない。 中国の古代の記録、特に『変化記』は彼の思想を予見させる。 しかし、紀元前16世紀にチョウ王朝が成立して頂点に達した中国文明の古典的な時代の法律や習慣が非常に尊重されたため、個人主義の発展は長い間抑えられ、チョウ王朝が崩壊し、無数の独立した王国が成立して初めて、自由な思想の豊かな花を咲かせることができたのである。 老子と宗師(荘子)はともに南方人であり、新派の最大の論客であった。 一方、孔子は多くの弟子たちとともに、先祖伝来の慣習を保持することを目指した。 道教は儒教の知識なしには理解できず、その逆もまた然りである。
道家の絶対的なものは相対的なものであると述べた。 道家は倫理学において、社会の法律や道徳規範を非難した。 定義とは常に限界であり、「固定」や「不変」は成長の停止を表す言葉にすぎない。 葛原は言った-"賢者は世界を動かす"。 私たちの道徳の基準は、社会の過去のニーズから生まれたものだが、社会は常に同じであり続けるのだろうか? 共同体の伝統を守ることは、個人が常に国家に犠牲を払うことを意味する。 教育は、強大な妄想を維持するために、無知を助長する。 人々は本当に高潔であることを教えられるのではなく、適切に振る舞うことを教えられる。 我々が邪悪なのは、恐ろしく自意識過剰だからである。 良心の呵責を感じるのは、他人に真実を告げるのが怖いからであり、プライドに逃げ込むのは、自分自身に真実を告げるのが怖いからである。 世界そのものがあまりにも馬鹿げているのに、どうして人は世界と真剣に向き合えるのだろう! 物々交換の精神はいたるところにある。 名誉と貞節 善と真を売り込む自己満足のセールスマンを見よ。 いわゆる宗教を買うことさえできるが、それは花と音楽で聖別された一般的な道徳にすぎない。 教会から付属品を奪って、何が残るというのか。 天国への切符のための祈り、名誉ある市民権のための卒業証書。 もしあなたの本当の有用性が世間に知れ渡ったら、あなたはすぐに競売人によって最高額で競り落とされてしまうだろう。 なぜ男も女もこれほどまでに自分を宣伝したがるのか。 それは奴隷の時代に由来する本能にすぎないのではないか。
この思想の活力は、現代思想を打ち破る力だけでなく、その後の動きを支配する力にもある。 道教は、私たちが中国と呼ぶようになった中国統一のエポックである新王朝時代に活発な力を発揮した。 現代の思想家たち、数学者たち、法律や戦争に関する作家たち、神秘主義者や錬金術師たち、そして後の楊堤姜の自然詩人たちに与えた影響に言及する時間があれば、面白いことになるだろう。 白馬は白いから本物なのか、それとも固いから本物なのかを疑った実在論者たちや、禅の哲学者たちのように純粋なものと抽象的なものをめぐる議論に興じた六朝の対話主義者たちを無視すべきではない。 何よりも、道教が天人気質の形成に貢献し、「翡翠のように温かく」控えめで洗練されたある種の能力を与えたことに敬意を表するべきである。 中国の歴史には、道教の信奉者が王侯や隠者を問わず、その信条の教えに従ってさまざまな興味深い結果をもたらした例がたくさんある。 この物語には、教訓や娯楽がないわけではない。 逸話、寓話、格言に富むだろう。 私たちは、生きたことがないために決して死ぬことのなかった愉快な皇帝と語り合いたい。 私たちはリーツェと一緒に風に乗り、私たち自身が風であるために風がまったく静かであることに気づくかもしれないし、天と地のどちらにも支配されないために天と地の間に生きたホアン・ホーの老人と一緒に宙に住むかもしれない。 現在の中国で見られる道教に対するグロテスクな謝罪でさえも、他のどの教団にも見られない豊かなイメージを楽しむことができる。
しかし、道教のアジア生活への最大の貢献は美学の領域であった。 中国の歴史家は常に道教を「この世に存在する芸術」と呼んできた。 神が自然と出会い、昨日と明日が分かれるのは、私たちの中なのだ。 現在とは移動する無限であり、相対の正当な領域である。 相対性は調整を求め、調整は芸術である。 人生の芸術は、周囲の環境に絶えず再調整することにある。 道教はありのままの日常を受け入れ、儒教や仏教とは異なり、苦悩と心配に満ちたこの世に美を見出そうとする。 宋の三酢飲の寓話は、三つの教義の傾向を見事に説明している。 釈迦牟尼、孔子、老子の三人はかつて、生命の象徴である酢の入った壺の前に立ち、それぞれ指を浸して酢を味わった。 実直な孔子はそれを酸っぱいと感じ、ブッダは苦いと言い、老子は甘いと発音した。
道家は、誰もが統一性を保てば、人生の喜劇はもっと面白くなると主張した。 自分の立場を失うことなく、物事の割合を保ち、他の人に場所を譲ることが、俗世のドラマで成功する秘訣である。 私たちは自分の役割を適切に演じるために、劇全体を知らなければならない。 ラオッツェはこのことを、彼の好きな「真空」の比喩で説明している。 彼は、真空の中にこそ真に本質的なものがあると主張した。 例えば、部屋の実態は、屋根や壁そのものではなく、屋根と壁に囲まれた空虚な空間にある。 水差しの有用性は、水差しの形や材質ではなく、水を入れるかもしれない空虚さに宿っていた。 真空はすべてを含んでいるからこそ、すべての力を発揮する。 真空の中だけで運動が可能になる。 自分自身を、他者が自由に入り込むことのできる真空状態にすることができる者は、あらゆる状況の支配者となる。 全体は常に部分を支配することができる。
こうした道家の考え方は、フェンシングやレスリングに至るまで、私たちのあらゆる行動理論に大きな影響を与えてきた。 日本の護身術である柔術の名前は、『桃庭記』の一節に由来する。 柔術では、無抵抗、真空状態によって敵の力を引き出し、使い果たそうとする一方で、最後の闘いでの勝利のために自分の力を温存する。 芸術においても、同じ原理の重要性が暗示の価値によって示されている。 何かを語らないことで、見る者はアイデアを完成させるチャンスを与えられ、こうして偉大な傑作は、実際にその一部になったかのように思えるまで、抗いがたくあなたの注意を釘付けにする。 空虚な空間があるからこそ、そこに自分が入り込み、自分の美的感情を完全に満たすことができる。
生きる術を会得した者は、道家の「真の人」である。 彼は誕生と同時に夢の世界に入り、死によって現実に目覚める。 彼は自分の明るさを和らげ、他人の曖昧さの中に自分を溶け込ませる。 彼は "冬の小川を渡る人のように消極的で、隣人を恐れる人のように躊躇し、客のように敬意を払い、溶けかけた氷のように震え、まだ彫られていない木片のように控えめで、谷のように空虚で、荒れた水のように形がない"。 彼にとって人生の3つの宝石とは、「憐れみ」「経済」「慎み」であった。
ここで禅宗に目を向けると、道教の教えを重視していることがわかるだろう。 禅とは、瞑想を意味するサンスクリット語のディヤーナから派生した名前である。 禅の教えは道教の教えを重視しており、瞑想によって至高の自己実現に到達できると主張している。 瞑想は、成仏するための6つの方法のひとつであり、禅宗では、釈迦牟尼が晩年の教えの中でこの方法を特に強調し、その規則を高弟の迦葉に伝えたと断言している。 彼らの伝統によれば、禅の最初の家長であるカシヤパはアナンダに秘伝を授け、アナンダはそれを歴代の家長に伝え、28代目の菩提ダルマに到達した。 菩提達磨は6世紀前半に中国北部に渡り、中国禅の最初の家長となった。 これらの家長の歴史とその教義については不明な点が多い。 その哲学的な側面において、初期の禅は、一方ではナーガールジュナのインド否定論と、他方ではサンチャラチャリヤによって定式化されたグナン哲学と親和性があるように思われる。 現在私たちが知っているような禅の最初の教えは、中国南方禅の創始者である中国第6代家長イェノー(637-713)に帰せられる。 禅を天界生活に生きた影響を与えた偉大な芭蕉(788年没)がその後に続いている。 芭蕉の弟子である比丘女(719-814)は、最初に禅寺を設立し、儀礼と政務の規則を定めた。 芭蕉の時代以降の禅宗の議論では、ヤンツェ・キアン思想の戯れによって、かつてのインド観念論とは対照的な土着の思想様式が流入している。 宗派のプライドがどのように主張しようとも、南禅が老子や道家の対話派の教えと類似していることに感銘を受けずにはいられない。 擇木道』にはすでに、自己集中の重要性と、禅の瞑想の実践に不可欠な呼吸を正しく整える必要性についての言及が見られる。 老子』の最も優れた解説書のいくつかは、禅学者によって書かれている。
禅は道教と同様、相対性の崇拝である。 ある老師は、禅を南天の北極星を感じる術であると定義している。 真理は対立するものを理解することによってのみ到達できる。 繰り返しになるが、禅は道教と同様、個人主義を強く主張している。 私たち自身の心の働きに関わること以外は、何も現実ではない。 第六祖の円応は、あるとき二人の僧が風になびく塔の旗を見ていた。 ある人は「動くのは風だ」と言い、ある人は「動くのは旗だ」と言った。しかし円生は二人に、本当の動きは風でも旗でもなく、自分の心の中にあるものだと説明した。 比丘女(ひゃくじょう)が弟子と森を歩いていたとき、一羽の野ウサギが二人に近づくと慌てて飛び去った。 「なぜうさぎはあなたから離れて飛ぶのですか? 「彼は私を恐れているのです」。 「いや、それはお前たちに殺人の本能があるからだ」。 この対話は、道士である宗師(チャウンツェ)の対話を思い起こさせる。 ある日、宗師は友人と川のほとりを歩いていた。 「魚たちが水の中でどんなに楽しんでいることか。 友人はこう言った: 「あなたは魚ではありません。どうして魚が楽しんでいることがわかるのですか? 「どうして私が魚たちが楽しんでいることを知らないことを知っているのですか」。
道教が儒教と対立したように、禅はしばしば正統仏教の戒律と対立した。 禅の超越的な洞察力にとって、言葉は思考のお荷物に過ぎず、仏教経典の全貌は個人的な思索の解説に過ぎなかった。 禅の信奉者たちは、物事の内面との直接的な交わりを目指し、外見上の付属物は真理を明確に認識するための障害としか考えていなかった。 禅宗が古典的な仏教学派の精巧な色彩の絵画よりも白黒のスケッチを好むようになったのは、このような抽象的なものを愛したからである。 禅の中には、イメージや象徴を通してではなく、自分自身の中に仏陀を認識しようとした結果、図像破壊的になった者さえいた。 ある冬の日、焚き火をするために木彫りの仏像を壊してしまったタンカウォショがいる。 「なんという冒涜だ!」恐怖に慄いた傍観者は言った。 「私は灰の中からシャリーを取り出したいのです」と禅は穏やかに言い返した。 「しかし、この像からシャリー像を得ることはできないでしょう!」と怒りの反論をすると、短歌はこう答えた。 そして、焚き火で身を暖めようとした。
東洋思想における禅の特別な貢献は、日常的なものが精神的なものと同等の重要性を持つという認識であった。 物事の大いなる関係において、小と大の区別はなく、一個の原子は宇宙と同等の可能性を持っているとした。 完全を求める探求者は、内なる光の反射を自らの生活の中に発見しなければならない。 禅寺の組織は、この観点から非常に重要であった。 不思議なことに、修行僧には軽い仕事が任され、最も尊敬される上級の修行僧には、より厄介で雑用的な仕事が任された。 そのような奉仕は禅の規律の一部であり、どんな小さな行為も絶対に完璧に行わなければならない。 こうして、庭の草取りをしながら、カブを切りながら、あるいはお茶を出しながら、多くの重みのある議論が続いた。 茶道の理想全体は、人生の些細な出来事の中に偉大さを見出そうとするこの禅の観念の結果である。 道教は美的理想の基礎を提供し、禅はそれを実践的なものにしたのである。
〜
〜
IV.茶室 ←次は下記〈リンク〉で紹介
〜
〜〜
【参考】
【青空文庫】「茶の本」(The Book of Tea) 英文著者: 岡倉覚三, 翻訳: 村岡博
URL> https://www.aozora.gr.jp/cards/000238/card1276.html

第三章 道教と禅道 先頭ページ

第三章 道教と禅道 最終ページ
〈リンク①〉
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」その4【IV. The Tea-Room】
〈リンク②〉
【Project_Gutenberg_200im】「THE BOOK OF TEA」By Kakuzo Okakura 【Contents】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
