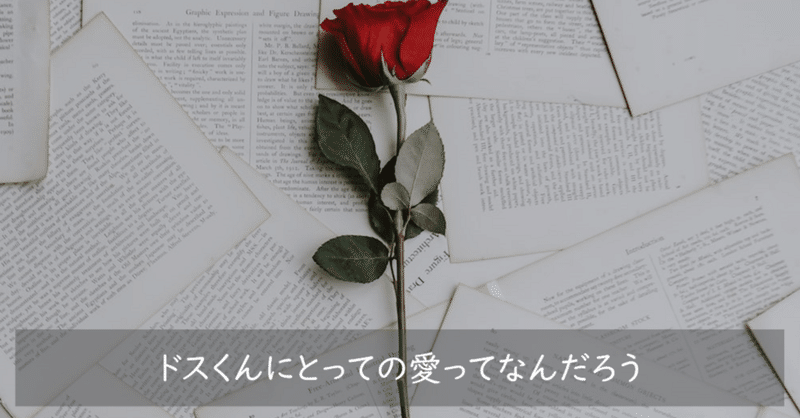
ドスくんにとっての愛ってなんだろう(お題箱から)
※この記事は文豪ストレイドッグスの考察です。
※お題箱に頂いたお題への返信です。
頂いたお題はこちら:
ものあしさん、はじめまして。いつも考察楽しく読ませていただいています。
何事にも終わりは必ずやってくる、ということで、ドスくんの今後について思いを馳せている日々なのですが、その点に関して少しご意見お聞きしたいなと思い質問送らせていただきました。
彼が逮捕された時どうなるかというのは明かされていますが(ムルソー行き)、それ以外で彼が迎える最後といえば、それは文字通りの「最期」なのか、良くて行方を晦ますのか、めちゃくちゃどハッピーエンドをもぎ取って味方になるのかの三択かなと個人的には思っています。
そこでふと気になったのが、ドスくんが終わりに至るまで(撃破されるまで)の彼の心情の変化についてです。
以下、以前ものあしさんが、吸血鬼に関する考察を拝見して思ったことです。
文ストで吸血鬼といえばブラムですが、ドスくんも「吸血鬼のような」と表現されていますよね。そして原作『ドラキュラ』ではラブロマンス要素はあまり見て取れませんが、文ストでは吸血鬼(=ブラム)に与えられたテーマとして、「愛」があると個人的に思っています。
「愛」とは人間が持ちうる刹那的な感情の一つではありますが、作中ではブラムによってその永遠性が示唆され、「愛」という感情が人間の感情の中でも一際大きな激情であることが示されていると感じました。
そこでこの「愛」が、ドスくんを崩すキーになるのではないかなという考えが浮かびまして。
吸血鬼に与えられたテーマが「愛」なら、そう例えられたドスくんもそれを準えることができるのではないでしょうか。彼は独特の(キリスト教的西洋思想が基盤となった)価値観のもと「愛」という感情を持っていますが、もしこの「愛」が彼の中で変化していったとしたら?
ものあしさんが以前、「ドスくんの暴走が止まるとしたら「少女の純真さ」、「良心の呵責」がキーになるのでは」とおっしゃっていましたが、ドスくんが心情を変化させる可能性があるとして、そこに「良心の呵責」があるのであれば、「愛」の基準が彼の中で変動した結果そこに至るという可能性はあるのかな、と個人的に考えたりしまして。心情の変化とはなかなかに抽象的で流動的かつ不動の側面も持ち合わせているので難しいのですが、もしお時間ありましたら、ドスくんの中で起こりうる心情変化について、ものあしさんのご意見お聞かせいただけたらと思います。
やばいやばい。ドスくんの最期もうやってきちゃったんですけど!どうでしょう?お題主様的にあの最期はどうでしたでしょう?救いもなく、優位性もなく、一見すると無様な完敗でした。
しかし最期のあの言葉は、神の僕という自負のあったドスくんらしい言葉でもありましたね。
キリストは死後3日で復活を遂げたことから、いまのところドスくんも復活する説が定着している感じでしょうか?
だいたい「異能力バトル漫画」で、ラスボスに近い人が異能力で死なずにヘリの爆発で死ぬっていうのは、個人的にはナシだろと思ってるので、何かしらの形でドスくんの面影というのは今後も作中に出てくるのではないかなと期待しています。
ということで、もう一度違う形の最期があるんじゃない?という希望を持ちながら、「愛」というテーマを中心にして、ドスくんにとっての愛ってなんだろう?というところや愛によってドスくんにどんな変化が起こり得るかを考えてみたいと思います!このようなお題について考える機会が巡ってくるとは思いもしなかったので、本当に素敵なお題を頂いたお題主様に感謝です。
ドスくんと対比させるために、まずはブラムの愛からもう一度確認してみましょう。アニメ60話で、ブラムが思い浮かべた女性が妻ではなく娘ということが発覚しましたので、もともとの「永遠の恋情」というイメージは崩れ、代わりに「家族愛」に近いメッセージ性が付与されたかなと感じます。
映画ドラキュラでは、400年前の妻と瓜二つの女性に出会って恋をする設定でしたが、文ストではそれが娘に置き換わり、400年前の娘と瓜二つの子供に出会う、という設定になったのかなと。
かつての娘を大切にするがごとく、文ちゃんを守り大切にしようとする。父性というのが現時点でのブラムの愛のカタチといえますね。
「永遠の恋情」の方が強烈で衝動的で鋭いインパクトがあった分、60話を経てブラムの愛の感触はだいぶ柔らかくなったかなと感じます。
そうであっても、誰かを大切に想う気持ちが永続している点で、広い意味での愛の永遠性は語られているといってもいいでしょうか。
ここでまず、同じ「吸血鬼」という括りで表現されているブラムとドスくんの間にひとつ決定的な違いが浮かび上がります。
ブラムは妻であろうと娘であろうと「誰か」を想う気持ちや「誰か」のために身を捧げることができる人ですが、ドスくんにとっては「誰か」のためという概念が今のところ存在していないように見えます。
自分か、もしくは人類か、そのどちらかしか見えていない。ドスくんの愛のカタチは漠然とした人類愛ではないだろうか、と個人的には感じています。
ではドスくんにとって女性との出会いをきっかけに愛のカタチが変わっていく可能性はあるのかどうか、史実の方から少し探ってみましょう。
■ドストエフスキー作品の愛のカタチは死ぬほど歪んでいる
ドストエフスキー作品の男女関係ってほんとに引くぐらい歪んでましてですね…特に主人公まわりなんですが、女性への愛をこじらせているというか…女性が原因で破滅していく人が多いのです…それを紹介しますね。
作品のあらすじと顛末も書きますので、これから小説を読むぞ!という方はネタバレにご注意ください。
それとあまり記憶力がよくないため、うろ覚えとなっている部分が多くて、細かいところなど間違ってるかもしれませんがご容赦ください。
①罪と罰
とりあえず一番まともなところから。
罪と罰は一番美しく、女性による救済が描かれている作品です。
「自分は非凡人だから、世界をより良くするために殺人を犯す権利がある」というイカれた思想に憑りつかれた主人公が、老婆を殺し、そのままの勢いで老婆の妹を殺してしまったせいで、犯行後ずっと心の中が乱れる。この主人公の心の乱れを、ソーニャというヒロインが救います。決め台詞は「大地にキスしなさい」
エピローグでは主人公もソーニャへの愛に気づき、二人は一緒に復活を遂げます。ドストエフスキー作品にしては珍しく、美しいラストが待っている。
ソーニャがいなければ主人公は救われなかったことから、女性の愛が主人公の心境に変化をもたらすという点で理想的なカタチと言えるかもしれませんね。
この作品でのソーニャの役割は「大地としての女性」だと言われています。単なる恋愛感情だけでなく、母なる存在の愛を感じて大地と再び繋がることで人間性を回復する。それを体現したのがソーニャという人物でした。ドストエフスキーの描く愛って…深く広くて謎めいているんですよね。決して単一の感情では語らないところが魅力かなと思います。
②悪霊
スタヴローギン(主人公といっていいかな?)も女性によって変化していく人物。この作品では12歳の少女がその中心的な役割を担います。
なんとこのスタヴローギン、12歳の少女を凌辱(レ〇プ)してしまいます。
しかし意外や意外。12歳の少女に抵抗されると思いきや、少女はずいぶんと乗り気なご様子。その姿を見て嫌悪感を感じるものの、とりあえず最後までやりとげる。
翌日以降(確か翌日…)少女は「神様を殺してしまった」と言って沈鬱していきます。スタヴローギンを見るたびに怯えたような、だけど受け入れようとする微笑みを湛えたような複雑な表情を浮かべる。
その後、スタヴローギンは少女が自殺しようとする気配を察知。
少女はまもなく自殺するだろうと確信めいたようなものを抱きながら、自殺をしに行く少女を黙過し、見殺しにします。完全にコトが終わるまで、きっちり35分待つ。そして自殺の現場に死体をのぞきに行く。首を吊ってぶらさがっている少女を目視で確認してOK。
その後、スタヴローギンは神聖なものを見る度に彼女の微笑みが脳裏に浮かんで精神的に追い詰められる。その幻影に耐えられなくなって、最終的にはスタヴローギン自身が首を吊って自殺。これでおしまい、ちゃんちゃん。
これは…だめですね…
③地下室の手記
自意識過剰の主人公がみすぼらしい娼婦に出会います。こいつは可哀想な娼婦だと憐み、そして説教を垂れる。ちょっと話すうちにこの娼婦と自分は似たようなぼろ雑巾同士だと気付き、好きになってしまいます。
だけど俺のほうが賢いし世の中のことをよくわかっている、彼女が俺によって救われて足元にひざまずきながら、愛情で身を震わせることとか妄想し始めます。娼婦に自分の家に来てほしくて彼女を待ちながらも貧乏で乞食のような生活を見られるのが恥ずかしい。
やがてついに娼婦が家に来るが、屈辱と恥ずかしさでいっぱいになり、ヒステリーの発作を起こします。自分の恥辱を覆い隠すために、彼女を侮辱する。俺にとって愛するということは横暴な振る舞いをして精神的に優位に立つことなのだと考えながら、とっとと出ていけと娼婦に言い続け...
そして娼婦がついに部屋を出ていきかけたその時、手にお金を握らせる。だけど娼婦はお金をこっそり机の上に置いてから出ていく。そんなお金は必要ありません、とちょっとばかし主人公より精神性が高いことを見せつけながら。
そうして主人公のメンタルはぐじょぐじょのズタボロになり、その後20年間地下室に引きこもる。
...どういうこと?素人には理解しかねるよ...
④白痴
ドストエフスキーの至高の恋愛小説!白痴!恋愛小説なんだから素敵な結末が待ってるに決まっている。
白痴は三角関係のお話です。主人公のムイシュキンは白痴の男性であり、キリストのように無垢で純粋。
このムイシュキンと女性の取り合いをするのが、ロゴージン。こっちは反キリスト的存在。ストーカーをしたり粘着質に執着してストレートに容赦なく女性を愛するタイプ。
ヒロインはとってもきれいな女性ナスターシャ。
ムイシュキンはこのナスターシャを憐憫によって愛します。可哀想だから、幸せにしたい。
だけどナスターシャはそんなムイシュキンを拒否する。一緒にいると、ムイシュキンの清らかさを汚してしまう、それがこわいからいやだ、他の女と幸せになってくれ、そう言ってムイシュキンのもとから去ろうとする。
そうしてナスターシャはロゴージンのもとに度々逃げる。避難場所としてのロゴージン。そこでは自分の汚らわしさを幾分か紛らわせることができるから、という理由もあってのことでしょうか。
最終的にロゴージンはナスターシャを自分の部屋で殺害します。なぜ殺害したかと言えば、死によって彼女を完璧に支配できるようになるから。強烈な恋情の果てに生死の境を超越する。
その部屋を訪れた恋敵ムイシュキン。殺害されたナスターシャを見て死体に静かに寄り添う。キリストのように清らかな男性だから、ロゴージンめ糞野郎!とか言わない。責めたりせずに一晩をロゴージンの部屋で明かす。
その後ロゴージンは監獄へ、ムイシュキンは白痴の症状がひどくなって色々なことがわからなくなっておしまい。
…なんですかね、この恋愛小説は?
ここからは完全に個人の主観ですが、ドストエフスキーの作品には女性は天使、男性は地上的存在、という構造があるのかもなあと感じています。
女性を起点にして、男性の中のなにかがあぶり出されていく。女性が男性の中の醜さを照らし出す鏡となっているような。
そうしてあぶり出された己の醜さに耐えきれなくなって男性は自ら破滅する、こういう形のものが多い気がしています。
かといって、男性が清らかすぎると、今度は女性側が自身の醜さを反射して耐えられなくなって逃げてしまう、それが白痴だったのかなあと。
女性と男性という単なる性の違い以上に、与えられている象徴的な役割があるような感じもします。天使的な役割の存在と醜い人間として葛藤する役割の存在のふたつの軸で構成されているような?
これらを考えると、ドスくんにとって「天使的な役割」の人物が登場したならば、ドスくんはその人によって己の内面の醜さや過去の悪行を照らし出されて「良心の呵責」などによって自滅していく、そういうのが一番ドストエフスキーとして自然なパターンかなあという感じがやっぱりしてしまいます。
罪と罰のように、大地のような揺るぎない寛大な愛を持つ存在であれば、あるいは救われることもあるのかもしれませんね。
■顔のある人を愛せない
ドスくんの愛について話したいことがまだあと二つあります。
一つは「顔のある人を愛することができない」、もう一つは「隣人愛の克服のためには楽園が必要だ」です。
人類にたいする抽象的な愛とは、ほとんどいつも自己愛に帰結してしまいます。
この鋭い言葉、的を得ているなと思います。ドスくんの人類愛もやっぱり自己愛に帰結してしまっているのではないでしょうか。
ドストエフスキーは「顔のない人(抽象的な「人」という概念)なら愛せるが、顔のある人は愛せない」という人間の特性をカラマーゾフの兄弟の中で書いています。
「僕は一つおまえに白状しなければならないんだよ」とイワンは話しだした、「いったい、どうして自分の隣人を愛することができるのやら、僕にはどうにも合点がいかないんだ。僕の考えでは隣人であればこそ愛することができないところを、遠きものなら愛し得ると思うんだがな。(略)
誰かある一人の人間を愛するためには、その相手に身を隠していてもらわなくちゃだめだ。ちょっとでも顔をのぞけられたら、愛もそれきりおじゃんになってしまうのさ」
「このことはゾシマ長老がよく話しておられましたよ」とアリョーシャが口を入れた、「長老様もやっぱり、人間の顔は愛に経験の浅い多くの人にとっては、時おり愛の障害になると言っておられました。」
顔のある人間を愛せない、というのはなんとなくわかる気がしてしまいます。人間という概念だけで考えたときには、存在そのものが美しいように感じられるけど、特定の誰かの顔を思い浮かべるとそこには認めたくないような醜さが付随してしまって、その途端になんだか自分の中にあった大きな愛情のようなものが消え失せてしまう。
人類はすばらしい、人間は美しい、そういう賛美は実際のところ人間そのものを直視しておらず、自分の思想を賛美しているだけなのだ、ということでしょうかね。
これはなんとも鋭い視点だなあと私はドストエフスキーのこの言葉を見て胸を抉られています。
その観点でいくと、ドスくんが人類に対して愛情を抱いていたとしても、それは実際のところ、自身が持っている思想に酔いしれているだけの自己愛なのだということができるかもしれませんね。
ドストエフスキーは隣人愛の難しさに気づいていたので、これを解決するために楽園が必要だと言っています。
隣人を愛すためには、自我を取り除かなければならない。自我を取り除いて全体と一体になってようやく隣人愛は実現する。全体とひとつになるということは、地上的な存在から脱却して神の国を実現すること。ひとりひとりが天使のような存在に生まれ変わることが必要だ、それだけ隣人愛は難しい、と。
この辺のドストエフスキーの思想は、そのままドスくんにも引き継がれている部分が多くあるのではないかなと思います。
自我というのは原罪によって生まれたので、原罪をすすげばおそらく自我は消える。だからドスくんは自我をなくすために終末をもたらそうとしているのかもしれませんね。それもこれも隣人を愛することができない苦しみから脱却するためだったり...と妄想が膨らみます。
ということで、今回のお題の結論はこんな感じです。
・ドスくんは女性によって救われるかもしれないが、それよりも破滅してしまう可能性の方が高い。
・誰かを愛することの難しさを理解しているので、その困難を克服するために終末を実現して神の国をもたらそうとしている可能性がある。
ドストエフスキーはあまりに深すぎて「愛」という一つの部分を切り抜いただけでも語り尽くせないほどの論点がありますね。
とても深いお題でしたので、満足頂ける内容をお答えできたか自信はありませんが、少しでもドスくんの解像度を高めることの一助になっていれたら幸いです。
ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
