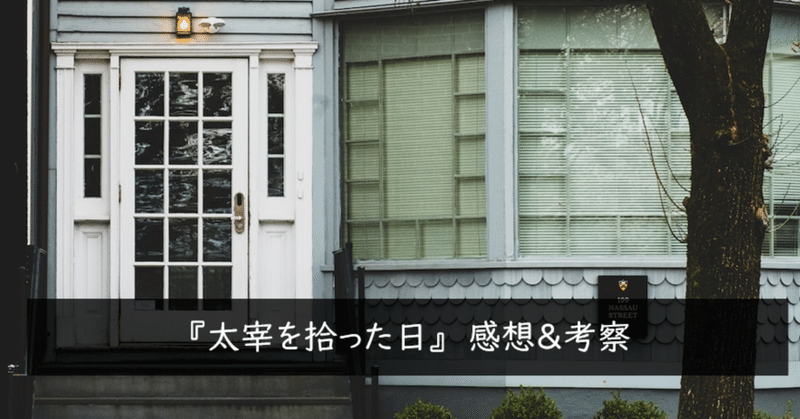
『太宰を拾った日』感想&考察
※この記事は文豪ストレイドッグスの考察です。
※『太宰を拾った日』のネタバレがあります。
■はじめに
発売してから気づけば1週間以上の時が経ちましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。電子派の私は発売日の0時ちょうどに携帯に『太宰を拾った日』が格納されたのを確認し、その後すきま時間にちまちまと読み進め、時折劇場特典版も手に取りつつBEASTもざっくりとおさらいしつつ、だらだらと時間をかけて記事を執筆しました。時間をかけてしまったことによってとても長くなってしまいましたので予めお詫び申し上げます。
■銀幕BEASTとの「適切なお付き合い」
今回改めて読んで思ったこと。この本は銀幕BEASTと距離を近づければ近づけるほど破壊力が増す。遠ざけることによって軽傷に抑えることができる。
文庫本としての『太宰を拾った日』はこれ単体で独立していますが、もともとは劇場特典として配布されたもの。
当時自分があれほど苦しんだ理由は、銀幕BEASTの内容がこの特典によって補強され解像度が上がり、劇場で漏らした嗚咽がそこに加わったことでわけのわからない感情の濁流となって発狂していたからだということを思い出しました。
銀幕BEASTと太宰を拾った日。この二つは決して接近させてはならない。
銀幕B、Side-B、Side-A。三者が不可解な負の連鎖を引き起こし、三者ともがマイナス方向にひどく引っ張られて重篤な事故を巻き起こしてしまう。ゆえに、己の情緒を守りたくば徹底的に自衛すべし。刺激が足りない場合にのみ、三者を同時に積極摂取すべし。
■人格とは「便宜的な仮説」
私が太宰を拾った日を読むときにいつもつまずいて苦しんでしまう箇所、それは太宰という人間の人格の落差です。
B軸の太宰の演技の度合いが一向に掴めず、本当に人格が変わったのか、それとも人格が変わったように見せかけているだけなのか、その点がとても気になっていました。
そんな私の苦悩に光を射してくれる一節を今回読み込んでいて発見。
我々の人格、魂は、痛みや恐怖という原始的本能の上に立脚した、便宜的で不安定な仮説にすぎない
Side-Bで太宰はこの言葉を2度繰り返す。
さっと読んだだけではすっと意味が頭に入ってこないので今まで素通りしていた言葉ですが、この言葉を繰り返すからには、もしかしたら太宰自身も含めてあらゆる人格は「便宜的で不安定な仮説」であると、太宰は言いたかったのかもしれない。
人格とは便宜的で不安定な仮説。これは一体どういう意味なのでしょう。
痛みや恐怖という原始的本能が獣なのだとしたら、便宜的仮説の方とは一体?
ここで再び山月記を持ち出さなければならないあたり、文ストの主人公は本当に敦くんなんだなあと実感せずにはいられないのですが、山月記の一節を参照したいと思います。
人間は誰でも猛獣使であり、その猛獣に当るのが、各人の性情だという。己の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。
性情あるいは感情の部分が猛獣であるなら、猛獣の上に立脚した仮説の部分には猛獣使いがいるのではないか。人格とは、猛獣使いである。そして、BEASTというのは、猛獣使いが猛獣を調教する代わりにひたすら追いかけた世界であり、自由の身となった猛獣たちが縦横無尽に駆け回った世界。
もしかしてそういうことだったりしないだろうか。
では、不安定というのはどういうことなのでしょう。
自動的に生起する感情を前にしたときに、便宜的仮説である猛獣使いはどんな可能性を持っているのか。
おそらくありとあらゆる可能性を持ち、完全な自由にさらされている。
感情が生起したというだけではまだまっさらな状態。
感情を起点に正義の像を結ぶのか、それとも感情を起点に悪の像を結ぶのか、猛獣を抑え込むのか、それとも野放しにするのか、それらは感情が決めるのではなく、獣に直面した猛獣使い、つまり人格が決めるもの。
力強く駆け回る獣とは裏腹に、猛獣使いの態度は変幻自在であるために朧気で変容しやすいということだろうか。
では獣の上に立脚する仮説とは?
そもそも、獣である感情は言葉を持たない。
感情とは考えて創りだすものではなくどこかから自然とやってくる現象。感じている感情を言葉で表すことが難しいように、感情とはいわゆる「語りえぬもの」に属しているのでしょう。
阻止することもできなければ別の感情に置き換えることもできない。自然の摂理の一部のように降りかかって来たり突き上げて来たり、生体に組み込まれた本能的な現象として自動的に生起する。
だが、感情が認識された途端にその感情は猛獣使いの手に渡り、言葉の領域に属するものとなる。説明され、思考され始める。「これはどういう感情でどういう理由で生じ、私はこの感情にどう影響され、それによりこう考えこう行動する」と。
猛獣使いの調教のもとでは、言葉によって連なった情報が檻となり鞭となって、感情に対する反応と行動を決め、それが次第に人格として形成されていくのではないか。猛獣使いは言葉の使い手であるともいえる。
人格というものが、猛獣使いから放たれる言葉によって作られているのなら、人格とは文字の羅列であり、それは小説の文字とあまり差異がない。表層情報であり、文字列であるが故に入れ替え可能な便宜的で不安定な仮説。ABCからBCAに容易に変換することができるもの。
カフカ先生いわく太宰はドーナツのように中心が空洞であるということだけれども、人格が仮説でしかありえないことを知っているが故の空洞だったりするのかもしれない。
太宰にとってはすべての人格が同じ程度の軽さを持ち、同じように薄っぺらいということもあり得るのでしょう。
ABCだろうがBCAだろうがCBAだろうが、どれも自分でありどれも自分でない。どれを選択するかは常に自由であり、形の固まった人格などそもそも存在しない。
人格とは流動的なものであり、選択式のもの。
A軸からB軸への変化は、言葉の羅列がひょんなことで変わってしまっただけのもの。というより、敢えて理性の柵を取り払って獣を野放しにしてみたのがB軸であり、B軸の人格もA軸の人格も、太宰にとってはどちらも不安定な仮説にすぎず、どちらも同程度に便宜的、すなわち「一時的な間に合わせ」で「その場しのぎ」にこしらえた「張りぼての工作物」だということなのかもしれません。
しかしそんな便宜的仮説を立脚させている痛みや恐怖という原始的本能は決して仮説ではなく、より実在に近くリアルで不動で、生物としての人間の根源にあるもののようです。
猛獣使いが猛獣を野放しにした世界で、敦は恐怖心と罪悪感を走らせ、芥川は憎しみと復讐心を走らせましたが、太宰が走らせたものはなんだったのでしょうか。
■太宰は「痛みの専門家」
痛みはいい。痛みは生きている証拠だ。もっといい事もある。強い痛みは人間を支配し、考えを変えさせ、時として人格すら吹き飛ばしてしまう。
この言葉は、太宰が拷問をしているときに脅すようにして言った言葉ですが、B軸のキャラたちの言葉は、自分が発した言葉が自分に返ってくるという反射現象がちょいちょい見られるように思うので、上の言葉も太宰自身のことを言っている側面が多少あるのかもと感じています。
痛みを肯定する太宰というのは個人的にはなかなかインパクトがあり、ずっと真意を測りかねていました。「痛いのは嫌いだ」と言った本編の太宰が道化だったのか。それとも「痛みはいい」と言う気狂いめいた太宰がただ単にとち狂っているのか。
A軸の人格もB軸の人格も同程度に軽く薄っぺらいと考察してきましたので、ここではどちらも同程度に偽りであり同程度に本当であるということにしておきたいと思います。
嫌いと思うのか、いいと感じるのか、それらは便宜的なものとして自由に選択可能であるにせよ、太宰を苛む痛みそのものは、便宜的仮説ではないものとして確実に太宰の中に存在しているはずです。むしろ痛み以外、実際のところ確固たるものはなにも太宰の中にはないのかもしれません。
太宰を取り巻く痛みはわかっている範囲でおおまかにわけると二つあるかなと思っています。
一つが、織田を喪失した痛み。
もう一つが、生きる行為そのものから生じる痛み。
本編の太宰にとって、どの痛みがどれほど太宰を蝕んでいるのかは分厚い便宜的仮説の膜によって蓋をされて見えなくなっているわけですが、その蓋を開けてみたら、織田を喪失した痛みがあらゆる痛みの中で圧倒的に強かった、その結果のBEASTだったということなのでしょうか。
恐怖をかき消すものは、やはり恐怖だ。あの日から君は、許容量を超えた恐怖を感じ続けている。一秒も休まることなく……そのことが、別の恐怖に対する反応を奪ってしまったんだ。
太宰はBEASTで敦に対してこの言葉を投げかけますが、この言葉も反射して太宰に返ってくる言葉だと言えます。
織田の喪失を見た日以降、B軸の太宰は許容量を超えた痛みを感じ続け、そのことが別の痛みに対する反応を奪ってしまった。
そうして太宰は、自分を一番傷つけた「喪失による痛み」を排除するためにあらゆる手段を尽くした。そのことによって別の痛みが生じようとも、痛みの強度は喪失の痛みに勝ることがない故に、痛みの感覚は次第に麻痺し、いとも容易く他者を傷つけることができるようになった。
太宰の獣は、己の痛みを処理するためだけの独裁政権という形でBEAST世界を走ったように思います。
■BEAST太宰と「生きること」
B軸の太宰には生存に対する苦悩がないようです。
なぜ生きるのか、なぜ死ぬのか、それらを問わずとも明確になっている。あるいは生存による痛みが感覚の麻痺によって感じられなくなったことで、苦悩しなくなったとも言えます。
なんとなくですが、B軸の太宰は生きることに対するハードルが低いようにも見える。生きるという行為への没入感がある状態。銀幕BEASTの累生くんの真剣な眼差しがよく脳裡に浮かびます。
不確実性の中でゆらゆらと浮いている本編とは違ってBEASTは確実さで埋め尽くされた世界。この宇宙で最も崇高な事象である確率の遊戯が存在しない世界。出会いの奇跡、偶然の連なりから起こる感動が根こそぎ排除され、見え透いた行軍で埋め尽くされている。
フィクションの中にいて、そこがフィクションであることを知ってしまった男が、世界をフィクションとして塗りたくってしまったのだとも言えるでしょうか。
そもそも太宰というのは「生」を軽視する人間のはずでした。
常に軽やかに死の匂いを漂わせ、死に限りなく近い場所に住む男。
生に執着する人間を悟りすまして冷眼視している、そういう男のはずでした。
それなのに、そんな太宰が価値基準を180度回転させて、軽視しているはずの生に最もこだわる。かけがえのない瞬間の共有よりも、誰かの生を、単なる生を、重視する。とても不思議な感覚です。
これも便宜的で不安定な仮説がもたらす七変化のひとつなのでしょうか。
太宰にとって、友が生きている間に感じた痛みは「生きることによる痛み」が中心だったようですが、友を失ってからは、「喪失の痛み」がそれを凌駕してしまい、過去のそのほかの痛みをすべてかき消してしまった。そういうことであれば、太宰にとっては生死に対する価値基準うんぬんよりも、友人という存在のほうがはるかに価値が重いものであり、友人が大切に思うもの以外、すべての価値基準が無に帰した状態になるというのは、当然といえば当然なのかもしれません。
■BEAST太宰と「愛すること」
「あなたには生きていてほしい。私の命や他のあらゆる犠牲を捧げてでも」というのは母性愛に近いような無条件の愛だと思います。
B軸の世界で太宰の理性を取り除いた結果、痛みとともにそこにあったのが特定の誰かへの愛情だったというのは、なかなか興味深いなと感じます。
悲しみでも怒りでも苦しみでも恐怖でもなく、愛情。それも無条件の愛という人間が持ちうる感情の中で最も高尚にして清いもの。
普段太宰さんはこの愛情をどこに隠しこんでいるのだろうと気になってしまいます。本編の太宰も理性をひょいっとひとぬぐいして取り払ってみたら、最も目立つところに愛という感情が鎮座しているのでしょうか。
だけど愛情さえも解放することを恐れ、それを押さえ込んでいるのでしょうか。愛にさえも傷ついてしまうから、身体を包帯で巻いて守るように愛情も見えない包帯でぐるぐる巻いて隠してしまう。
おそらく私が愛情と呼んだものは、惜しむ感情から発生しているものなのでしょう。惜しむあまり、それが煮詰まって、すべてを尽くそうとするような無条件の愛へと昇華されていくのかもしれません。
風の妖精にふさわしくカラッとした風が吹きつけている本編とは異なり、どこか湿気に満ちているB軸の太宰。出口のない、吹き飛んでいく場所を持たずに充満し停滞する湿度が、世界を陽光から隠し、雨粒を結んで大地を濡らしていくようです。そんな湿り気のある友への愛情が、太宰の飼うもう一匹の獣だったと感じます。
■織田と「救われること」
救いとは呪い。
救われた人はそれを契機に否応なしに変わることを宿命づけられる。
たとえ変わりたいと思っていなかったとしても。
出会う前と出会う後、知る前と知る後とでは同じ自分でいることができず、心の細胞が気づけばひとつひとつ入れ替わってしまう。
救いとは、変化という呪い。
もとの自分のままではいられなくなる呪い。
他人によって自己を創り変えられていく呪い。
他人の掌の中を生きさせられる呪い。
本編の太宰は織田の遺言の中を生きている。
しかし織田も織田で、夏目の言葉の中を生きたとも言えます。
夏目が書いた本によって脳細胞が入れ替わり、何かのスイッチを点されてしまった。
もし夏目が織田を救わなければ、織田は小説家になろうとする夢なんぞ持たずに済んでいたかもしれない。孤児を養うなんてこともせず、孤児たちを失うことの壮絶なる痛みを経験することもなく、感情を伴わない殺し屋として淡々と生き淡々と死んでいったはず。その方が、よっぽど楽な人生だったかもしれません。
夏目は織田を救ったのでしょうか。それとも過酷な道へと突き落としたのでしょうか。孤児を失った織田のあの慟哭は、本当に織田が経験しなければならなかったものなのでしょうか。
あの慟哭のある人生と、あの慟哭のない人生と、どちらかを選べと言われたら、織田は一体どちらを選ぶだろう。
A軸の慟哭か、B軸の友人の犠牲か、あるいは小説家という夢を持ったことがそもそも間違いだったのだと考えて、未だ存在しないC軸を作って一生誰とも繋がりを持たず殺し屋として生き、殺し屋として死ぬことを選ぶでしょうか。
B軸を考えるとき、いつも私が感じるのは「これは太宰が望んだ物語で、織田が望んだ物語ではない。」ということなのですが、だからといって織田がどの世界を望むのかは、いくら考えても答えが見つかりません。
手間はかからなかったが、人間を相手にしているという気がしなかった。感謝の言葉が聞けるとは思っていなかったし、暴れたり不満を云われたりするよりはずっと楽だったが、終始落ちつかない気分にさせられた。
暴れたり不満を云われたりするよりは織田にとって楽だったSide-B。Side-Aで不満を云われ注文をつけられ続けている自分を見て、織田はA軸の自分を憐れんだりするのでしょうかね。面倒なことになるとわかっていても、なぜか自ずから棘の道を歩んでしまうのが織田作ならば、頭では「間違った選択だ」とわかっていたとしても、ついつい本編世界を選び取ってしまう織田作というのも目に浮かびます。
ところで、Side-Aには暇を持て余した太宰に織田が夏目先生の三部作を読み聞かせてあげるシーンがありますが、織田にとっては人生の転機となった小説も、違う人にとっては波風立たない退屈な話にしかなりえないというのは面白い描写だったなと感じます。
夏目先生の本そのものに何かのウルトラパワーがあったというわけではなく、シンプルに、そこに書かれた物語が織田の中で化学反応を引き起こしただけのことだったと思うと、運命のようなものと表現される「人間と本との出会い」は、文スト世界にも現実の世界にも共通する神秘的な現象だなと感じます。
■あとがきと「感情」それから「物語」
さて、ここからは小説の内容とはあまり関係のない話。
カフカ先生のあとがきを読んで、感じたこと、思い出したことを書き残しておこうと思います。
考察ではなく、どちらかというと私の個人的な話になりますので、ご興味ある方だけどうぞ。
BEASTが感情にフォーカスを当てた話である中で、カフカ先生のあとがきもやはり感情にフォーカスを当てたものになっていて、感情とはなんだろうということを年末年始に考えておりました。特に、感情と物語の関係性について。
そしてずっと忘れていたあることを思い出したのです。
私、以前にフィクションを敬遠していた時期があるのですが、その理由がまさしく感情でした。
昔はこう考えていたんです。
私が自分の感情だと思っているものは、人間なら普遍的に持つ「Aを与えられたらBが出る」という条件反射に過ぎず、物語とはその条件反射をうまく利用しているもの。感情の奴隷である人間はいとも簡単に物語の奴隷になってしまう。
物語を観て悲しんでいる私は、私ではなく、単なるホモサピエンスの一個体と化している。ホモサピエンスの一個体として、精神的な麻薬を投与され、操作され、受動的にきっかけを摂取し、反射的に悲しんでいるだけだ、と。
だから作り物の架空の世界の中で、作り手の狙いどおりに操られて生まれる感情は偽物の感情である。そんな偽物の感情を生起させて一体なんになる?こんなことを考えていた偏屈な人間でした。
いまはもう大人になったので、こんな反抗的なことは考えていません。というか、幼少期にはセーラームーンに、思春期にはフルーツバスケットに頭のてっぺんまでどっぷり浸かって影響受けまくってたやつがどの面下げてそんなこと言っとんのじゃボケと今ならひっぱたいてやります。
それに近頃ようやくわかってきたことがあります。
物語には自己を投影する余地がある。当たり前のことなのですが、その真価は最近になるまで全然わかっていませんでした。
物語が自分自身の魂に近ければ近いほど、そして自分を投影する隙間や余白が多ければ多いほど、物語は外部からやってくる他者ではなく、自分の内部で色々なものと複雑に絡み合った自己の一部になっていくらしい。
そのときに感じる感情の動きは、物語の中で生まれて物語が終われば完結する類のものではなく、日常や人生の中に侵食し、自分がもともと持っているナラティブを形成する一部となっていく。ときには自分自身のナラティブが摂取した物語によって書き換わっていくこともある。
自己啓発書によって理性のもとで己を書き換えていくという方法もあるけれど、物語にも同等か、それ以上の効能があると感じています。
物語を経由して変容した自己というのは、自己啓発書によって意識的に変容させた場合と違って、痛みや感情に立脚している分、より強固なものとして自分自身に根を下ろしていくのかもしれません。
自分を映し出す鏡となり自己を客体化させる力を持つ物語、ナラティブを書き換え人格を変容させる力を持つ物語。心理療法のひとつとしてアニメ療法や物語療法というものもあるくらいですので、大切な物語を自分のそばに置きながら生きていくというのはとても価値あることだなあと今は思います。
太古の昔から人は語り部によって語られる物語に夢中になりましたが、獣としての本能と、想像力を持った理性的で社会的な存在というふたつの人間の姿を結い繋ぐ魔法の架け橋、それが物語なのでしょうね。
「実」である獣と「虚」である猛獣使い、不動の本能と変幻自在の理性、これらの対比が鮮やかに際立っているのが、A軸とB軸がふたつ合わさって一つの本の中に存在している『太宰を拾った日』だとも感じます。自分の内面を「感情」と「人格」に分解して考えてみるきっかけを与えてくれる面白い作品でした。
4度も5度も小説を読んでる人が、改めて感想とか書くとこういう新鮮みのないことしか言えなくて真面目くさっててなんかあんまり自分では気に入らないのですが、この辺で終わりにしたいと思います。
お読み頂きありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
