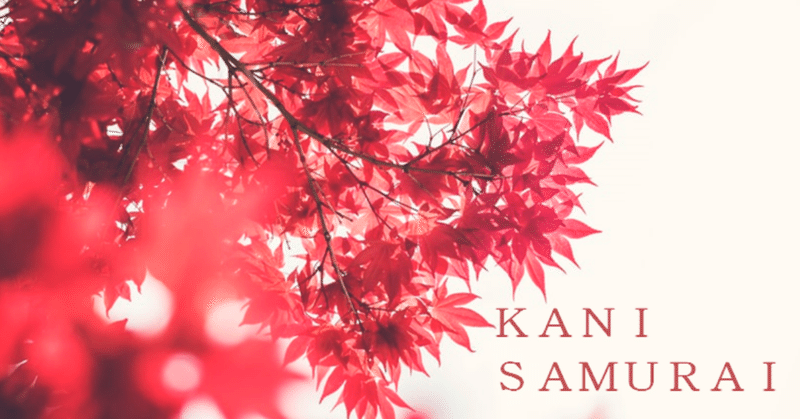
短尾無双アフターマン
「やめてくだせぇ……娘を茹でないでくだせぇ……!」
老海老のあげた悲痛な叫びは、その頭ごと踏み砕かれた。廃城に陣取る荒くれの数、十七つ。巨大な鉗脚を打ち鳴らしてっぽうで死体を撃ち抜く海老のもの。戯れに床を殴り砕つけて周囲をねめつける蝦蛄のもの。山と見紛うばかりの巨体を窄め呪詛を唱える高足のもの。そして頭目と思しき足らばのものは、大きくひび割れた甲羅に無法を表す「訳あり品」の刺青。いずれもがにたにたと嗤い、酒を浴びせられる娘のざまを愉しんでいた。
「よぉく飲ませて酔わせろ。暴れるからな」
「お前の兄貴の茹で汁、熱かったぞ」
「生きたまま茹でられたくらいで、喚いてな。みっともなかったぞ」
「あんまり汁をはね散らかすから、蓋をしてやったわ」
娘は狂ったように喚き返し、酒瓶で殴られた。その触覚の三寸先に転がるのは、赤く茹であがった兄の亡骸。それだけではない。剥がれた殻はうず高く山をなし、切り取られた尾は十を超えている。先日、荒くれの一団により、攫われ、慰み者となった、村の海老たちの成れの果てであった。廃城は本来、万年も昔、殻なし共の学徒の城として築かれたもの。しかし、今やその学び舎に敬意を示すものはなく、教壇もキチン撒き散らす酸鼻に沈むばかり。
「そういえば、ボンボリ。聞いたかあの噂」
頭目の問いかけに、ボンボリと呼ばれた毛のものが親爪をすり合わせた。
「へい。あの〈短尾無双〉が動いているとか」
「大仰な名だ。所詮は我々と同じ蟹。茹でれば赤くなることに変わりあるまいに」
「御尤もで……ガッ!」
ボンボリの息の根を止めたのは、ふんどしに突き立った村人の遺骸の爪である。
「何奴」
先ほどまでの騒ぎが嘘のように城内は静まり、味噌のように濁った殺意がどろりと対流した。その中に悠々と脚を踏み入れる渡りのものが一匹。その甲羅は美しく毛羽立ち、表面に「天下十脚目」「短尾無双」と刻まれている。
【続く】
