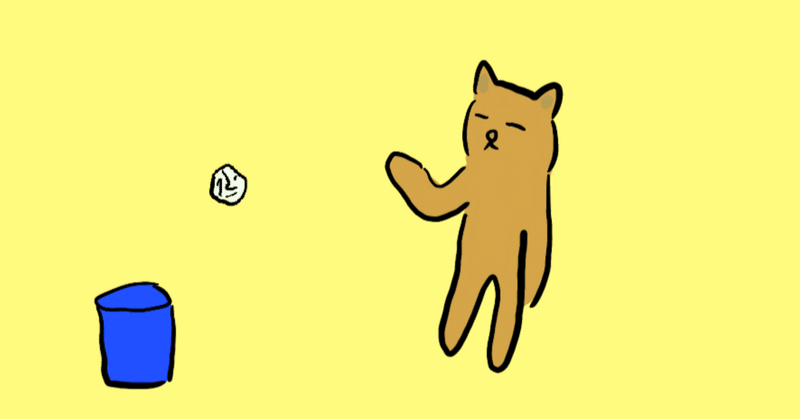
捨てる行き先へ、思いを馳せる。
小学校では、社会科で水道やごみの処理など自分たちの暮らしについて、4年生で学ぶ。その学習の一環としてゴミ処理場へ見学に行く。
回収された大量のゴミはゴミピットと呼ばれる場所に集められ、30m弱もの長いクレーンでゴミを挟み、移動させる。それはさながら巨大UFOキャッチャーのようで、子どもたちを釘付けにした。
その後ゴミは破砕機と呼ばれる処理しやすくするための機械に通される。
その際、金属など固いものが混じっていると粉砕出来ずに、機械を止めなければいけないらしい。
また焼却炉の中に、燃えないものが入ると、場合によっては稼働にさし障りがある。その際は稼動を止めた後、中に入って除くこともあるそうだ。
燃えた後の灰は、埋め立て地へ運ばれる。
しかし埋め立て地も有限であり、未来のことを考えると燃やすゴミは少なければ少ないほど良い。
集められたペットボトルは加工して資源として再利用されるが、加工に不要なラベルや蓋が付いていると手作業で取らなければいけない。
また、汚れたままや液体が入っているペットボトルは資源として再利用することは難しい。
「捨てておしまい、じゃなくてその先にいる人のことも考えてくださいね。」
そう話す、施設の方。
捨てた、その先にいる人。
捨てた、その先のこと。
わたしは考えられていただろうか。
今住んでいる地域は、前にいた地域に比べゴミの分別はかなり緩いと思う。
常時収集BOXに入れられるので、可燃ゴミであれば、曜日ごとに分けて出さなくても良い。ペットボトルをそのまま一緒に捨てているゴミ袋もある。
わたしはペットボトルと他のゴミを分けている。が、同じタイミングで出しているので、結局燃えるゴミとして扱われているのかもしれない。
ラベルと蓋も、いつも外していたかと問われると自信がない。
外でペットボトル飲料を買って空になれば、何の気なしに駅のゴミ箱に捨てていた。
きちんとラベルと蓋を外す。
水ですすぎ、スーパーのペットボトル回収コーナーに入れる。
このひと手間がゴミを資源へと変える。
出来ることをきちんとやらねば、と思わされた。
一人一人の行いはささやかだ。
しかし小さなひと手間がたくさん集まると、大きく違ってくるかもしれない。
「捨てる、その先にいる人」のことを考え、行動することが、人そして自然を守ることに繋がってゆく。
子どもの学習のための社会見学が、大人であるわたしにとっても、大切な1日になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
