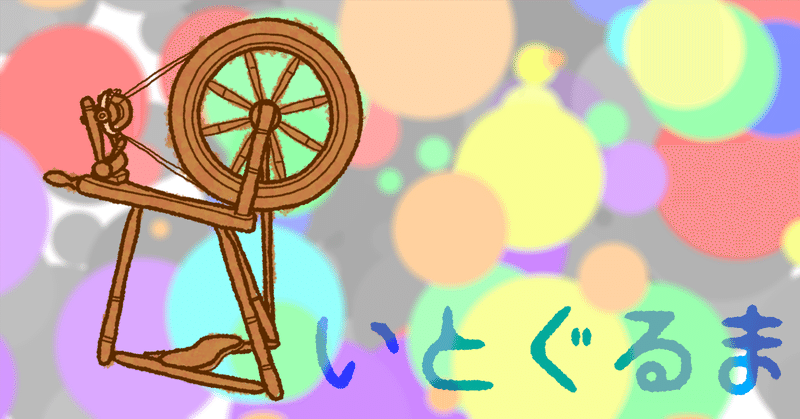
【創作小説】『いとぐるま』第6話
コロナは幸いにも陰性だった。
風邪の症状も、1番ひどいところからは脱したらしかった。
熱を何度か測ってみると、平均して37℃台後半というところで、1番しんどい39℃台は抜け出したようだった。頭痛とめまいもかなり落ち着いて、それに伴って吐き気もあまりしなくなった。
だいたいの症状は落ち着いてきたのかもしれなかったけど、わたしにはその実感がなかった。
身体が、いつまで経っても、だるくて重い。そして、頭痛はもうだいぶ収まってきたのに、頭が重いような感じがして、何も考えられない。
窓もカーテンも閉めきった部屋で横たわるわたしは、カーテンの隙間から漏れる光で、いまがたぶん日中なのだろうということは分かった。
何時間寝て、いまが何時なのかにも無頓着。ずっと寝ていて、川上さんが持ってきてくれた食料や飲み物も、ほとんど手つかず。
頭の中にもやがかかったような感じがするし、身体も鉛のようなので、そもそもベッドから起き上がれる気がしない。
コロナの検査をなんとかやったきり、またコテンと寝そべってしまったわたしは、川上さんに連絡しないといけないのを思い出して、携帯を探した。そしてメッセージアプリを開いて、指先をなんとか動かして文字を打ち込んだ。
川上さん
コロナ陰性でした
熱は少し下がったし頭痛とかもかなりよくなったんですけど、倦怠感がひどくて
ここまで打ち込んだわたしは、最後のフレーズとその前の接続詞を消して、また書き直した。
川上さん
コロナ陰性でした
熱は少し下がったし頭痛とかもかなりよくなりました
まだ本調子じゃないですがなんとか回復してきてるみたいなので、もう少し休みます。迷惑かけてすみません
文章の推敲をするところまではこれ以上頭が回らなくて、そのまま送信ボタンを押した。
身体のだるさがひどいことを伝えたら、またいらぬ心配をかけてしまう。結局、川上さんには言い出せなかった。
目覚まし時計を見ると、もうすぐ11時という頃だった。外は晴れて暑いのか、部屋の中の温度も上がってきているらしい。ヨロヨロ立ち上がって冷房のスイッチを入れて、またベッドに横たわる。まるで、重病人みたいな気分だ。
このまま起き上がれなくなって、この部屋の外に出ることもないまま、わたしは死んでいくんだろうか。自分では寝たと思ったはずが、ほんとはそのまま死んじゃったりして。がんばってないわたしは、そのまま地獄に堕ちるんだろうな…と、死んでしまうことばかりが頭をよぎる。何も考えられない状態なのに、こういうことは普通に頭の中に浮かんでくる。気分が滅入ってしまったわたしは部屋に背を向けて、壁の方を向いて体を丸めた。
枕の隣に、羊くん……ムームーを寝かせたままになっていた。わたしはあまり寝相がよくないけど、ムームーは見たところわたしの寝相の被害は受けていないみたいだった。
「ムームー。なんかしんどいのが治らないよ。なんでかな…」
ムームーは表情を変えない。でも、キョロっとした目でわたしを見つめながら、わたしの話をちゃんと聴いてくれているように見えた。
「介護の仕事さあ。ハローワークの適職検査でも1番に上がってきてたし、ムームーは知らないと思うけど、わたし小さい頃よつばでボランティアしてたんだ。おじいちゃんおばあちゃん達喜んでくれたし、介護の仕事向いてるのかも、って思った。やりたいレクとかもあったけど…なんか、仕事続ければ続けるほど、どんどん苦しくなってくよ。仕事ができないっていうのはもう周りの人にはバレバレだけど、それを誤魔化そうとして…醜いね、わたしは…」
流れた涙が枕に吸い込まれていく。目の前のムームーが滲む。
「…ねえムームー。もう、今の仕事……辞めた方が、いいのかな。わたし、自信ないよ。このまま続けても…自分が壊れてしまいそうで…こわい」
一呼吸置いて、わたしは続けた。
「わたしさ、最初はね、よつばで自分のパフォーマンスが披露できたらいいな、レクで呼んでもらえて、おじいちゃんおばあちゃんたちに自分の作ったもので喜んでもらえたらいいなって、そう思って川上さんにメッセージしたの。そしたら川上さんすっごく喜んでくれてさ。うち、来ない?って、誘ってくれたんだ。ボランティアしてたことと、ハローワークの適職検査のこともあったから、介護の仕事ならわたしでもうまくやっていけるかも、って思って、少し悩んだけどよつばで働くことにした。でも…まさか、自分がこんなに仕事ができないなんて思ってなかったよ。……どこに行っても、仕事…続かないね、わたし…。働くの、向いてないのかな。生活保護、受けるしかないのかな」
ムームーの輪郭が分からなくなるほど、視界が揺れている。
わたしはムームーの身体を両手でぎゅっと握ると、そのまま自分の胸に当てた。心臓が、1秒に1回くらいのペースでどくんどくんと脈打って、その度にムームーの身体が僅かに揺れた。
「変な話聞かせてごめんね。ほんとはこういう相談、職場の人にできたらいいのにね。でも…きっと皆さんにご迷惑がかかるから。やっぱり言えない。…わたし、いままでも何にも言えないまま、仕事辞めてきちゃったから」
点々としてきた職場のことを、ぼんやりと思い出す。
なんとか大学を出て、なんとか就職。前々からやりたかったエンタメ系の仕事だったけど、激務と職場の文化に馴染めず、トラブルを起こしてしまったりして、結局半年ほど在籍して辞めてしまった。
年単位で休んで、そのあとに見つけた薬局のパートは、いままでの仕事の中では1番続いた方だったけど、それでもたった1年半。職場のとある女性の態度がきつく、それに耐えられなくなって逃げるようにして職場を去った。「困ったことがあったら相談してね」と、たまにやって来る本部の方にも言われていたけど、結局コロナになって、その人たちに面と向かって相談することはほとんどできないままだった。
そうしてまたしばらく休んで、よつばに勤めるようになって…いまのわたしは、27歳。
もういい大人なのに、自分の人生ひとつ自分でまともに決められない。もどかしい。
こんなはずじゃ、なかったのにな。
大きな溜め息をひとつついた。
涙を拭い、鼻をすすって、ムームーの顔を見てみると、わたしの顔を見上げるその目は、少し不安そうな、わたしのことを心配してくれているような、そんな風に、わたしには見えた。
「全然…大丈夫じゃない。でも、どうしたらいいかわかんないの」
わたしはぽつりと呟いた。
もう、以前の職場のように何も言わずに…言えずに、逃げるように辞めるのだけは嫌だった。でも、つらいということも、しんどいから助けてほしいということも、なかなか言い出すことができない。ずっと、同じところでぐるぐるしている。
抜け出したい。抜け出せない。ぐるぐるぐる…。
まためまいがしたような気がして、わたしはぎゅっと目を閉じた。そして、ムームーを胸に抱いたまま、わたしはまた、うとうとと眠りに落ちた。
窓の外で、雀が鳴いている。
窓から光が差し込んでいるのか、目を閉じていても明るいのが分かった。
首元が何故かごわごわする。それに、カーテンを開けた記憶もない。
あれ?と思ったわたしはぱちりと目を開けて、なんとなく壁の方を向いた。
「うわっ!」
ムームーの大きな黒い顔が、わたしの方を向いている。わたしはびっくりして固まってしまった。
ムームーの方はいつものキョロっとした目でこっちを見ていて、どうやらわたしのことを見守ってくれていたらしい。
右腕がわたしの首の方に伸びていた。首元がごわごわしたのは、ムームーが腕枕をしてくれていたからだということが分かった。
「ありがと、ムームー」
わたしが鼻先にそっとキスをすると、ムームーは恥ずかしそうに顔をそらして、空いていた左手でやさしくわたしの頭を撫でてくれた。
わたしはベッドから起き上がった。あれ?なんだか身体が軽い。風邪なんて元から引いてなかったかのようだ。頭も…割とすっきりしているし、熱っぽい感じもない。頭痛もめまいも、どこかへ飛んでいってしまったみたいだ。
ムームーもベッドから起き上がっていた。トントン、と肩を叩かれてわたしが振り向くと、ムームーは床を指さしていた。そこには、見覚えのある濃い灰色の糸が、ねじねじと巻かれて束になっていくつも積み上げられていた。ムームーが初めて紡いだ、あの糸だ。
わたしは糸の束をひとつ拾って、窓から差し込む光の下で、改めてじっくりとその糸を見てみた。
濃い灰色の糸には、やっぱり色んな色の繊維が混じっている。糸の束をぎゅっと握ると、いろんな気持ちが湧き上がってきた。
自分なりの気遣いでやったことが、仕事の効率を上げる上で無用だと言われたときの恥ずかしさ。
1度注意されたことを忘れて同じミスを繰り返して、他のスタッフに溜め息をつかれたときの、恐怖感や情けなさ。
自分の不注意で利用者さんにケガをさせそうになってしまったときの緊張感や不安感…などなど。
ネガティブな気持ちが圧倒的に多いけど、そんな中にも僅かながら、ポジティブな気持ちも混じっている。
自分が主催したレクで利用者さんがたくさん笑ってくれて、ココロの底からホッとした気持ち。
利用者さんの話し相手になって、寂しそうにしていた利用者さんが喜んでくれたときの嬉しい気持ち。
レクで出かけたとき、桜がきれいだねえ、と、感動を利用者さんと共有できたときの喜びの気持ち…。
この糸には、働いている上でのわたしの色んな気持ちが詰まっている。
見た目は黒っぽい灰色で地味だけど、よく見ると色んな色が混じっているのは、きっとそういう理由だろう。それだけ、色んなことを考え、感じながら、仕事をしてきたんだ。だから、決して…決して、がんばってこなかったわけじゃない。やり方は下手くそかもしれないけど、この1ヶ月半、自分なりにがんばってきたんだ。
俯きながら立っているわたしの隣にムームーが立って、こちらを覗き込んでいる。
「大丈夫だよ。ちょっといろいろ、思い出してただけだから」
ムームーは、やさしくわたしの頭をポンポン、と撫でた。そしてわたしの手から糸の束を取ると、身体をごそごそとまさぐってハサミを取り出し、何箇所か固定のために結んであった糸をパチンと切って、大きな糸の輪っかを作った。
「これ、ここからどうするの?」
ムームーは自分の両腕を輪の中に通して、ピンと両側に引っ張って見せた。そしてその輪をそのままわたしの方に差し出した。
「腕を通して、ピンってすればいい?」
ムームーは頷くと、わたしの腕に輪っかを預けて、じっとその輪っかを見つめた。そして糸端を見つけると、手に取ってくるくると巻き始めた。
ムームーが、腕を揺らすようなジェスチャーをした。最初はどういうことか分からなかったけど、どうやら糸を巻き取るのに合わせて、巻きやすいように腕を動かしてほしい、ということのようだった。どうやらこれから、毛糸玉を作ろうとしているらしい。
わたしは腕を広げて糸をピンと張り、ムームーが糸を巻くのに合わせて腕を上下左右に動かした。
ムームーが親指を立ててみせた。こんな感じでいいらしい。
わたしは腕を動かし、ムームーは手先を動かして、ひたすら糸を巻いていく。糸を巻く向きを何度も変えて、しばらくすると、絵に描いたような小さな丸い毛糸玉がひとつ出来上がった。直径5cmくらいの、小さな玉だ。
ムームーの手のひらの上の、小さな毛糸玉。
わたしの「気持ち」がたくさん詰まった毛糸玉。
わたしが生きていて、働いていて、色んなことを感じたからこそ生まれたもの。色はやっぱり地味だけど、ムームーを作り上げたときのような愛おしさを感じた。
ムームーと糸車がなかったらできなかったものではある。だけど、自分から生まれたもの、自分の気持ちがそのまま形になったもの、という意味で、わたしには何か特別な、愛情のようなものがこの毛糸玉に対して生まれていた。そして、毛糸玉への想いがあふれて、それといっしょにますます目の前のムームーが愛おしく思えて、糸車を買ってきてほんとうによかったと、ココロの底からそう感じた。
ムームーはわたしの手に出来上がった毛糸玉を持たせると、次の束を拾って支度をし、また大きな輪っかを作ってわたしの腕に通した。そしてまた糸端を探すと、いま作った毛糸玉の糸端と結んで、また糸を巻き始めた。
そうして、糸の束をいくつか使って作った毛糸玉は、最終的に直径が12cmほどもある大きな玉になった。編み甲斐のありそうなサイズの毛糸玉ができて、思わず微笑んだ。
…ん?編み甲斐?
わたしはいままで、編み物はやったことがない。
大昔に祖母に指編みを習ったことがあるけど、それすらやり方を覚えていない。
編み物っていうのは、針を持ってくりくりと手先を動かして作品を作っていくんだという、漠然とした知識はあるけど、針仕事や羊毛フェルトみたいな手先を使ったちまちました作業がどちらかと言えば苦手なわたしは、そもそも編み物をやってみようと思ったことすらなかったのだった。
でも、目の前には出来上がった素敵な毛糸の玉がある。これを何か形にできたら…きっと楽しいんだろうなあ。
ふと気づくと、ムームーがわたしの目を覗き込んでいた。
「ああ、ごめんごめん。この毛糸で何作ったらいいのかなって考えてたの。でもわたし、編み物なんてやったことないしなあ」
ムームーは、大きく息を吸ってフンッと勢いよく吐き出すと、片腕を曲げて自慢気に二の腕をわたしに見せつけた。
「え?もしかして、力こぶのつもり?」
ムームーの細い腕には筋肉なんてとてもあるようには見えなかったけど、がんばれ、と言いたいのが伝わってきた。
編み物なんてやったことないけど、せっかくだしこの機会に、新しい趣味として始めてみようかな。moumouのメルマガにも、「あたらしい趣味を始めてみませんか」って書いてあったし。
わたしたちは力を合わせて、残っていた灰色の糸をすべて毛糸玉に仕上げた。野球のボールくらいの、握りやすそうな大きさの玉が5つ出来上がって、わたしは嬉しくなってムームーとハイタッチした。そして、そのままぎゅうっと強く抱きしめた。
「ムームー、ありがとね。わたし、もうちょっと頑張れそうな気がするよ。この毛糸を使って何か作ってみたいしね。…なんか、すごくわくわくする」
ムームーは嬉しそうに、わたしの頬に頬を重ねた。そして、わたしの背中をポンポンとやさしく、ゆっくりと叩き始めた。すると、穏やかな眠気がやってきて、わたしはムームーに抱きしめられたまま、すやすやと眠ってしまった。
第7話はこちら
こちからから全話読めます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
