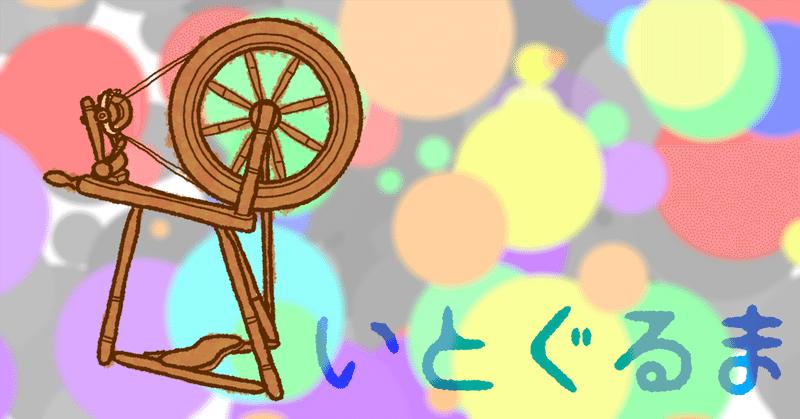
【創作小説】『いとぐるま』第5話
ジリリリリ!
いつものように目覚ましがけたたましく鳴った。時刻はいつもと同じ、朝の6時。
今日は珍しく、ぱっちり目が覚めた。
調子がいいのではなくて、その逆。調子がものすごく、ものすごく悪いのが、目が覚めた瞬間に分かった。
寒い。寒すぎる。
ひどい寒気がするけど、最近少しずつ暑くなってきていて、ブランケットに肌布団という薄いものの組み合わせしかないので、2枚とも頭から被ってがたがたとベッドで震えている。
そして、頭がガンガンする。めまいもしているようで、天井が回っているように見えた。
完全に、風邪を引いてしまったようだ。
布団の端から手だけを伸ばし、ベッドサイドの引き出しを手探りで開けると、その中の体温計を取り出して腕をヒュッと引っ込め、吐息で温めてから脇に挟んだ。
ピピピピ、と測定終了の音が鳴って、表示を見てみると39.6℃になっていた。ひどい熱だ。
熱も頭痛もめまいもひどいし、身体はだる重くてまともに動かせそうにない。
ああ。昨日風呂当番のあとにシャワーを浴びないまま仕事してたから、身体が冷えちゃったのかな。まさかこんなひどい熱が出るなんて…。
4月から今まで無欠勤でがんばってきたけど、まさかこんなところでつまづくとは。はあ〜、と大きな溜め息が出る。
さすがに無断欠勤はまずいので、7時になるのを待って職場に電話をかけた。
「はい〜、おはようございます〜。デイサービスのよつばです〜」
調子の良さそうな男性の声がした。施設長だ。
「おはようございます。原田です。施設長すみません、今日体調がものすごく悪いので、仕事休みます。すみません」
「えっ、風邪引いたん?」
「そうみたいです。熱と頭痛とかめまいもひどくて、動けそうになくて…」
「ありゃー、それは大変や。大丈夫?ご飯とか食べれそう?」
「うーん、動けそうにないのでちょっと厳しいです」
「そうか、分かった。こっちのことは任しといて、なんとかするし。そんなに体調悪いんやったら1日で治すんは難しそうやし、何日か休まんか。どのみちもしコロナやったらしばらく出勤は難しいし、ゆっくりしたらええよ。無理したら余計ひどくなってまうよ〜」
施設長はいつも通りの朗らかな雰囲気で応対してくれた。わたしは施設長にお礼とよろしくお願いしますの言葉を伝えると、電話を切った。そしてそのままぱたっと、気絶するように眠ってしまった。
次に目が覚めたのは、もうすぐ16時になろうとする頃だった。外はまだ明るかったのでお昼くらいかと思ったけど、どうやら電話の後9時間ほども眠りこけていたらしい。
まだ寒気はひどいし、頭痛は少しマシにはなったけど、めまいが残っているのか少し吐き気までしてきた。身体は相変わらず鉛のように重い。
さむい。いたい。きもちわるい。だるい。
頭の中はこれでいっぱいで、すべての思考がストップしている。ただ天井をぼーっと見つめて時間が過ぎていった。
そうしてぼーっとしていると、玄関のチャイムが鳴った。
誰だろう。どうしよう。動けるかな…。
わたしは気力を振り絞って身体を起こすと、足を床に下ろして、ゆっくりと立ち上がった。めまいがして転んだら起き上がれなくなりそうで怖くて、壁伝いにヨロヨロと玄関まで歩いた。
鍵を外してドアを細く開けると、目の前に川上さんが立っていた。川上さんはわたしを施設に誘ってくれた人だ。元バレー部主将だったらしく、しっかり者で優しくて、新入りのわたしにも優しく丁寧に接してくれる。
「まゆちゃんやっほー。ひどい顔しとるじ、大丈夫か?」
「…熱ひどくて…めまいと吐き気とだるいのもあって…」
そこまで言って、わたしはマスクをつけていないことに気づいた。
「あ、マスク…」
「いいよいいよ、世の中的にもコロナ落ち着いてきとるし、そこまで頑固に心配することないやろ。とにかく今はしんどそうやし、とりあえずベッド戻って休まんか。戻れる?」
川上さんは靴を脱いで部屋に上がると、持っていた荷物を下ろしてわたしに肩を貸してくれた。
少しよろけながらもなんとかベッドまで戻ったわたしはベッドに仰向けに横になると、そのまま布団を首元まですっぽり被った。
川上さんはベッドの横に座って、しばらくの無言のあと、口を開いた。
「ねえまゆちゃん。最近無理してるんじゃない?」
答える代わりに、わたしの目には涙がじわあっと溢れてきて、こめかみの辺りに落ちていった。
泣きたくはなかったけど、勝手に涙が溢れてきて止まらなくなった。
「………ごっ、う…」
「ん?なんて?」
「…ご、ご…ごべんだざい………」
日本語にすらならない言葉が飛び出した。
嗚咽ばかりが漏れて、うまく言葉が出てこない。
「なんで泣くん?なんで謝るん?まゆちゃんなんも悪いことしとらんやん。よく頑張ってきたやん」
最後の一言が、わたしのココロにぐさっと刺さった。
そうだ、わたしはがんばっている…いや、これは嘘。いろいろやってはいるけど、なかなか思い通りに動けなくて何度も失敗して、時には叱られて…。
どんなに自分なりに力を尽くしても、なかなかうまくいかないわたし。それってつまり、なんにもがんばってないことの裏返しなんじゃないか…と、思うようになっていた。だからわたしは、ほんとうはがんばってなんかない。
「がんばって…ないでず…」
涙と鼻水で顔をびしゃびしゃにして、嗚咽を無理やり抑え込みながら、わたしはなんとか答えた。
川上さんは膝立ちになって、わたしの顔を覗き込んだ。ぐしゃぐしゃになった顔を見られたくなくて、とっさに両手で顔を隠す。
今更隠したところで、もう泣いていることはバレているけど、こんな情けない姿を、職場に誘ってくれた川上さんに見せたくなかった。こんなはずじゃ、なかった。
「まゆちゃん、ごめんね」
わたしは、川上さんの口から、1番聞きたくなかった言葉を聞いてしまった。絶対に、絶対に聞きたくない言葉だった。
「うちに何回もボランティアしに来てくれとって、まゆちゃん優しいし、お年寄りと話すのすごく好きそうやったし、何よりおしゃべりしたおじいおばあがすごく嬉しそうやったから、まゆちゃんから久々に連絡きて嬉しかったんよ。ぜひうちに来てほしいと思った。まゆちゃんのできることを活かして、うちで頑張ってほしいなと思ったんよ。でも…それが、まゆちゃんにとってはしんどかったんやね。ほんとうに…ごめん」
耳を塞ぐ気力もなくて、川上さんがそう言うのをただただ聞いていた。
…聞きたく、なかった。
わたしに期待して、職場に誘ってくれたのに。
期待に応えるためにも、仕事をバリバリこなしていこうと思っていたのに。
たった1ヶ月半でこんなことになってしまうなんて…。
川上さんを、職場の皆さんを、がっかりさせてしまったのだと思うと、やるせない気持ち、そして、どうしようもない後悔ばかりが襲ってくる。
わたしはやっぱり川上さんの言葉に答えられなくて、声を殺して泣くことしかできなかった。
「まゆちゃん、しんどいんにいっぱい話しかけてごめん。レトルトのおかゆ買ってきた。その様子やと朝から何も食べれてなさそうやし、チンして器に入れて置いとくね。あと、食べやすそうなものと水分持ってきたし、よかったら食べてね。あ…それから、一応コロナの検査キットも持ってきたし、置いとくね。身体が楽になったときでいいから、検査したらわたしに連絡してほしいな」
川上さんはおかゆの準備をしてくれているようだった。キッチン上の収納からお椀を取り出す音がした。しばらくするとチン!という音がして、おかゆが出来上がったようだった。
「お椀、汚れないようにラップ敷いてあるから、洗わなくて大丈夫。スプーンもらってきたから、それ使って。あったかいうちに食べてね。…っと、こんなもんかなあ。じゃあ、帰るね。鍵…どうしよっか」
わたしは手で涙を乱暴に拭うと、ゆっくり起き上がって川上さんといっしょに玄関まで行った。
「じゃあ…ゆっくり休んでね」
扉を閉める前に、わたしはまともに川上さんの顔を見てしまった。
彼女は、困ったような笑顔を浮かべていた。目の前のわたしを心配させたくなくて、笑顔を見せてくれたのかもしれないけど…。
こんな顔、させたくなかったのにな。
わたしはそう思いながら、川上さんにお礼をして、ゆっくり扉を閉めると、足音が聞こえなくなってから鍵を閉めた。
よたよたと部屋に戻ると、ぐうぅ、とお腹が鳴った。朝から何も食べていないし、何も飲んでいない。
テーブルの上には、出来たての玉子がゆ。時間は…17時前。晩ご飯には少し早いけど、お腹がすいて仕方ないので、わたしはへなへなと座り込むと、いただきますもせずにおかゆを食べ始めた。
あつあつのおかゆを、あちちと言いつつ、ゆっくりゆっくり食べる。栄養が身体じゅうに染み込んでいくような気がした。
パックひとつ分のおかゆではお腹が満たされなくて、川上さんが持ってきてくれたレジ袋を見ると、中にはレトルトのおかゆ…白がゆと梅がゆが1つずつ、日持ちしそうな菓子パンが2つ、フルーツゼリーのドリンクが3つ、チョコレートのアソートパックが1袋、夏によくテレビで宣伝しているペットボトルの経口補水液が3本、解熱鎮痛剤1箱、額に貼る冷却シート1箱、そしてコロナの検査キット…が入っていた。川上さんの思いやりがたくさん詰まっている。
甘いものが食べたかったので、チョコレートの大袋を開けた。適当につかんだらビターチョコが出てきた。鼻が詰まっているのか、口に入れても味があまりよく分からない。
頭がぼーっとして、噛むことも忘れて口の中でチョコレートが溶けていく。口の端からこぼしそうになって、慌てて飲み込むと、変なところに入ってむせ返った。もらった経口補水液をゆっくり飲んで身体を落ち着かせる。軽く脱水状態だったのか、すいすい身体に染み込んでいくようで、500mlのペットボトルの半分ほどを飲んだ。
また寒気がして、頭痛もあまりよくならないので、川上さんがくれた解熱鎮痛剤を飲んでベッドに身体を預ける。
歯を磨きたい。顔を洗いたい。お風呂にも入りたい、けど…この状態で、なんにもできそうにない。
ふと、この「なんにもできない自分」が怖くなった。
この狭い部屋でひとりぼっちのわたし。川上さんが来てくれたとは言うものの、もしわたしがこの部屋で倒れて、そのまま死んでしまったら、どうなってしまうんだろう。独居老人でもないのに、孤独死…そんな恐ろしい考えが頭をよぎって、思わずかぶりを振る。でも、その考えは消えてはくれなかった。
この部屋で、ひとりぼっち。わたしに何かあっても、きっと誰も気づいてくれない。
その考えで頭がいっぱいになってしまった。
誰かに、助けてほしい。でも、誰もいない。
いや、いないわけじゃない…けど。川上さんがさっき来てくれたじゃないか。でも…そうやってわたしを助けてくれようとしている人に、わたしはなかなか、「助けて」が言えない。さっき川上さんがベッドの横に座ったとき、わたしが何か言うのを待っていた瞬間があったと思う。そのとき、言えばよかったと思う。でも…助けてくれるその人を前にして、わたしは何も言うことができない。
わたしは、誰に助けを求めればいいんだろう。誰になら、思っていることを素直に話せるんだろう。
天井を見つめていた目を、そっと閉じる。
夢の中で見た、羊くんのキョロっとした、優しい眼差し…。
…そうだ。わたしには羊くんがいるじゃないか。
羊くんになら、思っていることを話せそうな気がする。それに…羊くんは、わたしのほんとうの気持ちを知っているような、そんな気がした。なんとなくだけど。
身体を起こして、ベッドの足元の手芸棚を見る。
こちらから見ると、はずみ車越しに椅子に座った羊くんの顔が見えた。小さな背中だけど、いまは頼もしく思える。
ベッドの足元に寄って、羊くんと糸車を近くで見てみると、羊くんはやっぱりボビンに手をかけていた。その手をそっとどかすと、淡いオレンジ色の糸が現れた。
棚の下を見ると、ボビンが10個ほど落ちている。
半分は黒っぽい色の糸で、それから水色の糸が2、3巻き、そしてフライヤーに残っているのと同じオレンジ色の糸も2、3巻きあった。
落ちていたボビンを集め、フライヤーに残ったボビンも外して、手のひらに乗せてじっと見る。
1番多い黒っぽい色の糸をよく見ると、ラメのようなものが入っているのか、部屋の明かりを受けてちらちらと光って見えた。
わたしは、昨日見たあの夢を思い出した。
月と星の明かりがきれいな夜。柵を飛び越える羊たち…。
この糸は、もしかするとあの星空だろうか。吸い込まれそうなほど黒い夜空に輝く、満天の星々。
あの光景を思い出して、ささくれ立った気持ちの波が少しずつ凪いでいくのがわかった。
じゃあ、この水色は?
少しくすんだ、灰色がかった水色の糸を見て、わたしはふっと悲しい気持ちになった。
柵を飛び越えるのに失敗して、千切れてしまった羊くんの右足。それを、ニードルで必死に「治療」したけど、左右の脚の長さが変わってしまったこと。
わたしは羊くんを手に取って、脚を見てみた。
脚の長さが確かに左右で違っている。これでは歩くことも、糸を紡ぐために糸車のペダルを踏むことも難しかっただろう。
「羊くん、うまく治してあげられなくて、ごめんね。うまく歩けなくなっちゃったね、ごめんね…」
滴り落ちた涙が、羊くんの身体に吸い込まれていく。昨日の夢と同じだ…と思って、残った淡いオレンジ色の糸を見た。それは…やさしさがいっぱい、いっぱい詰まった色だった。
泣いているわたしをぎゅっと抱きしめて、そっと撫でてくれた、羊くんのやさしい手の感触と、もこもこした身体の感触。そして、羊くんの体温を知り、温もりに触れられた嬉しい気持ち。それが、この糸には詰まっているような、そんな気がした。
確かそのあと、あのレンガの小屋で、羊くんが糸を紡いでいたんだっけ…わたしの額から伸びた「綿」で。
…羊くんは、わたしの「気持ち」を紡いでいるみたいだ、と、そう感じた。だって、糸を見ただけでその時の気持ちをありありと思い出せる。きっとそうに違いない。
悪夢を見た一昨日の晩。翌朝灰色の糸がたくさんたくさんできていたのは、きっとモヤモヤした自分の気持ちを羊くんが必死にせっせと紡いでくれたからだろう。そして、帰宅して部屋を見たとき、ピンクっぽい色の糸ができていたのは…お風呂に入って、ホッとしたから?
わたしは涙を拭うと、ふふっと笑って、羊くんを見た。
羊くんは相変わらず、キョロっとした段違いの目でわたしを見つめている。
「ねえ、羊くん。ありがとう…わたしができないことをしてくれて」
人差し指で、やさしく羊くんの頭を撫でる。
「こんなに大切なひとなのに、ずっと羊くんって呼んでるのも変だね。名前をつけてあげる。何がいいかな…。…あ、そうだ。moumouで買った羊毛で作ったから、今日からムームーって呼ぶね。よろしくね、ムームー」
羊くん…ムームーは、ちょっとキョトンとしているように見えた。もしかしたら、この名前を気に入ってないかもしれないけど、やさしさがたくさん詰まっている「このひと」にはぴったりの名前だと思う。
わたしはもう一度、ムームーの頭を撫でた。
「ねえムームー。やっぱりひとりぼっちは寂しいね。今日はいっしょに寝てくれる?」
やっぱりキョトンとしているムームーに微笑むと、わたしは部屋の明かりを消した。まだ19時にもなっていないけど、風邪を引いて消耗しているのか、とても眠い。
わたしは枕の横にムームーを寝かせると、ムームーにも布団を被せてやって、自分も布団にくるまった。
「おやすみ。いい夢が見られますように」
ムームーを見つめながら目を閉じた。そしてそのまま、溶け入るように眠ってしまった。
第6話はこちら
こちらから全話読めます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
