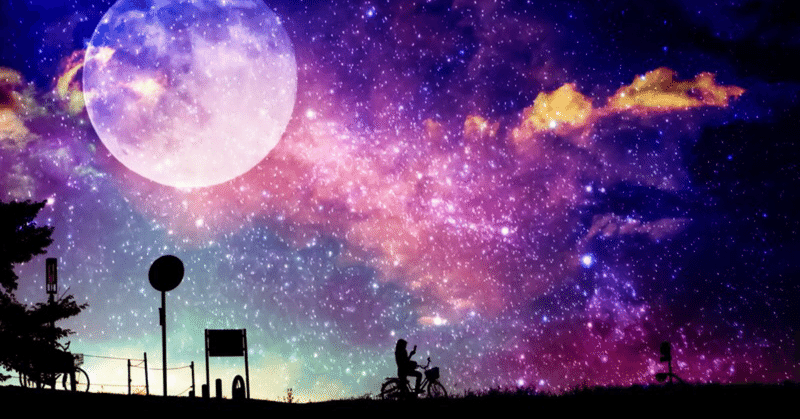
つよがり ー満月の夜ー
これは、松下洸平さんのメジャーデビュー曲、「つよがり」を聴いて書いた私の妄想小説です。
※曲とは一切関係ございません。
残業終わり、会社を出て空を見上げると満月が明るく輝いていた。
明るい満月がどうしても彼女の笑顔に重なってしまい、胸がキュッと痛くなる。
別れから1ヶ月。
もう彼女と会うことは二度とないだろう。
そう分かっていたのに、あの夜僕は「さよなら」を言わなかった。
☆。.:*・゜☆。.:*・゜☆。.:*・゜
彼女との出会いは、去年の初夏。梅雨が開けたばかりのカラッと晴れた、暑い日のことだった。
本社から下町の営業所に営業事務として異動してきた彼女は、会社の1期上の先輩。
明るく溌剌としていて、よく笑う彼女が異動してきたことで、殺伐とした雰囲気だった営業所は一気に明るくなった。
澄んだ瞳に、屈託のない笑顔。どんな時でも楽しそうに仕事をする姿。すぐに、僕は気づいたら彼女のことを無意識に目で追うようになっていた。
「はい。頼まれてた顧客データ。明日の取引先との打ち合わせ、頑張ってよ。」
「あ、ありがとうございます。」
彼女の左指の人差し指には薄紫の石が付いた指輪が光っていた。
「それから、昨日の夜、高橋くんあの棚の上に財布置いて帰ったでしょ。はい。」
「え、あ、財布??棚の上に忘れてたんだ…。すみません。ありがとうございます。今気づきました。」
僕は彼女から財布を受け取った。
「…うそ、財布ないことに1晩気づかなかったの?嘘でしょ。どういうこと。あはははは。」
彼女は豪快に笑った。
「普段、電子マネー使ってるんで、気づかなかったです。はぁ。財布無くしたり、忘れたり…もう何十回もやってます。」
「そんな、落ち込まないで。でも、今回は拾ったのが私だったから良かったけど、他の人だったらどうなってたか分からないよ。気をつけてね。」
「本当にありがとうございます。拾ってくださったのが早瀬さんで本当によかったです。でも財布って意外と落としても毎回見つかるんですよ。」
彼女はため息をつき、それから笑った。
「それさ、財布とかスマホとか無くしがちな人皆言うよね。そうやって油断してるからまた忘れるんだよ。本当に気をつけてね。心配だよ。一応、中身確認しといたら。」
「はい。確認します。あと、資料ありがとうございます。」
「それにしても財布置きっぱなしにして1晩気づかないって高橋くん本当に面白い…」
「早瀬さんちょっと来て」
「はい。」
彼女は上司に呼ばれて元気よく返事をして、小走りで去って行った。
彼女の笑い声が余韻として胸の中に残っている。
財布の中身を一応確認しながら、マスクの中の口元が自然と緩んでいることに気づき、僕はハッとした。
取引先との打ち合わせは明日だ。
仕事に集中しなければ…。
気を取り直すも、3分後には上司と話す彼女の後ろ姿をちらっちらっと確認してしまう。
彼女の左手の細くて長い指に着いてる指輪は、自分で買ったものでは無いだろう。
僕はなぜか分かってしまった。
本気になってはいけない。
この気持ちはまだ恋じゃない。
あの時はそう思っていた。
まだ引き返すことができると…。
夏が終わり、日が短くなってきたある日、新人さんが大きなミスをして僕たちはその対応に追われていた。
久々に営業所には殺伐とした空気が流れている。
「ミスは誰でもするから今回は気にしないでね。今後同じミスを繰り返さなければ大丈夫。」
ミスをした新人さんの今にも泣きそうな顔を見て、僕はいたたまれなくなって声をかけた。
その途端、隣の席の同僚が「はぁ〜。」と大きなため息をついた。
僕の発言に「なに呑気なことを言ってるんだ」という空気が周りに流れ始める。
オフィスに流れる冷たい空気に耐えきれず、小心者の僕は自分の発言を後悔しかけたその時、
「ははははは。高橋くんがそう言うとなんか説得力あるよね。」
彼女の発言で場の空気が一変した。
「1年目の新入社員の教育やミスのカバーは先輩の仕事だからフォローするのは当然のこと。全く気にしないのはダメだけど、気にしすぎも良くないから気にしすぎないように。大丈夫。落ち込まないでね。」
…やっぱり好きだ。
新人さんに向けて話す彼女の笑顔を見て僕は改めてそう思った。
彼女の左手の人差し指にはピンクの石が付いた指輪が光っていた。
その指輪の送り主は…?
見ないように気をつけてた彼女の細くて長い指が気になって仕方がなかった。
「早瀬主任、高橋主任。申し訳ございませんが終電の時間なのでお先に失礼します。」
オフィスにいるのは、彼女と、職場から家までの距離が1駅のため徒歩で帰ることができる僕の2人だけになった。
26時を過ぎた頃、ようやく仕事が落ち着いた。
「ようやく終わったね。高橋くん遅い時間までお疲れ様。」
「お疲れ様です。無事終わってよかったです。早瀬さんがいなかったらどうなってたことやら…本当にありがとうございます。」
「いやいや、こちらこそ高橋くんがいてくれてよかった。ありがとう。」
彼女は帰宅する準備を着々と進めている。
「終電の時間過ぎてしまいましたけど、家、近くなんですか?」
「あははははは。終電ね、逃しちゃった。高橋くんこそ、大丈夫なの?」
「え、大丈夫ですか?僕は徒歩で帰ることができるので全然大丈夫です。」
「あ、徒歩で帰れるんだ。私はタクシーで帰るから平気。」
「あ、じゃあ僕タクシー呼びますよ。すみません。残っていただいて。」
彼女は僕の方を見て、疲れを感じさせない満面の笑みでこう言った。
「高橋くん頑張ってるの見てたら帰れなくて。それに、2人で仕事するの楽しかった。」
彼女のキラキラとした笑顔に僕は吸い込まれてしまった…。
…残業が続いている中、部下のミスのフォローをして疲れたからだろうか…。
それとも、好きな人と2人で仕事をするのが本当は嬉しくて、その気持ちを無理やり隠していたのに満面の笑みで「楽しかった」と言われたからだろうか…。
僕は気づいたら、彼女にキスをしていた。
彼女のキラキラとした笑顔に吸い込まれて、気づいたら唇を重ねていた。
一瞬だったか、数秒経ったかは分からない。彼女はそっと僕から離れた。
「あ…。申し訳ございません。僕、なんてことを…疲れてたのかもしれ…」
「あっはははははは。ははは。なんか笑いすぎて涙出る。疲れてるのかな。」
彼女は僕の言葉を遮って、いつものように豪快に笑った。
笑いすぎて涙が出ていた。
僕は彼女の涙を拭おうとしたが、彼女は自然とかわし、自分で涙を拭った。
「前から思ってたんだけど、高橋くんって帰国子女?リアクションとかちょっと外国っぽいとこあるよね。」
「あ、いえ…そういう訳では…。」
思わぬ言葉に僕は戸惑った。
「あ、違うのね。なんだ、今いきなりキスしてきたからやっぱり帰国子女なのかって確信したんだけどな…。違ったのね。」
彼女はカバンを持ち、カバンからスマホを取り出した。
「でもいつも助かってるよ。今日も重かった空気が高橋くんの急な一言でなんか穏やかになったし。」
「…」
それは違う。僕は場違いな一言を言っただけ。場の空気が穏やかになったのは早瀬さんがフォローしてくれたからだ。
「近くに彼氏が住んでて迎えに来てくれるって。だから私は大丈夫。お疲れ様。ごめん、鍵閉めお願いしていいかな。」
彼女はスマホを見ながらそう言ってオフィスから出ていった。
嘘だ。
何となくそう思ったけど、僕は追いかけなかった。
「高橋くん、今日の夜暇?ちょっと飲みにでもいかない?」
彼女から急に誘われたのは、それから1週間後の事だった。
あれから僕は彼女に何となく声をかけることができなくなっていた。彼女は普通に接してくるが、僕はどうしてもよそよそしくなってしまう。
「え、いいんですか。」
彼女のことは忘れよう。そう決めていたのに、僕は嬉しくて誘いを受けてしまった。
彼女の左人差し指には、黄色の石の付いた指輪が光っていた。
僕達は飲みの席で色んな話をした。
仕事のこと、趣味のこと。
彼女はドラマや映画を見ることが好きだと言っていた。僕はテレビをほとんど見ない生活をしているため、彼女の趣味の話にはついていけなかった。
彼女は「彼氏」の話をし始めた。
彼氏は仕事が忙しくて、ほとんど休みがないこと。
女性からモテること。
でも彼女はそんな彼氏が大好きで支えたいと思っていること。
彼氏も彼女が大好きだが、彼氏のために交際していることは秘密にしなければならないこと。
恋人のことを語っている彼女はどこか寂しそうな表情をしていて、僕はいたたまれなくなる。
「ごめんね。どうでもいい事まで話しちゃった。こんな話聞きたくなかったよね。」
聞きたくなかった。とは言えず、僕は否定した。
交際を秘密にしなければならない?どういうことだろう。気になって不倫なのかと聞いたが、彼女は否定した。僕なら寂しい思いはさせないのに…。
「高橋くんは?彼女いるの?」
「います。」
僕はつよがって咄嗟に嘘をついてしまった。
「じゃあ、そろそろ帰ろうか。お互いの恋人にも悪いしね。ただ、食事しただけだし悪いことは何もしてないけどね。」
その日は解散した。
その日以来、僕たちは週に1回、仕事帰りに食事をするようになった。
お酒が進むと彼女は恋人の話を始める。
本当は恋人はいない、僕が好きなのは貴女だとは今更言えず、彼女の話をただ聞いていた。
彼女がいつも左人差し指にしている指輪は彼氏から貰ったものだということ。彼女は彼氏のことを心から愛していることと、なかなか会えない寂しさが伝わってきて、僕の心は毎回ギュッと痛む。
よく一緒に飲みに行く同僚以上の関係になることはなかったが、仕事帰りに2人で食事に行くことができるだけで僕は幸せだった。
彼女が恋人の話をする時間は少し胸が痛んだが、彼女が自分のことを話してくれるだけで嬉しかった。仕事の愚痴を共感し合えるだけで良かった。
…はずだった。
一緒に食事をするようになってから半年経った春の日、僕は残業で少し遅れていつもの居酒屋の個室へ向かった。
「すみません、遅れてしまって…」
と言って個室へ入り彼女を見て僕は驚いた。
彼女はお酒を飲みながら泣いていた。
「どうしたんですか。」
僕は慌てて席へ着く。
「ごめん。もうね、寂しくて。」
彼女はお酒を飲み干し、追加注文をし始める。
「大丈夫ですか。無理しないでください。」
こんなに酔っ払った彼女を見るのは初めてだ。
追加のお酒が届くなり、彼女は飲み始める。
「早瀬さん、飲み過ぎですよ。もう終わりにしましょう。」
僕が手で止めるがお構いなく飲み始めようとする。
「ちょっと。早瀬さん。」
「私、寂しくて。彼のために色々と我慢してるのに。もう限界。」
数分に渡り彼女を止めつつ話を聞いていたが、彼女が泣きながら手を握って来たせいで、理性が吹っ飛んだ。
僕は彼女にキスをした。
「お酒臭いからやめて。」
彼女は僕から離れ、ため息をつき、再びお酒を飲み始める。
理性が吹っ飛んでいる僕はため息を聞き流して再び彼女に熱いキスをする。
舌が絡まり、彼女がキスを受け入れたと確信した次の瞬間、僕は突き飛ばされた。
「違う。高橋くんじゃない。そういうことじゃない。私たちは恋人じゃないでしょ。ただの同僚でしょ。」
「あ、すみません。帰国子女っぽいところが出てしまって…」
彼女の言葉を聞いて一瞬で理性が戻った僕は、一連の言動を軽いジョークで誤魔化そうとしたができなかった。
彼女は号泣していた。
彼氏の家が近くにあると聞いていたため、場所を聞いたが彼女は答えなかった。仕方がないため、彼女の家までタクシーで連れていく。
「茜!」
男の人の声がした。
声の方を向くとサングラスとマスクをした男が立っていた。
「早瀬さんの彼氏さんですか?すみません、早瀬さん、だいぶ酔っ払っているみたいで…。」
僕は咄嗟に声をかけた。
「ここまで連れてきてくださったんですか。申し訳ございません。ありがとうございます。」
男はサングラスとマスクをしたままそう言った。
僕は彼女を男に引渡し、逃げるようにその場から去った。
空には満月が明るく輝いていた。
あの男、どこかで見覚えがある…。
僕は気になって仕方がなかった。
「高橋くん。昨日家まで連れて行ってくれたみたいで、ごめんね。私昨日のこと何も覚えてなくて…。あんなに酔っ払ったの初めてだったから…。」
翌朝、彼女からそう言われた。
彼女は何も覚えてなかった。
何も覚えてなくてよかった…。
僕は心から思った。
それからも彼女との週1回の仕事終わりの食事は続いていた。
1つ変わったことは、彼女が全く恋人の話をしなくなったことだった。
僕も彼女に恋人のことは何も聞かなかった。
しかし、1ヶ月後、彼女との関係は突然終わりを迎えた。
「今日で最後にしようと思って。」
いつものように仕事終わりに2人で食事をしていた時、彼女は突然そう言った。
彼女の右手の薬指に指輪が光っていた。
「プロポーズされたんですか?」
僕は表情を変えずに言った。
「よくわかったね。」
彼女は右手を隠した。
「何となく、そう思いました。」
僕は笑ってそう返した。
「高橋くん、鈍いと思ってたけど、こういうところ鋭いのね。」
彼女も笑った。
「半年間、一緒に食事してくれたお礼として伝えるね。これ、誰にも言わないでね。」
彼女はこう前置きして僕に言った。
「実は私の彼氏…じゃなくて、婚約者、高柳晃なんだ。」
「え、高柳晃ですか…?あの、大人気俳優。え、凄くないですか?」
僕は驚くフリをした。
「やっぱり、高橋くんって鈍感なんだね。私が酔っ払って家まで送ってくれた日、彼、高橋くんと会って会話したって言ってたよ。」
彼女はまた笑った。
「え。あの人、えええ。全く気づかなかったです。サングラスとマスクしてたので。」
全部嘘だ。
サングラスとマスクをしていたとはいえ、どこかで見覚えがある人だと思った。
あの日から僕の中でずっと引っかかっていた。
昔の知り合いかな?会社の人…?
そう思って知ってる人を一通り照らし合わせたが誰か分からなかった。
そうモヤモヤとしていた頃、電車でお酒の宙吊り広告に高柳晃が映っているのを見て、男に見覚えがあると思った理由がわかった。
最初は、まさか彼が彼女の恋人のはずがないと思ったが、彼女が彼氏の仕事が忙しくて会えないと寂しそうな顔をしていたこと、彼女の趣味がドラマと映画鑑賞で、話に出てきた作品にほとんど彼が出ていたことと辻褄が合った。
そして、彼女が酔っ払って寂しいと泣いていた日は、高柳晃と共演若手女優の熱愛報道が出た日だった。
写真を取られた訳ではなく、ただ報道が出ただけで双方の事務所が否定していたことを考えると恐らくデマなのだろう。
彼女は芸能人の彼氏を守るために自分の恋人の正体を隠し続けていたのだ。
相当な覚悟を持って交際をしているのだと僕には分かった。
僕は彼女の恋人の正体に気づいたことを誰にも言わなかった。もちろん彼女にも。
そして、僕も自分の気持ちを誰にも伝えることなく心にしまうことを誓った。
「だから、この夜で最後の夜にしようと思って。」
彼女の決意のような一言に僕は祝福の言葉を返した。
「おめでとうございます。すごいな。月9で主演を務める俳優の奥さんだなんて。」
彼女は見たことがないくらい幸せそうな笑顔で僕に言った。
「高橋くんだから言うんだよ。信頼している同僚であり、なんでも話せる友達だから。」
ずるい。
そう思う気持ちを抑えて、笑顔で彼女に伝えた。
「本当におめでとうございます。幸せになってください。」
「うん。ありがとう。高橋くんもね。」
僕はうなづいた。
彼女と別れて外に出たら満月が輝いていた。
「さよなら」は言わなかった。
彼女は相手は僕以外の誰にも明かさず、結婚することを伝えて会社を寿退社した。
そして、別れから1ヶ月後の満月の日の朝、高柳晃は一般女性と結婚したことを発表した。
彼女との思い出を誇りにして、胸の奥にしまって歩いてみよう。
大好きだったよ。幸せになってね。
僕は満月を見上げて心の中で呟いた。
今まで小説を書いて公開したことはありませんでしたが、松下洸平さんの「つよがり」という曲を何度も聴くうちに頭の中に妄想が広がり、
書いてみようと思いました。
素敵な曲調と歌詞、表現力豊かな歌声…本当に素晴らしい曲です。
下手な物語を読んで下さりありがとうございました。
※冒頭にも書きましたが、この物語は曲とは一切関係ございません。
※あと、高柳晃という名前にも意味は全く無いです。書いている時に何となく思い浮かんだ名前です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
