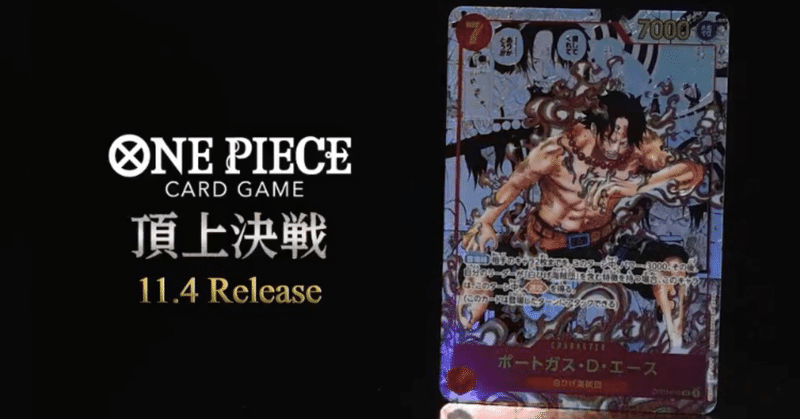
頂上決戦環境 環境推移
頂上決戦が発売されて約2ヶ月が経ち、CSも残すところ宮城と東京のみとなりました。
1弾環境では緑キッドがトーナメントシーンの中心でしたが、2弾環境からは一変しました。
今回はそんな環境推移を記録していきます。
○発売当初
《錦えもん》、《ヤマト》、《光月おでん》の登場および前期からの引継ぎもありシーンは緑が牽引していた印象でした。
緑デッキの強みは不利デッキが少ない所です。
ゲーム進行においても動きがそれなりに安定しており、《7キッド》、《おでん》でライフを削り切るというシンプルなデッキとなっています。
緑以外の注目デッキは、
・安定性を上げる《ダダン》を手にした赤系デッキ。
・7000ラインでの攻撃を得意とする新リーダー《イワンコフ》の青デッキ。
・2弾から本格参戦の黒デッキ。
これらが環境に影響を及ぼすと考えていました。
○最初の3週間
大坂CSまでにいくつか行われた非公認大会では様々なデッキが優勝していました。
まず発売直後の非公認大会では
【イワンコフ】、【ドフラミンゴ】と、青デッキのワンツーフィニッシュでした。
個人的に【キッド】から【錦えもん】へ緑リーダーを変更することで、《8キッド》が不採用になる可能性があり、それが【ドフラミンゴ】に対して影響があるのではと考えていました。
1弾環境で【ドフラミンゴ】相手のゲーム方針は、ライフを受け続けて《8キッド》で相手の攻撃をシャットアウトして勝つというものでした。
したがって、《8キッド》の減少=【ドフラミンゴ】に対するメインの勝ち筋が減ると考えていました。
(結局は構築の変化に伴って、受けて戦うスタイルから攻撃メインのスタイルになっただけでした)
☆最序盤だけみると青一強の結果でした。
翌週、個人戦の非公認大会がありした。
優勝は【ロー】。
トップ4に【錦えもん】×2、【ゾロ】。
1週間で青デッキが消え、2弾で強化された他デッキが台頭してきたのです。
【イワンコフ】が勝ち上がれなかった要因として以下のように考えています。
・《ホーキンス》の存在
緑が先後どちらの場合でも《イワンコフ》よりも先に《ホーキンス》が置けます。
《ヤマト》をキープしておくことで《ルフィ》の回答となり、【イワンコフ】のメインプランを潰すことができます。
また、《ルフィ》以外の7000ラインは《ホーキンス》対面では動きづらいため、このカードが盤面にいることで大きな制約を与えます。
青デッキは7コスト以下の処理に長けていることから【イワンコフ】対面では《7キッド》を優先して回収することは少なく、《ボニー》からのサーチで積極的に《ホーキンス》を回収できます。
さらに、新カード《おでん》は8コストであることから青デッキの除去圏外であり、成立するとかなり場持ちがいいことから《ホーキンス》で盤面、《おでん》でライフと攻撃先を分業することでシステム勝ちが見込めます。
・強化された【ゾロ】
1弾の【ゾロ】は2コスト4000を採用した構築でした。
しかし《ダダン》の登場で構築は一新されます。
2コスト4000は全て抜け、《ダダン》、《マキノ》、《ゴードン》、《サニーくん》、《ビスタ》が新たに採用されました。
1コスト帯増加による単純なコスト軽量化だけでなく、それぞれ効果も強いのが良いところです。
【イワンコフ】対面では後手の場合、6ドンのタイミングで
・《マキノ》を絡めたライフの押し込み
・《ゴードン》+《ロビン》/《ビスタ》で盤面処理
など、一瞬でライフ+盤面に圧をかけられます。
また青デッキの除去手段がバウンスのため低コスト多めの【ゾロ】には効果が薄いのもポイントです。
☆1週間である程度メタが固まったように見えます。
また【錦えもん】、【ゾロ】共にテンプレとなる構築が公開されたことから、この大会の入賞構築がシーンのベースとなりました。
さらに翌週、チーム戦が開催されました。
リーダー被り禁止の大会でしたが、【錦えもん】+【ゾロ】+αというチームが多かったようで、メタの中心がこの2デッキであることがわかります。
○大阪CS

大方の予想では【錦えもん】か【ゾロ】と思われていましたが、
優勝 【ゾロ】
準優勝【ゾロ】
緑は残らず【ゾロ】ワンツーフィニッシュとなりました。
さらに構築にも大きな変化が見受けられました。

決勝両名の構築に採用されていたのが《エドワード・ニューゲート》(以降、白ひげ)でした。
《白ひげ》の採用は【ゾロ】対面のゲームメイクに大きな影響を与えます。
まず、ミラーマッチにおいて打点ラインの要求値が突然上がります。
【ゾロ】はリーダー効果により展開した盤面で5000ラインを作りやすく、手数で圧倒するスタイルです。
またミラーマッチは互いのキャラ数、ライフ、手札と様々な要素を考慮しながらプランを立てる必要があり、とても繊細なデッキです。
例えば中終盤「6000〜7000ラインで3回攻撃してライフを削りつつカウンターを使わせよう」と考えていた場合、《白ひげ》はその計算を狂わせます。
・7000ラインが1000カウンターで捌かれる
・6000ラインではそもそも届かない
・返しのターンにカウンター不可能な打点(白ひげ)による攻撃
など、1枚で大きなリターンも得られるのです。
ことミラーマッチにおいては採用の有無で大きな差が出るカードでした。
次に【錦えもん】側への影響です。
【ゾロ】と対面する際、《白ひげ》を認知しているか否かで、根本的なゲームプランに関わってきます。
従来の【ゾロ】へのプランは盤面を処理し、タイミングでライフを一気に削るというものでした。
盤面を整理せずにライフを削ると【ゾロ】側の手札が増えてしまい、速攻持ちキャラで押し込まれるリスクがありました。
ところが、2弾からはそのプレイが敗北に直結することとなり得ます。
理由①サーチ札の増加
以前は《ナミ》しかサーチ手段がなかったため、手札切れを待つという戦い方ができました。(そのため1弾のゾロ側はウタで手札補充をしていました)
しかし、《ダダン》の登場でその戦い方は否定されます。
単純に手札を補充するだけでなく、《ダダン》から《ナミ》を加えることができるため、《ダダン》1枚から《ナミ》+麦わらと最大2枚までカードが補充できます。
また【ゾロ】がある程度動きが決まってる際、あえて2枚目の《ダダン》をプレイせずキープしているというケースがあります。
相手視点ではマナカーブ通りに動かれてしまうと察知することが難しく、リソース勝負に持ち込もうとしたタイミングで《ダダン》をプレイされ一瞬でプランが崩壊します。
理由②軽量キャラ増加
従来では2コスト帯が多く、そこそこドンを消費しながら盤面を作っていました。
しかし、《ダダン》の採用により2コストから1コストへ軽量化され、展開も軽く早くなりました。(従来なら4コストで2面展開だったところが、現在は1×4体や2+1×2の計3体のような展開ができるように変化しています)
展開数が増えるとミラーマッチはともかく、緑側は追いつけません。
序盤緑側は多くても1度に2体までしか展開できないため、こちらの攻撃回数より相手の展開数の方が多くなります。
その間、リーダーゾロはこちらのライフを攻撃してくるため、ライフレースで差をつけられてしまいます。
理由③《白ひげ》
①、②と話が繋がります。
ライフを殴っていないのに相手の手札が減らず…①
盤面を攻撃しているのになかなか形勢が変わらない…②
そんなこんなで9ドンの時間。
《白ひげ》プレイ、リーダー7000に。
もう手遅れです。
ライフを削りたくても7000ラインの壁は高く、逆に次のターンからリーダーゾロと《白ひげ》にこちらのライフが削られます。
(実際は《おでん》などで対抗できますが、盤面ばかり見て大型を出さないと本当にこうなります)
と、《白ひげ》によりこのような影響があったと考察しました。
緑に関しては細かいことの積み重ねで負けてしまったというパターンもあると思います。
・ライフを削らなかったせいで《白ひげ》に屈する
・序盤中盤、考えもなしにレストのナミをリーダーで攻撃してテンポロス
・お菊で雑に攻撃してブルックやマイナスで取られる etc...
《白ひげ》は【ゾロ】ミラーを強く見ているカードです。
加えて情報もあまり出回っていなかったことから《白ひげ》入りに対する各種デッキの対策が不足していたとも考えられます。
完璧なメタ読みおよび構築を用意した《白ひげ》入りの【ゾロ】が大阪CS環境の勝ち組デッキだったと言えるでしょう。
また【イワンコフ】が勝ち上がっていたことから対策の追いついていないデッキはトーナメントシーンにおいて悪くない位置にいると考えられます。
○福岡CS

大阪CSから3週間弱。
この期間に目立った構築は2つ。
1つが大阪CS直後の非公認大会で全勝優勝した【おでん無し錦えもん】です。
もう1つが愛知CS直前、非公認大会で【錦えもん】が2名全勝優勝していました。
注目する点は《ホーキンス》が0〜1まで減っていました。
これは緑のミラーマッチにおいてプレイするタイミングが限定的である点、
【ゾロ】相手に効果的な場面が少ない点
の2点が理由だと考えられます。
緑ミラーにおいて、
先行5ドンで《ホーキンス》を立てると返しにリーダー効果により3コストで《ヤマト》→《ホーキンス》レスト→3ドンつけて8000リーダーで《ホーキンス》という流れで綺麗に取られてしまいます。
後手6ドンでは《お菊》+《ドレーク》のターンとなり置くことができません。(先行最速《おでん》の対抗用で出すことはあります)
となると先後問わず1番起きやすいのは10ドンからになりますが、その頃には大型で攻撃する時間帯なので5ドンを確保するのは難しいことがあります。
【ゾロ】の連覇か、【錦えもん】が覇権を取るのか...
優勝 【キッド】(8キッド型)
準優勝【錦えもん】
福岡CSは緑のワンツーフィニッシュでした。
【キッド】が【錦えもん】と差別化できる点は終盤の決定力です。
【錦えもん】はリーダー効果で序盤ワノ国を展開し盤面有利のまま押すデッキです。
対して【キッド】はコスト通りに展開していくため【錦えもん】に比べると展開速度は遅くなります。
しかし、終盤戦になると評価は逆転します。
リーダーの攻撃回数が異なるため
極論ですが、【錦えもん】は盤面のキャラを全て倒されるとリーダーの1回しか攻撃ができません。
また緑には速攻がいないため、相手視点【錦えもん】は《おでん》が絡まない場合、攻撃回数の想定ができ、
・ブロッカーを置く置かない
・ブロックするしない
・カウンター切る切らない
の判断がしやすいです。
対して【キッド】はリーダー効果で任意の2回攻撃ができるため、
相手視点2回攻撃ありきでプレイを想定する必要があり、ドンの使い方や守り方が窮屈になります。
そんな【キッド】には2種類のタイプが存在します。
1つ目が1弾環境のような攻撃型です。
《7キッド》、《おでん》、《お菊》などのアタッカーを展開し、リーダー2回攻撃などで一気にゲームを決定づけるデッキとなります。
2つ目が福岡CS優勝、大阪CSベスト8のような防御型(通称:要塞型)です。
構築は以下のようなものとなります。

福岡CS優勝と大阪CSベスト8【キッド】の大枠のコンセプトは同じで、
「《8キッド》成立まで相手ライフは削らず、成立後は《8キッド》を死守しながら相手ライフを削り切る」
という内容です。
しかし、2者には1点大きな違いがあります。

福岡CS優勝構築にはアタッカー(1000カウンター付き)が存在しているのです。
《8キッド》着地までにライフが押し切られないよう攻撃先は盤面のみ、自分の盤面が完成したタイミングで一気に押し込みます。
その際、《5ヤマト》がいると
ダブルアタックでライフレースを早め、バニッシュで手札の補充を防ぎます。
相手視点、この攻撃は受けづらいためカウンターを切ります。
しかし、徹底してライフを《5ヤマト》以外で削らないため手札補充が間に合わずどこかのタイミングでカウンターが無くなり攻撃が通ります。
1度《5ヤマト》の攻撃が通ってしまえば相手の手札にカウンターがないことが透けるため、残りの3点を
テキトーなキャラ+リーダー2回+《8キッド》の4回攻撃でリーサルも狙えます。(余裕があるなら次ターンにもう一度《5ヤマト》から仕掛けて確実にリーサルを狙うこともありそうです)
従来の【防御型キッド】は《8キッド》の横で《モモの助》、《ボニー》、《雷ゾウ》らで手札を増やしながら、相手のライフを削るというコンセプトでした。
このタイプはブロッカーが1体だとレストにするカードでブロッカーを無力化し、余ったドンを全てつけた攻撃で突破されるリスクがあります。
それを防ぐため2体以上のブロッカーを置きますが、2体並べると、
《8キッド》+ブロッカー×2=3面使うため、手札を増やすキャラは2体までしかおけません。
相手の攻撃回数次第ではジリジリ手札とブロッカーが削られてしまいます。
対して《5ヤマト》システムの良い点は、手札を増やすシステムとは別にライフを削りに行きます。
《8キッド》+《5ヤマト》+ブロッカー×2+手札補充キャラ
のような5面でゲームを進行すると思います。
また、相手のライフを削るとリーサルを回避するために相手はブロッカーを展開します。
その際、ドンを攻撃ではなく、ブロッカーに消費します。
つまり、その分打点に回せるドンが余らず、
・攻撃時の打点が下がる
・攻撃回数が減る
ことで《8キッド》の生存確率が上がります。
その間も《5ヤマト》で攻撃し相手を先に息切れされるシステムとなっています。
(攻撃は最大の防御)
《8キッド》は強いです。
相性的な強さでは
・青系デッキ
・ロー
に対して強いです。
予選ではどちらにも当たる可能性があるため、大阪CSの《白ひげ》同様、構築勝ちも狙えます。
概念的な強さでは
「戦い方を知らない人」に対して滅法強いです。
《8キッド》は大抵の場合、隣に1〜2体ブロッカーがいます。
状況にもよりますが、ブロッカーがいる場合は8000ラインで攻撃するのが定石です。
例えば、
相手:《8キッド》+ブロッカー×2、手札5枚
自分:6ドン余りで《7キッド》×2+リーダー
が攻撃できる状況だとします。
ここで《7キッド》に3ドンずつ分けて10000×2回をするとブロッカー2体で守られて終わります。
→消費2枚(ブロッカー×2)
そうではなく、8000.8000.9000という分け方をして攻撃します。
→消費3枚(カウンターorブロッカーを計3枚)
【キッド】は《8キッド》を死守してきます。
8000の攻撃に対して1000カウンターが無ければ迷わず2000カウンターを使います。
8000の攻撃に対してカウンターが無ければ迷わずブロックします。
つまりブロッカーがいる場合の《8キッド》に対しては、攻撃の回数=相手が使うカードの枚数となります。
ブロッカーがいないのであれば少し高い打点を作って手札をたくさん使わせましょう。
大阪CS以降研究が進み、緑側が【ゾロ】に対するプレイがある程度確立したこと、周知されていないタイプのデッキの台頭が結果として緑のワンツーフィニッシュをもたらしたと考察できます。
【ゾロ】は大阪CSでとても完成度の高い構築がベースとなった結果、構築における変化の伸び代は少ないようにも感じられました。
対して緑側は《ネコマムシ》や《トラファルガー・ロー》の採用など細部の調整により相性差を生む余力があるように見受けられました。
○愛知CS

2022年最後のCSとなった愛知大会。
下馬評では【ゾロ】がやや減少傾向にありました。
理由は主に2つあり
・各デッキの【ゾロ】に対する立ち回りが確立されつつあること
・不利デッキの存在
が挙げられます。
重要なのは2つ目の「不利デッキの存在」です。
まずは【錦えもん】です。
これについては【錦えもん】側の理解度が上がったことによるボトムアップで勝ちづらくなったという印象です。
《白ひげ》を考慮してライフレースで遅れないように立ち回り《おでん》を置いてしまえば概ね勝ちです。
(さらっと書きましたが、このあたりから緑側で
《おでん》 > 《7キッド》という考えが生まれてきました)
次に【イワンコフ】の存在です。
きちんとマイナス札(《ゴードン》や《お玉》)を引けていれば問題ありませんが、引けていない場合、7000ラインの処理が難しい【ゾロ】はライフを押し込まれる危険性があります。
また【イワンコフ】側の構築も変化しており1コストカードが多く採用されるようになりました。(主に《ペローナ》)
1コストキャラは緑相手の《モモの助》、《ボニー》を倒せるだけでなく、小型での攻撃がメインの【ゾロ】のキャラをリーダーではなく、キャラで倒せるようになりました。
従来の構築の場合、《バギー》が引けていないとリーダーでキャラを倒すしかなく、その分ライフレースに遅れを取り、【ゾロ】にライフを押し込まれるような印象でした。
しかし、1コストキャラの増加により低打点キャラを使って【ゾロ】のキャラを取ることができるようになりました。
結果として、リーダーでライフを詰めやすくゲーム速度が上がったという印象です。
最後に愛知CSよりシェアの増えた【白ひげ】です。
先の大阪CSにて【ゾロ】が《白ひげ》を使うとミラーマッチで有利になると記しました。
リーダー白ひげは常時6000のため、【ゾロ】が得意とする5000ラインでの手数攻撃プランを否定できます。
また攻撃面では常時6000でのリーダー攻撃だけでなく、《モビー・ディック号》の採用により、後半の打点ラインが一気に跳ね上がり押し込みが可能です。
場持ちのいい《マルコ》や除去として展開していた《ビスタ》がアタッカーとなり無駄なく攻めに転じることができます。
以上の理由から【ゾロ】が勝ちづらい環境に変化したのではないかと考えられます。
そんな愛知CSを制したのが
優勝 【イワンコフ】
準優勝【錦えもん】

【イワンコフ】はその安定感から《イワンコフ》を決めやすく、ゲーム展開の再現性がとても高いデッキと言えます。
1dayトーナメントにおいて
a.安定感は低いが爆発力のあるデッキ
b.パワーは下がるが安定するデッキ
のどちらかが勝ちやすいと考えられます。
【イワンコフ】は動きの再現性の高さからbの要素が強く、《イワンコフ》→《ルフィ》が2度決まれば圧倒的優位になることからaの要素も兼ね備えています。
トーナメントで勝つためのデッキ選択がこのような結果に繋がったと考えられます。
(【錦えもん】も《ホーキンス》を採用していたため、大会に合わせたいい構築でした)
今大会の注目する点は【白ひげ】の台頭です。
構築は主に3タイプあり
・白ひげ海賊団軸
・麦わら軸
・《白ひげ》+カウンター多め
となります。
また【白ひげ】の中でも《白ひげ》の採用の有無が分かれており、狭いカードプールの中でいくつかのタイプが存在しています。
(配信の【白ひげ】ミラーも別タイプでの対戦でした)
【白ひげ】が勝ち上がった要因は以下のように考えています。
①有利デッキがある
【ゾロ】、【イワンコフ】、【カイドウ】、混色に有利と言われており、相性勝ちが狙えます。
②研究がされていない
あまり出回っていないタイプのデッキのため、対面のプレイが定まっておらず、適切な対応ができないままゲームが終わっていると考えられます。
・【白ひげ】側への盤面処理
・ライフを攻撃する打点
・手札の削り方
などが研究できておらず、負けたというパターンがあるように思えます。
今となっては《マルコ》を5000ラインで攻撃して手札を削るプレイが出回っていますが、初見でマルコを出された際に、そのようなプレイが取れるかは難しいと思います。
初見の相手にはアドリブ力が試されるので、研究がされていないデッキはその部分で差がつき勝てるのではないかと思えます。
これらの理由から【白ひげ】が愛知CSで勝ち上がったと考えられます。
○総括
以上が、愛知CSまでの環境推移総括です。
現状、母数が多い【錦えもん】が決勝トーナメントまでは来るものの、その分研究も進んでおり対応できる形のデッキが勝ち切っているという状況です。
ここ最近はTwitter/noteやYouTube等により情報流通が早く、構築単位での寿命が短くなっている印象を受けます。
今日強い構築も翌週には対策された構築やデッキタイプが出現し、勝ち切れなくなっているようにも見受けられました。
来週には宮城CSがあります。
トップシェアが勝つのか、新たに研究された構築/デッキタイプが勝つのか。
各プレイヤーの練習の成果が発揮される宮城CSが待ち遠しく思えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
