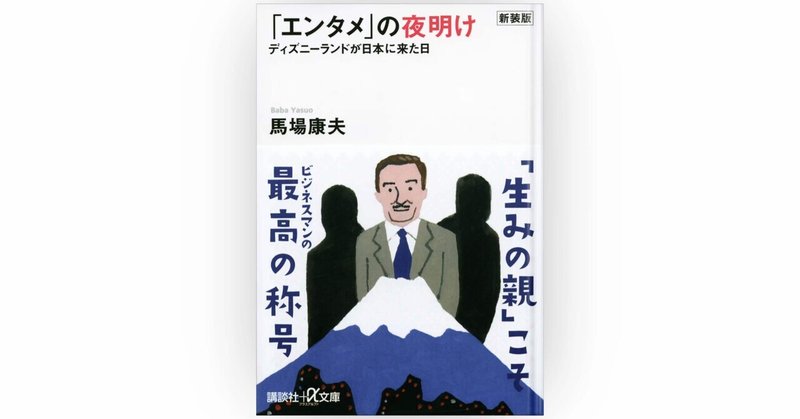
正力松太郎氏のテレビ普及から学ぶ!『61日目』
エンタメの夜明けを読んでます
こんにちは、いしいです。
今、『エンタメの夜明け(著:馬場 康夫)』を読んでいます!
内容は戦後日本のエンタメビジネスの草創期から東京ディズニーランドの招致までを、小谷正一と堀貞一郎:2人のプロデューサーを軸に描いた物語です!
この本の中に、テレビ文化の普及やCM文化の創り出す場面が描かれています。
そこで打たれたテレビ普及のための切り札がすごすぎると思い、言語化していきたいと思います!
正力松太郎の一手
話を遡ると、
その当時、日本はまだまだラジオ文化でした。
そして、NHKが日本で最初にテレビ放送を始めたときの契約台数は866台でした。
そのため、誰もがこのような契約台数で民間放送を立ち上げても、スポンサーはテレビを広告媒体として捉えないと考えていました!
ただ、日本テレビ創始者でもある読売グループ総帥の正力松太郎氏はテレビの民間放送の可能性を感じていました!
そこで、正力氏は機材を集め、広告も何とか取り付け、放送にこぎ着けることができました!
それとは別に!
正力氏は、私財(今の価値でいうと5億円以上)を投じて、100台ものテレビを購入し、都内の繁華街に設置させました!
そして、テレビ放送が始まって2カ月ほど経った頃、ボクシングフライ級チャンピオン白井義男氏の王座防衛戦が日本テレビで中継されました!
その際、街頭テレビの前にあふれた群衆が車道や線路をふさぎ、警察が放送中止を求めるほどの騒ぎになったそうです!
この時、ラジオとテレビのスポンサーだったアサヒビールが、どちらのメディアで広告に接触したかを調べたところ、テレビの方が多い結果になりました!
街頭テレビの前に大衆を集めることで、正力氏はテレビ広告に価値があることを証明しました!
良いものを使うと戻れなくなる
そして、ここからは自分の血肉にしていくために、言語化していこうと思います!
ここで学べると思うことは、テレビがほぼ0の文化から、市民権を得るまでのプロセス原理です!
人間は、一度良いものを使うと、前に使っていたものに戻れなくなってしまいます!
今、人とやり取りするために手紙を使う人はほとんどいないと思います。それは、メールやSNSの方が良いと知っているからです!
その当時のテレビも、あったらいいけど、なくても困らない技術・サービスだったと思います!
けれど、正力氏は街頭テレビで魅力を知ってもらい、テレビをなくてはならないものに変えさせました!
根本となる考え方
知ってもらい、なくてはならないものにする
私は文化を作ろうとした時に、これは根本となる考え方だと感じました!
テレビの普及の時も、その前からラジオでの広告需要があったように、0→1 で文化が作られることはほとんどないと思っています!
そして、私のやろうとしていることも、「食」という大きな需要から派生した文化を作ろうとしています!
そのため、今回読んでいる『エンタメの夜明け』は文化を作っていくうえでとても良い勉強になっています!
おわりに
まだまだ言語化が全然終わっていませんが、今自分でわかるところはこれくらいです。
ただ、まだまだ何か言い表せてないものが残っているようでもやもやしています!
本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
