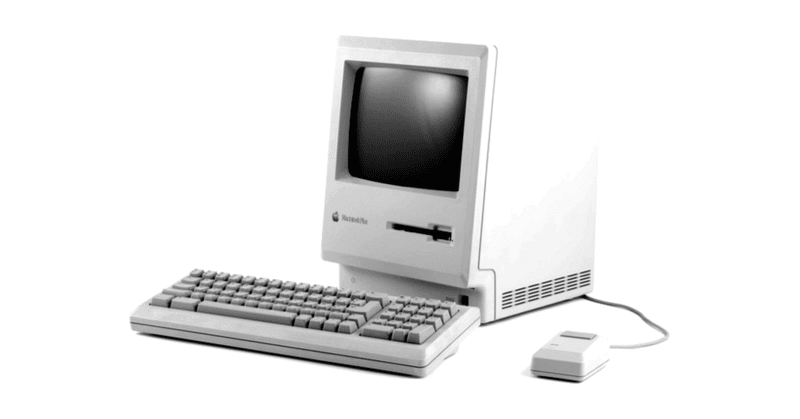
漢字は情報処理向きの文字体系
日本語は世界で一番難しい言語です。というのは、日本語以外で複数の文字体系を使用している文化圏は有りません。多分、ベトナムとか朝鮮や韓国等の旧漢字文化圏では、漢字が多少生き残ってるかもしれませんが、基本はベトナム語やハングルです。日本語は、漢字、平仮名、片仮名の三文字体系です。その所為か、日本語の発音は非常に単純化されてます。漢字を含めて日常生活で使用する文字数は数千ですが、其等の発音は五十音に纏められており、書き言葉に注力した言語体系です。
厩戸皇子と稗田の阿礼・太安万侶が文字を発明した時は、一文字が一つの意味を持ち、固有の発音と結び付いてました。漢字が数千文字有るのを考えれば、当時の人々は数千の発音を聞き分けてたハズです。此は中国では生き残ってます。中国語では、一漢字一発音で、五十音に制限された日本人の耳には、中国語の似た発音の言葉は聞き分け不能です。
文字の使用が一般化すると、文字体系の簡略化が進みました。数千の漢字の書き方と発音・意味を覚えるのは記憶力の優れた小学校低学年でも苦行で、況して大人には無理です。文字体系簡略化の第一段階として、似た形の漢字を纏めて一つの漢字に複数の意味を持たせました。其時、文字形で結合したので、一つの漢字が複数の全く異なった意味を持つ様になりました。
一つの漢字が複数の意味を持つ様に成ると、音だけを表現して意味を持た無い文字が派生的に生れました。其が表音文字で、平仮名と片仮名です。平仮名は琉球で生れ、片仮名は朝鮮で生れた様です。日本政府に武力で占領される前の琉球王朝では、漢字と平仮名を使用してました。其処から日本に逆輸入された様です。片仮名の発祥・発展は古文で漢文を学習した人達にはお馴染でしょう。
平仮名の導入に際し、言葉の発音を五十音に制限しました。いろは唄に観られます。その際に、何故だか「R」の音と「L」の音を纏めました。今日「R」音と「L」音を区別出来無いのは世界で日本人と韓国人だけと言われてます。因みに、日本人が「らりるれろ」と発音すると「らり」は「R」で「るれろ」は「L」に聞こえるそうです。「R」と「L」を分けて、五十五音に纏めてれば日本人の英語嫌いは、も少しマシだったかもしれませんね。
其後、平仮名は「海の路」を通じて南アジアを経由し、西アジアからヨーロッパに伝わりギリシャ文字・アルファベットの元となりました。一方、片仮名は朝鮮から「草原の路」を経由してシベリア、中央アジア、東ヨーロッパに伝わりました。所謂キリル文字です。朝鮮と中国・ロシアが仲が良いのは歴史的背景が有りそうですね。
では、何故文字セットが情報処理に関連するかというと、情報を伝達する効率に効いてきます。情報処理の最小単位を、此処では「情報素子」と呼びます。片仮名では「トークン」です。是等2つの記載を比較すれば、同じ4文字でも「トークン」では、説明を加えないと意味不明ですが、「情報素子」と言えば漢字圏のヒトなら説明しなくても概念は伝わります。端的に言って、漢字なら一文字で一情報素子ですが、表音文字だと、意味を持つのは単語なので数文字で一情報素子です。つまり、表意文字は、表音文字と比較して、同じ文字数で数倍の情報伝達が可能になります。例えば、人工知能の使用量は情報素子単位で課金されます。日本語は一文字一情報素子で、英語なら一単語一情報素子で、日本語の方が高く付く様な気がしますが、情報処理としては合理的って感じです。ただ、日本語では平仮名と片仮名の分だけ損してる気もしますが、きっと中国語が沢山使われてるんでしょうね。
思考や言語に依る情報処理は言葉に依存します。単位時間内に流せる文字数が一定とすると、漢字を使うと、表意文字の場合と比較して数倍の情報処理が可能です。中国人を観てると、情報の共有が非常に速いし的確な感じがします。CIAが中国の脅威に付いて語ってたけど、アメリカ人を観てると、中国語の聞き取りが出来ても意味の理解が追い付いて無い、所謂諜報活動が出来無い。頭の出来が違うって感じですね。ただ、その能力を何に使うかは別問題です。
ところで、昭和世代の人達は覚えてるかもしれませんが、テレビが一般化し出した頃、「一億総白痴化」と言われました。其現象は、テレビに依って平仮名の話言葉が優勢になり、漢字を使用し無くなった事で説明できます。では、白痴になった頭の良い人達を何て呼べば良いんでしょう?やっぱり、「頭の良い人」かな。本当の処、頭の良い人が「頭が良い」と言われるのは、本人が「頭の良い人と呼んでくれ」とお願いするからそう呼んでるダケで、頭の良い人の知力には無関心です。本人も、太祖母に「家は代々頭の良い家系だから」と言われて虚勢を張ってるだけで、知力を磨く意志には欠ける。アインシュタインが良い例です。博士と言うよりコメディアン。そいえば、戦争してる国にもコメディアン居ましたね。クワバラ、クワバラ!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
