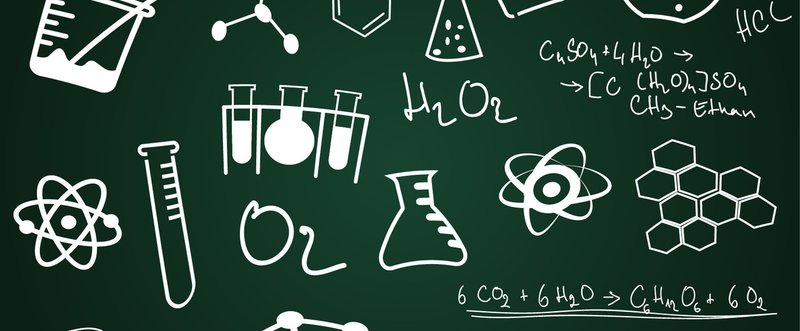
揺れる星、瞬く星
夜空の星って、本当にゆらゆら揺れているのってご存知でしょうか?
小説や詩の中では、『揺れる』、『瞬く』という表現がよくありますが、単にロマンチックを演出する表現なのではなく、事実を言い当てている表現なのです。
こんな動画を見てみましょう。
とある天文台の望遠鏡が木星を撮影した動画です。
まるで、水面に映したようにゆらゆら揺れていますね。
なんでこんな事が起こるのでしょうか?
![]()
1.シンチレーション(scintillation)
光の屈折率は強い風や水蒸気によってかわります。
地上が凪いでいても、空の上の、上の方には強い風が吹いたり、また、地表付近では水蒸気が渦巻いていたりして屈折率は一定ではありません。
そこに星の光が来るので、光の経路が曲げられてしまいます。
この現象は、天文の分野ではシンチレーションと呼ばれ、これを抑えるために標高の高い所や砂漠、果ては地球外に天文台を設置してこの現象の影響を抑えています。
![]()
2.より瞬いて、揺れる星
肉眼で見る際、太陽系外、地球からはるか遠いところにある星で、この揺らぎが起きたらどうなるでしょうか?
太陽系外にある星は、安価な望遠鏡でのぞいてみても、肉眼で見るのと変わらないような光点がみえるだけです。
今回紹介した動画に写っている木星は、縁がゆらいで見える程度です。しかし、太陽系外の星はさらに光点が小さいため、シンチレーションによって、星全体が小刻みに移動します。また光の色によって屈折率が違いますから、条件によっては赤や青の光が星の縁から滲み出して見えることもあります。
なので、遠い星ほどより揺れて、瞬いて見えるのです。
(もちろん、単純な輝きの強さは、単純に地球からの距離だけで決まるものではありませんが)
そんな感じで、揺れる星、瞬く星の話でした。
![]()
3.おまけ
発光分光分析という方法があります。これは、発光する物質をカメラでとらえ、その光を構成する光の波長を分析することによって、その光の中にどんな元素や分子が含まれているかを調べる方法です。
この方法は、当然夜空に輝く星の光にも適用することができます。星の光を解析することでその星の大気の成分を知ることができるのです。
宇宙の話は、壮大で現実離れしたようなものばかりですが、身近な技術を使うことで頭の上で輝いている星への足掛かりがあると思うと、何だか楽しくなってきませんか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
