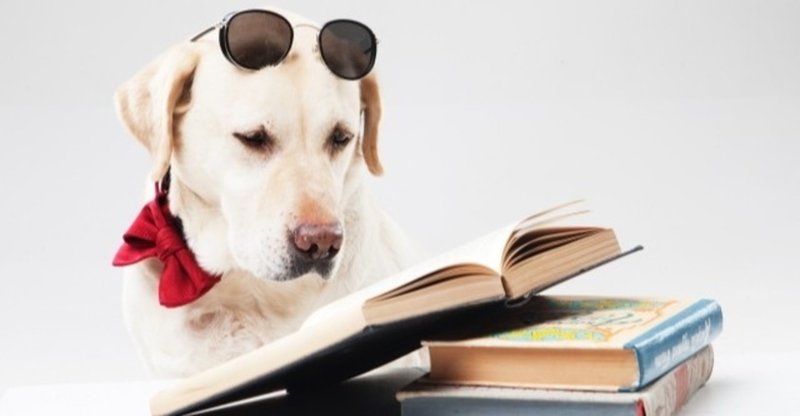
リキチャンシュタイン博士ってどんな教育者?[ボイス感想・ネタバレ有]
~~~~~~~~~~~~~~~
2021年3月6日追記
前作にあたるハロウィンボイス2019の常設販売が開始しました。現在までに発表されたリキチャンシュタイン博士が登場するボイスはすべて入手可能になったということです。
当記事はネタバレを含みますので、ぜひ視聴されてからお読みいただけると幸いです。
~~~~~~~~~~~~~~~
ボイス作品を小難しく考えながら聴く人間、あごひげ20cmです。
ハロウィンの翌日、ジョー・力一(りきいち)の新作ボイス「リキチャンシュタイン博士リターンズ」が発売された。
【ジョー・力一 個人ボイス販売開始!】
— にじさんじ公式🌈🕒 (@nijisanji_app) November 1, 2020
本日11/1(日)より、オフィシャルストアにて、ジョー・力一(@JoeRikiichi)の個人ボイス
「リキチャンシュタイン博士リターンズ」の販売を開始いたしました!
販売ページはこちら!▽https://t.co/33hGmSZcR0
リキチャンシュタイン博士は、にじさんじハロウィンボイス2019で一度登場しただけにもかかわらず、一年経ってなおファンから愛されている架空のキャラクターだ。2020年10月にはボイス一周年を記念して「#リキシュタ60分一本勝負」というワンドロ企画がTwitter上で盛り上がったほどである。
自分はそんなファンの熱にあてられ、ハロウィンボイス2019が再販された折に購入。感動のあまり半ば衝動的にしたためたのが前回の記事↓。
このたび発売されたリターンズは2019の後日譚となっている。リキチャンシュタイン博士自体がジョー・力一という人格を離れた派生物なのに、そのスピンオフ作品が発表されたのだから驚きである。
昨年のハロウィンボイス2019で登場したマッドサイエンティスト・リキチャンシュタイン博士のボイスが登場です
— ジョー・力一(りきいち)🤡🎈 (@JoeRikiichi) November 1, 2020
昨年自らの手で生み出した生命体との、その後の暮らしと小さな事件が収録されています(ジョー・力一は出てきません)
超スピンオフですがいいボイスになったと思いますので是非聞いてね〜! pic.twitter.com/6VYZ7cjuT2
自分は普段はボイスを買わないのだが、前回の続き物ということでさっそく購入してすぐに鑑賞。相変わらず良かった……。博士のことがますます好きになっちゃったよ。
長くなった前置きはこれくらいにして、以下では自分が感じた博士の魅力について整理しながら綴っていきます(ストーリー自体の考察は少ないです)。
前回のボイスが聴けてないけど、今回のボイスから聴いても良いのかしら…?と不安な方もいらっしゃるでしょう。
今回のボイスから先に聴くのもアリだと、自分は思います。鑑賞にあたって必要な事前知識(場面設定や人物像など)はさりげなく説明されているからです。
ただ、前回のボイスの魅力の大部分はその後の展開を解釈する余地にあり、その点が多くの人に愛されている所以かと思うので、自分で妄想を膨らませるのが好きな方はボイス再販or常設販売を待たれた方が良いかもしれません。(※追記:2021年3月に常設販売が開始されました!悩まずに2つとも買ってください!)
当記事では、前回ボイスのネタバレは可能な限り避けつつ、今回のボイスについてネタバレしながら語ろうと思います。ぜひボイスを聴いてからお読みください。
1. 一年で変わったこと、変わらないもの
最高傑作が生命活動を始めたのは、ある年のハロウィン。それからおよそ一年後ということだから、翌年の9~10月頃だろうか。
たった一年近くの間に最高傑作はめざましい成長を遂げたようだ。言語を習得し、身体能力も向上、社交性も獲得した。おおよそ小学校低学年くらいの印象を受ける。
人造人間を産み出しただけでも十分な偉業であるのに、こんなに豊かに成長するとは。しかもまだまだ伸びしろが感じられる。博士の天才っぷりを改めて思い知らされる。
しかし、相変わらず博士は世間から白い目で見られている。学会からは認めてもらえず、近所の人々からは距離を置かれている様子だ。倫理を逸脱した研究をしているのだから当然かもしれない。それでも博士は自分の研究室にこもって自分のやりたい研究を独力で進めている。いつかは認めさせてやる・賞賛せしめる、という闘志を燃やしながら。
こう書くと、「成長し続ける最高傑作⇔世間に認められないままの意固地な博士」という構図に見えるかもしれない。しかし、そこに悲しさや暗い雰囲気は一切ない。むしろ、博士のブレなさがあたたかく描写されていると感じた。
博士が最高傑作に提示する「常識と好奇心なら好奇心をとれ」「何をすれば楽しいのか、自分の頭で考えろ」などの教えは、博士自身のこれまでの生き方を集約したものだ。なんと力強く説得力のある人生哲学だろうか。自分を突き通す博士という存在がどっしりと構えているからこそ、この教えは最高傑作にとって信頼できる行動規範になっているのだと思う。
以下では、そんな博士の生きざま・姿勢を掘り下げながらその魅力をさらに考察していく。
2. 研究者としての博士
自己紹介でも"天才科学者"と豪語するなど、たびたび自分の能力や成果を誇示する博士だが、研究の最中は正反対な一面を見せる。つまり、自分を過信しない。慢心はバイアスになりうるからだ。目の前の現象として最高傑作を静かに観察するという姿勢。
離れの小屋で犬をかくまい始めた最高傑作に対しては、すっぱり関与をやめる。ヒアリングを強制することはしない。距離が離れてからも最高傑作の動向や雑感をボイスレコーダーに録音し続けるが、その声に焦りの色はない。落ち着いたトーンだ。
感情や思惑を抜きにして対象を見つめるのは案外難しい。人間は感情を推し量ってしまう生き物だからだ。動物の何かしらの行動を見て「きっとこう感じているだろう・こう考えているだろう」と思った経験は誰にでもあると思うが(それが当たっているかどうかはともかく)、そうした雑念は研究の解釈を歪めてしまう恐れがある。
そこで研究者は研究手法を工夫する。リキチャンシュタイン博士が最高傑作の成長過程を記録するためにまず選んだのは、ヒアリングという手法だ。これは、対象に自発的な発言を促すことで観察者のバイアスが極力入らないようにするものだ。
ヒアリングを拒否されてからは、サブの手法として行動観察を続けた。行動観察をする上で大事なことは、対象に影響を与えないように細心の注意を払うことだ。距離を詰めることなく最高傑作の動向を静観する博士の姿にも、研究者としての信条が表れている。
一方で、主観が混じる日々の雑感などはボイスレコーダーに録音する習慣のようだ。音声媒体は後で精査するときに膨大な時間を要するといったデメリットはあるものの、多くの情報を手軽に残すことができる。こうした副次的な記録の積み重ねが、後々聴き返して重大な発見につながることも往々にしてある。ぬかりない二段構え。
博士の人生哲学は『楽しさ・好奇心を大事にする』であるが、研究者として最高傑作の前に立つときはできる限り感情を排して冷静な観察者に徹する。このギャップ。ただの享楽にふけるマッドサイエンティストでないことは前回の感想記事でも指摘したが、改めて実感させられる。
3. 教育者としての博士
最高傑作を育てる博士の基本スタンスは放任である。街を好きなように歩かせ、自由を浴びさせる。何がしたいか、どうすれば楽しいか、自分の頭で考えさせる。
この放任っぷりは、上述した研究者としての姿勢と無関係ではない。最高傑作の意思を尊重するという教育方針と、観察対象に干渉しすぎないという研究上の基本姿勢はおおむね合致する。
最高傑作に話しかけるときの博士の声には優しい響きがある。しかし博士が見せる"優しさ"は声だけではない。陰ながらさりげなく最高傑作をサポートするという、行動をともなう優しさもあわせ持つ。
たとえば、犬に食べさせてはいけないものがあることをそれとなく伝えたり。飼育に際して足りないものがあればこしらえると提案したり。最高傑作がより遠くへ逃げる可能性を見越して小型ジェットを持ってきたり。
このような博士の細やかなサポートがあってこそ、最高傑作は思う存分 自由を追求することが出来ている。「自由には責任がともなう」はフロイトの言葉だが、半人前の最高傑作の自由に対して、今はまだ博士が面倒を見ている格好だ。
博士の家を訪ねてきた犬の飼い主らに対して、最高傑作の代わりに頭を下げた博士の姿はとりわけ印象的だった。まるで周囲を顧みない人物かのように誤解されがちだが、基本的に博士は他人の感情を思いやった配慮ができる暖かな心の持ち主である(結局は、天秤にかけた上で自分の好奇心を優先しがちなのが玉に瑕……)。教育者、あるいは親としての一面が、犬の飼い主らへの対応のうちに見え隠れする。
そんな博士が犬の飼い主に言った台詞は、イチオシのパンチラインだ。
最高傑作の、この先の未来をどこまでも観測し続けたい。(中略)
そのためなら多少の非合理や手間暇をいとわない。
そういうもんでしょ、幸福って。
同意を求めるような口ぶりでありながら、最高傑作に対する博士の真情がありありと吐露されている。
研究者としての言葉と、教育者としての言葉。それらを『幸福』と総括する博士の、なんと力強く気高いことか。
今回のボイスのさらに続編が出るかどうかは、現時点では分からない。この先、二人は世間からどう見られるのか。最高傑作がどんな選択をして、どう成長していくのか。気になってしょうがない。
でも、一年たっても決してブレることなく、最高傑作との過去・現在・未来を『幸福』と断じる博士がいてくれれば、少なくとも最高傑作の豊かな成長と二人の間の幸せは保証されている。そう感じずにはいられない。
願わくば、ジンゴや飼い主の母子らとの交流をきっかけに、ふたりの幸せの境界が外へ外へと広がっていきますように。。。
(はし書き) どうしても語りたかったメタな話
この記事の冒頭で「鑑賞に必要な事前知識はさりげなく説明される」と書いた。そのさりげなさの肝はボイスレコーダーに録音するという体で「地の文」が描写される点にあると思う。
上述したように、レコーダーに日々の雑感を記録することは博士の習慣になっているようだ。研究者の振る舞いとしてごく自然な範疇であるし、あくまでレコーダーに記録するために喋っているから回顧録的な独り言が多分に混じっても違和感がない。
作品への没入感を高める工夫としてよく出来ているな~~~、とボイス初心者は膝を打つほど感心しました。
(了)
最後まで読んでくれてありがとうございます! 「スキ」やSNSへのシェアなどしてくださると励みになります。 万が一、もしも有料サポートをいただけましたら、推しVtuberにスパチャを投げます。非効率なので非推奨。

