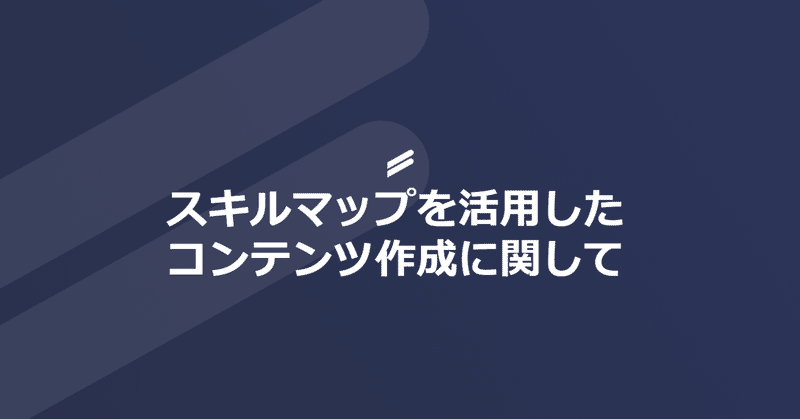
スキルマップを活用したコンテンツ作成に関して
こんにちは、株式会社ブレーンバディの兒玉です。今回はスキルマップを活用したコンテンツ作成に関して解説していければと思います。
学習量やスキルデータを活用した分析は理解できたが、特定のスキルをレベルアップさせるための学習コンテンツを、どのように作ってよいかわからない、何を作れば良いかわからない、質の高いコンテンツが作れないなど、コンテンツ作成回りのご相談をいただくことが非常に多いです。
よくある失敗例として、組織全体でヒアリングスキルをアップさせるために、ハイパフォーマーが意識していることや、マネージャーの知識や実践内容などを網羅的にカバーした研修や勉強会、コンテンツ作成を行っているケースが多いと思いますが、全体に理解させるために基礎的な内容が多く成果にヒットしているかわかりずらい、テクニックが強すぎて模倣しずらいなど、こういったケースが多いのでは無いでしょうか。
こういったケースを防ぐためにも、スキルマップを起点にしたコンテンツ作成をおすすめしています。
1.どのようなコンテンツを作るべきか
下記のような、ヒアリングスキルマップがあると仮定します。

例えば、組織としてヒアリングレベル1は全員クリアできていると仮定して、レベル2に関してはクリアできているメンバーが少ないという現在地がスキルマップを活用したアセスメントで把握できたとします。
そのケースの場合、全体のヒアリングスキルレベル2に引き上げるために、レベル2項目の網羅率をチェックします。
網羅率・・・各スキル項目に対して、アセスメント対象メンバー全体に対
して、何人チェックが付いているか。
レベル2の項目が、下記の網羅率だったとします。
・基本的なヒアリングができている 10人中/10人 網羅率100%
・クライアントの反応に違和感なく反応ができている 10人中/7人 網羅率70%
・顧客関係性が築ける 10人中/5人 網羅率50%
・顧客の解決したい問題をヒアリングできる 10人中/3人 網羅率30%
このようにスキルマップのアセスメント結果を活用すれば、ヒアリングスキルの中でどの項目ができていないメンバーが多いのか把握することができます。
2.コンテンツを作るにあたって
上記、アセスメント結果、網羅率から具体的なコンテンツ作成の項目が割り出せたと思います。この網羅率が一番低いスキル項目を改善するのが、一番成果にインパクトのあるコンテンツと言えるかと思います。
冒頭、よくある研修、勉強会、コンテンツ作成の失敗例を書かせていただきましたが、コンテンツ作成を含む、研修や勉強会などの多くは、目的設定の時点で失敗に導かれやすいケースが多いです。
目的設定の悪い例(ヒアリングスキルを上げるためにの場合)
悪い例:目的「組織全体のヒアリングレベルをあげる」
良い例:目的「ヒアリングレベル2に向けて、顧客が最も解決したい問題を
ヒアリングできる能力を身に着ける」
スキルマップを活用することにより、より具体的な目的設定が実現可能になります。この目的設定を明確にした上で、コンテンツ作成に進みます。上記のケースの場合であれば、「顧客が解決したい問題をヒアリングできる」にチェックがすでについているメンバーに、実践できていることや意識していることなどの、情報収集をすることにより、コンテンツの精度をより上げることができます。そして、実際このテーマで勉強会やコンテンツを作成した後に、次回アセスメント時に該当項目の網羅率が改善しているかどうかで、育成施策の効果も定量的に取ることができます。
3.まとめ
■スキルマップのアセスメントデータをためる
■コンテンツを作る前に、網羅率を取りに行く
■コンテンツ作成の目的設定を明確にする
■管理者は網羅率が改善しているか、モニタリングを実施する
=====================
株式会社ブレーンバディでは、「一人でも多く、パフォーマンスが発揮できる機会を提供する。」をミッションに、様々な営業組織におけるノウハウを発信中です。
ぜひ下記メディアもご参照ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
