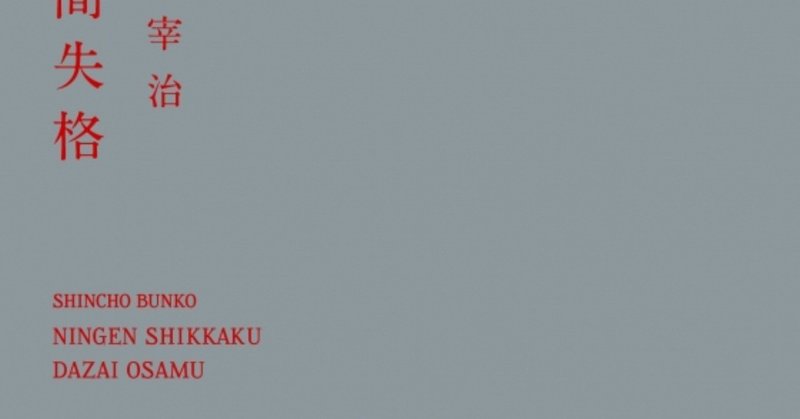
文学 「人間失格」
驚いた。
太宰治は、今まで「走れメロス」ぐらいしか読んだことはなく、その奇怪なストーリーにはほとほと嫌気が刺してしまい、ただの暑苦しい男、ぐらいの印象しか残っていなかった。
それが、どうだ。
初めて、人間失格を読んでいるのだが、なんと村上作品の主人公に似たものか。
これは、手記のようなものだろうか。
太宰の語る「恥の多い人生」の、馴れ初めを語ったものであり、同時に自分の生涯の言い訳をまるごと作品にしてしまったものなのだが、なんと孤独で陰鬱で、屈折しているのか。
その妙な孤独さが、かえって女を呼び寄せてしまうという描写も、(あるいは真実かもしれないが)、なんともそっくりなのである。
(また一方で、幼い頃より忖度を強いられ、自分の意見がわからなくなり、道化に転じることでなんとか自分の存在を保ってきたという点、幼い頃より女性に囲まれて育ってきたので、女性の扱い方に長けているという点が、実に彼にそっくりではないか。)
それにしても、恐ろしい人だ。
自分の死に際に、愛人である富恵と心中を図ろうとする間際に、自分の生涯、馴れ初めを全てしたため作品にしてしまうなんて。
なんとも、いたたまれない作品である。
彼がどうしてこのような末路を歩むことになってしまったのかをひたすら弁明した、不幸としか言いようのない鬱屈とした雰囲気がそこら中に漂う作品であるにも関わらず、読者をその不遇の中へ、ゆっくりと、しかし足取りはしっかりと引き込み、ページをめくる手を休ませない。
文体はあくまで主体的なのだが、作品中に述べられた太宰の人間に対する姿勢は、恐ろしいほど客観的であり、実際太宰は人間を畏怖している。いえ、正確に言えば尊敬の念は抱いていないのだが。
子供の頃から忖度を余儀なくされ、顔色を常に伺って育った子供は、将来自分で選択することができない、はたまた自分の意思というものが分からなくなってしまう。
つまり、究極の他人軸の中でしか生きられなくなってしまう、ということを、太宰の数々のエピソードと共に、読者にまさしく身をもって諭しているわけなのだが、最も物悲しいのは、太宰自身がそのようになってしまった自分自身を一番悲観していた、という事実だ。
分かっていながら、止められない。よもや、人間に対する信頼を完全に失ってしまった今となっては、そうするより他に無かったのだ。
酒、女、タバコ、薬。
一通り手を出さなければ、太宰が人前で正気を保つことは出来なかった。
それほどまでに、傷つきやすい、壊れやすい繊細な心を持っていたのだ。
誰にでも優しいように見えたのは、本当は、自分自身を守るために他ならなかった、という事実を、太宰は作品中でも繰り返し語っている。
生きることのやり過ごし方、人生のやり過ごし方を20代にして知ってしまった太宰が選んだのは、死、はたまた自殺という終焉。
究極の自己防衛。
生涯孤独に苛まれ、愛されること、そしてありのままの自分を受けて入れてくれる場所を探し求めた太宰が、やっと見つけた安息の地。やっと見つけた、本当の居場所。もう、自分を飾り立てる必要など無いのだ。偽る必要も、その結果罪悪感に苛まれる必要も無いのだ。
そうですね、
この世界は、あなたには少しばかり厳しすぎたのかもしれない。
どうか向こうで、恵まれますように。
合掌。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
