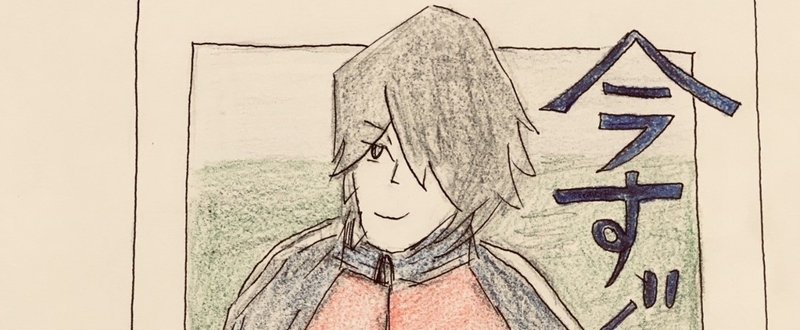
無口な土曜日 『ヴィンセント海馬』3
4月8日土曜日。にぎやかな河川敷に3人の高校生。
村上美南、大澤直也、そしてヴィンセント・VAN・海馬
別々の高校に進学した彼らが3人が集まった目的は、少年サッカーの応援だった。大澤直也の弟、健也が出場している小6の市民リーグ開幕第1戦。弟、ブラザー・ケンケンはキャプテンを任された。腕に巻かれている赤いキャプテンマークがりりしい。
「すごいね、ケンケン、キャプテンじゃん! なんか昔よりイケメンになってるんだけど」
美南がほめるが兄のナオは素直に受け取らない。
「他のヤツが下手なだけだよ。あいつがキャプテンとか終わってるよな」
「うん」
「うん?」
ヴィンセントが会話そっちのけで観ているのはもちろんリストだ。市民大会にしてはかなり立派な、主催者が子どもとその親のために張り切って作ったパンフレット。フルカラーで全チームの情報が詳細に載っている。
この市民リーグに登録されたすべての少年の顔と名前と背番号、ポジション、あこがれの選手、そして将来の夢はボサボサの銀髪の奥にしっかりと刻み込まれた。
リストをのぞきこんだ美南が、ケンケンの『憧れの選手』の欄にあった名前を見つけて喜んだ。
「かわいい! お兄ちゃんの名前書いているし!」
「なぬ! おい・・・ハズッ! あいつぶっ飛ばす」
「とかいって嬉しいくせに」
「あいつ本物のサッカー選手、ぜんぜん知らないんだよ。ていうかオレ、もうサッカーやめたんだぜ」
直也はスマホのゲームの画面に目を落とした。美南は手元に生えている草をむしって友だちに投げつける。
「もったいな。結構うまかったのに。外でゲームとかしてんなよ。バカじゃん。あーあ、直也がJリーガーになれば、わたしも自慢できたのになぁ」
「オレよりうまいヤツなんて1億人くらいいるよ。ていうかもったいないのは――」
直也は顔を上げて海馬を見た。
「お前だよ。サッカー弱ぇとこ行って。しかもさっそく学校サボってる」
「ケンケンの期待は裏切れない」
「スルーでいいよ。誰にでも観に来てって言うんだ、アイツ」
「なに、ヴィンセント、今日学校なの?」
「まあ。でも土曜日はイベントが多いから毎週休むことにした」
中学時代から海馬との会話に慣れている2人はその発言に少しも驚かない。
それより――
直也はキツめに言った。
「ていうか美南、アホだろオマエ、入学式しか行ってないとか」
「しょうがないじゃん。ウザいヤツしかいないんだから。先生も生徒もみんなキモいんだけど。メガネしかいないし」
「メガネバカにすんなよ。お前こそメガネかけろ。ケンがイケメンとか」
強すぎるくらい大きな音でホイッスルが鳴らされ、キックオフ。バックパスを受けた新キャプテンがいきなりロングシュートを打った。ボールは大きく右に逸れ、ゴールキックとなった。兄はイラっとくる。
「下手くそ! 届かないくせに調子にのんなよ」
8人制サッカーだ。ヴィンセントは試合に出ている16人だけでなく、ベンチにいるメンバーや審判の動きをじっくり観察している。基本的に試合を見るときのヴィンセントは無口だ。直也はゲームをしながら器用に会話する。
「美南さ、今からでもいいから学校行けよ。ズルいぞ」
「ズルい?」
「こんなかでオレだけかよ、がまんして行ってるの。ていうか高校やめたら詰むぞ」
「つむって?」
「人生終わるってこと」
「早っ! わたし、もう終了?」
「バイトするにしても高校行ってないやつはムリだろ。せっかく苦労して受験して受かったのに、1週間しないでやめてどうすんだよ。お金だってもったいないだろ。とりあえず休むな。行け!」
親と同じ罵声を浴びせられた美南はヒートアップする。
「は? ナオヤだってサッカーやめたくせに、ウザいんだけど。セレクション落ちたのがショックとかウケる」
「でも学校はちゃんと行ってるぜ」
「せっかく会ってるのにゲームばっかしてんなし。消せっ!」
「やだ」
「おい、ケンカするならもう帰れよ。試合に集中できない」
美南と直也は黙り込む。そして直也はスマホのゲームを閉じ、目の前のサッカーゲームを眺めた。
フィールドからだいぶ離れたところなのに、応援の親たちの歓声がうるさい。わりと知ってる顔がいる。あの近くに行くと、あいさつされたり、高校のことをあれこれ聞かれるに決まっている。
スコアボードがないから試合が何対何なのかわからない。雰囲気からするとケンケンのチームが押しているっぽい。
「いいなぁ、小学生は頭からっぽで」
「頭カラカラ星人のおまえに言われたくないな」
「わたしたちも1000日くらい前はあんなだったんだよ」
「あんなって?」
「勉強とかなくて。楽しいことしかない毎日で」
小学校にも勉強はちゃんとあったが、海馬は引き続き無口をキープ。
「どうして受験とかあんだろう。小学校から中学に行くときみたいに、みんな同じ高校だったら良かったのに」
美南は本当にこまっていた。
いきなり学校がキライになった。
もう行きたくない。中学校に戻りたい――春休みにも宿題があって、新学期が始まるのも早くて。4月4日、5日、6日と、この3日で何回・何時間泣いたかわからない。誰に相談しても「早まるな、とりあえず4月はがんばれ」とキレ気味に言う。直也もあんなとこへ「行け!」と言う。じゃあ、このヒトは――
「ねぇ、ヴィンヴィン」
「ねぇ、その呼び方やめてくれって言ったの134回目」
冗談じゃなくて、本当に134回目だった。
「ヴィンヴィンさ、高校・・・たのしい?」
ヴィンセント・VAN・海馬は、試合から少しも目をそらさずにさらりと答えた。
「オレ、高校生じゃないから」
こ う こ う せ い じ ゃ な い ?
直也が大声を出す。
「おい、マジかっ! ウソだろ、もうやめたのかよ?」
「ちがうよ。自分を高校生だと思うから悩むんだろ」
「え?」
どういうこと? 美南は海馬の言葉を反芻する。
じ ぶ ん を
こ う こ う せ い だ と
お も う か ら な や む
「どういうこと?」
「オレたち、今、草の上に座ってるけど、草じゃないだろ」
「当たり前だろ」
「そう当たり前。だから学校に行ってるからって、高校生になる必要はない」
が っ こ う に
い っ て る か ら っ て
こ う こ う せ い に
な る ひ つ よ う は な い
「あれれ? なんだ?」
美南は慌てる。
「ヴィンヴィンの言ったことが初めてフツーにわかった。わたしスゴっ!」
「なんか、オレもちょっとわかったよ」
海馬は笑顔の2人とは違い、笑いもせず続けた。
「直也さ、ガットゥーゾって闘犬知ってる?」
「とうけん?」
「闘う犬で闘犬」
「誰のわんちゃん?」
「イタリアのサッカー選手のあだ名。ミランっていう超エレガントなチームにひとりだけ混ざっていた、ウルトラスーパー野生児。オレも動画でしか観たことないけど、めちゃくちゃすごい」
「ふーん」
「さっきケンに言ったんだ。バカな兄貴に憧れてる場合じゃない。今日はガットゥーゾになれって」
「ウザッ!」
「ガットゥーゾのすごさをケンに伝授したよ。ガットゥーゾは自分のことを、サッカーが下手な奴の希望って呼ぶんだ。もう名前通り、ガッツと闘争心にあふれてる。どんな格上のスター相手にも全く、少しもひるまない。人の10倍走る。あとムネアツなのがさ、試合の日は、誰よりも早く、独りでグラウンドに入ってきて、独りで観客をあおるんだよ。想像してみなよ。でっかいスタジアム。何万人もいる大観衆の中、たった独りでベンチ裏から走って登場してきてセンターサークルの真ん中に立つ。スタジアムは静まり返る。闘犬はボールを真上に思い切り蹴り上げる。そこで――ウォォオオオオオ!って心のそこからデカい声で叫ぶんだ。静寂は破られ、観衆と仲間に力がみなぎり一体になる。数万人が闘犬のようにいっせいに咆哮する。ウォオオオオオオオって」
「スゲェ迫力!」
「観たことないけどわかる。めっちゃミラクルな光景だよ。そういう生き様を見せられるのがプロだと思う」
「でもケンケン叫ばなかったね、さっき」
「そのかわり、キックオフのあといきなりシュートを打った」
「おお、たしかに!」
「今もほら――」
少しも休まず、走り続けている。
「当たれ!」「戻れ!」「オーケー、ナイッシュー!」
キャプテンらしく、ときには笑顔で、力強く、仲間に向けて声を出し続けている。直也はブラザー・ケンケンの雄姿を見て、弟のかわいい秘密をひとつバラすことにした。
「たしかに海馬の闘犬のアドバイス、アイツにぴったりだ」
「ん?」
「そのパンフレットに何て書いてあるか知んないけど、アイツの本当の夢ってね、じつは警察犬なんだ」
「けいさつけん?」
「そう。アイツね、頭おかしいくらいハナがすごいんだよ。だいぶ前にさ、グラウンドに誰のかわからないジャージが落ちてたときがあったの。それをケンに嗅がせたら、2人のにおいがするとか言うわけ。伊藤くんのにおいと、梶山くんっぽいにおいだって。実際、当たってたの。そのジャージを落とした伊藤って子はさ、梶山って子の兄ちゃんにそのジャージをもらってたんだ。落ちてたジャージの持ち主と、その前の持ち主を当てたっていう」
美南ちゃんは爆笑する。
「ぎゃはは! エグっ! すげーハナ!」
ヴィンセント海馬くんも笑った。
「警察じゃなくて警察犬になりたいんだ!」
「ウケる!」
キャプテンマークを巻いて駆け回る警察犬が夢の弟。それをゲーム片手にうだうだ見ているサッカーをあきらめた兄貴。どう考えてもこっちはカッコ悪い。アホはオレだ。直也はあっさり降参した。
「なんか、アイツすごい気がしてきた。チビのくせにえらいな」
ヴィンセントは持ってきた黄色いボールを手に取り、クルクルっとひとさし指の上で回転させると、前ぶれもなくいきなり、美南のかわいい秘密をあばいた。
「美南の夢は写真家だろ」
「はっ?!」
何を突然!
そして・・・
あ っ て る し !
ヴィンヴィンにはすぐに当てられてしまう。
もう、どこでどう情報が伝わったのかを聞いてもムダ。
今さっきのパンフレットも、何気ないこんな会話もぜんぶぜんぶ覚えちゃって、そしてたぶん、みんなもこんなふうに言い当てられちゃうんだ。
キミの将来の夢は――警察犬だろ。
キミは、写真家だろ
「美南はどんな写真を撮りたい?」
「どんなって・・・」
「人? 風景?」
「どちらかというと・・・人かな。わかんないよ、まだ」
ここで直也が珍しくまともなことを言った。
「おい、夢ならハッキリと言えよ」
同じ。あのときと同じだ。あのときは、試験官以外、知ってる人が誰も見ていないから口にできた。高校受験の面接のときに言ったあの将来の夢――親友の男の子2人に恥ずかしさをガットゥーゾ的に振り切って伝えた。
「わたし、人を元気にする、元気な人の写真を撮りたい」
銀色の長髪が春風になびく。
ヴィンセントは試合から目を離すと、力強い目で美南の目をまっすぐに見つめた。口元に優しい笑みをたたえている。
「オレは――美南は詰まないと思う」
「詰まない、のかな?」
「ぜったい詰まない。大丈夫だ」
「うん、ありがとう」
「高校なんて行っててもいいし、行ってなくてもいい。どこにいても、オレたちはオレたちだ。ただし――」
「ただし?」

ヴィンセント・VAN・海馬くんはグラウンドを指さした。
「何を?」
「写真に決まってる。あそこに頑張ってる元気なヤツらがいるじゃん。撮りまくればいいよ。そしてお金がいるんだったら、撮った写真を売りまくればいい。ママさんたちに。お金持ってそうなパパさんもいるよ」
「え? そんなことしちゃダメじゃない?」
「なんで」
なんで? ん? なんでだろう・・・
わかんないけど、まだダメ・・・なのかな?
「WIN、WINだよ。そうすれば美南の夢は今すぐかなう。夢と関係ないバイトなんてしなくていい。ママさんたちも喜ぶ。子どもが大好きだからきっと、超喜ぶ。インスタにさくらとかタンポポの写真を上げてる場合じゃない」
み ら れ て た !
「さくらもタンポポもいいけどさ、美南は人を撮りたいんだろ。その気持ちに高校とかまったく関係ない。ほら、ダッシュ!」
「でも、今日カメラ持ってくるの忘れたし、あとスマホも・・・」
「じゃあ、これで撮りなよ。一石二鳥だ」
海馬くんは直也くんのスマホを奪うと、パスコードを手早く打ち込み、美南ちゃんに投げた。
「オレはここにいるから」
「おい! てか、なんで解除できんだよ!」
「ナオヤはあっち!」
「は?!」
「またサッカーやるんだろ。ゲーム中毒だったから体力激減してるはず。自主練してこい」
「・・・」
海馬は親友に黄色いボールを投げ渡す。
「ガットゥーゾみたいに頑張れ!」
河川敷なのに風が緩やかで、もうグラウンドコートはいらないし、ジャージでも暑く感じる。
気持ちよい。ほんとうに気持ちよい季節だ。
こんな素晴らしい土曜日。学校を休んで大正解。
時計を見ると9時30分だ。
「うーん・・・」
今戻れば3時間目くらい? 4時間目の現国に間に合ってしまう。
新しいクラスメイトの顔がくっきり、リアルに思い浮かぶ。
ついでに誕生日の水野先生の悲しんでる顔も浮かんでしまった。
こうして同じ中学だった3人の少年少女は、少しだけ膝を交えた後、ふたたび別々の道を走り出した。かわいい秘密をそれぞれの胸に抱いて。
読後📗あなたにプチミラクルが起きますように🙏 定額マガジンの読者も募集中です🚩
