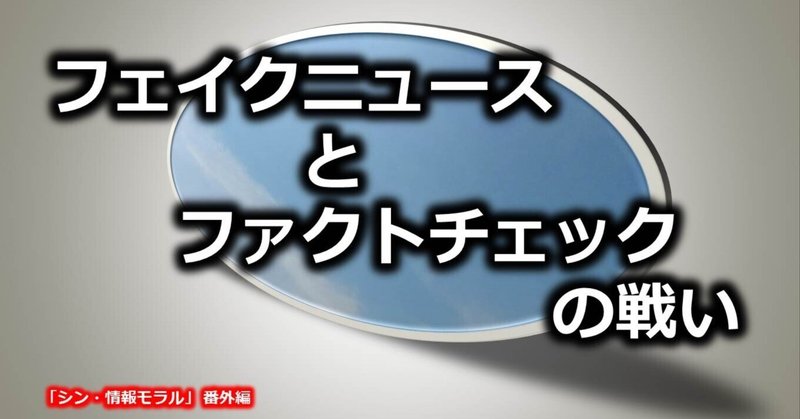
フェイクニュース圧勝 【シン・情報モラル 番外編】
フェイクニュースに気を付けろという。
ファクトチェックが大事という。
両者の対決、その勝敗は?

対戦者の紹介
まずは、両者の定義。
フェイクニュース
統一された定義はないが、代表的なものを2つ。
あらゆる形態における虚偽の、不正確な、又は誤解を招くよう情報で、設計・表示宣伝されるなどをとおして公共に危害が与えられたもの(故意でも過失でも)。
○ 研究者によって様々な定義がある。
○ 嘘やデマ、陰謀論やプロパガンダ、誤情報や偽晴報、扇情的なゴシップ
やディープフェイク、これらの情報がインターネット上を拡散して現実世
界に負の影響をもたらす現象。
○ 必ずしも「フェイク(嘘)」ではないものも含まれている。
○ 嘘か真実かは主観によって変わる可能性のあるものもある。
○ ネット上だけでなく、従来のマスメディアの報道を批判する際に言及さ
れるケースもある。
ファクトチェック
これも定義は固まっていないが、代表的なものを1つ。
ファクトチェックとは、社会に広がっている情報・ニュースや言説が事実に基づいているかどうかを調べ、そのプロセスを記事化して、正確な情報を人々と共有する営みです。
一言でいえば、「真偽検証」です。
平たく言えば、その情報がホントかウソかを調べること。
さらにホントとウソの間のグレーゾーンがある。

対戦結果
フェイクニュースやデマの類は、その情報を受け取った人の1%を騙せば成功だろう。
下手な鉄砲、数撃ちゃ当たる。
ジャンルやテーマにもよるが、1割の人を信じ込ませれば大成功か。
フェイクニュースを偽情報と気づいてる人は、
新型コロナ関連では58.9%、
国内政治関連では18.8%。
政治がらみでは8割の人がフェイクニュースに騙されている。
これでは、選挙に大きく影響してしまう。
もう1つの別の調査。
新型コロナウイルスや米大統領選挙などのフェイクニュースについて、
75%の人が正しい情報と思った、もしくは、判断がつかなかったと回答。
7割強の人が惑わされている。
フェイクニュースの圧倒的勝利。
ファクトチェックの敗因
敗因1:何それ?
「フェイクニュース」を聞いたことのある人は86%。
しかし「ファクトチェック」は29%。
ファクトチェックの知名度は低い。
用語の問題ではない。
そもそも情報を確認するという姿勢を持たない人が多いということ。
戦う以前の問題。
敗因2:めんどくさい
情報を検証することは、言うほど簡単ではない。
頭を使うし、時間も使うし、なのに直接的に得るものはない。
音楽や映画でさえ、早送り飛ばしながら楽しむご時世に、いちいち情報の検証などそんなコスパの悪いことはしない。
直観的におもしろいものを見つけたら楽しんで拡散するだけ。
1つの情報に時間をかけない。
敗因3:本物を知らない
本物を知っていないと、偽物は見抜けない。見極めようがない。
知識や教養を身に付けていないと、受け取った情報を判定する根拠がなく、直観的感情的に判断してしまう。
...と、今まではそうだった。
しかし、本物を知っているが故に騙される危険性が高まってきた。
ディープフェイク。
最近の観た映画で、俳優本人と思っていたのが、実はAIによる声だったり映像だったりと後で知るということが増えている。
簡単な文章や単純な写真の合成でさえ騙されて大騒ぎしているのに、音声や映像までもが本物そっくりにフェイクされてしまうと太刀打ちできない。
自分の中にある本物に関する情報に合致していれば、作り物でも逆に自信を持って本物と判断してしまうかもしれない。
知らぬがホトケ。
敗因4:疑うことを知らない
私たちは、人を疑うとか情報を疑うという訓練を受けていない。
逆に、与えられた情報を鵜呑みにするという学校教育を長年にわたって受けてきた。
先生の言うことを聞きなさい。
親に口答えしてはいけません。
監督やコーチの言うとおりにしなさい。
フェイクニュース対策として「情報リテラシー」の向上が必要であると判で押したように言われるが、教育現場では真逆の指導が行われている。
敗因5:フェイクニュースは違法ではない
フェイクニュースを作ったり、発信したりすること自体は法律で禁じられていない。
もし、違法なら多くの人が犯罪者となってしまう。
しかし、逮捕者が出たこともある。
熊本地震(2016年)の時のライオン逃げた事件。
熊本地震の発生直後に「地震で動物園のライオンが逃げた」などと、うその内容をツイッターに投稿し動物園の業務を妨害したとして、20歳の男が逮捕されました。
この事件は、フェイクニュースだめよという指導の際によく引き合いにだされている。
ところが、罪名は偽計業務妨害。
(たぶん、本人としては単なるネタのつもりが、強引にうたわされた?)
個人のジュークやいたずらは厳しく責められる。
一方で、FIJの「新型コロナウイルス特設サイト」では、厚生労働省、大臣、自治体の長、警察、新聞社などが発信した情報が指摘を受けているが、それで誰も逮捕されてはいない。
※ なお、FIJのサイトには、
「検証の内容は記事掲載時点のものです。また100%正しいとも限りませ
ん。」との但し書きがある。
さらには、ファクトチェックする組織の中立性も課題ではある。
敗因6:フェイクが現実になることも
「嘘から出た実(まこと)」という言い回しがあるが、時として、フェイクニュースが現実になる。
コロナ禍の2020年2月から3月にかけて、トイレットペーパー品薄騒動が日本全国を席巻した。
この騒動は、元の「品薄になる」というデマはたいして広まらなかったが、それを公共機関が「信じるな」と打ち消す情報を大量に流したことで広まった。
そして、多くの人がデマと思いながらも念のためと買いだめに走り、その様子をマスコミが全国に放送することで一気に品薄に拍車がかかったという分析が報道されていた。
フェイクニュースを公共機関やマスコミが拡散し、ライオン逃げた事件とは比較にならない程の迷惑や業務妨害を発生させた。
ところが、この件でもだれも逮捕されてはいない。
これが許されるなら、今後、善意や注意喚起を装ったフェイクニュースが流行るかもしれない。
敗因7:人はフェイクニュースを欲している?
人は、ひとりでは生きていけない。
なので、集団に属するように心がプログラムされているのだろう。
集団を率いる指導者の教えを無条件に受け入れ、集団独自のルールを厳格に守ることで、自分の居場所が与えられ安堵できるというシステム。
そこでは、集団の発する情報に疑いを持つことは許されない。
その情報が事実でなかろうと、外部からどんなに非難されようと動じてはいけない。
情報社会とはいえ、人間の本性はまだそんなところにある。
正しいかウソかで、人は生きていない。
信じるか、信じないか。
ファイクニュースは必要悪?
フェイクニュースの天下は続く。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
