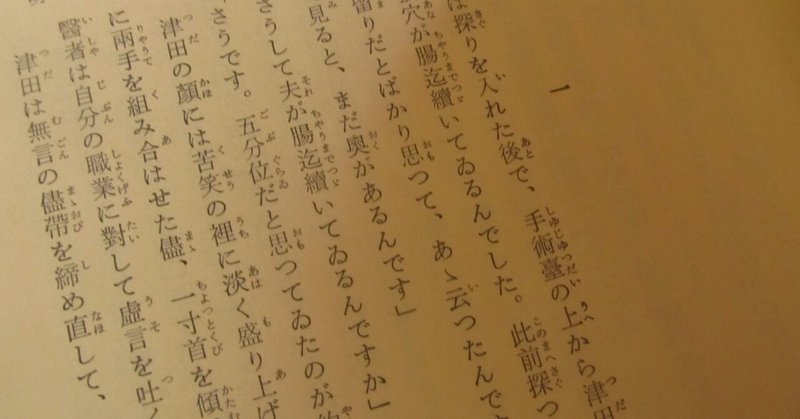
漱石「明暗」を読む
医者は探りを入れた後で、手術台の上から津田を下した。
「やっぱり穴が腸まで続いているんでした。この前探った時は、途中に瘢痕の隆起があったので、ついそこが行きどまりだとばかり思って、ああ云ったんですが、今日疎通を好くするために、そいつをがりがり掻き落して見ると、まだ奥があるんです」
「そうしてそれが腸まで続いているんですか」
「そうです。五分ぐらいだと思っていたのが約一寸ほどあるんです」
漱石は疾走する。
前置きはない。そんなものは振り落とされる。
長尺の長篇にもかかわらずのっけから主題に切り込む。
その感動的な鮮やかさと迫力と、戦慄すべき内容と。
手際がいい、というのでは済まされない、傑作に相応しい簡潔で、すっと入っていくことのできる書き出しであると同時に、近代日本文学でこのような文章はすでにして他にない。
人間の物理的な内部に「穴」があり「奥」がある――漱石が精神分析に興味を持っていた痕跡は伝記上に少し残っていたはずだが、そんなことはどうだってよく、フロイティズム的な場所論としての無意識が、この書き出しにおいては(別様の、漱石なりの想定の仕方でなのだが)明らかに意識されて、読み手を誘導するよう企図されている(次の「二」ですぐ回収される)。
そして場所論の無意識よりもしたたかなのは、これが同時に「身体」の問題だからである。制御不可能なかたちで内部になにかを侵食させるそれは、直接的に目にみえるかたちで今、ここに実在するものでもある。
その二つのどちらも、漱石はここで捉えている。
津田の顔には苦笑の裡に淡く盛り上げられた失望の色が見えた。医者は白いだぶだぶした上着の前に両手を組み合わせたまま、ちょっと首を傾けた。その様子が「御気の毒ですが事実だから仕方がありません。医者は自分の職業に対して虚言を吐く訳に行かないんですから」という意味に受取れた。
津田は無言のまま帯を締め直して、椅子の背に投げ掛けられた袴を取り上げながらまた医者の方を向いた。
「腸まで続いているとすると、癒りっこないんですか」
「そんな事はありません」
医者は活溌にまた無雑作に津田の言葉を否定した。併せて彼の気分をも否定するごとくに。
「失望の色が見えた」とあり、「医者は活溌にまた無雑作に津田の言葉を否定した。併せて彼の気分をも否定するごとくに」と来て、すでに多声性をほのかに聴き取ることができる。気分を否定するためには、否定する分の津田の心情が「すでに」描かれていなければならず、「すでに」それができてしまっている。二人が他者同士になってしまっている、それぞれに声を持ってしまっている。といっても、それは簡潔な人物描写のコントラストを浮き彫りさせるようにして、対立の中の他者の質感が出ているのであって、対話による声では勿論、ない。なににしろ、もうこの時点で淡く、決まっている。日本文学が十九世紀的な小説を始めて書く事態は、ここの「併せて彼の気分をも否定するごとくに。」の箇所ですでに予兆されている。
手っ取り早く、ちょっと意地悪する。
津田は失望した。医者は上着の前に両手を組み、首を傾けて津田を見た。
「御気の毒ですが事実だから仕方がありません。医者は自分の職業に対して虚言を吐く訳に行かないんですから」
「腸まで続いているとすると、癒りっこないんですか」
「そんな事はありません」
医者は津田の言葉を否定した。
無作為に、雑に削って、かつ地の文を科白に移した。
医者は探りを入れた後で、手術台の上から津田を下した。
「やっぱり穴が腸まで続いているんでした。この前探った時は、途中に瘢痕の隆起があったので、ついそこが行きどまりだとばかり思って、ああ云ったんですが、今日疎通を好くするために、そいつをがりがり掻き落して見ると、まだ奥があるんです」
「そうしてそれが腸まで続いているんですか」
「そうです。五分ぐらいだと思っていたのが約一寸ほどあるんです」
津田は失望した。医者は上着の前に両手を組み、首を傾けて津田を見た。
「御気の毒ですが事実だから仕方がありません。医者は自分の職業に対して虚言を吐く訳に行かないですから」
「腸まで続いているとすると、癒りっこないんですか」
「そんな事はありません」
医者は津田の言葉を否定した。
緊張関係があるという点で、まだ大丈夫といったところだろうか。やはりモチーフが明確だからだが、叙述も大事になっていくのは言うまでもない。これがこのまま、この調子を保って続けば「雰囲気」が出て終わりだろう。
なぜこだわるかというと、くり返しになるが、「併せて彼の気分をも否定するごとくに。」の箇所で、すでに多声性が淡く、確認できるのである。
いうなれば「併せて彼の気分をも否定するごとくに。」の段階をもって、他のあらゆる近代の作家たちは、だれもこのように文章を書いたことがない、似た内容、病院のシーンなり、なんなりを書いたものがあったとしても、書けなかったわけである。
思うのは、
津田の顔には苦笑の裡に淡く盛り上げられた失望の色が見えた。医者は白いだぶだぶした上着の前に両手を組み合わせたまま、ちょっと首を傾けた。
「苦笑の裡に淡く盛り上げられた失望の色が見えた」、「白いだぶだぶした上着の前に両手を組み合わせたまま、ちょっと首を傾けた」、――どちらも複雑というか人間の仕種として強い意味が込められた、センテンスの長い描写だが、音が非常に綺麗に整っているから、蕪雑さは感じさせない。むしろすっと軽く読ませることによって人物の輪郭が手際よく、しっかりと整理づけられるように書かれていく印象を、読み手(私)は持つ。「苦笑の裡に淡く盛り上げられた失望の色」、小さい音の「く」、淡くの「あ」から色の「い」の流れを感じていただきたい。これは音としては破綻がないだけではない、単に凸凹さがないというのではなく押韻があり、後者も同様である。
その様子が「御気の毒ですが事実だから仕方がありません。医者は自分の職業に対して虚言を吐く訳に行かないんですから」という意味に受取れた。
ここはいわゆる「神の視点」(敢えて概念を用いずに平俗に、自然にやるとする)であり、医者の側に寄ったものとも、津田の視点から「受取れた」わけでもない、宙ぶらりんの叙述になっている。受け取るとしたのならば津田であり、受け取らせるのは医師なのだが、どちらの側にも就いていない。「津田は」……のところから助詞を始めとして点検してみても、この叙述のあり方は異質であり、およそ頭を抱える他なくす。圧倒的である。この文章を宙ぶらりんにさせるためには「津田の顔には苦笑の裡に淡く盛り上げられた失望の色が見えた」、ひとまずはこの文章が、それを可能とさせるよう成立していなければならない。問題はただこの叙述の高度さではなく、叙述全体がその遠近感を保ち続けることである。そして恐らくそれを可能たらしめるためには、あの奇妙な押韻がたゆまずに必要とされていることなのである。
ここの一部分は、医者が本当にはなにを考えているのか分からない、ブラックボックスである他者であるということを強調するように作用する、非常に強い描写であり、私は一文に触れた途端に上手いと感じる。この場合の上手いというのは、単に他人を感じさせる音づくりとしてみて、上手い。
「ただ今までのように穴の掃除ばかりしていては駄目なんです。それじゃいつまで経っても肉の上りこはないから、今度は治療法を変えて根本的の手術を一思いにやるよりほかに仕方がありませんね」
「根本的の治療と云うと」
「切開です。切開して穴と腸といっしょにしてしまうんです。すると天然自然割かれた面の両側が癒着して来ますから、まあ本式に癒るようになるんです」
津田は黙って点頭いた。彼の傍には南側の窓下に据えられた洋卓の上に一台の顕微鏡が載っていた。医者と懇意な彼は先刻診察所へ這入った時、物珍らしさに、それを覗かせて貰ったのである。その時八百五十倍の鏡の底に映ったものは、まるで図に撮影ったように鮮やかに見える着色の葡萄状の細菌であった。
津田は袴を穿いてしまって、その洋卓の上に置いた皮の紙入を取り上げた時、ふとこの細菌の事を思い出した。すると連想が急に彼の胸を不安にした。診察所を出るべく紙入を懐に収めた彼はすでに出ようとしてまた躊躇した。
「もし結核性のものだとすると、たとい今おっしゃったような根本的な手術をして、細い溝を全部腸の方へ切り開いてしまっても癒らないんでしょう」
他の漱石作品にもある「マジックタッチ」を取り除くように、つまり強いて一音一音に耳をそばだてて聴くように読むと、やはりどうもおかしい。ただの日本語の文章ではない。
身体も津田にとっての他者なわけである。得体の知れない、どんな働きをもたらすか分からない、そしてまた目の前の医師によってそれが適切に処置を施されるのかも分からない、なにものかであり、またくり返しだけれどもそれは津田自身の中に抱え込まれたものとしてある。
この段階で主役なのであろうと見当をつけることのできる人物、その人物とは、主役ながらに他性を抱えた者である。主役ながらに、というのは、「津田の顔には苦笑の裡に淡く盛り上げられた失望の色が見えた」でも思ったことだが、三人称の叙述として、距離感がとても遠い三人称のあり方をしている。主人公にまず読者を突き放すような質感がある(「感情移入できない」といった読み手によって変わる曖昧なことを言っているのではなく、技巧についての領域に鮮やかに属した事柄について私は言っている)。
「結核性なら駄目です。それからそれへと穴を掘って奥の方へ進んで行くんだから、口元だけ治療したって役にゃ立ちません」
津田は思わず眉を寄せた。
「私のは結核性じゃないんですか」
「いえ、結核性じゃありません」
津田は相手の言葉にどれほどの真実さがあるかを確かめようとして、ちょっと眼を医者の上に据えた。医者は動かなかった。
「どうしてそれが分るんですか。ただの診察で分るんですか」
「ええ。診察た様子で分ります」
この二人はかつてなく切実な問題を扱っているわけである。大上段ではなく、そういう言い方をせざるを得ないのだ。いかに自然主義の作家たちがなにを言おうが、他の流派からなにが飛んでこようが、近代日本文学史で、「最も切実な問題」に、この津田と医師とは、かくのごとく話をしているのである。
なぜならば「明暗」は十九世紀的なポリフォニー性のある近代日本の唯一の小説であり、ポリフォニー性とは多声、「他者」の声にまつわるものだからである。
「どうしてそれが分るんですか。ただの診察で分るんですか」
「ええ。診察た様子で分ります」
その時看護婦が津田の後に廻った患者の名前を室の出口に立って呼んだ。待ち構えていたその患者はすぐ津田の背後に現われた。津田は早く退却しなければならなくなった。
「じゃいつその根本的手術をやっていただけるでしょう」
「いつでも。あなたの御都合の好い時でようござんす」
津田は自分の都合を善く考えてから日取をきめる事にして室外に出た。
それは身体の緊張関係と、身体という他者を巡る他者同士の対話であり、不信感があらわになりかけたところでもって、二人の関係は断ち切れる。他者の謎が、謎のまま保留にされる、あるいは謎が謎のままであり続けなければならない、他者が他者であり続けることを、読み手は予兆させられる。
速やかに手術の「約束」、次の展開へと繋げるテンポの良い流れでもって、「一」部分は終わる。この鮮やかさもただただ、普通に美しい。だが、幾度も念を押すが、注目すべきは「併せて彼の気分をも否定するごとくに。」の一文である。この一文を中心とするかのごとく、「一」部分は稠密に書き込みが成されており、すでにこの「一」部分で全体の構造の用意となっていると、直観されるほどである。
やはり漱石は疾走している。
ゆるやかに、モデラートに一文一文を改めるのではなく、速さ、スピード感に乗っているうちに次から次へと的確な表現が出てくるかのごとき印象。
この「一」段階ですでにそれがある。
□
どんな概念を使って、どういう風に戦略的に、……とか準備にもたついていて書き出せないのがバカバカしいから(ずっとやってみたかった)、ただなんの考えもなしに無軌道、無計画に、ただひたすら「実作者」の態度から始める、というのはつまり突っ掛けで、即興演奏のように。理論的にではなく、感覚的1に。地金が出てしまうがそれは仕方がないだろう。もとよりさんざここで、してきてしまった。
明暗の「一」部分を全文引用した上でそれに寄り添い書くが、「読書ノート」、読みながら気になった点やらを記すのでなく、読んでいる私の頭の中で起こっていることを書き起こしていく……(んな意識の流れみたいなことは本当にはできはしないが)ようなリアルタイム性を重んじるかたちで、垂れ流しにアウトプットしていく/されていったなにか、である。文章と「対話」してみる、といってもいいが、それも御大層だ。それがなにか、ということを私は考えない。私はただ読む。
本当は浄書(原稿用紙に書き写す)しながらやるといいのだが、その手のスピーディーさ、効率の良さを重視したいため、しなかった。いわば読むように書かれた文章だと言わせていただきたい。
静かに本を読みたいとおもっており、家にネット環境はありません。が、このnoteについては今後も更新していく予定です。どうぞ宜しくお願いいたします。
