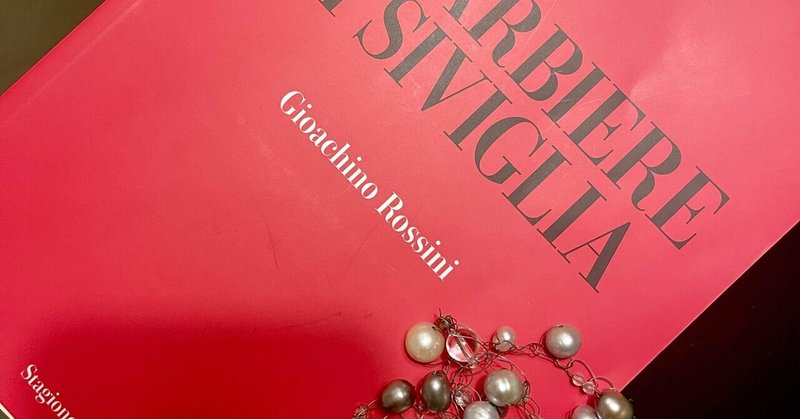
スカラ座という特別な空間
長年夢だったスカラ座を訪れた。
ミラノといえばスカラ座、スカラ座と言えばミラノ。もちろん名前だけなら知らない人は、とくに日本ではほぼゼロと言って過言では無いだろう。
私にとって最初のオペラは、東京で観たニューヨークのメトロポリタン・オペラだった。
その頃はオペラのオの字も知らないで、ただプラシゴ・ドミンゴの名前だけ知っていて、当時付き合っていたBFに誘われて、カッコつけてついていった。だから今では演目さえ覚えていない始末だ。
けれど父の影響で、元々クラシック音楽をずっと聴いて育ってきた身だったので、その壮大なエンターテイメントに心を動かされたのは事実で、それまであの盛大な歌い方と声の良さがわからなかった私に、人間の声はここまで美しい音を奏でるのだということを教えてくれた。
それからの私は日本に海外オペラが来る度に聴きに行くようになり、スカラ座、ウイーン国立歌劇場、バイエルン、ボリショイオペラ、大御所は東京で全て制覇して、その結果、私はすっかりオペラの虜になった。
人間の声の美しさの極限が聴ける。それはどんな楽器よりも美しく、そのビブラートは空気を伝って聴いている私たちの身体まで震わせる。
実はクラシック音楽を私以上に愛好して、日本で最初にモーツァルト愛好会などというグループまで立ち上げた兄は、オペラだけは苦手だった。でも、まずはオペレッタで準備運動させようと、かつてボーイフレンドに引きずられた私が、今度は兄を引きずり込んだ。兄はフレンチカンカン付きのオペレッタに夢中になり、その結果、私以上にオペラを聴くようになった。
さて、そのオペラだが、やはりスカラ座のオペラは別格と、誰もが口を揃えて唱える。ニューヨークのメトがどんなに素晴らしくても、スカラ座は何かが違う。
それはレベルが違うとか、歌手が上手いとか、そういうことじゃなく、ただ、スカラ座だけ何故か特別なのだ。
そうして日本でスカラ座を観たとき、舞台が綺麗とか歌が美しいとか、確かに素晴らしかったけれど、正直、別格という意味がわからなかった。東京文化会館で観たアバド指揮のウイーン国立歌劇場の「魔笛」があまりに楽しかったから、スカラ座のラ・ボエムでさえ、別格という認識までには感情が到達しなかった。
昨日ミラノに来て、念願のスカラ座に来た。

奮発して取ったバルコニー席、それぞれパリからとシドニーから訪れた素敵なご夫婦とご一緒させて頂き、とても楽しい時間を共有させて頂いた。
カーテンが開く前、劇場を見回す。
重厚とか豪華とかそういうことじゃない。建物とか赤い絨毯とか金の飾りとか、全てが歴史の一部であるという、その空気が特別なのだと知った。
そしてその空気の匂い、室内に今も残るであろう、遠い昔の人々の爪痕、歌い手たちが飛ばした声と吐息、聴衆の拍手、今訪れている人々の囁きやドレスやスーツ、それらが分子レベルで充満して、年月を重ねて染み込ませているのがスカラ座なのだ。
エンターテイメントは作り手と演じ手と観客の共鳴から生まれる。
ここは、言ってみれば、地元に愛される劇場であり、オペラはミラネーゼの生活に特別であると同時に当たり前に存在する。そして人々の誇りでもある。
だから海外へ、言ってみれば出稼ぎでやってきた演じ手に、彼らの場所に属さない人々が聴きに来るというのは、空気も囁きも違う。言い換えれば愛情もプライドもレベル違いなのだ。
そういう私も同席したパリやシドニーのご夫婦もよそ者であり、その場に属している人々ではない。
でも、私たちはここに来て、ここの空気を吸って、ここに属する人々とここに属する音楽を聴いて舞台を観ている。
スカラ座にはマリア・カラスの亡霊が棲みついていて、「椿姫」を演目にすると失敗すると、まことしやかに語り継がれてきた。実際28年もの間、上演されることはなかった。
都市伝説と言えばそれまでだが、それこそ、ここの空気には人々の思いがずっと引き継がれてきた証明なのかもしれない。

今回はロッシーニのセビリアの理髪師を観たが、スカラ座で観ないとわからないオペラというものを、少しは理解できたと実感した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
