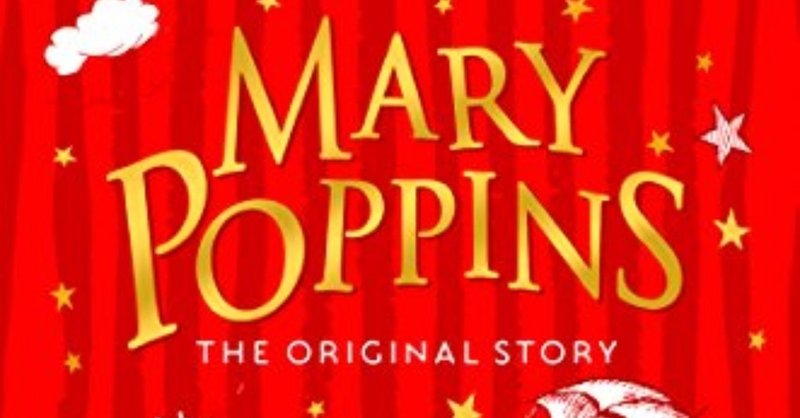
メリー・ポピンズはリターンズもいいし一作目もいいけど原作読んだらすごすぎて死んだ
今やってる「メリー・ポピンズ・リターンズ」がめちゃくちゃ良かった。
で、原作を読んでみたんだ。そしたら、原作がすごかったんだよ!!凄かった。すさまじかった。もう、おれの語彙力では説明できない。読みながらボロボロ泣いた。だから、原文から翻訳したんだ。もし気に入ったら、映画を見に行ったり、原作を買ってみたりしてくれよな。日本語版で読んだのは岸田衿子さんの訳のやつさ。詩人だから、訳がすげえんだ。
訳した原文はこれさ。お手頃価格だぜ。
これのなかの、「ジョンとバーバラの話」というやつだ。泣くぜ。間違いなく泣く。それではhere we go!
======================
ジェーンとマイケルはパーティに行きました。彼らが最も良く見える服に身を包んで。お手伝いのエレンは、そんな二人を見て「まあ、ショーウィンドウみたいだね!」と言いました。
その日の午後、おうちは静けさに包まれていました。誰もが自分の考えに浸かりこんでいたり、眠り込んでいたりしました。
キッチンでは、ミセス・ブリルが鼻にメガネを載っけて新聞を呼んでいました。ロバートソン・アイは、庭に座り込んでぼうっとしていました。バンクス夫人はソファに足を上げて沈み込んでいました。おうちはとても静かで、おのおのの夢や考えに没頭していたのです。
2階では、子ども部屋で、メリー・ポピンズが暖炉の前で洋服を乾かしていました。太陽の光が窓から差し込んで、白い壁に反射して、赤ちゃんたちが寝ている用ベッドの上を踊っていました。
すると赤ちゃんのジョンが、「もうやめてって言ったでしょ!僕の目に光が入って眩しいよ」と大きな声で言いました。
「それはごめんよ!」と、太陽の光が言いました。「でも仕方ないんだ。どっちにしろ、僕はこの部屋を横切ることになっているんだ。決まりは決まりだからね。僕は一日をかけて、この子供部屋の東から西へ移動しなきゃいけない。ごめんね!目をつぶっていてよ。そうすれば、僕のことに気づかないから」
黄金の光はますます長くなり、部屋を横切っていきます。そのためにジョンは体を動かさなければなりませんでした。
双子の赤ちゃんのバーバラは言いました。両手に輝く日光の暖かさを抱きしめながら。
「なんて柔らかくて、優しいのかしら!あなたのことが大好きよ」
「いい子だね」と日光は満足げに言いました。そしてバーバラを喜ばせるように、ほっぺと髪の毛を照らして、「僕の感じが好きかい?」と聞くのでした。
「デリーシャス!」
と、バーバラは幸せなため息をつきながらいいました。
その時です。窓から、甲高い声がしました。
「ぺちゃくちゃ、ぺちゃくちゃ、ぺちゃくちゃ!こんなにおしゃべりさんばかりがいる場所は見たことがないね。この部屋では、いつも誰かがおしゃべりしてるときてる」
ジョンとバーバラは窓を見上げました。するとそこに、煙突のてっぺんに住んでいるムクドリがいました。
「あら、わたしは好きよ」とメリー・ポピンズがすばやく回って言いました。
「貴方の方はどうなの?一日じゅう...それに夜の半分も、屋根や電柱に登ってるでしょ。そして唸ったり、吠えたり、叫んだり!あなたときたら、椅子から取れた足とでもおしゃべりするでしょうね。ボクシングのスパーリングをしてる人よりも最悪だわ。それが真実ね」
ムクドリはその頭を、メリー・ポピンズがいた窓枠のほうに向けて、彼女を見下ろしました。
「いいかね、メリー・ポピンズ」
ムクドリは言いました。
「わたしには、訪ねなくちゃならないビジネス相手がいるんでね。コンサルタントも、ディスカッションも、言い合いも、駆け引きもしなくちゃならん。そしてもちろん、ゴホン、静かな話し合いというものが必要なのさ」
「静かな話し合い!」とジョンは叫びました。そしてお腹の底から笑うのでした。ムクドリはジョンに言いました。
「きみに話をしているのではないよ、お若いの」
窓の敷居にひょいと降りて、ムクドリは言いました。
「どっちにしろ、君は話す必要がない。この前の土曜、君のことをずっと聞いていたよ。なんてこった、君は全然おしゃべりを止めるってことをしない!君は俺のことを一晩中起こしていたのさ」
ジョンは答えました。
「しゃべってたんじゃないよ。僕は...」
と言って止まりました。
「僕、痛かったんだ」
「ハン!」とムクドリは言って、バーバラが寝ているベッドを囲む木の枠に飛び乗りました。そしてベッドの方を見るまで、顔を横にそむけていました。
「さてさてバーバラ・B、今日はなにかこの古い友だちに言いたいことはあるかい、ええ?」
バーバラは木の枠を掴んでいましたが、ベッドの上に座り直しました。
「アロールート・ビスケット(子供用のビスケット)が半分あるわよ」とバーバラはいって、そのむくむくした手にビスケットを握りました。
ムクドリは木の枠から飛び降りて、バーバラの手からビスケットを掴み取り、窓の下枠に戻りました。ムクドリはガツガツとビスケットをつつき始めました。
「ありがとう!」
メリー・ポピンズが意味ありげに言いました。でもムクドリは、ビスケットを食べるのに夢中で、メリー・ポピンズに叱られたことにも気づきません。
「わたしは、”ありがとう”って言ったのよ」
と、メリー・ポピンズが少し大きな声で言いました。ムクドリが彼女を見上げて言いました。
「え?何だって?ああ、お嬢ちゃん、まあ固い事言うなよ。俺はそんなヒラヒラ飾りみてえな言葉に使う時間はねえんだ」
そしてビスケットを飲み込んでしまいました。一粒のくずだって残しませんでした。
部屋はとても静かになりました。
ジョンは日光の中でうとうとしていて、右足のつま先を、いまにも歯が生えてこようとしているところに突っ込んでいました。
「ねえ、なんでそんなわけのわからないことしてるの?」
と、バーバラは聞きました。その柔らかく、好奇心に満ちた声は、いつだって笑いでいっぱいなのでした。
「誰も見てないじゃない」
ジョンは、つま先で遊びながら言いました。
「わかってるよ。でも僕は、練習しておくのが好きなんだ。これって、すごく大人たち(Grown-ups)を喜ばせるんだよ。昨日僕がこれをやったとき、フロッシーおばさんがほとんどおかしくなっていたのを見た?『まあ!この子は、なんて、かしこくて、素晴らしい、生き物なの!』って言うのを聞いただろ?」
そしてジョンは足を投げ出して、フロッシーおばさんのことを考えて大きな笑い声をあげるのでした。
「あら、おばさんはわたしのトリックも好きなのよ」
と、バーバラは満足げに言いました。
「わたしのソックスを、両足とも脱いであげるの。そうすると、なんてかわいいの、食べちゃいたいっていうのよ。おかしいと思わない?わたしが”食べたい”っていうときは、本当に何かを食べたいときよね。ビスケットとか、ラスクとか、ベッドのノブとか。でも大人たちは違うでしょ?言ってることと本当にやりたいことが、同じだったためしがないのよ。わたしにはそう見えるわ。おばさんが、本当にわたしを食べたいってわけじゃないでしょ?」
ジョンは言いました。
「ああ、違うね。それが、大人たちの本当にバカバカしい喋り方なのさ。いつかぼくが大人たちの言うことを信じるようになるなんて、全然信じられないな!奴らは全員バカみたいだよ。ジェーンとマイケルでさえ、たまにバカみたいに見える時がある」
「そうね」
バーバラは同意しました。靴下を脱ぎながら。ジョンは続けました。
「大人たちは、僕らが言うことをひとつも理解しちゃいない。もっと悪いことには、他のものが何を言ってるかもわかってやしないんだ。なんでかっていうと、この前の月曜日、ジェーンが”ああ、風が何を話してるのかわかったらなあ”って言ってたんだよ」
バーバラは言いました。
「知ってるわ。すごく驚いたわ!マイケルも、ムクドリがいっつも”ウィー!ツイー!”って鳴いてるなんて言うの。本当はムクドリがわたしたちと全く同じ言葉を喋ってるっていうことを知らないのよね。もちろん、ママとパパにはわたしたちと同じ言葉を喋って欲しい、なんて期待はしないわ。彼らはなにひとつわかっちゃいないんだもの。でもあなたはジェーンとマイケルが...」
「昔は知っていたんですよ」
と、メリー・ポピンズが言いました。ジェーンの寝間着を畳みながら。
「なんだって?」
ジョンとバーバラは、ものすごく驚いて、同時に叫びました。
「ほんとうに?みんなも、ムクドリや風の言うことが...」
メリー・ポピンズは言いました。
「それに、木の言うことや、日光の言葉だって、星の言葉だってわかっていたんですよ。かつては。」
ジョンは、この信じられないことを理解しようというように、おでこにしわを寄せながらメリー・ポピンズに聞きました。
「でも、どうやって全部忘れちゃうの?」
「アハ!そんなことも知らないのか?」
ムクドリがビスケットから顔をあげて、叫びました。
「みんなが成長したからですよ」
と、メリー・ポピンズが言いました。
「バーバラ、お願いだからソックスを履いてちょうだい」
ジョンは
「すごくバカみたいな理由だ」
と言いました。メリー・ポピンズは、バーバラの足にソックスを履かせながら
「本当ですよ」
と言いました。ジョンは言い返しました。
「忘れちゃったのは、ジェーンもマイケルもバカだからだよ。僕は、大きくなったって、ぜったいにぜったいに忘れない」
「あたしだって忘れないわ!」
と、バーバラも、指をくわえながら続けました。
「ええ、そうでしょうね」
と、メリー・ポピンズはきっぱりと言いました。
「ハ!」
と、ムクドリはすごくバカにするような口調で言いました。
「奴らを見ろよ!自分たちが、世界の不思議だって思ってやがる。小さな奇跡さ!でも、俺はそうは思わないね!お前らも忘れるのさ...ジェーンとマイケルのようにね!」
「僕たち(わたしたち)は絶対に違う!」
と、双子はムクドリを殺してしまいそうな目つきでにらみました。
ムクドリはさらに双子をバカにするのでした。
「ああそうだろうよ、そうだろうとも。もちろん、お前らのせいじゃない」
そこからすごく優しい口調になって、ムクドリは加えました。
「お前らが忘れちまうのは、忘れるようになってるからだ。どうしようもないんだ。今までに、成長して、忘れずにいたことができた大人なんか、一人もいやしない。一人もだ。もちろん、ここにいる、メリー・ポピンズを除いてはね」
といって、メリー・ポピンズのほうに首をかしげました。ジョンは聞きました。
「どうしてメリー・ポピンズにできて、僕たちにはできないの?」
ムクドリは答えました。
「アアア!彼女は違うんだよ。偉大な例外ってやつだ。彼女みたいにはいかないんだよ」
そこまで言うと、ジョンとバーバラは黙りこくってしまいました。ムクドリはあわてて説明しました。
「彼女は特別なんだ。知ってるだろう?むかし、俺のハンサムな友達が...」
そこでメリー・ポピンズがエプロンを翻して
「失礼よ!」
と叫び、ムクドリのほうに向かっていきました。でもムクドリは、手が届かない高いところにひょいと飛び移りました。
「あんたにもそんな頃があったよな?メリー・ポピンズ」
ムクドリがメリー・ポピンズをからかうと、メリー・ポピンズは、つんとしました。
日光が部屋を横切って、細長い光を残していきました。おうちの外では、風が巻き起こって、道のサクラの木に優しくささやきかけていました。
「聞いて、聞いて、風がしゃべってる」
ジョンが言いました。
「ねえ。ぼくらが大きくなったら、ほんとにあれが聞こえなくなっちゃうの、メリー・ポピンズ?」
「聞くことはできますよ」
メリー・ポピンズが言いました。
「でも、理解できなくなるんです」
すると、バーバラが静かに泣き始めました。ジョンの目にも涙が浮かんでいます。
「どうしようもないことなんです。ものごとというのは、起こっていくものなんです」
と、メリー・ポピンズが言いました。すると、またムクドリがからかうのでした。
「見ろよ、見ろよ!やつら、泣いてやがる!卵の中のムクドリだってもうちょっとものごとってやつをわかってるぜ。やつらを見ろよ!」
いまやジョンとバーバラは、どちらもベッドの中で泣いていました。重苦しいすすりなきで部屋が満たされました。
その時、バンクス夫人が子ども部屋のドアを開けました。
「赤ちゃんが泣いているわ」
そして双子に駆け寄りました。
「どうしたの、メリー・ポピンズ?おお、わたしのかわいい子たち、かわいい小鳥ちゃん、どうしたの?どうしてそんなに泣いているの?この午後、ずっと二人は静かだったわ。全然音がしないくらい。いったい何があったの、メリー・ポピンズ?」
「いえ、何も。歯が生える頃だからですよ、奥様」
と、メリー・ポピンズは答えました。ムクドリの方を、見もしないで。
「そうね、そうよね!もちろんですよ、そのとおり」
と、バンクス夫人の表情がパアッと輝きました。
「もしぼくが、ぼくのだいすきなものを全部忘れちゃうんなら、歯なんかいらないやい」
ジョンが、ベッドにぶつかりながら言いました。
「わたしもよ!」
バーバラが泣きながら、枕に顔をうずめて言いました。
「ああ、わたしのかわいそうなこどもたち。やんちゃな歯が生えてくるのね。でも大丈夫よ」
と、バンクス夫人が言いました。ジョンは怒って叫びました。
「ママは全然わかってないんだ!歯なんかいらない!」
バーバラは言いました。
「そんなのおかしいわ、そんなの間違ってる!」
バンクス夫人は泣く双子にやさしく語りかけました。
「はい、はい。よしよし。おかあさんには、全部わかってますからね。歯が生えれば、何もかもよくなるのよ」
突然の騒音が、窓から入ってきました。ムクドリが笑った声でした。メリー・ポピンズはムクドリに一瞥をくれてやりました。それでムクドリは、これが全然笑える状況じゃないってことに気が付きました。
バンクス夫人は、双子をポンポンと優しく叩いてから、二人をリラックスさせるために、むにゃむにゃとした言葉をささやきました。すると、ジョンは泣くのを止めました。バンクス夫人は、何も悪くないからです。
ジョンはマナーというものを知っている男の子でしたし、母親に責任感を感じさせるのもいやでした。ああ、あわれな女性!いつだって間違ったことを言ってしまうのは、彼女のせいではないのです。ただ、彼女が「理解できない」だけなんです。ですので、ジョンはおかあさんを許した証を見せました。でんぐりかえしをして、涙を拭き、右足を口の中に入れたのです。
「ああ、賢い子!ああ、賢い子!」
バンクス夫人は大喜びで、可愛くてたまらないというように叫びました。彼女を喜ばせるために、ジョンはもう一回やってみせました。
するとバーバラも、枕から顔をあげました。顔は濡れたままでしたが、座った姿勢になって、靴下を脱いでみせました。
「素晴らしい女の子!」
バンクス夫人は誇らしく言って、バーバラにキスをしました。バーバラ夫人はメリー・ポピンズに言いました。
「見て、メリー・ポピンズ!またいい子になったわ。わたしはいつだって、二人をいい気分にさせることができるの。いいわ、すごくいいわ」
バンクス夫人は、子守唄を歌い始めました。
「もうすぐ、歯が生えてきますからね」
「その通りです、奥様」
メリー・ポピンズが静かに言いました。そして満足したバンクス夫人は、部屋を出ていきました。
母親がいなくなった途端、ムクドリがとんでもない大爆笑をはじめました。
「にっこりしちゃってごめんよ!でも、我慢できなかったんだ。なんてもんを見ちまったんだ!なんてもんを!」
ジョンはムクドリには気づきもしませんでした。ベッドの木枠に顔をつけて、バーバラに力強く呼びかけました。
「ぼくは、他の人とは違う。君に言うよ、僕は絶対忘れないって」
そう言うと、ムクドリとメリー・ポピンズのほうに顔を向けました。
「彼らが言うみたいには、絶対ならない!ぜったいに、忘れない!」
メリー・ポピンズはにっこりと微笑みました。それは「私のほうが、あなたよりもよく知っているんですよ」という微笑みでしたが、誰もそれには気づきませんでした。
バーバラも言いました。
「私も!絶対忘れないわ!」
ムクドリは金切り声をあげました。
「彼らの言うことを聞いてみろよ!彼らが忘れることをどうにかできるってな口調だ!なに、一ヶ月や二ヶ月、長くても三ヶ月ってとこだな。やつら、俺の名前もわかんなくなっちまうぜ。哀れなカッコウってな!バカな、成長途中の羽がないカッコウだ!ハハハハハ!」
そして窓から飛び去っていったのでした。
それからそれほど日にちが経たずに、たくさんのトラブルのあと、双子に歯が生えました。歯というのは生えることが決まっているものなんです。そして双子は、初めての誕生日を迎えました。
双子の誕生日パーティの後、ボーンマスで休暇を過ごしていたムクドリが、さくら通り17番地に戻ってきました。
「やあ、やあ、やあ!このわたしが、また来たよ!」
喜びに満ち溢れた様子で、ムクドリは窓枠に止まって叫びました。
「さてさて、お嬢さんの様子はどうかね?」
ムクドリはメリー・ポピンズのきらめく瞳を見ながら言いました。
「あんたに聞いてもらったところで、良くなるものなんかないわ」
メリー・ポピンズは頭を振りながら答えました。ムクドリは笑いました。
「おいぼれメリー・ポピンズは相変わらずだな。他のやつら、、カッコーの様子はどうだい?」
そう言うと、ムクドリはバーバラのベッドを見やりました。
「やあやあ、バーバリーナ」
とってもソフトな、転がすような声でいいました。
「お前さんの古い友だちに、今日は何かあるかね?」
「べーラーベラーベラーベラー!」
と、バーバラは答えました。アロールートビスケットをくわえながら。
ムクドリは最初、びっくりしました。そして、バーバラにちょっとだけ近づきました。
「あのな、」
ムクドリはもう一度、はっきりと、言いました。
「この古い友だちになにかあるかい、バービーちゃん、なあ?」
「バールー!バールー!バールー!」
むにゃむにゃとバーバラは言って、ビスケットの残りを食べながら、天井を見つめていました。ムクドリはバーバラを見つめました。
「ハ!」
ムクドリは言って、メリー・ポピンズのほうを、詮索するように見つめました。メリー・ポピンズの静かな視線が、ムクドリの眼差しとぶつかりました。ムクドリは、ジョンのベッドの枠に飛び移りました。ジョンは、大きなウールの羊の人形を抱きかかえていました。
「俺の名前はなんだ?俺の名前は?俺の名前は何だ?」
ムクドリは、神経質な声でジョンに向かって叫びました。
「エーンフ!」
ジョンは言いました。口をあけて、羊の人形をその口に突っ込みました。
「そうか、あれが起こったってわけか」
と、ムクドリはメリー・ポピンズに向かって静かに言いました。
メリー・ポピンズは、うなずきました。
ムクドリはすっかり落胆したようすで、しばらく双子を見つめていました。そして小さな斑点のついた肩をすくめるのでした。
「ああ、わかっていたよ。こうなるってことは、わかっていた。いつも奴らに、そう言ってきかせたもんだ。でもやつらは、信じようともしなかった」
ムクドリは少しのあいだ黙って、ベッドの中を見つめました。そして威勢よく身体を振って言いました。
「まあ、まあ。俺も戻らなくちゃならん。俺の煙突にね。春の掃除もあるし、いろいろくっつけたりしなくちゃならないし..」
ムクドリは窓枠に飛び移ると、振り返って、肩越しに部屋の中を眺めるのでした。
「やつらのいない暮らしなんて、おかしいもんになるだろうな。いつだって、やつらと話をするのはいいもんだったよ。やつらがいなくなって、寂しくなるだろうな」
ムクドリはそう言うと、すばやく羽で目を拭きました。
「泣いてるの?」
と、メリー・ポピンズがからかいました。ムクドリは起き上がって言いました。
「泣いてる?泣いてなんかねえや。ちょいと、あれだ、風邪。風邪をな、旅から戻ってくるまでにひいちまってさ。それだけだよ。軽い風邪さ。たいしたことはない」
ムクドリは、
「あばよ、ってとこだな!」
と言って、飛び立って行きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
