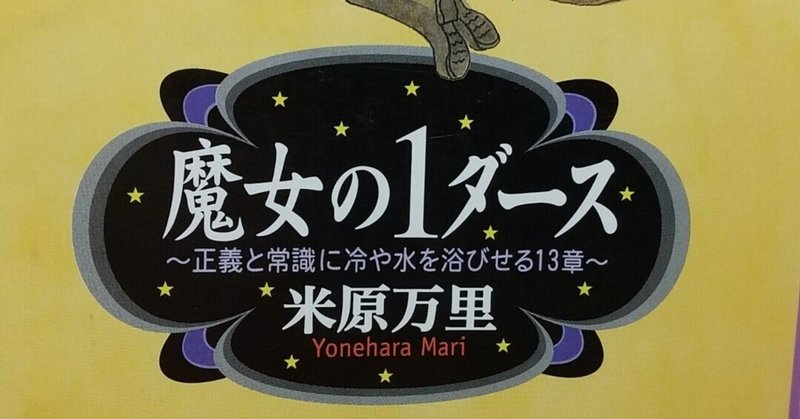
なぜロシアは
ウクライナに侵攻したのか、などという巨大で深遠な問いが、片田舎の主婦にもじわじわと染みて来ている。
もちろん、完全な答えなど持てよう筈がない。できることといえば、何人かの信頼できそうな人の話を聴き、新聞を読み、じっと想像を巡らせる位だ。
想像。
もしも、ロシアでもウクライナでもない一般の市民に。あるいは両国の専門家でも特に近しい関係者もいない普通の地球人に。
出来る事があるならば、それはあらゆる角度から一生懸命に想像するという行為から始める以外にないのではないか。
そんな思いから、もう10年以上前の愛読書、米原万里さんの「魔女の1ダース」を手に取った。
米原さんは、お父様の仕事の都合で幼少期をプラハのソビエト学校で過ごされ、長じてロシア語の同時通訳として活躍された方である。2006年に56歳で亡くなられた。
久しぶりに手にした米原さんの文章からは、生き生きとした知性とユーモアに溢れる、生身のロシア人の姿があった。
例えば。
「ロシア人の日本語通訳が 日本も東北地方になるとロシアに近いせいか言葉も似てくるようですね。ロシア語ではyesはダーですが、皆さんはyesの意味でンダーと言いますもの と述べて爆笑を誘い、緊張した雰囲気を一気に解きほぐしてくれた」(88頁より引用)
更には原因は違えど30年前との驚くべき類似性に、笑って笑えないような記述。
「ロシアにおいて、インフレがハイパー·インフレに限りなく近づき、通貨ルーブルの対ドルレートが暴落を続ける1993年、市場経済における金融制度について学ぶため日本に研修にやってきた経済関係官庁や国立銀行のロシア人職員グループがあり、わたし(筆者註:米原さん)が通訳を務めた。«中略»突然、ロシア財務省の局長が手を挙げてオズオズとたずねる。「あのー、あそこにある白い入れ物は何でしょう」。日本の銀行マンは首を傾げながら答える。·局長の指先が指し示すのは何の変哲もない屑籠だったからだ。「これは屑籠です。ゴミや業務上生じる、不用になった書類などを捨てる入れ物のことです。」
するとロシアの財務局長、「なるほどルーブル紙幣なんてのも、ここに捨てるわけですね 」(188~189頁引用)
にわかには信じ難いほどの自虐的いや、自制的ユーモアのセンスである。
2022年の今日。テレビやSNSに映るロシア人は、緊迫と悲壮感に溢れていることが素朴に悲しい。
どうか、ウクライナのためのみならず、市井に生きる普通のロシア人の為に。更にはきっとどんなロシア人の中にも根差しているであろうユーモアの力で。
戦火を止めて欲しい。
ロシアには戦争を終わらせるだけの勇気と力があると、信じる気持ちが、米原さんの著作から湧いてくる。米原さんに今生きていて欲しかったと、切に思う。
私に出来る事は小さい。でもやらぬよりマシではないか。
ロシアとウクライナを思いながら、今日出来ることを精一杯やりたいと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
