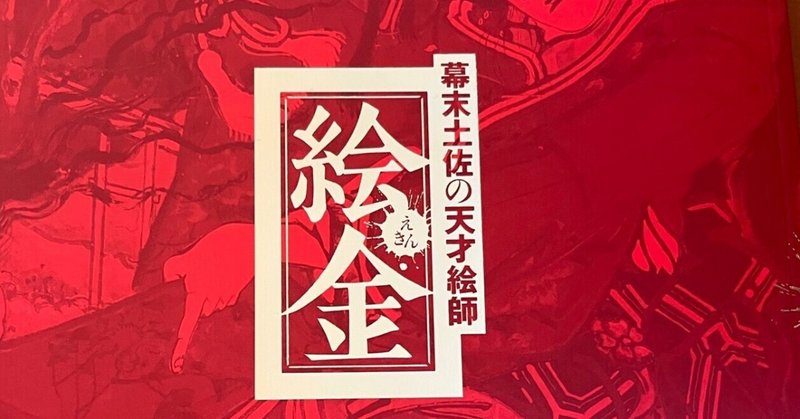
日記
『幕末土佐の天才絵師・絵金』
あべのハルカス美術館で行われていた展示会に行ってきました。
「絵金さん」というのは愛称でペンネームのほうは弘瀬金蔵。
江戸時代末期から明治にかけて活動していた浮世絵師です。

弘瀬金蔵は20歳にして土佐藩家老の桐間家の御用絵師となるが、33歳頃に贋作騒動に巻き込まれたことにより職を解かれ城を追放される。
その後は赤岡町に定住し「町絵師・金蔵」を名乗り、そこで芝居絵など数多く描き、地元民からは「絵金」の愛称で親しまれた。
江戸時代、商工業が栄えていた赤岡町には豪商が多く、商人たちは氏神様である須留田八幡宮の神祭で、地区ごとに芝居絵屏風の「絵比べ」を行った。「絵比べ」はより素晴らしい絵を持つ地区が勝ちとされ、勝者の商売繁盛が約束されるというもの。そういうわけで豪商たちは絵金に芝居絵屏風を依頼し、結果的に芝居屏風が絵金の代表作となっていく。


江戸時代に行われていた神祭の絵比べは、芝居絵屏風の展示として現在も受け継がれている。赤岡町に現存する芝居絵屏風23点のうち、18点は本町町内会の所有。残りの5点を所有するのは、本町町内会の隣に位置する横町町内会である。


歌舞伎や人形浄瑠璃、狂言などの山場を描いた極彩色の芝居絵屏風には、絵金の高い画力が結集されている。
異時同図法という物語の異なる場面を1枚の絵の中に収める手法を用いて、一枚の屏風にストーリーを持たせ、かつ構図もナチュラルなのでストレスなく見ることができる。
骨格や肉付きを表現する線の勢いは、描かれた人物が今にも動き出しそうなほどの迫力に満ちている。と同時に特に女性の手の線は繊細で、動と静をきっちり描き分けられているところも高い技術力を感じる。
また、血赤が多用された芝居絵屏風はおどろおどろしいと言われることが多いが、赤は邪気を払う色とされていたので、依頼者の要望に沿って魔除けの意味を込めて仕上げたと考えられている。
展示会でも屏風絵のダイナミックさ・迫力に圧倒されたので、いつか須留田八幡宮神祭に行って、夏夜の中に蝋燭の灯りで芝居絵屏風がほのかに浮かび上がる、幻想的な光景をナマで見て感じてみたい。
はじめてのあんみつ
あきやさんから広がっている「あんみつブーム」に乗っかって、自分も初めてはじめてあんみつに挑戦してきました!


思えば甘味屋さんに行っていつも頼むのは団子、ぜんざい、抹茶アイスとか、甘党まえださんなら画像にも映ってる「うずら」で、あんみつを選ぶということが今までなかったな…と思った。

はじめての挑戦なので、口の中リセット要因としてドリンクに抹茶オーレも頼みました。まえださんの抹茶オーレは甘味料が入ってないマジモノの抹茶なので、甘さが欲しい時は付属のガムシロップをお好みで足して調整するというスタイルです。
実際に食べてみて「確かにこれは溺れるな…」と思ったのがシンプルな感想でした。情報量が多くて食べるのが大変。うかうかしてたらアイスクリームが溶けてぐちゃぐちゃになっちゃう。白玉以外の要素が全部甘いので口の中が「甘味」でいっぱいになったので、抹茶オーレを頼んだのは英断だったな。自分はゆっくり落ち着いて食べたいのでシンプルなのが好きだな…と改めて思いました。逆に言えばブームがなければ挑戦しなかっただろうからいい経験になった。
「憧れ」の根源を考える
美術館に行った後は同じハルカス内のレストランで昼食をとったんですが、平日昼間の百貨店の客層って大体がお金にも時間にも余裕あるマダムなんだけど、自分の憧れって「そこ」なんだろうなーって思った。
自分の仕事上平日が休みになることが多く、よって動くのも平日が多いんですが、平日の美術館や百貨店などは特にマダム層が多い。そして彼女たちには独特の優雅さと余裕がある方が多いんですよね。周囲に穏やかな時間が流れているというか、今日をじっくりと楽しめる余裕があるというか…。
マダムたちの格好も各々、自分の好きな格好を取り入れてるんだろうなというカラフルで多種多様でおしゃれなスタイルの方が多くて素敵。そして背筋がしゃんとしている方々も多い印象。
自分の「穏やかで優しい丁寧な理想の生活を送りたい」という渇望の根源、ここなのでは…?と思いながらランチをとっていました。
今すぐには無理でも、その理想の姿に近づけるように日々自問自答していきたいと思った出来事でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
