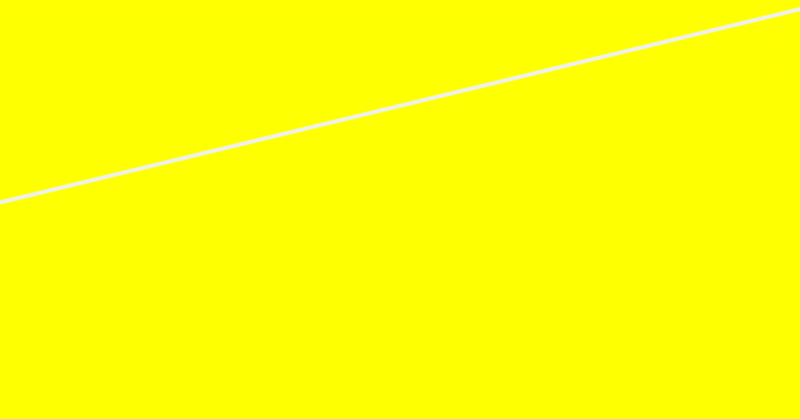
太陽のへその緒 #春ピリカ応募
黄色い絵の具を塗り込めたような冷たい表面に指を押し当てると、確かな手応えと共に明るい香りが解き放たれた。樹は指の力が抜けてしまった。その手から咲がそっと晩柑を取る。咲の手はごつくて褐色で、爪の周りに土がこびりついている。樹は背を丸め、光る青空に甘い香りが溶けていくのを眺めた。
昨日も晴れて、暑かった。小さな無人駅を出ると青い軽が停まっていて、咲が手を振っていた。「迎えなんてよかったのに」と言えば、「弟のしけた顔見に来たんや」と咲は笑った。がなるような洋楽を蜜柑畑に響かせながら、青い軽は時速200キロで走った。
縁側に並んで掛け、咲は晩柑を剥き、半分を樹に渡す。
「うちで手塩にかけた蜜柑やけん、味わって食べ」
晩柑はとろりとする汁ではじけんばかりだった。薄皮は脆くて、樹の骨張った白い指は何度も滑り、果汁に濡れた。甘い汁が惜しくて、彼は指ばかり舐めていた。
やっと辿り着いた果肉はふるふると柔らかく、透明な黄色に輝いていた。樹は甘酸っぱい果実に齧りつく。久し振りにものを食べた気がする。
「相変わらず葬式みたいな顔やな」
咲は弟をつつく。彼女自身は両親の葬式でも泣かなかった。
樹は晩柑の二房目を取る。指はやはりうまく動かない。剝がれなかった薄皮は痺れるような苦みを舌に残した。
「元気出し。いつまで居てもいいんやけんね」
咲は言った。この広い家には、咲夫婦しか住んでいなかった。樹は大学進学と共に上京し、在学中に書いた小説で新人賞を取った。
横を向くと咲が褐色の顔で笑う。その向こうで子供の頃の咲の顔がやはり笑っていて、この縁側で同じように掛けてうちの蜜柑を食べた、その何百回分もの記憶が、眩しい青空の下笑いかけてきたようで、樹は気が遠くなった。
「また、ぼーっとして…」
咲は彼の手から晩柑を取り、薄皮を剝いてやる。頑強だが器用な手。ずっと弟を守ってきた手だった。樹は再び庭を見る。木々は妙に生き物じみてぺかぺか光り、現実味に欠けていた。
樹は夢の中に生きていた。小さい頃から、空想のほうが彼にとっては現実だった。
それなのに、続きは書けなかった。
いつだって自分が一番読みたいと思う話を書いてきたつもりだった。しかしデビュー作の後、彼の書く本は売れなかった。
鉛筆を握れなくなった。箸の持ち方も忘れた。靴紐も結べなくなった。気が付けば爪を噛み指を吸っていた。指が、うまく動かなかった。
樹は夢の中に、回想の中に生きていた。
濡れた手に、咲は晩柑を載せて差し出す。樹はそこに、命を生み出すものの輝きを見た。
「咲、僕農業、手伝う」
彼は突然言った。咲は驚いたように目を見開いた。
「きついよ?汚れるし。焼けるし」
樹は首を振った。この指に命を繋げたい。姉のように何かを現実に生み出してみたいと願った。咲は少し笑って目を空へやった。
「…まあ、やってみ。そしてまた蜜柑の話でも書いたらいいやん」
完 1195字
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
