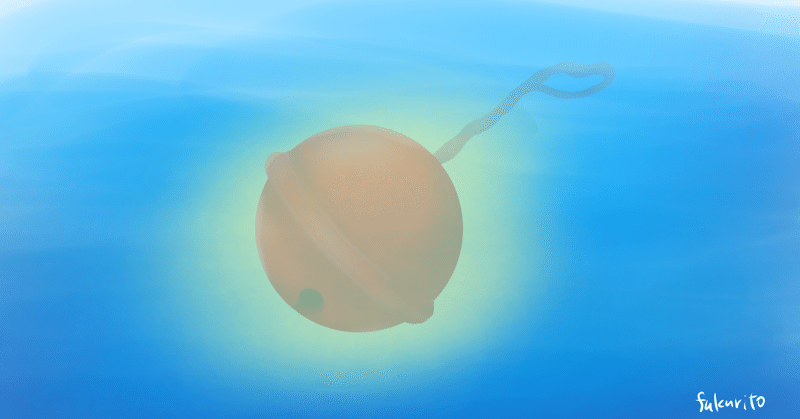
【小説】ゆづみつ④
「本当にしたいこと……ですか……」
みつおはしばらく黙り込んだ後こう言った。
「やっぱり、桜堂よりもパンをやりたいですね」
「ならそれを信じて進んでみたらいいんじゃない? やらない後悔よりもやる後悔! それにさ、桜堂は絶対にみつおが生きている間には潰れないと思うから、パン屋が潰れちゃったらになったら職人として桜堂で雇ってもらえばいいじゃん」
お店をしている人に『潰れる』なんてことは言っちゃいけないんだろうけど、元の形と違うとはいえ戻れる場所があるということは心の支えになると私は思っている。
「いや、桜堂もそうだけど、僕のパン屋も潰れることは無いと思いますけどね」
みつおはふふっと表情を緩めると私にそう言う。そして昨日の電話の時から感じていた違和感が無くなり、いつものみつおに戻った。
「都さんは強いですね」
帰り道、電車で来ていた私は家までみつおの車で送ってもらうことにした。その道中、ぽつりとみつおがそう言った。
「え? 全然強くないけど。むしろみつおのほうが最強じゃないの? ていうか、なんで急にそんなこと言い出すわけ? まさかこれから土砂降りとかならないよね?」
「それってどういう事ですか?」
「いや、みつおがそんな柄にもない事言いはじめるって、天変地異でも起こる前触れなんかじゃないか心配になってくるじゃん」
「柄にもないって。僕ほど謙虚な人間、そうそういないと思いますけど?」
「またまたー。でもさ、みつお。今日私が言ったことって、結構前にみつおが私に言ったことと同じなんだよ?」
「え?」
私は背もたれに寄りかかりながら、前を見たまま続ける。
「私が京都で無職の時、ああ見えて結構色々考えてたんだよ。跡取りとかそんなたいそうなレベルの話じゃないけど、これからの私の人生について。あのときみつお言ってくれたよね『前の仕事は楽しくはなかったですか?』『もう嫌いになりましたか?』って。その時に気がついたんだ。言い訳なら考えたら考えた分出てくるけど、楽しい事は無理に嫌いだと思いこまなくてもいいんだって。結果として体調を崩したけど、私はあの仕事のせいで体調を崩したんじゃなく、たまたまあの場所で体調を崩しただけ。だから、やりたい仕事に就いてまた体調を崩してしまうかもしれないと考えて、周りの勧めてくれた自分がそれほどやりたくない体調を崩さなさそうな仕事に就くよりも、好きなことをやってみてダメだったらまた他の方法を探そうって」
「僕、本当にいい事言いますよね」
「いやいや、そうじゃなくて」
思わず笑ってしまった私を見て、みつおも声を出して笑う。
「でも結果として、あの言葉で私は背中を押してもらったんだよね。そういう意味では素直にありがとうって言っておく」
「都さんにしては上からですね」
「ええ、私はいつも謙虚ですから」
そう言うと、私はみつおに向かってにっこりとほほ笑んだ。
雑誌の発売日の前日。
仕事が早く終わった私が家でゆっくりしていると携帯が鳴った。
「はい。もしもし」
「あ、都さん? 僕です。新堂です」
「みつお? どうしたのこんな時間に。あ、さては雑誌の発売が明日なもんで、落ち着かなくなって電話でもしてきた?」
「いやいや、都さん。僕を誰だと思ってるんですか?」
「みつお」
間髪入れずに私が答えると、みつおは思いっきり吹き出した。
「またそれですか。でも、そろそろ違う答えも用意しといてくださいよ」
「いや、だから何よ? 何の用事?」
「都さん、今家ですか?」
「そうだけど」
「わかりました。ちょっと待っててください」
そう言い残すと電話が切れた。
なんだろう。
待っててくださいって言うことはここに来るってことだろうか。とりあえず部屋着のままではまずそうなので、外に出てもおかしくない格好に着替えておくことにしよう。そう考えた私はのんびりと着替え始めることにした。
着替えが終わったころ、また携帯電話が鳴った。
「今着きましたんで、ちょっと出てきてもらってもいいですか?」
「出て行かなかったらどうなりますか?」
ふとしたいたずら心でそう答えてみる。
「それは……」
さすがにこの答えは想定外だったみたいだ。満足気にニヤニヤしていると、玄関のチャイムが『ぴんぽん』と鳴る。まさか。
「こうなりますね」
耳に当てた携帯からみつおの声が聞こえてきた。
「今出ます」
「はい。よろしくお願いします」
まだみつおには勝てないか。
少し残念な気持ちになりながら電話を切り、ドアを開けるとニコニコとしたみつおが立っていた。
「明日の発売日が不安ってわけでもなさそうだよね」
私がそう言うのを最後まで聞かず、みつおが口を開く。
「都さん、飲んでるんですか? さ、行きますよ。鍵閉めて下さい」
言われるがまま玄関の鍵を閉め、みつおの後をついて行く。車に乗り込んだ私が連れていかれたのはなぜかお好み焼き屋さんだった。
「お好み焼き?」
「ええ、お腹空いたんで。都さんもお好み焼き好きでしょ?」
「まあ、好きだけど、何で突然?」
「さあ、入って入って」
促されるまま店に入る。ここのお好み焼き屋さんは始めてだ。店の中を見回すと大きな鉄板を囲むようにカウンター席があり、離れた場所には座敷の個室があるようだ。
「予約してた新堂です」
みつおがそう言うと
「はーい。奥の個室どうぞー」
とお店の人が言った。
個室でお好み焼きを食べながら、私はみつおの顔色を読もうと頑張ってみる。しかしここに来る前に缶ビールを一本、そしてお好み焼きと一緒に持ってこられた瓶ビールを既に一本開けてしまったので、上手く読み取ることが出来ない。
「ささ、都さん。どんどん食べて下さいね」
みつおはコーラを飲みながら、私にお好み焼きとビールを勧めてくる。
「それはいいんだけどさ。今日はどうしたの? やっぱり明日の雑誌関連のこと?」
「半分正解ですね。明日の雑誌は都さんのおかげでとても満足のいく仕上がりにしてもらったと思っています。だから、その感謝の気持ちも込めて」
「んー。じゃあ、残りの半分は?」
「それはまあ、その。あ、ビールもう一つくださーい」
はぐらかされた。
でもみつおが変なはぐらかしかたをしてくるのは珍しい。酔いの回った頭で考えようとはしてみたけど、もう私の頭は単純な事以外は受け付けない体勢にはいってしまったようで応答しない。
まあいいか。ここのお好み焼きはめちゃくちゃ美味しいし。お酒も一人で飲むよりずっと楽しい。
明日の発売日が気になって仕方がないのはみつおじゃなくて私の方だ。だからこの時間がとてもありがたい。
「ごちそうさまでしたー」
私はお店を出ると財布も出さずにみつおにそう告げる。
「はいはいどういたしまして。都さん、かなり酔ってますね」
「いやいや、グラスが空くたんびにビールを注いでくれていたのはどこのどなたさまでしたっけ?」
「都さん、飲みたいかなーって思って」
「まあ、そうだけど。飲んだけど。だけど」
「はいはい。んじゃあ、ドライブでもしてから帰りますか」
「はーい」
みつおの車に乗り込むと私はすっかり酔っていたためかすぐに眠ってしまった。
どれくらい眠っていたのだろう。目が覚めた私は隣の席にみつおが座っていることを確認する。
「あ、目が覚めました?」
「うん。ゴメン。寝ちゃってた」
「いえいえ。知り合いの店の記事が出るのは、いつもの自分の記事を出すときより緊張するでしょうしね」
みつおは缶珈琲を私の方に出しながらそう言った。
「でもそれは紹介してもらう方も一緒じゃないの?」
プルタブを開けながら私は答える。
「でも、もうどんな記事が載るかっていうのは確認させてもらってますし、僕はそれほどでもないですね」
「ふうん。そんなもんかな」
珈琲に口を付けながら返事を返す。
「それでですね。都さん。明日雑誌が発売されると、しばらくお店の方がてんやわんやになるとおもうんです。明日から販売するパンの量もかなり増やすことになってますし。僕、しばらくかなり忙しくなると思うんです」
「うん。そうだろうね。体調、気を付けてよ?」
ただでさえ人気があるお店なのだから、そうなるのは当然の事だろう。
「じゃなくてですね……」
何だこの空気は。
「あのですね。僕は都さんのことがずっと気になってまして。それで、もしよかったら付き合っていただけませんか」
「え?」
「だから、都さんのことが好きです」
私は一瞬何を言われているのか理解できなかった。そしてその後みつおはストーカーじゃないかと思ったことがあるのを思い出す。
「みつおってば、やっぱりストーカーだった感じ?」
「はあ?」
「だって、なんかそんな感じしてたんだよね」
「いやいや、違いますよ」
「京都で初めて会ったときも、なんであんな場所にいたわけ?」
「あそこは昔から考え事する時によく使っていた場所ですよ。それにあの時、都さんが自転車で木に喧嘩を売らなかったら出会わなかったわけですし」
何も言われなかっただけで、木に突撃していたことはしっかり覚えているのか……。今更恥ずかしい思いをさせられるとは思ってもみなかった。しかもこんなシチュエーションで。
「料亭でだって、あのタイミングで居場所がわかるなんて、なんか私の携帯に仕込んでるんじゃないの?」
「いやいや、あれまでに何回待ち合わせしたと思ってるんですか? 都さんがあれくらい早めにお店に来ることはわかってましたよ。現に僕の方が先にお店に入ってたでしょう。どれだけ逞しい想像力してるんですか」
おかしい。なんとなく立場が弱くなってきた気がする。
「じゃあ、忙しくなる直前にそういうことを言い出すってことは、あれでしょ。忙しくなって監視出来ないからとかなんとかそういうアレでしょ」
「都さん、自分が何言ってるか理解してます?」
適当に話をしていることがバレたみたいだ。
「忙しくなる前にと思ったのは、もし振られても仕事に追われて考えなくて済むようにっていう僕の弱い気持ちからです。都さん、何考えてるかイマイチよくわかんないんで」
サラリと酷いことを言われているような。
「と言うわけで。好きです」
そう言いながらみつおは私の体をふわりと抱き寄せた。
「あのさ」
「はい」
「ストーカー? ってつい今の今まで疑われてた相手に普通そういうことするかね?」
「嫌だったら今こうやっておとなしくしてくれてないでしょう?」
「うわ。ほんとみつおって『世界は俺のために回ってる』を地でいってるよね」
「そんなことないですよ」
そんなこんなでよくわからない流れの中で、この日からみつおとお付き合いをすることになった私。世の中本当に何が起こるかわからない。
それからしばらくはお店の方が忙しくて電話を一日一回出来たらいい方ではあったけど、私とみつおの関係はいいかんじに進展していた。
そして一年ほど経った頃、私は幸せの絶頂期を迎えていた。
仕事も順調だし、みつおのお店も二号店を開く準備を始めるくらい繁盛していたし。パンは相変わらず美味しいし。
二人の仲も、小さな喧嘩はたまにするけれど大きな喧嘩をすることは無く、事あるごとに私はいつもみつおに応援されているんだと感じていた。
二人でいる時間はとても穏やかで、大阪の会社でみつおに対して『鼻につく』だなんて思っていたことはすっかり無かったことになっている。みつおは私にとってとても大切な人だ。
人生なにが起こるか本当にわからない。
そんなある日。
私たちは雰囲気のいいパスタ専門店で晩御飯を食べていた。
「あのさ、ゆづ」
珍しくみつおが真剣な顔をして私に話しかけてくる。
「ん? なに? 真面目な顔して」
「いや、あのさ。ゆづの休みの日って、土曜日だったよね?」
「うん、そうだけど。っていうか、私はずっと土日が休みだけど急にどうしたの?」
今の会社に入ってからずっと土日が休みなのに、今さら何を言いはじめたのだろう。
「再来週の土曜日、ゆづの実家に挨拶に行きたいと思ってるんだけど、ゆづのお父さんとお母さんの都合はどうだろう。よかったら聞いてみてもらえないかな」
「それって……」
「ゆづきさん、僕と結婚してくれませんか」
「いや、何で先に休みの日を聞いた? それでその次はお父さんとお母さんの予約? そして最後にプロポーズってなんか順番おかしくない?」
今まで見たプロポーズシーンはどれも女性が嬉し涙を流すのが当たり前だったはずなのに、このプロポーズシーンには私は笑い涙をこらえることが出来ない。
どうしてそうなった。
あれだけスマートな対応をし続けていたはずのみつおが私にとって人生最大のイベントでトチるだなんて。面白いにもほどがある。
笑いすぎて涙で滲んだ視界の中で、みつおは真っ赤な顔をして炭酸水をごくごく飲み始めた。
「ごめんごめん」
なんとか笑いを押し込め、私も涙をぬぐいながら水を飲んだ。
「いや、確かに順番間違えたらおかしくなるよね。ちょっと緊張しすぎて頭の中が真っ白になっちゃって……」
「ありがとう」
「え?」
「だから、ありがとうって」
私はみつおをまっすぐ見つめた。
「いや、笑っちゃってホントごめん。でもさ、いつも何でもそつなくこなしてきたみつおが頭の中が真っ白になるくらい緊張してくれたっていうのがなんていうか、物凄く特別な事じゃない? それに、涙のプロポーズより笑いのプロポーズの方が絶対に忘れられない思い出になるし。うん。私は今日のこのことは絶対に忘れない」
「出来れば忘れて欲しいかも……」
「いや、絶対に忘れない。そして将来子供が出来たら絶対に語り継ぐ。むしろ、今日帰ったら日記に書いて残しておこうかな」
「忘れて下さい。お願いします」
みつおは懇願するような顔つきでこちらを見ている。
しかしこんな記念になることを忘れるだなんてありえないだろう。なにせ、みつおに出会ってから初めてみつおをやり込めた日なのだ。
あ、もちろんメインは結婚を申し込まれた日だけど。
「うそうそ。日記にも書かないし、語り継いだりもしないよ」
「よかった」
心底嬉しそうなみつおに対して、私は改めて返事をした。
「ふつつかものですが、これからもよろしくお願いします」
「はい。こちらこそ。よろしくお願いします」
語り継がないと聞いた時よりも嬉しそうな顔をしていないのが少し不満ではあるが、まあ、嬉しそうだからヨシとしておこう。
「あと、再来週の日曜は僕の家に来てくれるかな?」
「うん。もちろん」
軽く返事をしたものの、みつおの実家に行くと考えただけでとてつもなく緊張してきた。桜堂には何度も行ったし、ご両親も何度もお見掛けしたけれど、結婚の挨拶となるとやっぱり敷居が高い。
「緊張しなくても大丈夫だよ」
そう言ったみつおの手には、いつの間にか指輪のケースが握られていた。
それから一週間。
同じ世界にいるはずなのに、何を見てもキラキラと輝いているように見えるし、嫌なことがあってもそれほど嫌だとは思わない。ああ、あの人にも色々あるわよね。なんて余裕を持って接することが出来るのである。
気持ちひとつで世界とはこんなにも変容するものなのか。
私は毎日が誕生日くらい幸せな気持ちで生活していた。
そして土曜日。みつおの仕事も都合がついたので、二人で一緒に来週の顔合わせ用の洋服を買いに行くことにした。
自分の実家はともかく、みつおの親御さんに会うのにくたびれた洋服で行くわけにもいかない。ちょうどいい機会なので私はスーツを新調することにした。
みつおはパン屋の勉強を始めてからスーツを着る機会なんてほとんどなかったらしいけど、サイズは全然大丈夫だそうだ。なんと羨ましい。私は……。まあ、私のことはひとまずおいといて。みつおもワイシャツがヨレヨレになっているのが気になるからシャツだけ新しく買うことにしたそうだ。
「うー、緊張するー」
買い物を終え、晩御飯を食べに入ったハンバーグの美味しいお店で私は水をぐいぐい飲んでいた。
「ゆづ、ちょっと水飲みすぎじゃない? そんなに緊張しないで。目の前で緊張されると僕まで緊張してくるし。それに今週じゃなくて来週。だから今から緊張してると身が持たないよ?」
確かにみつおの言うとおりである。
「プロポーズは盛大にやらかしたのに、なんか落ち着いてるのずるくない?」
私は顔の高さまで持ち上げた左手の薬指にはめた指輪をチラチラ見ながらそう呟く。
「いや、だからアレはもう忘れよ? で、ゆづは何にする?」
「もちろんチーズ乗せ!」
「ほんと、好きだよねー」
「みつおはおろしそでしょ?」
「残念。今日はデミグラスにしまーす」
「私がデミグラスって言ってたら?」
「おろしそだったかもね」
「そんな気がしてた」
くすくす笑い合う。大切な時間。
来週の顔合わせは緊張するけれど、みつおが隣にいれば大丈夫だろう。今までだってずっとそうだった。いつも支えてくれた。
私はみつおの顔を見ると、にっこりと笑った。
「ああ、お腹いっぱい! 美味しかったー」
少し離れた場所にある駐車場まで二人で並んで歩く。ここの間の道は街灯は少ないけれど、その分なんとなく夜の雰囲気があっていい感じなので私は大好きだ。
「そう言えば、来週の時間ってもう言ったよね?」
昨日の電話で伝えたはずだけど、もう一度確認しておきたい。
もう一度もう一度と言いながら、この一週間であとどれくらい私はみつおに確認するのだろう。
「うん。お昼ご飯一緒に食べるからって、十一時半だったよね」
みつおは何度聞いても嫌がらずにきちんと答えてくれる。こういうところは真似したいと私はずっと思っている。
「そうそう。たぶんね、お昼はいつもの仕出し屋さんのお弁当だと思うんだー。佐幸ってみつお知ってる? あそこのお弁当美味しいんだよね」
そう言い終わるか言い終わらないかのうちに私の体は思いっきり隣から押され、道端に吹き飛ばされた。
「いたた……」
思い切り地面に打ち付けた肩を抑えながら私は起き上がる。
あれ? みつおはどこにいったんだろう。
辺りを見回すと、電信柱に顔をめり込ませた白いセダンが見えた。
「え?」
急に震え出した体を抑えながら、私はゆっくりとその車に向かって歩き始める。一歩。また一歩。途中、街灯の灯がかろうじて届ている場所に白っぽいものが落ちている。あの色は見たことがある。あれはさっきまで私の隣を歩いていたみつおが着ていた服と同じ色。
「み つ お ?」
慌てて駆け寄ると、みつおが倒れている道路には黒い染みが出来ていた。黒い染み……? うそ。うそでしょ?
「みつお? みつお!」
名前を呼ぶとみつおは片手を上げた。
「今救急車呼ぶから!」
そう叫んだ私はカバンから携帯電話を取り出した。カバンに着けた達磨の鈴がその衝撃で『チリン チリン』と鳴った。
震える指で救急をコールしようとしてみても動揺からか、たった三ケタの番号すらきちんと押すことが出来ない。
「はやく。早くしないと」
気ばかり焦ってますます上手くいかない。
そんな私の手を真っ赤に染まった手でそっとみつおが触れる。
「ごめんね。今呼ぶから! 頑張って!」
私は涙をぼろぼろとこぼしながら私は必死に一一九を押そうとする。しかし何度やっても一一一や一一三になってしまう。どうして思い通りに動かないんだ。もう嫌だ。早く。誰かみつおを助けて。
その時、誰かがそばを通りかかったらしく「もう大丈夫ですよ。救急車呼びました」という声が聞こえた。
「ゆづ……もう大丈夫」
「みつお! 大丈夫? 痛い?」
身体を起こそうとするみつおを押しとどめ、私はカバンを頭の下に差し込んだ。『チリン チリン』とまた鈴が鳴る。
「ゆづが無事でよかった」
ダラダラと頭から血を流しながらみつおは微笑んだ。
いやだ。
こんな時に笑わないで。
「みつおも大丈夫だから。しっかりして」
みつおの手を握りながら私は叫ぶように繰り返す。
「ゆづ。僕はいつでも君を応援してる。それを忘れないで」
その時、救急車のサイレンの音が聞こえてきた。私はこれでみつおが助かるとホッとしながらも、救急車がいつまでたっても姿を見せないことに苛立ちも感じていた。
早く。早く。
「みつお、救急車きたから! もう大丈夫だから! 来週顔合わせするんでしょ? しっかりして!」
「ゆづ。……」
そのあとみつおが何を言ったのかは近付いてきた救急車のサイレンの音と、バタバタと駆け寄ってくる救急隊員の足音で聞き取ることが出来なかった。
救急車に乗せられたみつおは酸素マスクをつけられ、うっすらと開けた目はぼんやりと私を見ていた。
「みつお。しっかりして」
私はみつおの手を握り話しかけることしかできない。なんて無力なんだろう。私が代わりに轢かれたらよかったんだ。なんで。どうして。
ピーーーーーー
その時、耳障りな電子音が鳴り響いた。
救急隊員の人がみつおの胸に手を重ねて置くと一定のリズムで押し始める。
「触らないで。手を離して。声だけかけ続けてあげてください」
動きを止めることなくそう言う救急隊員の人の下で、みつおは同じリズムで体全体を波打たせているように揺れている。
なんだろう。この違和感のある揺れ方は。普段体を揺らしたり、衝撃を与えたりしてもこんな奇妙な動きにはならない。
うそ? 私の頭の中に最悪の事態が思い浮かぶ。
嫌。そんな未来は望んでいない。
無理やりみつおの笑顔を思い浮かべてみてもすうっと薄くなり輪郭を保つことができない。
どうして。
ついさっきまで見ていたはずなのに。
不自然に揺れるみつおを見つめたまま何もできず、ただただ涙を流し続けているうちに救急車は病院に到着した。
ストレッチャーで運ばれていくみつおを呆然と見送る。みつおをのせたストレッチャーは物凄い勢いで遠ざかり、やがて見えなくなってしまった。
もう会えないのかな。
そう思った瞬間、私の目の前が真っ暗になった。
私は左手を包み込んでいる暖かさを感じて目が覚めた。うとうととしながら右手をそちらに寄せようとしたところで肩に激痛が走る。
「痛っ」
「ゆづき? 目が覚めた?」
目を開けると、心配そうに私を覗き込むお母さんの顔が見えた。
みつお? そういえばみつおは?
最後に見た視界から消えていくストレッチャーを思い出し、思わず頭をふる。違う。そうじゃない。
「おかあさん。みつおは?」
お母さんは私の手を握っている手に力を込め、私をしっかりと見つめた。
「ゆづき。落ち着いて聞いてちょうだい。新堂さんは亡くなってしまったの」
「うそ……うそよ」
勢いよく体を起こした私の背中にお母さんはそっと手を添える。そして何も言わずゆっくりと背中を撫で続けてくれた。
嘘だ。嘘だ。みつおが死んでしまうなんて嘘だ。認めない。
私たちは今週末お互いの両親に挨拶をしに行くはずだった。そしてそこから結婚に向けて色々と準備を始めるはずだった。どうして。信じない。私は信じない。
この世界にみつおがもう存在していないだなんて信じるもんか。家に帰ればいつものソファーでうたた寝をしているに違いない。そうだ。家に帰ろう。
腕に刺さった点滴の針を掴むと私は勢いよく引っこ抜いた。真っ白なシーツに真っ赤な血が飛び散る。
「ゆづき!」
お母さんの悲鳴のような声が響き渡り、バタバタと廊下を走る足音が聞こえる。
私は家に帰るんだ。
みつおの待つ家に。
ベッドから立ち上がろうとする私を看護師さんが覆い被さるようにベッドに押し戻す。
私は帰るんだ。
みつおの待つ……
私の記憶はそこでぷっつりと途切れた。
良かったらスキ・コメント・フォロー・サポートいただけると嬉しいです。創作の励みになります。
