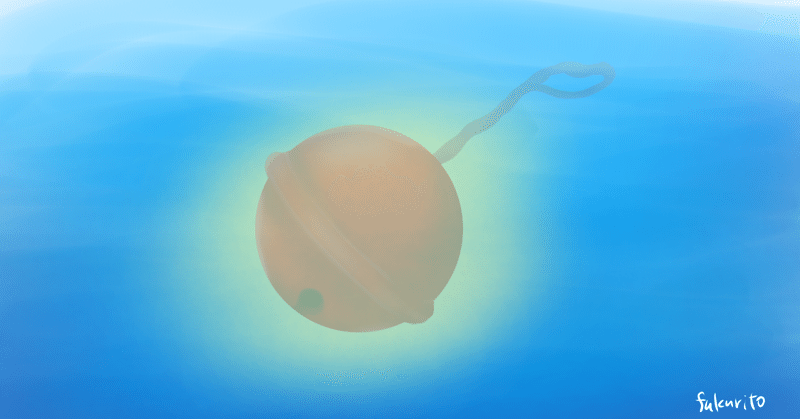
【小説】ゆづみつ③
「そういえばさ。どうしてみつおはパンを作ろうと思ったの?」
ドライブ中、私は疑問に思っていたことを聞いてみることにした。
「パンですか。なんででしょうね?」
「あの会社を辞める前から? それとも辞めた後? みつおはあの会社に入る前に他の業種も何個か回ってたんでしょ?」
「都さん。よく知ってますね。そんなこと」
「いや、あの会社の人間だったらみんな知ってるんじゃないの? 『有名な和菓子屋の一人息子なのに異業種を渡り歩いてる』って言うことくらいは」
「へえ。そんな噂が回ってたんですか」
なんかまずいことを言ってしまったような気がする。
「みつお、怒ってる?」
「いや、怒ってませんよ。別に。それに本当の事ですし、隠してたわけでもないですし」
みつおは怒ってはいないとは言うけれど、周りの空気を硬くしてしまった。ああ、もっと気遣いのできる人間になりたい。
私はみつおの顔をチラリと見た後、助手席の窓の外を流れていく景色をぼんやりと眺めた。
「都さん」
しばらく続いた沈黙を破ったのはみつおだった。
「さっきどうしてパンを作ろうと思ったかって聞きましたよね。考えてみたんですけど、僕はずっと桜堂の一人息子としてのプレッシャーを感じていたんです。もちろん父も母も『お店のことは気にせずにやりたいことをやりなさい』って小さい頃から言ってくれてました。でも、なんていうんでしょうね。父や母がそう思ってくれていても、周りの人間までもがそう思ってくれるわけでもなくて。だから、父や母が知らないところで僕は結構色々なことを言われていたわけです。それで高校を出てから家を離れて外の会社に就職し、色々な業種を回って社会勉強をしていたんですけどね。あの大阪の会社で都さんが調子を崩して退職された後、なんか今まで考えないようにしていたことが気になるようになってきたんです。店を継ぐ継がないは別にして両親が店をたたまざるを得なくなった時、僕はこのままの生活をしていて後悔しないだろうか。と」
きっかけが私の退職だったとは正直言って驚いた。
誰かが私の人生に大きな影響を及ぼすことはしょっちゅうあるけれど、私が他人の人生に干渉することがあるなんて想像したことすら無かったから。
「都さんが退職して一ヵ月後に僕もあの会社を辞めました。そして実家の手伝いもほんの少しだけしながらフラフラとしていた時に出会ってしまったんです。天然酵母のパンに。もちろん周りの人間には良くは思われていません。そんな時間があるなら家を継ぐ準備をするのがスジじゃないのかって。でも僕は家を継ぐよりもパンを作りたかった。だからみんなに認めてもらえるパンを作るために、酵母やパンについてたくさん学びました。そして最近、やっと納得のいくパンが作れるようになったんです」
「へえ。みつおって意外と努力家なんだね」
「意外とってどういう意味ですか? 僕はいつだって手抜きなんてしませんよ?」
「ああ。手抜きはしないのは知ってるよ。そう言うのじゃなくて、なんて言うのかな。んー。言葉にするのが難しい」
私は一生懸命言葉を探そうとしたけれど、なかなかいい言葉が見つからない。言葉に関わる仕事を目指し、夢が叶い、それで生活していたこともあるのに。くやしい。
それでも何か見つからないものかと考えていると、みつおが口を開いた。
「そういえば、都さん」
「ん?」
「都さんは、次の仕事も雑誌の仕事とか、そういう関連で探すつもりですか?」
何かをしなくてはならないとは思っていたけれど、具体的に考えることは無かったな。私はどうしたいんだろう。
「んー。まだ何も考えてないんだよね。実は」
「前の仕事は楽しくはなかったですか? 僕から見た都さんは、体調を崩すまでは天職のように生き生きと仕事をしていたように見えたんですけど」
「あの仕事は高校生の時からの夢だったから。それに本当に楽しかった。体調を崩さなかったら定年、いや、嘱託としてでも続けたかったよね。うん」
みつおに答えを返しながら、そういえば私はあの仕事がとても好きだったことを思いだした。すっかり忘れていた。
「もう嫌いになりましたか?」
嫌いになる? いや、今まで楽しかったことをすっかりと忘れていただけで嫌いになんてなるわけがない。
「全然。嫌いになんかならないよ。ていうか、今みつおに聞かれるまで、私は雑誌の記者っていう仕事がどれだけ楽しかったかっていう事を忘れてた。思い出させてくれてありがとう。うん、そうだよね。あれだけやりたかった仕事なのに綺麗さっぱり頭の中から抜けてた。変なの」
「まあ、都さんらしいじゃないですか」
「いやいや、それどういう意味?」
「いいじゃないですか。あ、そろそろお店に向かうのに丁度いい時間になりましたよ」
またみつおに適当にはぐらかされた。
でも何にせよ、私はこれから進む道がほんの少しだけ見えたような気がする。よし。明日から頑張ろう。
あれから二年が過ぎた。
私は地域の情報誌を作っている会社に入り、毎日愛車の軽自動車に乗り府内を忙しく走り回っている。
季節の情報や新しく出来たお店、老舗のこだわりなど多様な情報を取り上げる我が社の情報誌は『お店の人が主体となり作り上げる』というコンセプトにより、他の雑誌などでよく起こる『こんなつもりじゃなかったのに』や『ここをもっと取り上げて欲しかった』といった問題が起こらないと取材先からとても高評価を受けている。そしてそれが店主からお客さんに伝わり、そこからクチコミが広がり続け我が社の信頼は鰻登り。京都の本当の姿を知りたければこれを読め! とまでは行かないけれど、それに近いくらいの発信力を持つ媒体として注目を浴びている。
風の噂では近々近隣の県での取り扱い、いや全国区で発売される予定だとかなんだとか。
「こんにちはー。お邪魔しまーす」
店の扉を開けると中からふわっとパンのいい香りが私を楽しそうに出迎えてくれた。もちろんパンの香りからの側からすれば、まったくそんな意図は無いことは知っている。全て私の妄想だ。
今日の取材先は去年オープンしたパン屋さん。オープン当初から『ここのパンは別格』とリピーターが多数存在しているらしい。
天然酵母で作るパンということもあり一日に焼ける個数に限りがあるにもかかわらず、買いたい人は増える一方でなかなか手に入らない。そんなプレミア感も手伝って、このお店のパンの人気はとどまるところを知らない。
「いらっしゃいませー」
パンの香りの向こうから耳慣れた声が聞こえてくる。
「都さん。今日はよろしくお願いします」
「はい。こちらこそよろしくお願いします」
みつお相手に他人行儀な挨拶をしている自分がおかしくて、思わず笑ってしまう。いや、今日は仕事仕事。切り替えしないと。もう社会人になってから長いんだから。
そこから仕事モードに入り、二時間ほど雑誌に載せる記事の構成について話し合った。みつおも同じ会社で働いていたことがあるだけに、面白いくらいスムーズに話が進む。むしろ私が何もしなくても立派なページが出来上がる勢いだ。でも私はこの仕事が好きで戻ってきたのだという気持ちを思い出し、いつもより攻めたアイデアをたくさん出した。今までの打ち合わせの中で一番上手くいったかもしれない。
「お疲れさまでした。あ、ちょっと待っててくださいね」
全ての打ち合わせが終わった後、みつおはそう言うと奥の部屋へと入って行った。私は「はーい」と軽く返事をして、広げた荷物を片付け始める。カバンに全てを詰め終わる頃、珈琲のいい香りが漂ってきた。
「いいにおい」
思わず手をとめ、珈琲のにおいを胸いっぱいに吸い込んだ。
「お待たせしました」
そう言って珈琲を運んできてくれたみつおが持つトレイには珈琲カップだけでなく、山積みにされたパンまでもが乗っていた。思わずキラキラした眼でパンを見てしまった私を見て、みつおはクスクス笑いながら
「都さん、お腹すいたでしょ」
と、さも当然のように言う。
「いや、そんなにお腹空いてるわけじゃないよ?」
その言葉を遮るように私のお腹が『ぐう』と音を立てる。
どうしてこうもタイミングよく……。
「隠さなくてもバレてますから安心してください。さあ、食べましょうか」
珈琲とパン。最高の組み合わせだ。こんなに幸せな時間を過ごすことができるだなんて。みつおと友達で良かった。大阪にいた私にもし会えるなら『もうちょっとみつおに優しくしてあげてもいいんじゃない?』とでも言っておきたい気分である。
「そういえばさ、みつお」
私はパンをもぐもぐしながらみつおに話しかける。
「なんですか? 都さん」
「こないだ会って話した時、お店を開いたことご両親に言ってないって言ってなかった? それなのに、雑誌で大々的に宣伝なんかしちゃって大丈夫なの?」
「ああ、それですか」
みつおは珈琲をひと口啜ると、カップを両手で包み込みながら話を続ける。
「お店を開いたことは直接言ってませんけど、両親どころか桜堂の従業員たち全員このお店のことは知ってると思いますよ?」
「それって、ますます大丈夫なの?」
和菓子屋の跡取りである一人息子がパン屋を開いた。しかもその店は今や知る人ぞ知る有名店だとか、そんなことをしていて大丈夫なんだろうか。私は継ぐものがないし、跡取りになりえる場所もないので、そのような立ち位置の人が置かれている状況は想像するくらいしか出来ないけど、普通に考えるとちょっと結構キビシイものなんじゃないのだろうか。
「大丈夫なんじゃないですか? こないだアルバイトさんにお店を任せてた時間帯に両親がこっそりパンを買いに来てたらしいですし」
「こっそり!」
「別にこっそりしなくても僕は全然かまわないんですけどね」
「向こうからしたらかまうことなんでしょ」
「ああ。そうかもしれませんね」
そういうとみつおは肩をすくめて笑う。
「でも雑誌に出ちゃうと今までこのことを知らなかった桜堂の関係者にまでバレちゃうでしょ。それって問題にならない? 本当に大丈夫?」
どうして跡取りの一人息子よりも私の方が桜堂に気を使っているのだろう。そんなことを思っていると、みつおはパンをひとつ摘まむと両手で割きながらこういった。
「大丈夫です。雑誌が出るまでにちゃんと話をしに行きますから。それより都さん。今回のうちのページはいい感じにできあがりそうですよね? まあ、僕もアイデアを出しましたし、いい感じにならない方が不思議かとも思いますけど」
せっかく心配してるのに。といっても、私がどれだけ心配しても何ができるわけでもないもんね。気を取り直すと、私は今日の打ち合わせ内容を思い返す。
確かにみつおの提案は私が考えていたコンセプトを全て踏襲しつつ新しいアイデアまで盛り込まれていた。雑誌の編集という仕事もみつおにとって天職なんじゃないだろうか。うらやましい。
私はふと大阪の会社で働いていたときのことを思い出した。
企画に行き詰った時、どうしても上の了承が得られない時、いつもみつおが呟いたひとことや、さりげないアドバイスで乗り越えられていたことを。ああ、私はみつおにかなり手助けしてもらってたんだな。みつおはただ憎まれ口を叩いていただけじゃなかったんだ。
そういえば、私がもう一度この仕事に就こうと思ったのもみつおの言葉からじゃなかったっけ。それに、みつおと再会してからのここの二年の間もよく話を聞いてもらってた。
手元のパンからみつおの顔へ視線を上げると、珈琲を飲んでいるみつおと目が合った。
色々と助けてもらっていたことを思いだしていた私は、なんだか目を合わせるのが恥ずかしい。スッと目線を外すと何事も無かったかのようにパンを頬張り始める。
「そう言えば都さん」
「ん? なに?」
「顔、赤いですよ?」
「いや、そんなこと無いと思うけど」
「体調でも悪いんですか? 食欲はめちゃくちゃありそうですけど」
「なんでもないってば。あ、そろそろ会社に戻らないと。今日の原稿の締め切りまであんまり時間ないんだよね」
バタバタと席を立つ私にみつおは棚に置いてあった大きな紙袋を差し出した。
「これ、皆さんでどうぞ。『賄賂です』ってちゃんと伝えといてくださいね」
「あ、ありがとう。ラフが出来たら一番に見せるから」
紙袋を受け取った私は逃げるようにみつおの店から飛び出した。
ラフが完成した日、みつおに連絡すると夜ご飯を食べながら話をしようということになった。電話越しに聞いたみつおの声はいつもより硬かったような気がしたけれど、それは忙しい時間帯に電話をかけてしまったからだろう。急いで連絡を取りたかったけど、むこうの都合の良い時間に確認できるメールで連絡するべきだったな。
出来上がったラフをカバンの中にしまいながら私は少し反省した。
「都様ですね。どうぞ、こちらへ」
みつおに指定された場所はいつものカジュアルなお店ではなく、なぜだか料亭だった。こんなお店に上がる日が来るなんて。
店構えを見て怖気付いて帰ってしまおうかとも考えた。しかし、店の前でどうするべきか思い悩んでいる最中に携帯に着信が入った。
「都さん、もうお店の前あたりでしょ。僕はもう中に入ってますから早く来てくださいね」
どうして私が店の前にいることがわかったのだろう。
ありえないくらいの緊張からか、私はふいにこのタイミングで電話をかけてきたみつおがストーカーなんじゃないかと思いはじめた。
いやいや、ただ単にいつも約束の時間五分前にお店の前にいる私の行動パターンを知っているからだろう。なんで今更急にみつおのことをストーカーだなんてことを考え始めたのか。ばかばかしい。
我ながらおかしな考えだとみつおストーカー説を頭から振り払おうとしたとき、もう一つの声が聞こえてきた。
でも思い返してみなよ。みつおと京都で初めて出会ったあの場所。ちょっと不自然じゃなかった? もしかしてみつおは私があの場所を通ることを事前に知ってたんじゃないの? やっぱりストーカーじゃない? 職場の同僚がストーカーってよく聞くパターンだし。
確かにあの場所での出会いはちょっと不自然だったような気がする。
まさか本当に?
いや、そんなことは無い。
でもどちらの言い分も信じられるような気がする。悩ましい。
しかし、私がもう店の前まで来ていることをみつおは知っている。
もしみつおがストーカーだとしたら家の場所はバレているのですぐに家まで訪ねてくるだろう。店の前まで来ているにもかかわらず帰ってしまったことで刺激をしてしまって良からぬことが起こるかもしれない。
逆に、もしみつおがストーカーじゃなかったとしたら、店の前まで来ているにも関わらず帰ってしまったことがわかったらもう二度とみつおのあのパンを食べることが出来なくなってしまうかもしれない。
どちらにせよ、すぐに中に入る方が私にとって幸せな結末が待っている。よし。中に入ろう。私は覚悟を決める。
そうして色々な意味で意を決して足を踏み入れた私は入口で着物姿の仲居さんに出迎えられた。粗相をしてしまわないか、ますます緊張が高まった私の頭の中はもう限界が近い。ストーカー。その五文字が頭の中を占領していく。ストーカー。
お座敷に案内され、開けられた襖の奥にみつおの姿を見つけた瞬間、あれだけ頭の中でストーカーと連呼し恐れていた存在だったにもかかわらず、私はみつおの顔を見た瞬間ホッとしてしまった。
みつおがストーカーなわけないじゃん。
ですよね。
緊張し過ぎってこんなに頭の中がバグるんだ。怖い。
「どうも」
「都さんどうしたんですか? なんか変ですよ?」
余裕のあるみつおの正面に座った私はぎくしゃくしながら
「なんで今日はこんなスゴイところなのよ」
と小さな声でみつおに言った。
「だって、焼肉とか中華とかだとラフの紙が汚れちゃうじゃないですか。資料を気兼ねなく広げるにはテーブルが大きな個室の方がいいかなーって思ったんで。今日は僕のおごりなんで何も気にしないでくださいね」
気にするなと言われても。私はこんなお店で料理を食べたことがないので値段の想像がつかない。こわいこわい。前菜だけいただいてとっとと帰ってしまいたい。また頭が変になりそうだ。しかし、そんな私の気持ちを知ってか知らずか、みつおは平然とお茶を飲んでいた。
「いいと思います」
ラフをじっくりと確認したみつおはニコッと笑ってそう言った。
「ああ、よかったー。このあたりとか、ちょっとニュアンスが違うかなーとかドキドキしてたんだよね」
仕事の話が始まると、ここが料亭だなんてことは全く気にならなくなる。私は資料を指差しながら自分が思っていることを順番に伝え確認していく。
「この言い回しでちゃんと伝わるかな?」
「この写真、もうちょっと大きめの方がバランスよく感じるかな?」
「ここのフォント、これで大丈夫?」
そんな私を見ているみつおはやっぱりニコニコしている。
「ちゃんと聞いてる?」
「聞いてます。聞いてますよ。それにちゃんと確認しましたから。これでお願いします」
「じゃあこれで本当に出しちゃうからね? 後でここが! とか言っても駄目だからね?」
「わかってます。わかってますって。僕だって元同業なんですからそれくらい知ってますよ」
「じゃあこれで出すからね」
私はしつこいくらいに確認する。
「はい。お願いします。じゃあ、お料理お願いしましょうか」
そう言うとみつおは中居さんにお料理を持ってきてもらうように頼んだ。
仕事モードで気にならなかった時間がこの場所に対する緊張感を緩めたのか、頭の中も無事通常モードへと戻っていた。
そしてこの場所に初めて座った時に『何を食べているのか味なんてわからないかもしれない』と考えていたことは嬉しいことに杞憂に終わった。
「美味しい」
素材の味、お出汁の味。繊細かつ大胆なハーモニーが口の中に広がっていく。野菜も魚もこんなに様々な味わいを持っていたのか。普段そんなに考えて料理をしない私は次からはもうちょっと食材に対して真摯に向き合おうと少し反省した。
だいぶお腹がいっぱいになってきた頃、みつおがちょっと何かを考えたような顔をして口を開いた。
「都さん、聞いてもらってもいいですか?」
「なに?」
ご飯を口に運びながら私は答える。
「実家のことなんですけどね」
ゴクリとご飯を飲み込んだ私はそっとお箸を置く。
「うん」
「一昨日実家に行ってきたんです。と言ってもしょっちゅう顔は出してるんで暫くぶりって言う感じでもないんですけど。で、パン屋の話をしたくて、両親だけではなく桜堂の職人さんも数人同席してもらいました」
「……」
「結果としては、パン屋でこれから先生計を立てていくことに同意してもらえました」
「結果としては……ということは、途中何かあったんだよね。まあ、普通に考えたらすんなり『はいそうですか』とはいかないだろうとは思うけど」
「んー。言うほどの波乱は無かったんです。やっぱり、みんな僕がパン屋を既に開業していることは知っていたわけですし」
言うほどの波乱が無かったとするなら、どうしてみつおはこんなに浮かない顔をしているのだろう。そんな私の考えを読み取ったかのようにみつおは続ける。
「職人さんたちは最初は本当に怖い顔をしてましたね。『貴方、御自身の立場がおわかりですか?』なんて、今まで言われたことのないような口調で話しかけられましたし。もちろん僕は自分が桜堂の一人っきりの跡取りだということはわかっていますし、店の手伝いもせずに自分の店、しかも実家とはなんら関係の無いパンという商品を扱う店を開いているのが親不孝だという自覚もあります。だから僕は何も彼らに反論することは出来ませんし、ただ認めてくださいと頭を下げることしかできなかったんですが、両親がね」
そこまで言うとみつおはテーブルからコップを持ち上げ、水をひと口飲んだ。
「ご両親は反対してなかったんじゃなかったっけ?」
思わずそう言ってしまった私に一瞬目を向けた後みつおはコップをテーブルに置き、そこに目を留めたままこくりと頷いた。
「そうなんですよ。厳しいことをいう職人さんに対してね。うちの両親は『すまない。好きにさせてやってくれないか。本当に申し訳ない』って言いながらずっと頭を下げてるんですよ。頭を下げるのは僕の方なのに。両親が頭を下げ続けるもんだから、職人さんも最後には『わかりました』とは言ってくれました。でもね」
「でも?」
「許されてしまうと、本当にそれでよかったのかっていう気持ちが大きくなってきてしまってですね。桜堂の方も、最終的に僕が戻らなかったら職人さんの誰かに店を継いでもらうという話までつきました。実家の自分の居場所が無くなる寂しさも無いと言えばうそになるんですけど、まあ、それは自分がそうなるようにしてきた結果なんで。それに対しては何も言える立場ではないんですけど。んー。なんて言うんでしょう。この気持ちは」
私はポツリと呟く。
「……罪悪感?」
「そうですね、そんな気持ちに近いものだと思います。両親の『僕がやりたいことをするのが一番だ』という気持ちは本当だと思うんです。でも、僕がパン屋ではなく桜堂を選んでいたら両親はもっと幸せだったんじゃないかなって。職人さんだって、僕が継ぐことが両親の幸せだと考えているからこそ『立場』なんて言葉が出てくるんだと思うんで。みんな最後には僕が好きなことをすることを認めてくれました。そして僕が居なくても大丈夫だということを示すことで、僕の罪悪感も減らそうとすらしてくれました。でも、そうあればあるほど、僕がどれほど身勝手なことをしているのかということを突きつけられているような気がして。本当にこの道を選ぶことは正しかったのかどうか……」
怒鳴りつけられ否定されるのもつらいけど、それ以上に周りが理解しようとしてくれる方がキツイ事があるのは私にもよくわかる。
「でもさ、みつお」
かといってそこで自分の考えを曲げてしまうのはどうなんだろう。
「私は『継ぐ』とは縁遠い世界にいるし、子供がいるわけでもないから『親心』っていうものもどういうものなのかは想像することしかできないんだけどさ。自分の大切な人が自分の理想のために信念を曲げてくれるっていうのはその時は本当にめちゃくちゃ嬉しいと思うんだ。でもね。もしも、万が一その道で何か問題が起きた時、絶対に『好きなようにさせてあげていればよかった』って死ぬほど後悔すると思う。やりたいことがあるって言ってるのにそれをやめさせて自分の思い通りの道に進ませてしまったことが原因で、大切な人を苦しませてしまう。それまでの人生で自分が我慢してきたことが多い人ほど後悔してもしきれないくらい悔やむんじゃないかな」
他人の人生を失敗させてしまったのが自分であるという気持ちに耐えられる人間はそういないはずだ。ましてや我が子となれば良かれと思ってしたことであったとしても普通以上に耐えがたい気持ちになるような気がする。
本当に子供の為を思うなら、やりたいことを応援してあげるのが親の仕事。みつおのご両親はそう考えたんじゃないだろうか。
「それにさ、もしもみつおがご両親と職人さんの立場を考えて今から桜堂に戻ったとしてさ。ずっと心のどこかでパンへの気持ちっていうのは残ると思うんだ。桜堂で順調に進んでいるうちはいいよ? でも、もしも何か問題が起こった時。それが自分自身を壊してでも逃げたいと思うような出来事だった時に、みつおは耐えられる? 自分で選んだことなら大丈夫なことでも他人に決められたことって、結構耐えられないもんだよ。『アイツらのせいで』って敵を作ることで思考を停止させて自分を楽にしようとするのはみんな例外なくそうなるもんだし。だから、周りがどうとかじゃなく、みつおが今本当にしたいことは何かっていうのを考えたらいいんじゃない?」
私が偉そうに言える立場じゃないことはわかっているけど、どうしても口に出すのを我慢することが出来なかった。
良かったらスキ・コメント・フォロー・サポートいただけると嬉しいです。創作の励みになります。
