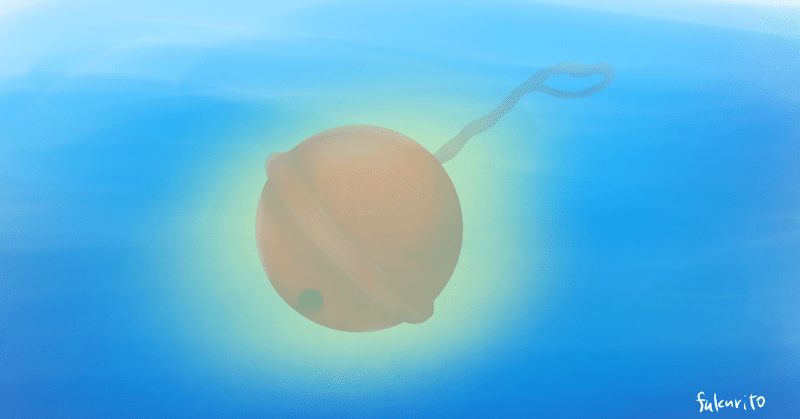
【小説】ゆづみつ⑤最終話
あれから四十年が経った。
あまりの辛さに記憶を混乱させて逃避していた時期も長いことあったけど、私は何度も夢に出てくるみつおに説得されて現実世界で生きていく覚悟を決めた。
とはいえみつおは夢の中で「ゆづ。笑って」とか「ゆづ。いつもそばにいるよ」とか「ゆづ。応援してるからね」なんてことしか言わなかったけど。
みつおの「ゆづ」と私を呼ぶ声を聞くたびに涙が止まらなくなるので、私は夢の中でいつも励まされながら泣き続けていた。
でもどんどん泣いて、泣いて泣いて頭がおかしくなりそうになるといつも決まってみつおは「都さん」と懐かしいあの呼び方で呼んでくれるのだ。ゆづと呼ばれていたよりもはるかに長い時間耳にしていた『都さん』という響き。
私はみつおに『ゆづ』と呼ばれると甘えてしまいたくなるのだけど、『都さん』と呼ばれるとなんだか昔と同じように、みつおに対して対等な立場でいなくてはいけないような気持ちにさせられた。
夢の中で前を向いて進んでみようかなとほんの少しだけ思う。しかし、でもやっぱり向き合うことが出来ないと悲しみに浸りなおす。そして私は涙で顔中どころか枕までぐしょぐしょに濡らしながら現実世界で目が覚める。
何度もそれを繰り返しているうちに、私が泣いていると夢の中のみつおが困ったような顔をし、私が少しでも元気だと夢の中のみつおは嬉しそうな顔をしていることに気がついた。
みつおは最期に『いつでも君を応援してる。それを忘れないで』と私に言った。
みつおが応援してくれいる。頑張らないといけない。
そして私は仕事に復帰した。
今日は私の最後の出社日。私も年を取り、ついに仕事を引退する時がきた。
この仕事を通じてたくさんの人と出会い、様々な職業について知ることが出来た。
みんな色々悩み、工夫し、乗り越えているのだ。そう思うことで私も励まされた。それと同じように私も誰かを励ますことが出来ていたらいいのにな。そう思いながらこの仕事と向き合った。
『応援しているよ』
その一言が何よりも背中を押してくれることを私は知っている。そしてみんなに知って欲しいと思っている。
定時のチャイムが鳴り響くと、オフィスのドアが開いて大きな花束が部屋に入ってきた。
「都さん、お疲れ様でした」
花束を渡してくれたのは後輩の女の子。この子とはいろんなところを一緒に回った。涙ぐんでいる彼女から花束を受け取ると、部屋の中の人たちが一斉に拍手をしてくれた。
「長い間、お世話になりました。これからは皆さんの出す雑誌の一読者として楽しませてもらいますね。変な記事を見つけたらすぐに電話します」
そう言うと「ええー。多めに見てくださいよ」と言った声がどこからか聞こえてきて、部屋中が笑いに包まれた。
「冗談です。それでは、本当にお世話になりました」
私は頭を一度深く下げると拍手に包まれたまま部屋を出た。
もうここに来ることもないんだな。そう思うと胸をギュッと掴まれたような痛みを感じた。
私は愛車に乗り込むと、途中桜堂のみたらし団子を買い、家へと帰る。
「ただいま」
誰もいない部屋に挨拶をして入ると電気をパチリと付けた。ソファーによっこいしょと腰掛け、ふうっとため息をひとつ。ここまでがいつものルーティンだ。
「さあ、今日は特別な日だから桜堂のみたらし団子食べましょ」
私は誰もいない空間に向かって話しかけるとお団子をひと口頬張った。美味しい。いつもと変わらない味。しかし、私は明日から仕事には行かない。いつもとは違った日常が始まるのだ。それがなんだか嬉しいような寂しいような、なんとも複雑な気持ちで頭が心に追いついてこない。
そしてみたらし団子を全て食べ終わる頃には、私の涙は止まることなく溢れ続けていた。胸が苦しい。締め付けられるように。悲しみで張り裂けそうな胸の痛み。そしてそれとは別の胸の痛みが私に襲い掛かる。胸の辺りをぎゅっと握り閉めた手に、額から伝った汗が涙と共に流れ落ちた。
ああ。私は今日仕事だけではなくこの人生にも終わりを告げるのだな。
激しい胸の痛みとは裏腹に、ぼんやりと私はそう理解した。
気がつくと、私の体は軽く、まるで重力から解放されてしまったかのようだった。さっきまでの苦しさも嘘のように消え、心の中までもが軽くなったみたい。そして私の身体はいつの間にか現れた光に向かってすうっと吸い込まれ始めた。
どれくらい運ばれてきたのだろう。まばゆいばかりの光は少しずつその勢いを弱め、徐々に視界が戻ってくる。
「か……わ……?」
目に映る世界に輪郭が戻ったとき、私の目の前にはゆったりと流れる大きな川が横たわっていた。
「へえ。これが噂に聞く『三途の川』っていうやつか。想像していたより、ずっと深いし、広いなあ」
目の前の大きな川の水は悠々とただただ流れている。サワサワという風の音を聴きながら、私はその場でゴロリと大の字に転がった。
たくさんの石が転がりボコボコしているように見えた河原は、横になってみると芝生の上に寝転がっているような気持ちのいい感触だったので私は少し驚いた。
ああ。よく生きた。
今までよく頑張ったね。
私が手足をグンと伸ばしながら自分にねぎらいの言葉をかけていたその時、胸の中にぽつんと黒い丸いものが産まれた。
点であった黒い丸は球へと成長し、そこからモヤモヤとした霧が吹き出した。そしてその霧はどんどんと密度を上げながら徐々に液体へと変化していく。サラサラとした液体はドロドロに変わり、私の中心部分から先端へと浸食をはじめた。
私が黒く染まっていくのと同時に私の目からは涙があふれ出し止まらなくなる。
今まで長い間ずっと我慢してきていたもの。
それが解放されていく。
もっと一緒にいたかった。
みつおが居なくなってしまったあの世界では我慢出来ていたものが今は我慢できない。こんな気持ちになるのはこの場所のせいなのか。それとも……
その時『チリン チリン』とどこかで聞いたことのある鈴の音が聞こえてきた。
「はい。どうぞ」
そう言ったみつおの声に顔を上げた私の目の前に、だるまの形をした鈴のお守りがゆらゆらと揺れていたあの日。
私の頭の中であの時の光景が蘇り、繰り返される。
みつおと久しぶりに再会した日、ふらりと立ち寄った法輪寺でみつおが買ってくれた達磨の形をした鈴のお守り。
この音はあの時の鈴の音。
私は体を起こすと涙をゴシゴシと袖で拭い、鈴の音が聞こえてくる場所を探し始めた。
あっけにとられるほど簡単に、その音の出所はすぐに見つかった。
それはいつの間にか現れた船着き場に停泊している小さな船から聞こえていたのだった。
『チリン チリン』
川岸に現れた立派な木製の船着き場と、そこに繋がれたオマケのおもちゃのような一艘の小船。
船が風に揺れる度に心地よい鈴の音がその後に続く。
いきなり船着き場と船が出てくるなんて普通に考えたらおかしな話だけれど、ここが三途の川だとすれば何が起こっても不思議ではないのだろう。
私は腰をあげるとその船の方へと歩き始めた。
小舟の上ではこんがりと日に焼けた青年が、三角座りを崩したような座り方でちょこんと座っている。目にかかるくらいの長さの髪をサラサラと風になびかせながら三途の川の向こう側をぼんやりと眺めている青年は、見たことが無いのに会った事があるような、そんな不思議な気持ちに私をさせた。
「あの、すみません」
青年の近くまで来た私は、恐る恐る彼に声をかける。
「はい、なんでしょう?」
くるりとこちらに振り返った青年は、見た目から想像した通りの爽やかな声でそう答えた。
「もしよかったらなんですけど、向こう岸まで乗せて行ってもらうことはできますでしょうか?」
「ええ、もちろんです。喜んで」
立ち上がった彼は口元に白い歯をチラリと覗かせると、私に向かって手を差し伸べた。
「ありがとうございます」
私は彼の手をそっと取ると、ゆっくりと彼の船へと乗り込む。
この船に乗せてもらい向こう岸に渡って私は一体何をしたいというのだろう。そんなこともわからないまま、私はこの川を渡ろうとしている。
「それじゃ、出発しますね~」
ぎっこぎっこという音をたてながら彼が櫂を漕ぐ。そのリズムに合わせて、鈴の音が鳴る。
『チリン チリン』
「この鈴の音……」
私は何度も何度もこの鈴の音を聴いたことがある気がする。
「いい音でしょ、これ」
そう言いながら、彼は船の縁に立っている一本の棒に括り付けられた、達磨の形をした鈴に目をやった。
「だるま寺? のお守りよね。これ」
「おねーさん、よくご存じなんですね」
ぎっこぎっこと船を漕ぎながら、彼が少しだけ嬉しそうな顔でそう言った。
うつうつと気持ちが晴れないままぼんやりと川面を眺めていると、また寂しい気持ちが襲い掛かってきた。初対面の人の前で泣くなんてことはしたくないので、私は少し顔を上げて空を見上げる。
そんな私の様子に気がついたのか、お兄さんは船を漕ぐスピードを落としながら「少し、お話してもいいですか?」と、遠慮がちに笑いながら私に話しかけた。
「ええ。もちろん」
私には急いで川を渡らなくてはならない理由なんて全く無い。それに彼と話をすれば少しはこの気持ちが軽くなるかもしれない。なんてことをちょっと期待しながら快く応じた。
彼は櫂を流されないように船の上にあげると、私の前によいしょと座る。川面に反射した光を受けてサラサラと揺れる彼の髪はキラキラと輝いている。綺麗だな。と素直にそう思った。
「おねーさんは、幸せでしたか?」
「え?」
思わず私は彼の顔を見つめた。
私が幸せだったか? なんでそんなことを聞くのだろう。そんなに私はつらそうな顔をしていたのだろうか。それとも彼はこの川を渡す人全員にそんなことを聞いているのだろうか?
「幸せ……?」
仕事は本当に楽しかった。
友人にも恵まれた。
私は幸せな人生を送ったといえるだろう。
しかし
みつおの居ない世界。
みつおの消えた世界。
取り残されてしまったあの世界は私にとって幸せな世界では無かったとも言える。
やっぱりこの場所は何かがおかしい。私は笑って楽しく暮らしていたはずなのに。それなのにどうしてこんな寂しい悲しい気持ちに今更なってしまうのだろう。
ますますやり場のないモヤモヤを抱えた私は彼から顔が見えないようにそむけ、川面へと視線を下ろした。
「おねーさん?」
少しして聞こえてきたお兄さんの心配そうな声が、私を私に引き戻した。
「あ、ごめんなさい」
「謝らなくても大丈夫ですよ。少し、ゆっくりしませんか?」
「ありがとう……」
私がそう言ったあと、お兄さんは「気にしないで」と言って私に微笑んだ。
どれくらいそうしていただろう。
川の流れがあるはずなのに、船はどこにも流れていかないで同じ場所でプカプカと浮かんでいる。定期的に訪れる波で、船に付いた鈴が『チリン チリン』と音を立てる。
その音を何回も何回も聞いているうちに、不思議と私の悲しい気持ちが段々と落ち着いてきた。ドロドロしていたものも薄くなり、モヤモヤが少しずつ晴れていく。
この鈴の音には溜まっていた何かを浄化する効果でもあるのだろうか。
「おにーさん?」
なんとなく話をしたくなった私は川面を見たまま、あぐらをかいて座っているお兄さんに話しかけた。
「はい、なんでしょう?」
「お兄さんは幸せでしたか?」
お兄さんはほんの少し考えた後こう言った。
「やり残したことや、思い残したことはたくさんあります。それはもう、本当に数えきれないくらいに。でもね、僕はいつも幸せでした」
心なしか、最後の『幸せでした』の部分が強調されていたような気がしなくもない。
「お兄さんも、そうなんだね」
私は口の中でかみしめるようにそう答える。
そうだよね。
多分、みんなそうなんだよね。
完璧に思い描いたような人生を走り抜けるなんてことは、実際には不可能なのは頭ではわかっていた。でもそれが今、やっと心に近付いたような気がする。
ほんの少し気持ちが軽くなった私は、なんとなく顔を上げてお兄さんの顔を見つめた。
今まで気がつかなかったけど、その顔はどことなくみつおに似ていた。よく見れば他人の空似程度かもしれないけど、私にはみつおの面影が感じられる。そう気がついてしまったが最後、私はお兄さんの顔から目が離せなくなってしまった。
吸いつけられるようにお兄さんの顔をじっと見つめていると、こっちを見たお兄さんとバッチリと目が合った。
「ごめんね。こんなにじっくり見られたら、お兄さんも落ち着かないよね」
そう言いながら私は視線をお兄さんの胸元に下ろす。
「別にじっくり見てもらっても構わないですよ。減るようなもんでも無いですし」
「うん。ありがとう」
そう言うと私はまたお兄さんの顔をもう一度そっと見つめた。
ちゃぷちゃぷという波の音と、『チリン チリン』という鈴の音。
それ以外の音は聞こえない船の上で、私はお兄さんの顔を見ながらやっぱりそうじゃないかと思いはじめていた。
ここは三途の川。何が起こってもおかしくない場所。
ということはこのお兄さんがみつおだということもあり得ない話とも言えないはずだ。
「お兄さん。変な事聞いていい?」
私は何気ない風を装ってお兄さんに聞いてみる。
「なんでしょう?」
「お兄さんは『新堂みつる』っていう人に心当たりない?」
「おねーさんの大切な人ですか?」
「うん。『だった』って言うのが正しいかもしれないけど」
「知っているといえば知っています」
なんとなくふんわりとした答えだ。ふんわりとした質問をしている限り、お兄さんはふんわりとした答えしか返してくれないのかもしれない。そう思った私は、直球で質問をぶつけてみることにした。
「もしかしてお兄さんがみつおだってことは無い?」
ゆらゆらと揺れる船の上で私とお兄さんはまっすぐに見つめ合う。
しばらくして、お兄さんは
「半分正解。僕は確かに新堂みつるでもあったけど、それ以外の名前の人生も歩んできているから、全てが新堂みつるでは無い感じと言えばわかってもらえますか」
「ああ、やっぱり」
私は目からあふれ出す涙を止めることが出来ないままお兄さんの顔を見つめ続けた。
「私はね。あの時どうしてみつおでは無く私が事故にあわなかったのか。どうして車の存在に気がつかなかったのか。それに、私がもっとしっかりしていれば、みつおは死んでしまわなかったんじゃないかってずっと考えていたの。あの一瞬ですべてが消えてなくなってしまった。私とみつおの幸せな時間。それまでの思い出も、それから先にあった未来も全部。他にもどうして一緒にあの人生を終われなかったのかずっと考えてた。みつおと一緒なら幸せだったのに」
あの分岐点で正解を選び取ることが出来ていたら手にしていた未来。私が願ってやまなかった世界。
「でもね、おねーさん。僕はおねーさんがあの時助かったことがとても嬉しいんです。僕はおねーさんが生きていてくれる。楽しいことをしている。それを見ていられるだけでとても幸せなんです」
「なんでそんなこと言うの? 私は全くそんなことは思わない。私はずっとずっと一緒にいたかった。たとえ一緒に死んでしまったとしても、そっちの方が私にとってはずっと幸せだったんだよ」
私は一気に吐き出すとお兄さんの手を握る。
「ユキちゃん」
お兄さんがそうつぶやいたような気がしたけど『チリン チリン』という鈴の音と重なって私の耳にははっきりとは届かなかった。
握った彼の手はとても温かかった。でもその温もりはみつおのものとは少し違う。彼が『すべてがみつおではない』と言ったのはこういう事なのだろうか。
そして彼がみつおでありみつおでないということは、私がゆづきでありゆづきではないということでもある。
私がこの川を彼の船に乗せてもらって渡るのは何度目なのだろう。はっきりとは覚えていないけど、なんとなく何回かこの船に乗って向こう岸まで運んでもらったような気がする。
「ねえ、お兄さん」
「なんですか?」
「私、お兄さんに船に乗せてもらって、この川を渡るの、初めてじゃないよね? 二回目ってわけでもないよね? よく覚えてないんだけど。なんか、そんな気がする」
「そうですね。僕は何回もおねーさんを確実に向こう岸に送り届けるために船を漕ぎましたね」
お兄さんは何かを思い出したように笑いながらそう言った。私は楽しくこの川を渡って行ったこともあったのだろうか。そして私は彼の言った『何回も送り届けた』という言葉に少しひかっかりを覚えた。
どうして気になったのかをよく考えてみると、私はこの場所に来てから彼としか出会っていないことを思い出したからだ。他の人は姿どころか存在感ですら確認した覚えがない。
ではどうして彼は私とこの場所で何回も出会い、そして船に乗せてくれることが出来たのだろう。
私は彼の手をそっと離し聞いてみる。
「どうしてお兄さんは毎回私がここに来るタイミングがわかるの? 私はこの場所に来てから、お兄さん以外の人の姿を見ていないんだけど」
「それは、僕がおねーさんを待っているから。いつも探しているから。その想いがとても強いからなんだと思います」
そう言うと、お兄さんは少し遠い目をした。
ちゃぷちゃぷという波の音の間にはさまる『ちりん ちりん』という鈴の音を聞きながら私は考えた。お兄さんはいつも探していると言った。そして待っているからだとも。
「ねえ、お兄さん」
呼びかけると彼は私の方へと視線をむけた。
「なんですか?」
「お兄さんは私を待っているって言ったよね?」
「ええ。そうですね」
「じゃあ、私もお兄さんのことをここで待ってたり、探してたりしたこともあったのかな?」
何度もこの場所で会っているのなら、彼が待っている時ばかりではなかったのかもしれない。でも私にはそんな記憶も、ましてやそんな感覚もこれっぽっちだってもってはいない。
それに彼は私にすぐに気がついた。でも私は彼になかなか気がつかなかった。これは私が彼を待つ番ではなかったからなのだろうか。そんな疑問を彼にぶつけてみる。
すると彼は少し困ったような笑みを浮かべながらほんの少し肩をすくめてこう言った。
「いえ。いつもおねーさんより僕のほうが先にここに来ますから、おねーさんが僕を待っていたことはありませんよ」
「え? そうなの?」
「ええ」
「なんで?」
まっすぐに彼の目を見つめてそう聞きながら、私はなぜだか少し怒りに似た感情が湧き上がってきていることに気がついた。でもその感情が急にどこから湧き上がってきたのかよくわからない。急に湧き上がってきたということは、ついさっきの彼の態度、もしくは彼の言葉に反応したのだろうか。彼がさっき何を言ったのか思い返そうとしてみる。しかしその時、彼が「あっ」という言葉を口にした。
「え? なになに?」
思わずその言葉に反応してしまう。思い返そうとした言葉も、湧き上がってきた感情も、全てが川の流れのようにさらさらと流れて私の元から去って行ってしまった。
「魚がね。いたんです。この川で魚なんて見るの、どれくらいぶりだろう」
一生懸命川を覗き込む彼の横顔を見ていると、ふいにどこからかパンの香りが私の鼻をくすぐった。
「パン……」
パンが焼きあがるときのあのたまらないにおい。ふんわりと、でもしっかりとしたあの香り。私は目を閉じて大きく息を吸い込んだ。
パン……
そうだ。パン。パンなのだ。
「お兄さん! パン! パンなの!」
私は勢いよく目を開けると、お兄さんに掴みかからんばかりの勢いでそう叫ぶ。
「え?」
川面から目をあげた彼はびっくりしたような、驚いたような、それでもなんだか嬉しそうな顔をした。
「だから、パン! パンなの! 早くいかなくっちゃ」
対岸を指さす私を見ながら、彼は櫂を手にとった。そしてゆっくりと対岸に向かって船を漕ぎ始めた。
「わかりました。では行きましょうか」
進み始めた船の上で、私はパンに想いを馳せる。もちろん船を漕ぐお兄さんのことが全く気にならないわけではない。でも彼よりもパン。パンなのだ。パンを手にするため、私は一刻も早く生まれ変わらなくてはいけないのだ。パン。パン。パン。もうパンのことしか考えられない。
対岸到着するやいなや私は勢いよく船を降りた。そして勢いよくお兄さんの方を振り向くと
「私はもう行かなくちゃ。ありがとう。お兄さん。また会えるよね?」
と早口でまくし立てた。そんな私にお兄さんはゆっくりと
「ええ。また。すぐに」
となんだか意味深に答える。
「じゃあ」
「ええ」
そんな言葉を交わした後、私はくるりと向きを変えるとある一点を目指して走り始める。どうしてその場所を知っているのかは知らないけれど、あの場所へ。あそこへ行けば私は新しい生を歩み始めることができる。早く。急げ! だってパンが待っているのだから!
……
「行っちゃいましたね」
生まれ変わって行ってしまう彼女を見送るのは何度目だろう。
満足しきった顔でここまで来るのに、いつも彼女はゆっくりと休むことな
くあっちの世界へと帰って行ってしまう。毎回懲りることなく、人生の幕引きの瞬間に抑えることの出来ないほどの未練を持ってしまう彼女。
彼女らしいといえば彼女らしい。
前回はみたらし団子。
その前はアユの塩焼き。
そのまた前は何だったかな?
いつか彼女がここでゆっくりとしていく日が来ることを僕は待ちわびてもいるけれど、心の奥底ではまた何かを思い出してバタバタと大慌てで帰っていく彼女を見送りたいと思っていたりもする。
生まれ変わって行く彼女の背中を幸せな気持ちで見送る。
もちろん悲しい、寂しい気持ちが無いわけじゃない。
今回はちょっと元気が無かったけど、彼女が元気を取り戻してくれたから安心した。
生まれ変わって行くためにはエネルギーが必要で。さっきみたいに彼女のエネルギーが少ないと川を渡り終わるまでどれくらいの時間がかかるか想像が出来ない。
僕は彼女を見失いたくないからこの場所で彼女を待ち、彼女が無事に川を渡っていく姿を最後まで見届けることにしたんだ。
僕は本当のことを言うと彼女とずっと一緒にこの場所にいたい。
悲しみも苦しみも何もない、永遠に続くこの平和な世界で。
でも彼女はいつも最後には躊躇することなく次の生を求めて行ってしまう。
ユキちゃん、キミは本当に強い。
それに比べて、本当に僕は弱い。
いつも僕が彼女の行ってしまった後を追うのは
彼女に確実に出会いたいから。
そして僕が彼女よりも確実に短い生を選ぶのは
彼女を失う痛みに僕は耐えられないから。
彼女はそんな僕の本当の気持ちに気がついてしまったら僕のことを恨むだろうか。
自分にばかり悲しい寂しい思いをさせてアナタは酷いと怒るだろうか。
恨まれても怒られても卑怯者だと言われても、それでも僕はただただ彼女の笑っている顔を見られたらそれでいい。
だから僕は彼女の後を追い、彼女より先にこの場所で待っている。
これから先もずっと。
「一休みしたら彼女を追いかけよう」
川に浮かべた船にゴロリと転がって、僕は雲ひとない空を見つめながら、ふふふっと笑った。
<終>
良かったらスキ・コメント・フォロー・サポートいただけると嬉しいです。創作の励みになります。
