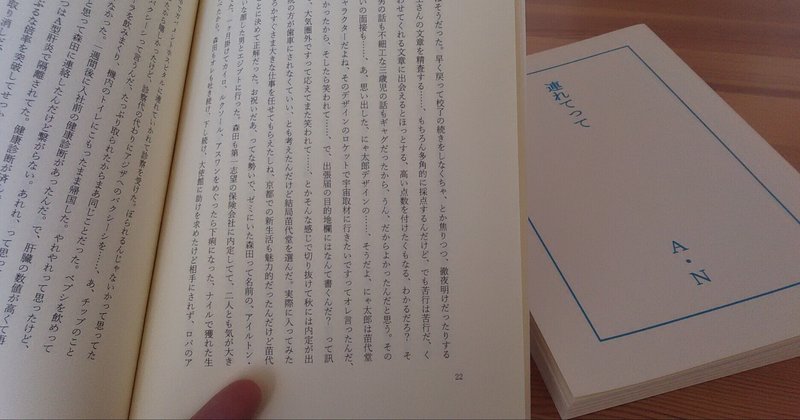
あの頃を忘れない
自作の小説について。
淡い話です。
苦悩や葛藤と真摯に向き合った小説こそが文学作品である、というような考え方に照らすと拙作は文学ではなく単なる、なんだろ、響き、に過ぎないように思われます。
とりわけ余韻であろうかと。
↓『連れてって』p2~p8
一方の文学研究会は硬派でも軟派でもなく、半端な感じだった。薄汚れた学生棟の中にある小さな部室、通称ボックスってとこでじめじめ活動してた。行くと床に一升瓶が転がってて隣に知念先輩が転がってた。知念先輩っていうのは日本文学部、通称日文の二年生で、つり目で天パでひげもじゃで、小さい頃から何かの障碍を抱えてて、だからニンジンみたいな手をして、くねくね歩いて、ろれつの回らないしゃべり方をしてたんだけど、そんな個性も目立たなくなってしまうほどに目立った大酒飲みだった。そして詩人だった。自分は何だ、バケモノかっ! みたいな叫びを書いてた。だけど日頃はすこぶる陽気で、かつひどく誠実だった。オレこの先輩が大好きだった。尊敬もしてた。
他に寛大前の……、あ、寛明大学は教養課程で寛大前に通うんだ、で、そこにいた部員は数人。笹木って名前の気障な二年生、こいつは初対面でオレの腕時計をチェックした。なるほどアルバか、とか言って手帳に書かれたオレの名前の隣にアルバって書き込んだ。僕はね、ひとを腕時計で判断することにしてるんだ、と笹木は言った。面白いなって思ったけど同時に嫌な野郎だって思った。
その笹木と同じ高校だったっていう唐木田、こいつは一年生だった。毎日寝る前にニベアをつけてそう、って思うしかないつるつるの肌をしてた。目が猫みたいで鼻が高くておちょぼ口。ま、不細工じゃなかったってこと。大江健三郎とドストエフスキーの信者だった。
あと三上。現代詩手帖に作品が載ったことがあるのが自慢だった。おかっぱの下の目がトカゲみたいだった。そんな目でひとをちらちら見るんでむかついて、だからときどき殴ってやった、ばきっ、じゃなくて、ぽかすか、くらいの強さでだけど。コカ・コーラって書いてある赤いベンチが部室にあって、オレが追い掛けると三上はその下に逃げ込んだ。ベンチの上に立って座面をがんがん蹴ったら板が割れた。それでも三上は這い出てこなかった。ベンチから飛び降りて下を覗いたら、やつはこっちを見て、うげげ、って言って笑った、喜んでた。一度実家に泊めてやったことがあるんだけど、夜中に目覚めたら至近距離からオレの顔見てて怖かった。
それと木下。チビ眼鏡。さらさらの髪してて肌が奇妙に生っちろかった。死ぬ気もないのに死んじゃうごっこを演じてご満悦だった。こいつの下宿近くの公園で、夜中に二人でブランコ漕いでた記憶がある。なんでだったかは忘れた。それから、そうだ、お姉ちゃんのいる飲み屋に初めて連れていってくれたのも確かこいつだった。
一、二年生が通う寛大前のボックスに常駐してたのはそのくらい。ずいぶん少ない。でもそれを補うように千代田の……、って専門課程の校舎があるとこだよ、そこのボックスから三年生や四年生が遊びに来てた。
藤川さんって三年生はセクシーな女性だった。いくらか目がぎらぎらし過ぎてたけど、まあ美人だったし、餅みたいに白い肌でおっぱいも尖ってた。四年生の桜井さんと付き合ってたんだけど、桜井さんが卒業後山にこもって陶芸をやるだとか言って、そんで喧嘩になってふられてた。学祭の夜も寛大前に来てて、すっごく荒れてた。オレ言われて酒屋にくっついてって、一升瓶買って、そんで体育会の本体が見張ってる正門はパスして裏の金網のとこから校内に潜り込もうとして……、そうなんだよ、学祭のときにはアルコールチェックってのがあったんだ、で、先に金網を越えた藤川さんに、外から瓶をラグビーボールみたいにパスしてね、そしたら彼女ちゃんとキャッチした、落として割ったりしなかった、しっかり抱きとめた。それで大事そうにしてた、夜目にはまるで赤ちゃんを抱いてるように見えた。それからオレも金網のぼって、……てっぺんから夜空を仰いだら真ん丸の月があって、満ちてるなあってしみじみしたりして、で、飛び降りたら藤川さんが体育会のやつらに捕まってた。悔しそうに顔を歪めて、と思ったらぎゃあって泣き出した。揃いの黒Tなんて着た二人が、我々も手荒なことはしたくないんですが……、とか言いながら指をぼきぼき鳴らした。ボクシング部と柔道部だって名乗られて、ちょっと勝てないなって思ったから大人しく一升瓶を差し出した。黒Tに向かって、学校側の犬っ、とか叫ぶ藤川さんをなんとかなだめてボックスに戻った。そしたら藤川さんにひっぱたかれた。このやろって思って、桜井さんにふられたくせにって言ってやった。すると彼女め、またひゃんひゃん泣きながら反対の手でオレの反対のほっぺたをひっぱたいた。
それでそのあと三年生の田崎さんっていうスフィンクスみたいな顔した巨漢がやって来て、体育会のゴキブリどもがっ、とか吼えてオレを誘った。何しでかしたかっていうと学生棟の廊下で焚き火をした。黒Tがありんこみたいに集まってきて、スフィンクスとオレは執行室に連行された。始末書書けって言うからふざけて珍妙なポエムを書いてやったら黒Tたち真っ赤になって怒ってた。漫画みたいなやつらだ、って言われた。なんか悪い気しなかった。
それと部長の氷川さん、この人は赤城山合宿のとき夜這いごっこをしたオレを助けてくれた。美濃部さんっていう真面目な女性が、叱ってやってください、って氷川さんに言って、で、オレ氷川さんに言われた。おまえなあ、世の中にはやっていいことと……、やって楽しいことがあるんだぞ。いい先輩だったな。
それから性格のよさそうな室町さんって女性。酒豪の知念さんが惚れてたんだよ、室町さんに。のちにオレ知念さんを応援して告白させようとしたんだけどうまくいかなかった。
瀬田さんって聖書マニアもいたし、村野さんっていう何考えてるのかわからない人もいた。今思っても三、四年生は層が厚かったな。面白い人がたくさんいた。
それに比べて寛大前チームのしょぼさったらなかった。だから新入部員が欲しくて。とか思ってたら飛んで火に入る夏の虫って感じで郁美ちゃんが現れた。見学に来たんだ、一人でふらっと。日文の一年生、小柄な女子だった。もぐらの目を大きくしたみたいな顔してた。貶してないよ、オレもぐらが好きなんだ。児童文学研究会にも所属してるとか言ってた。童話や絵本が好きだったのかな。詩を書くって聞いて絶対逃がしちゃいけないって思った。プレイボーイになったつもりで口説きまくった。そしたらどうなったと思う? なんと入部してくれたんだよ。でかした、って先輩たちから褒められた。
月曜日はシャイニーレモン、火曜日と木曜日だったかは情報誌の編集部でバイト、それ以外の夕方は土日も含めてたいていボックスに詰めてた。それで酒を飲むか花札をやるか卓球をやるかしてた。文学の研究はしてなかった。オレ以外の人はもしかしたらこっそりやってたのかもしれない。
線路に立って走ってくる電車に向かって小便をする、って肝試しもやった。そうだよ、小学生じみたことしてたんだ。電車がまだ豆粒なのにチビ眼鏡の木下はさっさと逃げちゃって、オレと三上の一騎討ちになった。うげげの三上め、なかなか逃げない。見るとまだ小便終わってないし。こりゃやばいなって思って腕掴んで線路脇に引っ張り出した。三上のズボンを小便まみれにしちゃったんだけど死なれるよりましだろ。この事件はのちのちまでスタント・バイ・ミー事件って名前で語り継がれた。
そんなわけのわからないサークルに入れられたのに郁美ちゃん、文研寛大前支部の一人娘としてわりとのびのびやってた。学食で三上と仲良く飯食ってたりもした。うげげな河童野郎と一緒にだよ、びっくりしたなあ。そのあとぬかりなく三上をぼこぼこに殴っといた。
郁美ちゃんに誘われたのは、夏がまだ少しだけ残ってるくらいの秋だった。バイトのお金が入ったからおごってあげる、って言われて。で、天長町のジャズ喫茶に連れていかれた。
あの頃を忘れない。
文庫本を買わせていただきます😀!
