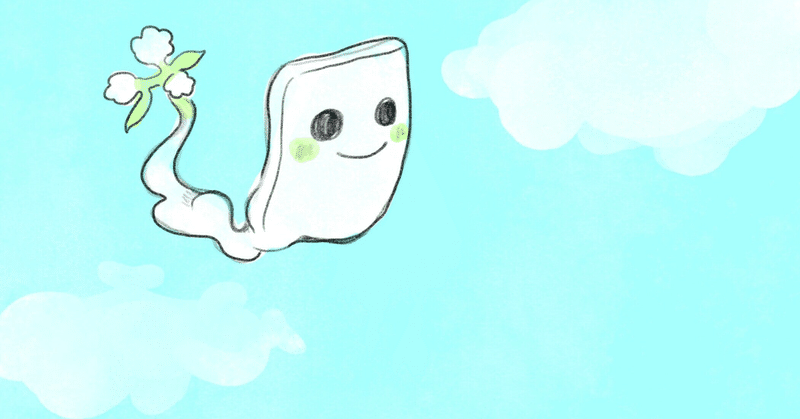
【小説】はうつー成仏
白いものがふわりと青空に舞い上がった。風が吹いていてそれは思ったより高く波打ちながら空中を昇ってゆく。よくみると白くて細長い布キレだった。そういえば、死んだ後の魂というものはああいう妖怪・一反木綿のような形状をしていると思っていた。
「実際は違ったなあ」
ふと声に出た。それでも私の声は誰にも届かない。聞こえる人がいるとすればそれはもう死んだ人ということになる。たまに勘の良い人には聞こえるのかぴくりと立ち止まって振り返ったりすることもある。私はいつものように繁華街のアーケードの入り口にある看板アーチの天辺に座り、絶えず行き来を続ける人通りを見下ろしていた。
「サチ子さん、また靴を落としたりしてはいけませんよ」
後ろから声がして振り返るとユク夫さんがふわふわと浮かんでいた。今日もきちんとネクタイを締めてスーツのジャケットとスラックスを身に着けている。どこかでアイロンをかけてきたのだろう、スラックスの折り目が尖ったようにユク夫さんの足元に至るまではっきりとした直線を引いていた。
「ユク夫さんだって鞄落としたことあるくせに」
「そんなこともありましたね。でも意図的ではないです」
「私だって意図的じゃなかったですよ」
淡々と語るユク夫さんをちらりと睨む。
風がぴゅうと私たちの間を吹き抜けて私のロングスカートを翻し、ユク夫さんの前髪を揺らした。ユク夫さんがそっと自分のおでこに手をやる。今日は風が強い。青い空にワタアメの塊から引き抜いたような細切れの雲がおんなじ方向を目指していくつも流れていく。
私たちは自分の所有物だった物なら触ったり身に着けたりすることができる。私たちが触れている物は生きている人には見えないけれど、離れると途端に現世に戻る。二カ月ほど前、今と同じようにアーケードのアーチの天辺に座っていた私の足から靴が脱げてうっかり落としてしまった。下を歩いていた禿げ頭のおじさんに靴が一瞬乗ったので大笑いしているのをユク夫さんに見られてしまったのだ。それがユク夫さんとの出会いだった。ユク夫さんはその時死んだばかりでどこかで泣き腫らしたのか目を真っ赤にして彷徨っていたところ、大笑いする私の声が遠くから聞こえてきたのだそうだ。とても怖そうな女がいると思ってしばらく遠目から私を眺め、安全を確かめてから意を決して話し掛けたらしい。ユク夫さんは享年四十四歳のサラリーマンで三十六歳の奥さんと四つになる一人息子がいた。ユク夫さんは髪が薄くなりつつあるようで、気になるのか風が強く吹くときはそっと前髪のところに手を添えるのが癖なのだった。私が大笑いしていた理由を後日聞いたユク夫さんは大真面目な顔をして、
「だめですよ。空から靴が降ってきたら驚かれるでしょう」
と私を叱った。私は享年三十五歳なのでユク夫さんよりは年下になる。叱られて素直にすみませんでしたと謝ったものだ。
「今日は何かありましたか?」
ユク夫さんが尋ねる。見るとユク夫さんはアーケードのそばにある大きなケヤキの木の天辺でこちらを向いて正座している。ユク夫さんの声は細くて高くて小さい。生きている時ならこんな距離では人の声なんて大声を張り上げてもとても聞こえない。声も意識なのだ。ユク夫さんが自分の声と認識している意識を私に飛ばしてきて、私は耳か頭かわからないけれどそれをユク夫さんの声としてキャッチする。
日曜日の昼下がりだった。週末、賑わう繁華街。ひっきりなしに行き交う人々を私は眺めて過ごすことが多かった。ユク夫さんは死んでからも自分の家に滞在しているようだった。結婚して六年目だった奥さんの育美さんと息子のたけしくんをずっと見守っている。気丈に明るく振る舞う育美さんが、たけしくんを寝かせた後、ユク夫さんの位牌の前で声も無く涙を流す夜。そんな日の翌日のユク夫さんは盛大に目を腫らせてやってくるのだ。
(つづく)
自費出版「ゆうちゃん」収録作品
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
