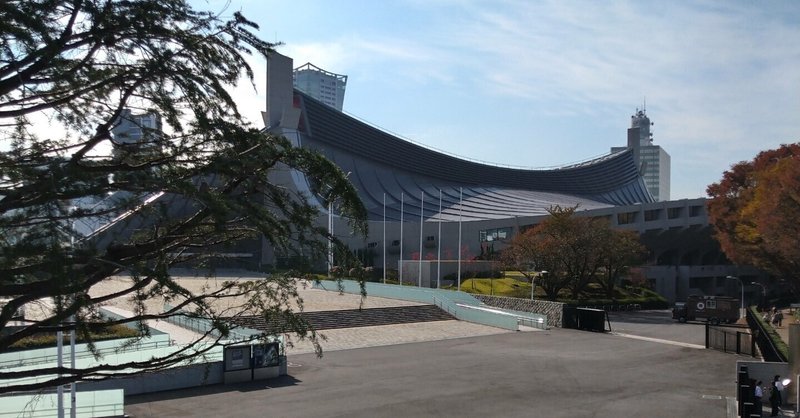
【小説】推しグル解散するってよ③
泣きに泣いて真っ赤になった目元をハンカチで抑えて、千晶はそっと正座した。お客さん……? と真紀に目線を向けると、真紀はううん、と先ほどの変わらずバスタオルを目に当てたまま首を横に振った。物音に気にしている様子も無い。
「修だよ。」
真紀が一人の男の名前を口にした。
「修、くん?」
聞き覚えのあるその名前を千晶は意図せず復唱した。
「修さ、今日、私が使いもんにならないと思ってさ、来てくれるってさっきメールがあった。」
真紀が言った。
5秒前まで泣きじゃくっていた千晶の背筋がピンと伸びた。
「修くんが今からここに来るの?」
「そう。」
千晶が聞くと、真紀は画面に目線を合わせ泣きじゃくったまま頷いた。
玄関先のゴソゴソ音は、鍵を開けるガチャガチャ音に変わった。ガチャ、っと音を立ててドアが開く音がする。それからドサッと、何かを床に置く音、割と聞きなれた、そうだ、スーパーの袋(しかもぎっしりと物が入ったもの)が床に置かれる音がして、靴を脱ぐ音。
「姉ちゃん来たよー。」
真っ赤な上に腫れた目を無理くりに開いて、声の主の方へ目をやった。
「マジの修くんじゃん。」
「・・・・・・マジの修くんです。」
声の主を、割と失礼な第一声で迎え入れた。
マジの修くん、名前は森永修。真紀の弟。それから、千晶の同級生。
「姉ちゃん大丈夫?」
「修・・・姉ちゃん全然大丈夫じゃない、大丈夫じゃなああああああ、うわあああああああん。」
修が姉である真紀に声をかけると、身内を見た安心感なのかなんなのか、今日イチの大声で泣いた。修はそれを笑うことなく、穏やかな目でそっかそっか、と手に持っていたスーパーの袋をキッチンの流し台に置いた。
千晶の姉はオタクとはかけ離れた人間で、青春期にはすぐに彼氏を作り、20代前半には現在の夫と付き合い始め、20代後半にはその人と結婚した。1男1女の母親。“いつまでも”オタクである妹のことを理解することはなかった。だから千晶は、泣きじゃくるアラフォーの姉をバカにすることなく、穏やかに対応する弟の修に目を丸くした。
「ちいちゃ……あ、米村さん来てたんだね。久しぶり。」
「ひ、久しぶり。」
一瞬だけ、幼い頃の呼び名で呼ばれかけて、それから修正された。千晶は少し上ずった声で返した。
修はスーパーの袋から6缶セットのビールを2セット出した。12缶あれば足りるでしょ?と二人に聞いて、泣きじゃくる真紀が返事ができないので千晶が、足りると思うと答えた。二人が座るリビングに腰を下ろすことなく修は袋から冷凍の餃子とチャーハンを出した。
「俺、料理とかできないからこんなんしか無いけど。良かったら米村さんも食べてって。」
修がCMさながらにその冷凍食品を顔の横に出して、千晶に言った。お、オッケーと上ずり声のまま答えた。
修は冷凍餃子のパッケージを見ながら餃子をフライパンに並べている。水も油もいらないってどういうこと?と独り言を言いながら。
隣にいる真紀は先ほどよりも激しく泣いて、ライブビデオを見ていた。それに対して何の反応もしない修、そんな光景を少しうらやましく感じる千晶だった。
修が部屋に入ってきて、千晶は少しだけ緊張した。人見知りだとかそういうことではない。
千晶は少しだけ苦手なのだ、修のことが。
真紀のことは大好きで、もはやバディ化しているが修には緊張する。
綺麗に通った鼻筋、少し薄い上唇に上がり気味の口角、柔らかく微笑む二重の瞳。
修は美しい顔をしていた。
この姉弟とは幼馴染で付き合いも長いが、成長過程においてどんどん美しくなっていく修と、千晶はあるあたりから上手くコミュニケーションをとれなくなってしまった。
アイドルに命を懸けているような、自分のようなオタクが、修と仲良くしているのはおかしいんじゃないかと心の距離を置くようになってしまった。
「ちぃ、見て、ここの大二郎、初めての武道館で泣いてんの!もうこの時、うちらもやばかったよね!」
千晶が少し物思いに耽っていると、真紀がテーブルをバンバンと叩きながら言った。結成5年目、初めてのGAPの武道館ライブでリーダーの大二郎が泣いてしまったシーンがテレビ画面で流れる。このライブにも千晶と真紀は二人で行った。普段リーダーらしくしっかり者として振舞っている大二郎が初めて泣いた時だった。修に一瞬気をとられていたが、千晶はパブロフの犬かの如く、画面を見た瞬間またボロボロと涙を流した。
「うう・・・思い出が多すぎる・・・・。」
真紀がもはや声にもなっていない声でつぶやく。修はいつの間にか餃子と炒飯を完成させていて、二人に声をかけないようにそっと料理を盛った皿を運んだ。
食べ散らかした生ハムとチーズの残骸の横にそっと置く。香ばしい匂いがした。
「修くんありがと。」
千晶は泣き過ぎて、さっきとは違う種類の上ずった声で言う。
「こんなものしか作れなくてごめんね。」
修は柔らかく笑った。
千晶は飲みかけのビールを口元に持っていきながら、その笑顔を思わずじっと見た。
「何?」
修に聞かれると
「な、何でもないないないとうたかし。」
と、謎のダジャレを言った。
「何それ。」
修に冷静に返されて、何でもないです、と自分も真顔に戻った。
それから、
「修くんも飲んだら?」
と、缶ビールを彼に向けた。じゃあもらおうかな、と修はプルトップを開けた。
プシュと音を立てたビール。なんだかよくわからないけれど、その音すら修から放たれると爽やかに聞こえた。
修がお疲れ、とビールの缶を傾けて二人に向けたが真紀は画面の大二郎に夢中だったので、千晶と二人で缶をぶつけた。
気が付けば時計は23時を回っていた。
「姉ちゃん、米村さんの終電あるから今日はお開きにしよ?」
修が時計を見て、真紀に言った。
用意したビールの缶はすべて空になっていた。主に真紀と千晶が飲んだのだろう。
二人とも酔いと悲しみでグチャグチャになっていた。
「わかった……ちぃ来てくれてありがと。修もありがとおお、お、おおおおおお、二人ともありがとおおおおおおお。」
真紀は完全に潰れている様子で寝転がりながら泣いた。通常ならば滑稽に見えるその様子も千晶にはまた涙を誘うものだった。
「真希ちゃん、私も一人で過ごすなんて無理だったからさ……んぐっ……誘ってくれてありがとおおおおおおお……。」
最終的に何を言っているかわからないほどの震える声で千晶は言った。
真紀は起き上がれないくらいに泣いていて、バスタオルを顔面に押し付けていた。
「姉ちゃん、米村さん駅まで送るからそのままで居ていいよ。」
修はチラリと千晶を見て、言った。
「修うううううありがとおおおおおお、大二郎おおおおおおおおおおおおおおおおおおお愛してるよおおおおおお。」
「真紀ちゃん、じゃあ私帰るけどまたすぐ来るよ!絶対また耐えられっなくっなるっかっらっ・・・・・・・。」
修は二人の言葉を遮ることなく、見守ってから、じゃあ行こうか、と千晶に言った。
真紀の家から最寄り駅までは徒歩15分ほどある。修も酒を飲んだので二人でゆっくりと歩いた。
本来終電は1時間も後だったが、ベロベロに酔っぱらって目を腫らした千晶を落ち着かせるために修は少し早く家を出た。
二人で初夏の夜を歩いた。
「修くん、色々気ぃ遣ってもらっちゃって・・・・なんかごめんよ。」
千晶が少し呂律を混乱させながら言うと、修は、ああいうのは慣れてるから大丈夫、と笑った。
真紀とはこの20年しょっちゅう会っていたが、修と会うのは久しぶりだった。20代前半の頃の同窓会以来、もう10年近く会っていなかった。
「修くん、イケメンだった記憶あるけど・・・今でもかっこいいんだね。」
千晶が下を向きながら修の目を見ずに言った。
「そう?自分じゃよくわかんない。」
修は照れてる様子でもなく、かといって言われ慣れていない雰囲気でもない、ただシンプルな自分の感想のように返した。モテそうだね、と千晶が言うと、そうでもないよ、と返す。
「俺、性格がこんなだから、大してモテないよ。」
性格がこんなだから、と言われたがここ10年の彼の性格を知り得ないので、千晶はそうなんだ、とだけ呟いた。
さっきまであんなにつらくて悲しくて泣いていたのに、どうしよもない気まずさが千晶を襲って、涙が引っ込んだ。ただ、初夏の蒸し暑さがじとりと肌にまとわりついて汗にもならない湿気が腕に貼りついた。
二人で歩いていたらたびたび互いの腕がふっと触れる瞬間があり、その湿気がべたッと交わった。そのたびに修は千晶に、暑いね、と笑った。
千晶はその空気感に耐えられなくなって口を開いた。
「あ、あのさあ!修くんっていつも真紀ちゃんにあんな感じなの?」
緊張のせいか妙に声がデカかった。
我ながらよくわからない質問だと千晶は思った。修は案の定、あんな感じって何?と聞き返した。
「いや、なんていうか、うちはさ、親もお姉ちゃんも私がアイドル追っかけてると、そんな暇があったら結婚しろって言うばっかりだから!こういう私を受け入れてくれてない感じというか……!」
早口で修に言う。
修はその早口をゆっくりと咀嚼するように間をとって、
「そっか。確かに米村さん以外は芸能人のファンになるような家族じゃなかったかもね。」
と答えた。
「そう!そうなの!いや、だから、その、修くんは真紀さんに優しいんだなと思って……引いたりしないんだなと思って。」
千晶は少し声が上ずっているのを自分で感じた。大好きで愛しくて最愛のアイドルが解散することを今日知って、それから10年越しに苦手としていた幼馴染に久しぶりに会って。
一日に起きたことが自分でも整理できていなかった。
修はうーん、と返答に少し迷った後、ポリポリと頭を掻いた。
「慣れてるからって言っちゃえばそれだけなんだけど……俺、結構好きなんだよね、GAPの話してる姉ちゃんのこと。」
「ほ、ほお。」
「大好きでたまらないものを目キラキラさせながら話してる感じ。本当に大好きなんだなあ、大二郎見てる時が一番幸せなんだなあってこっちにも伝わってくんの。」
「はは。そうなんだ……。」
「うん、米村さんにも感じてたよ、中学の頃。」
急に自分の名前が出てきて、千晶は一瞬ドキッとした。
ドキッと言ってもときめきの類ではなく、ギクッに近いもの。
「げへっ?私に?ウソ。」
慌てすぎて、変な声が出た。
ホントホント、マジでだよ、と修が笑った。
蒸し暑さからなのかなんなのか、千晶の額から汗が伝った。
「何で私に?」
「GAPにハマってからもそうだけど、それ以前もさ、漫画とかアニメとか、米村さんって好きなものの話になると目キラキラさせて話してたから。」
「小学生の時とか?」
「そう。周りがそれをダサいとか言ってきてもさ、自分が素敵だと思ってるものをちゃんと自分の言葉で語ってたの。米村さんって!」
修の語気が少し上がった。むしろそれを話してくれている修の目がキラキラしているなあと千晶は思った。
修はそのままのテンションで続けた。
「俺、一つのものに夢中になるってあんまり無いから。なんかうらやましくて。」
華やかな外見の修の方が断然うらやましかったけどな、と千晶は思った。
「いやいやいや、あの頃の私ってクッソ太ってて、今からえーっと20キロくらい太っててさ!ほら、男子から私、なんて呼ばれてたか覚えてる?スーパーワイルドどすこい相撲部だよ!略してどす子とか呼ばれててさ!あいつらのネーミングセンスすごいよね。黒歴史だけどあのセンスは未だに感心するよ。てか、ほんと私ってそんな感じだからうらやましがられる要素ゼロだったでしょ!」
やけに褒められるので、千晶はどんな表情をすればわからずものすごい早口で話した。そんな千晶の表情が「どんな表情をすればいいかわからない表情」であることをなんとなく察して、修は慌てて頭を掻いた。今日は頭を掻いてばかりいる。
「あ、えっと、ごめん、何か俺・・・・変なこと言っちゃったよね。今、米村さんのこと困らせてるよね?」
「や、全然、変とかそういうんじゃなくて、あの、そう、なんかびっくりしただけ!急に褒められて!あ、褒めてないのか別に!アハハ」
急に申し訳なさそうにする修に千晶も慌てて変なことを口走った。
「そうだよね、急にこんなこと熱弁されたら米村さんもびっくりするよね。」
「え、いや、違う、びっくりって別に悪いびっくりとかじゃないんだけど、あの、なんだろ・・・修くんがそんなこと思ってたなんて知らなくて!良い意味!良い意味の話!良い意味!」
「いや、なんか俺も、久しぶりに会うのにガチャガチャしゃべっちゃって・・・ごめん、アハハ、アハハ。」
二人が慌ててよくわからない会話をしていると足は最寄り駅に着いた。千晶は、戸惑いを誤魔化すように、駅だ、と呟いた。
「あの・・・・私、終電あるから。」
「うん、終電、ね。」
「あの、修くんありがと、送ってくれて。」
「うん、気をつけて。」
なんだか変な空気になったので、千晶は本来ならまだ時間の余裕があったが、終電終電と言いながら走って駅の中へ入って言った。
修はその後ろ姿に一振りだけ手を振って、それからゆっくりとその手を下げた。
駅の周辺には陽気な酔っ払いがいたり、水商売風のお姉さんと初老の男性が腕を組んでいたり、それぞれがそれぞれの初夏を歩いていた。
先ほどまで早口のアイドルオタクと話していた端正な顔立ちの青年は一人、酔った頭を逃がすようにその場で大きく深呼吸をした。
④に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
