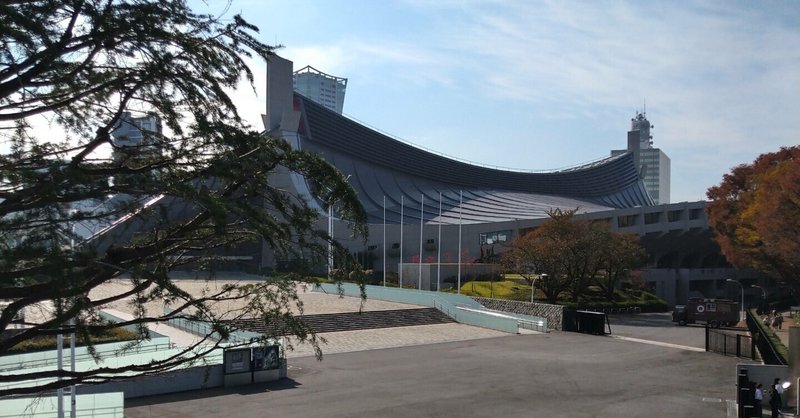
【小説】推しグル解散するってよ⑧
真紀は冷えた床の上で、婚活アプリを開いた。
自分に「イイネ」の評価をくれた男性陣を見ていたが、色々な男性を見すぎて頭が混乱していた。
ルックスの良い男性はアイドルで補給すれば良いと思っているので、真紀はあまり恋愛において外見を気にしない。だからこそ迷いが多かった。
全員が良い人に見えるし、全員が悪い人にすら思えた。
自身の年収が高いせいで、年収が低い男性にも申し訳なさを抱えながらも惹かれなかった。かといって、年収が高く、自己紹介写真に高級車を映り込ませている男性にもダサさを感じてしまった。
(このメーカーの車は性能がイマイチなんだよな、無駄に部品代かかるし、それをわかりもせずに乗ってるならダサいなあ)
自動車メーカーに勤めているせいで、車にはこだわりがあった。
きっと、ちゃんと向き合えば良い人なんてたくさんいるのだろう、だけど頭の中でこの人は自分とは合わないだろうと勝手に結論づけてしまってどうしよもない状態。
総じて自分は異性から見たところの“メンドクサイ女”だろうなと意識せざるを得なかった。
「結婚とか普通に無理ゲー・・・・・。」
真紀はスマホを床に放った。
放ったスマホの先に、開けないままのフォトブック。
開けない理由は解散が悲しいからだけではなかった。
ダサいタイトルのせいだった。
あのダサいタイトル、「NEXT STAGE」という言葉がずっと真紀の中で引っかかっていた。
正直、自分自身は結婚なんてどうでもよかった。
仕事で大成して、周囲の人たちよりも年収も高く、充実した毎日を送れているつもりだ。
だが、あのタイトルが自分を追い詰めてくるような感覚があった。
私っていま、何か変わらなきゃならない感じなの?
今まで通り、普通に仕事を頑張って、結果だして、そういう自分のままじゃダメなのかな。
私もNEXT STAGEとやらに進まなきゃならないのかな。
2022年の年始、GAPからは新年のあいさつ動画がファンクラブ限定で届いた。
今年もみんなで楽しもう、と4人は笑顔で、いつものように笑っていた。
この20年、ずっとそんな風にそばにいてくれていた彼らが、今年も来年もその先も変わりなくそばにいてくれると思わせるような笑顔で。
このままの自分でいれば、そのままそばにいてくれると思っていた。
急に次のステージへ行くと言い出したことに勝手にショックを感じていた。
置いて行かれるような、そんな気分。
「なーにがNEXTSTAGEだよ、クソが。」
私たちがずっと共に生きていくのだと信じ切っていた時間、彼らは着々とさよならの準備をしていた。
自分が一番感じたくなかった恨みだとか怒りだとか、そんな感情すら彼らに感じてしまいそうで、だから、フォトブックを開けなかった。思い出話をされるにはまだ早い。
まだ、彼らとの時間は終わっていないのだから。
勝手に行くなよ、次のステージになんて。
私たちはまだ、「いま」目の前のステージで舞い踊る君たちを追いかけていたいのに。と。
「やばい、ミスった。」
気づいた時にはもう遅かった。
勤続16年、大手自動車メーカーに営業事務として入社してすでに真紀はベテランだ。ミスをしたことが無いと言えば嘘になるが、仕事のほぼ全てを網羅して、新しい顧客にもフレキシブルに対応できる真紀は社内でまさしく完璧な社員だった。営業事務としての域を越えて、今ではマーケティング関連のミーティングにも参加し、力を発揮している。
何でもできる、それでいて愛想も良い。
それが、ここ最近おかしな状況になっていた。
「あー……お疲れ様です、森永です。すみません、田島モータースに提出したエクセルなんですけど、一行ずつズレてます。すぐ修正したもの送り直します。ハイ、申し訳ないです、すみません。」
こんな電話を取引先や営業にかけたのはこの数か月で何度目か。
新入社員でも起こさなそうなレベルのミスを連発していた。
これまでのキャリアでミスが少なかったおかげで、怒られることは無いが、心配は何度かされた。その度に自分の中での情けなさが募った。
この16年、どんな悩みがあろうが仕事中は切り替えてきた。
それなのに。
あー、情けない。
たかが、推しグループの解散じゃないか。自分の収入が減るわけじゃない。生活が変わるわけじゃない。そう言い聞かせても、よく聞く「心に穴が開く」とはこのことか、そうかそうかと感心してしまうほどに、喪失感が襲い掛かってきた。情けなかった。
迷惑なんて周囲にかけたくなかった。
迷惑をかけたくなかったから一生懸命仕事をしてきたし、上司のフォローも、後輩の指導も、完璧にこなしてきたつもりだった。
自分が入力した数字一つで営業の努力が水の泡になるかもしれない。取引先の未来が変わるかもしれない。
考えすぎだとしても、奢った考え方かもしれないとしても、そのくらいの気概で仕事をしてきた、つもりだ。
「森永さん。」
話しかけてきたのは五年後輩の女性営業、佐々木だった。座席は遠いが、佐々木の担当顧客の事務をいくらか担当しているので、割と仲の良い営業だ。
「ああ、佐々木ちゃん。ごめんね、私なにしてんだか。」
自分としてはありえないミスの連発に気を落とした真紀は、うなだれて言った。
佐々木は首をブンブンと横に振った。
「森永さんほどミスしない人いないんで。そんなことはいいんですよ。」
それより、と佐々木はポケットから一口サイズのチョコレートを出して、真紀の机に置いた。
「ちょっと、給湯室、付き合ってもらえませんか?」
その言葉は、少し話したい、という合図だった。
誰彼ともなく始まった社内の暗黙の合図。
真紀以外にも、個人的に話したい時に使われるローカルな表現だ。
これまで、後輩から仕事の相談でその合図を使われたことが何度もあった。
給湯室に行き、真紀と佐々木はコーヒーを作った。特別なそれじゃない、ただのインスタントコーヒー。
それをゆっくりとすすりながら、佐々木は言った。
「あの・・・・。」
「ん?・・・・」
「森永さん、もし何か気がかりなことがあるんだったら休んでください。有休とか、使っちゃってください。」
佐々木は親指を立てて、グッドサインを真紀に向けた。
そんなことを後輩社員に言わせるなんて、よっぽど自分が情けない姿を晒しているのだと真紀は感じた。悟った。
「いや、別に大したことはないよ。何にもないよ。」
大丈夫、と笑う。佐々木はコーヒーがこぼれるほどの勢いで手をブンブンと振る。
「じゃあ、何にも無くてもいいですよ。どのみち森永さん休み全然取らないんだから、リフレッシュ休暇でも取ってください。」
ありがたい、ありがたいけれども、うーん、と答えにならない音を出して、真紀はコーヒーをすする。
「でも私が休むと、営業が困るでしょ。私の担当顧客多いから・・・。」
「森永さん!」
真紀がウダウダと答えると、佐々木はわざと語気を強めた。
「営業は一応、新入社員の時に事務の仕事も一通りやらせてもらってるんで、自分の顧客の責任は自分で取ります!もしいいかげんな奴がいたら私が張り倒しますから!」
営業職をやっている人間の声は大きい。自分に自信があろうがなかろうが、商品を売らなければならないとなれば嫌でも語気を強めたり、上手いこと言えるようにだんだん訓練されていくものだ。
入社当初、気弱だった佐々木も例に漏れず、いつの間にかトークを上手く運ぶことができるようになった内の一人だ。
「森永さんに何があったのはわからないし、聞きません。でも、私は入社してから何度も森永さんに救われてきました。」
「そうだっけ・・・・。」
「そうですよ、森永さん覚えてないかもしれないけど、私、5年目くらいで家族に色々あったんです。」
「そうだっけ・・・・。」
「あん時、私めっちゃ病んでて・・・営業の先輩にはそのことがつらいって言えなかったんです。でも、森永さんには言えたんです。言えて、それで・・・・っ、森永さんはそういう私の感情を甘えだとかそんな風には言わなかった。」
そうだっけ、と真紀は何度も同じ言葉を発した。特別な感情を持って、その会話をしていなかったから何も覚えていなかった。
佐々木は真紀の反応を気にすることなく、続ける。
「森永さん、言ってくれたんですよ。人が何をどう感じるかはそれぞれだって。誰かが平気なことでも他の誰かにとってはつらいことかもしれない。もし佐々木にとって今がつらいなら、泣けばいいし、休めばいいって。仕事がすべてじゃない、自分の人生を大切にしなさいって言ってくれたんです。」
佐々木はとても熱く語っていたが、当の真紀はそうだっけ、と変わらぬ返答をした。
覚えていないとは決して冷たい感情ではなかった、真紀はいつもただ、そう思っているだけだったから。
「森永さんは人にはそう言ってくれるけど、自分の人生は仕事に捧げてるみたいで……それって悪いことじゃないんですけど、なんていうか、ただ……。」
他人の為に、私のために、こんなに懸命に言葉を選んでくれる後輩社員がいたのかと真紀は少し嬉しくなった。
「ありがとう、でも私、仕事に人生捧げてないよ。趣味が金かかるから仕事してるだけ。」
真紀はハハハ、と笑った。
「それって最高じゃないですか!」
佐々木はまた大きな声を出した。声大きいなあと真紀は口元を緩める。
佐々木が続ける。
「私も、森永さんも明日死ぬかもしれないし、下手したら今日帰り道で事故で死ぬかもしれないし、もしかしたらいま給湯室が爆発して私たちだけ死ぬかもしれないんですよ。」
「は、はあ。」
「森永さんがいま爆発しても、下の人間が仕事できる環境にならなきゃいけないんですよ。」
いま爆発しても、なんて物騒な言い方するなあと少し笑えたが、ハッとさせられた。
佐々木の“呼び出し”は優しさだ、間違いない。けれど、自分に対する誠実な忠告でもあったのだと気づく。
「確かに、それはそうだ。」
多分、今日初めての素直な言葉。
「森永さんが頑張ってくれるのってすごく嬉しいし、私たちもやる気になるし、頼りになるし、最高ですけど、森永さんがいない日のみんなも頑張ってるんです。営業事務も若い子たちも、めちゃくちゃ頑張ってますよ。森永さんはもっと、信じてくれていいんです。みんなを。」
あ、泣きそうかも、私。
真紀は頭の中でそう感じながら、ぐっと涙をコーヒーで流し込んだ。
「信じてくれていいんです、かあ。すごいこと言うね。」
「あ、ごめんなさい、調子乗りました!」
佐々木は慌てて謝る。いや、そうじゃなくて、と真紀は笑う。
「そうじゃなくて、なんていうか・・・ありがとう。」
「え・・・。」
「ありがとう、なんか、嬉しいし、少し反省もする。」
コーヒーを包みこむカップは赤い椿の九谷焼。千晶とツアー遠征した石川県で購入したものだ。柔らかい椿模様を指でなぞりながら、真紀は佐々木の言葉を飲み込む。
自分が頑張っていなければいけないと思って、懸命に仕事をしてきたし、悪いことではない。信じてくれていいという言葉はどこか寂しさを感じさせたが、そうか、と解散発表以来、ずっと止めたままだった息をようやく吐けたようなそんな気分になった。
やっと呼吸した姿見れた気がする!と佐々木も言う。そうか、そんなに息を止めていたのか。仕事に打ち込んでいれば逆に気がラクだったからと、躍起になって。そのくせ柄にもなくミスをして。
「完璧じゃない森永さん、私好きだし、きっとみんなも好きです。」
しゃきしゃきと話す佐々木の爽やかさに真紀はやられそうだった。
まぶしいなこの子は。
真紀はコーヒーを飲み干すと、佐々木に
「人生で一番おいしいコーヒーだった。」
と笑った。
佐々木は
「・・・・そういうところ、ほんと好きです。」
と、笑った。
⑨へ続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
