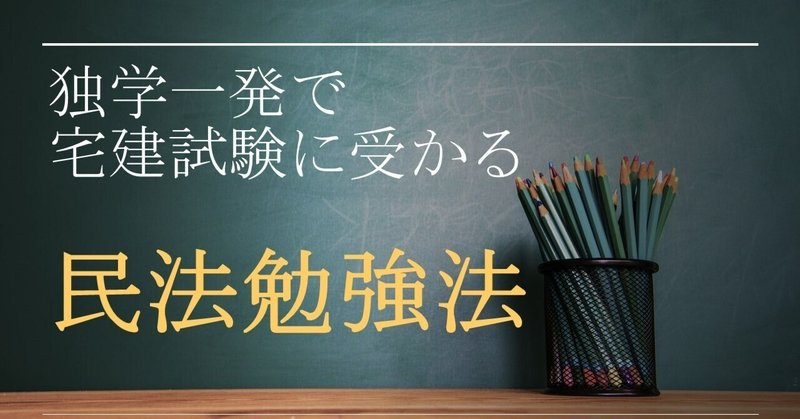
独学一発合格のための宅建士試験民法の勉強法&テクニック
宅建士試験の「民法等」の科目で高得点を取るための方法について、独学3か月で宅建士試験に一発合格した私が本記事で詳しく解説します。
※本記事では以下「民法等」を「民法」と表記します。
民法は試験範囲が広く問題の難易度も高いため、苦手にする受験生が多い科目ですが、勉強方法を工夫したり、ポイントを絞って勉強することで短期間の学習でも高得点を狙うことも可能です。(私も本試験での民法の得点は14点中9点でした)
民法の勉強法に悩んでいる方や、短期間(3か月以内の勉強)で宅建士試験の合格を目指している方、宅建士試験の民法科目で高得点を取りたい方は、ぜひこの記事を参考にして試験合格を掴んでください。
民法とはどんな科目?
まずは民法がどんな科目なのかをご紹介します。
試験内容と試験範囲
宅建試験における民法の科目では「民法の規定」や「民法の判例」についての正誤が主に出題されます。正解をするには正しい法律の知識をつけることが不可欠です。
試験範囲は民法および関連法規となっており、民法では不動産業務に関連する「売買」「賃貸借」「代理」「抵当権」「相続」などが頻出分野となっています。民法以外の法規は「借地借家法」や「区分所有法」「不動産登記法」が頻出分野です。
配点と目標点数
宅建試験の民法の配点は14点です。
宅建士試験は「民法」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」分野の4つの分野から全50問(各1点)が出題される50点満点の試験です。
民法は毎年14問が出題されており、全体の28%を占めています。
民法の目標点は5点から8点程度に設定するのがよいでしょう。
宅建士試験の合格最低点は例年34点から38点であり、得点率に直すと68%から76%程度なので、単純計算では民法の目標点は配点14点の7割程度=9点から10点程度となりますが、民法は他教科と比較して問題の難易度が高く、得点を取りずらいため目標点はもう少し引く設定するべきです。
直近の宅建士試験合格最低点の推移
令和5年-36点
令和4年-36点
令和3年12月-34点
令和3年10月-34点
令和2年12月-36点
令和2年10月-38点
※令和2年と3年は10月と12月の2度試験実施
民法のつまずきポイント
続いて民法を苦手にする受験生が多い理由をご紹介します。
民法は試験範囲が膨大
民法を苦手にする理由で最も多く聞かれるのが「試験範囲が広い」ことです。民法だけでも条文は1050条もあり、さらに判例まで含めるとその試験範囲は膨大な量になります。実際近年の試験でも以下のような難問が出題されています。
民法の規定によれば次のうち誤っているものはどれか?
3.船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
ちなみに「船が遭難した場合の遺言の方法」について触れている宅建士試験の参考書は見つけることができませんでした。つまり「いくら対策しても当日の試験には全く知らないものが出てくる」のが民法という科目なのです。
専門用語が飛び交い理解が難しい
民法を苦手にする理由で2番目によく聞くのが「専門用語がわかりずらい」ということです。確かに法律の条文や判例は独特の言い回しや専門用語が多いので、一読しただけでは理解できないこともあると思います。
民法の学習ではそのような難しい日本語を読み解かなければならないため、難しいと感じてしまいがちです。
短期間で高得点を稼ぐ最強民法勉強法
ここからは短期間で民法を得点するための勉強法をご紹介します。
テキストを読み込む
まず大切なのはテキスト(参考書)の読み込みです。民法のテキストは専門用語が多く難しく感じると思いますが、ひとつひとつの内容を理解しながら読み進めることが重要です。「債務者」「債権者」といった基本的な用語から「抵当権」や「権利設定者」「時効の援用」などの応用的な用語まで、分からない単語があれば辞書で調べたり、インターネットで検索するなどして理解するようにしましょう。
また文言で理解するだけでなく、実際の法律の状況を想像しながら読み進めることも効果的です。例えば「抵当権が設定されている土地を購入した場合~」という内容であれば、「自分が土地を買ったらその土地に抵当権がついていた」と自分のこととして妄想・想像してみましょう。より具体的に内容をイメージできるので理解が促進し、記憶も定着しやすくなります。
ただし、テキストを読み込むことばかりに注力していると問題を解く力が身につきません。本番の試験でどのように知識が問われるか、というのを知るためにもテキストの読み込みと並行して問題集での演習も行いましょう。
目安としてはテキストを1章読み切ったらすぐに問題集などで当該章の問題演習をするようにしてください。
過去問の活用方法
民法は過去問の類題も多く出題される科目です。
例えば直近の令和5年試験においても以下のような問題が出題されましたが
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 0円
2 200万円
3 400万円
4 800万円
これは以下の平成27年度の試験問題とほぼ同じ問題です。
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権 (債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金 5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
2.BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
3.BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
4.BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
過去問で問われた知識は勿論のこと、解法や周辺知識を中心に勉強を進めることで効果的な学習をすることができます。
おススメの学習方法は以下の5つのステップです。
①過去問に挑戦する
②答え合わせをする(OXをつける)
③過去問の解答・解説を読む
④出題内容を教科書・参考書で確認し周辺知識も身に着ける
⑤繰り返し同じ問題に挑戦する
丁寧に同じ問題を解き続けることで知識が定着し本番の高得点につながるはずです。
本番で使えるテクニック
最後に本番の試験で得点をとりやすくするテクニックをお伝えします。
試験問題を解く順番で差をつけろ!
まず大事なのは試験問題を解く順番です。
私のおススメは民法は最後に解くです。
民法は冒頭で述べた通り「いくら対策しても当日の試験には全く知らないものが出てくる」科目です。なので、一番最初に民法から説き始めてしまうと全く分からない問題にぶつかってしまい動揺してしまったり、無駄に時間を使ってしまう可能性があります。そうなると民法以外の科目の得点にも悪影響を与える可能性があります。なので他の科目を先に解いて最後に落ち着いて民法に取り組むことがおススメです。
高確率で正解できるラッキー問題とは?
難問が多い民法において高確率で正解できるラッキーな問題があります。それは判例文読解問題です。判例文読解問題とは実際の判決文を読んで、それをもとに問題を解くタイプの問題です。具体的には以下のような問題です。
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
1.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
2.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。
3.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
4.所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
判例問題は一見難しい問題に見えますが、判例文の内容をしっかり理解できれば前提知識が全くなくても正解にたどり着くことができます。本番試験で判例文問題が出題されていたら、民法の中でも優先的に時間をかけて解くようにしてみてください。ほぼ確実に1点を得点することができます。ぜひ注目してみてください。
まとめ
この記事では宅建試験の民法科目の攻略法についてまとめました。
民法は苦手にする人が多い科目ですが、この記事の勉強法を参考に勉強を進め高得点を獲得し試験合格をつかみ取ってください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
