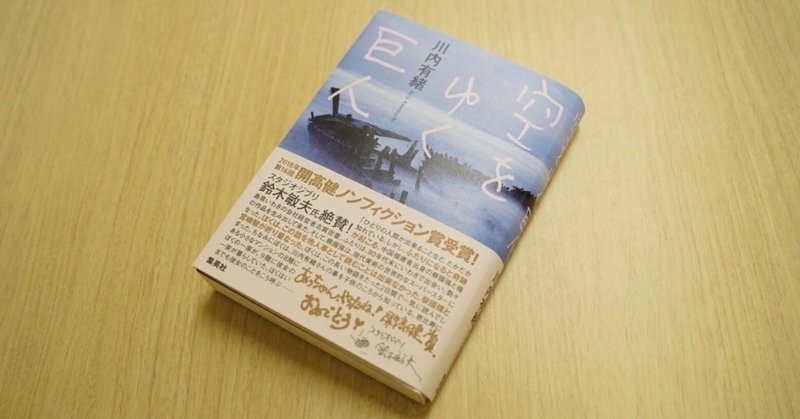
全文公開『空をゆく巨人』 第七章 キノコ雲のある風景
第16回 開高健ノンフィクション賞受賞作『空をゆく巨人』(集英社)をnoteで全文公開中。今回は第七章です。
第七章 キノコ雲のある風景(ニューヨーク・一九九五年)
眠らない街の小さな家族
生い立ちも国籍も職業も異なりながら、お互いに惹かれあい、一緒に宇宙へと光を放った志賀と蔡。もし彼らが宇宙に浮かぶ星だとしたら、志賀はどっしりとした木星、蔡は輝く尾をたなびかせ飛翔するハレー彗星(すいせい)のようだ。広い宇宙で偶然に交差したふたつの星は、いまやすごい勢いで遠ざかっていた。志賀はいわきに残り、蔡は摩天楼の都市へ——。
「二〇世紀はアメリカの世紀だというのは明らかでした。だから、少しの間アメリカに住むのは良さそうだと思ったのです」(『Cai Guo-Qiang』 Phaidon)
世界中から移民が集まるニューヨークは、アメリカの自由と夢、繁栄のシンボルである。松明(たいまつ)を高く掲げる自由の女神は、一三〇年もの間、この街にやってくる移民たちを見守ってきた。大西洋を横断してきたヨーロッパからの移民たちは、船上からこの像を見つけ、新天地に来たことを実感したという。
またニューヨークは、第二次世界大戦後に「芸術の都」の称号をパリから奪取した街でもある。アンディ・ウォーホル、ロイ・リキテンスタイン、ジャクソン・ポロック、ドナルド・ジャッド、と二〇世紀を代表するアーティストたちがこの街で暮らした。
いまでも彼らの背中を追うように、数え切れないほどのアーティストがこの街に群がる。高層ビルに切り取られた四角い空を見上げ、けたたましいサイレンをBGMに眠り、夢に手を伸ばすのだ。
フランク・シナトラは『ニューヨーク・ニューヨーク』でこう歌う。
俺は目を覚ましたいんだ
あの眠らない街の片隅で
そして、ナンバーワンになるんだ
頂上まで上りつめて
この街で成功できるとしたら
どこででも成功できる
さあ、おまえ次第だ
ニューヨーク、ニューヨーク
(作詞 フレッド・エブ/訳 川内有緒)
さて、蔡と紅虹、長女の文悠の三人家族がニューヨークに到着したのは、一九九五年の九月のことだった。蔡は九年にわたる日本での活動が認められ、アジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)の奨学金を受けられることになった。ACCは国際文化交流支援を目的とする非営利組織で、草間彌生や村上隆など日本の現代美術界を牽引するアーティストを多数支援してきた。
蔡は、ACCが所有するアパートに居を定めた。以前は村上隆が住んでいた部屋で、残されていた皿や箸をそのまま受け継いだ。
〝一九九五年の九月〟と聞いた私は、勝手に興奮してしまった。一五歳で中国に行った私が、大学を卒業し、アメリカに留学したのは、同じく一九九五年の九月だった。飛行機で最初に降り立ったのは、ニューヨーク。当時の私は、自分でも持て余すほどにこの街に恋い焦がれていた。フランク・シナトラが歌うように、その街の片隅で目を覚ましたかった。しかし残念ながら、私のほうはニューヨークに縁はなく、結局は別の都市の学校に進学することになり、卒業後はそのままその街の企業に就職した。それでも六年のアメリカ生活で、ニューヨークに通った回数は数えきれない。だから一度くらいは蔡一家と街角ですれ違ったかもしれない。
私とは正反対に、蔡のほうはそこまで長くアメリカに住むつもりはなかったらしい。一年の奨学金期間が終わったら日本に帰ることを予定していた。
作品制作の拠点に選んだのは、ニューヨークのクイーンズにあるMoMA PS1(モマ・ピーエス・ワン) 。美術館でもギャラリーでもなく、現代美術の巨大な実験場というのがふさわしい。元は小学校の校舎だった建物には、やる気に満ち溢れた世界中のアーティストが多数集まり、「駆け出しのアーティスト」の群れから頭ひとつ抜け出そうとしのぎを削っていた。
日本の美術界では少しは名が知れてきた蔡だが、アメリカではまだ無名の存在だった。しかも、それまで英語を勉強するチャンスがなかったので、周囲とのコミュニケーションもおぼつかない。だから蔡は、再び「異国からやってきた言葉が不自由な男」という状態からスタートしなければいけなかった。しかも今回は、幼い娘まで一緒なのだ。
苦労したのは蔡だけではなかった。「言葉がわからないなかで子育て……、はい、とても苦労しました」と紅虹は語り、長女の文悠も「あまりにも違う環境で、難しいトランジション(変化)でした」と当時の状況を振り返る。何しろ、ついこの間までのんびりした茨城の田舎町にいたのだ。深夜になれば、コンビニといくつかの飲み屋から明かりが漏れるだけの町から、突如人口七三五万がひしめく「眠らない街」に放り込まれたのである。
問題は知名度や言語だけではなかった。アメリカでは美術館や作品制作のシステムも日本とはまったく異なっていた。
「アメリカでは、現代美術はひとつの産業のようでした。たとえるなら、アメリカでは現代美術は正規軍。中国ではゲリラ部隊で、日本では民兵です。日本では市民と一緒に活動することができました。普通の人たちが(アーティストである)自分と一緒に働いてくれました。アメリカでは違います。すべてがプロフェッショナルなのです。もし壁に何かを架けたければ、許可が必要になります。誰かに石を拾ってもらうにも、許可がいります。すべてを〝プロフェッショナル〟にやらなければいけない。そういうことが、たぶん私の仕事のやり方を変えたのです」(前同)
いままでやってきたような、市民との共同作業はもはやできそうにはなかった。よくよく考える必要があった。少ない予算で、ひとりでも制作でき、言葉で説明しなくても直感的に伝わる作品。アートに目が肥えたニューヨーカーが、あっというような作品。
——さて、何をつくろうか? 蔡は考えを巡らせた。
マルコ・ポーロが忘れた物とは
蔡の作品の魅力のひとつが、品のあるユーモアではないかと私は思う。物事をシリアスにするのは簡単だが、クスッと笑わせるのは難しい。それが、文化的背景を異にし、言葉が通じないとなればなおさらだ。その笑いを誘うという人間的な部分が、蔡の作品が世界中で愛される理由のひとつではないだろうか。それをよく表す作品があるので、時計の針を少しだけ戻そう。
アメリカに移住する直前の一九九五年の夏、蔡の姿は、かの有名な現代美術の祭典、ベネツィア・ビエンナーレにあった。この世界最古の国際美術展覧会は、別名「現代美術界のオリンピック」とも呼ばれる。メイン会場のジャルディーニには各国のパビリオンが立ち並び、国の代表に選ばれたアーティストが展示を行う。会期の最後には、優秀なパビリオンや個人に対し賞が付与される。そんなこともまた「オリンピック」たる所以(ゆえん)である。
この年、中国はまだ公式パビリオンを持っていなかったが、蔡はビエンナーレの後援企画である「トランスカルチャー展」に招待されていた。異なる文化間のコミュニケーションをテーマにし、オーストラリア、アフリカなどから一五人が参加していた。
そこで蔡が発表した作品は、《マルコ・ポーロの忘れ物》——。
「今年はマルコ・ポーロが泉州を出港し、海のシルクロードを通ってヴェニスに帰港して七百年にあたります。彼は東洋から多くの珍品を持って帰ったが、精神までは持ち帰らなかった。だからこの機会にマルコ・ポーロが忘れた東洋の精神をヴェニスに持っていこうということです」(『東京人』一九九五年七月号)
——はて、東洋から持ち帰らなかった東洋の精神とはいったい何のことだろう。
マルコ・ポーロが生まれたのは、一二五〇年代のベネツィアだ。商人だった彼はインドや中国などをめぐり、そこで見聞きしたミステリアスな文化や風習を『東方見聞録』にまとめた。蔡の故郷、泉州でもマルコ・ポーロは有名で、多くの子どもたちが『東方見聞録』を読んでいた。しかし、蔡自身はその内容に違和感を覚えた。本では東洋が奇異な習慣を持った国々として描かれていた。
その違和感はずっと彼の奥深くにくすぶっていたようだ。それから時が巡り、今回、泉州生まれの蔡がマルコ・ポーロの故郷・ベネツィアで作品を発表する機会がやってきた。そこで「よし、いまこそ自分が東洋の精神をヨーロッパに伝えよう」と考えた。
まず蔡は、中国に戻って古いジャンク船を手配しベネツィアに送った。七〇〇年近く前に泉州を訪れたマルコ・ポーロが見たものと基本的には同じ木造の帆船だ。
芸術祭のオープン当日、世界中から集まった観光客は、歴史ある運河に奇妙な古い船が帆に風を受けてゆっくりと入ってくるのを目にした。
何だ、あれは?
これは、演劇の始まりのような巧みな演出だった。船上にいる蔡は、風向きやスピードを緻密(ちみつ)に計算し、オープニングに間に合うようにジャンク船を入港させ、人々を驚かせたのだ。
「みんな、あんな古い中国の船は見たことがなかったですね。びっくりしてました。あれは面白かったです」
蔡は、その日のことをいまでもおかしそうに笑う。
しかし、ここからがショーの本番。蔡はジャンク船を運河沿いのギャラリーの外につけると、大きなずだ袋をせっせと船から運び込んだ。その姿は、まるで中国からやってきた商人さながらで、袋のなかには朝鮮人参が一〇〇キロ分も入っていた。
これで、東洋の精神を代表する「気」を高める薬湯をこしらえ、訪れた人に振る舞うというのが今回の作品だった。供されるのは、中国の漢方医師と相談して配合した本格的なものだ。同時に、日本風の自動販売機も設置し、瓶詰めの漢方薬ドリンクも販売した。
芸術祭に訪れた人々は、運河の涼しい風に吹かれながら、おっかなびっくり特製ドリンクを飲み、マルコ・ポーロが持ち帰り忘れた〝東洋の精神〟を体に取り入れた。
「ベネツィア・ビエンナーレの会場は広くて疲れるから、展示室ではリラックスしてもらいたかった」と語る通り、気遣いとユーモアを感じさせる作品なのだが、よくよくひもといてみれば、文明発見史、異文化の交流、中国の伝統、そして日本風の自動販売機など、過去と現代、ヨーロッパとアジアの要素が巧みに融合されている。一般の観光客や市民を楽しませる「わかりやすさ」の奥のもうひとつのレイヤーに、美術関係者も舌を巻いた。
「蔡さんの発想って大きいんですよね。大陸的だなと。本物のジャンク船を持ってくる発想や、現代美術の世界に中国の漢方を持ち込んで、鑑賞者にも参加させるということが、すごく新鮮に思えました。蔡さんは、独特なやり方で人々をアートに関わらせて、関わった人は心身ともに少しずつ変化してゆくんです」
そう語るのは、現・横浜美術館館長の逢坂恵理子で、実際に《マルコ・ポーロの忘れ物》の漢方薬ドリンクを体験したひとりである。
逢坂は、このベネツィア・ビエンナーレの一年前に、水戸で蔡と出会った。一九九四年四月に逢坂は水戸芸術館に学芸員として赴任、その直後に開催された同館のグループ展に蔡が参加していたのだ。逢坂が語る通り、東洋の精神や中国伝来の漢方は、蔡の作品に繰り返し現れるテーマのひとつである。振り返れば、いわきで菊の花をお茶にして出したのも漢方をベースにした考えだった。「風水を信じる町」で生まれ育ち、シャーマンの教えとともに生きてきた蔡は、自分の国の伝統をきちんと作品の中心に取り入れる。ときには古臭いと一蹴されるような伝統こそ、大事にし、伝えたいものだった。
「漢方も風水も私にとっては同じく宇宙の一部。そして人間もまた宇宙の一部なのです」
蔡は古いジャンク船に乗って運河を往来し、観光客の目を楽しませ続けた。
そんなある日、蔡が船に乗っていると、「蔡國強! 君は賞をもらったぞ!」という大きな声が聞こえてきた。
最初はなんのことかさっぱりわからなくて、ギャラリーの外にジャンク船をつけました。みんなが、おめでとう! と私に言うので、賞をもらったことを理解しました。「ねえ、その賞って賞金も出るんですか」って聞いたら、みんなちょっと止まったあとに、「イエス、イエス、イエス」と答えました。のちにこのジャンク船は、泉州からベネツィアの海洋史博物館へプレゼントしました。だから、東洋から来た船は本当に彼らのものになったのです。 (『A CLAN OF BOATS』)
蔡が受賞したのは、第一回ベネッセ賞だった。国際交流基金と福武總一郎(当時ベネッセコーポレーション代表取締役社長)が設立した福武学術文化振興財団(二〇一二年より公益財団法人福武財団)が共催したものである。賞は現金の他に、瀬戸内海のアートの島、直島(香川県)に滞在して作品を制作することができるというものだった。
キノコ雲のある世紀
一九九五年のニューヨークに話を戻そう。
大きな資金、そして友人や美術館のサポートも望めない新天地で蔡が思いついたのは、ネヴァダ州の砂漠地帯に行くことだった。
ベネツィアの作品が「過去の光」を表しているとすれば、こちらは「現在の影」——。
ネヴァダに着いた蔡の頭上には、抜けるような青い空があり、目の前には荒涼とした砂山や崖が広がっていた。生き物の痕跡は何もない。大地には、クレーターのような穴が無数にあき、奇妙な図形のような模様が重なっていた。
そこは、アメリカを代表する核実験場で、大地に描かれた図形は、宇宙人へのメッセージなどではなく、何百回と繰り返された地下実験の痕跡だった。
それにしてもよくそんな警備が厳しそうな場所に一介のアーティストが入れたものだ。
「ACCの援助がありましたから、許可を取るのは難しくなかったです。私は、核実験場に入った初めての『中国から来た中国人』になりました」
その不毛の地で、蔡は砂漠を見下ろせる高台に立ち、吹きつける強い風のなか、少量の火薬を詰めたFAX用紙の芯を取りだした。
いまだ——。
右手で小さな筒を掲げ、なかに詰めた火薬に火をつける。
ボン! という爆発音と共に、白い煙が空に広がる。それはまるでミニチュアのキノコ雲のように見えた。
これが、《キノコ雲のある世紀:20世紀のためのプロジェクト》と題する連作のパフォーマンスの始まりだった。
「20世紀物質文化の急速な発展とともに誕生した原子爆弾は、私たちに気づかせたのです。人がつくった物質文明は、その果てに、人類自身を破滅させることもできるのだと」(『第7回ヒロシマ賞受賞記念 蔡國強展』)
蔡の新天地、アメリカは世界有数の核保有国だった。そして核実験の多くがこのネヴァダ核実験場で行われていた。
その後も、蔡はアメリカを象徴する場所に赴いては、細い筒を取り出し、小さなキノコ雲をつくり続けた。紅虹や娘の文悠も同行し、父親の奇妙なパフォーマンスを温かく見守った。一連の行為は写真や映像に収められ、それが後に美術館で展示する作品となった。写真や映像のなかで蔡は後ろ姿を向け、手元から小さな白いキノコ雲が上がっている。言ってしまえば、たったそれだけの作品だ——。
だが、どこか不吉なイメージを呼び起こすビジュアルのインパクトは絶大だった。作品は、センセーションを巻き起こし、写真は書籍『一九四〇年以降のアート:存在の戦略』(Art Since 1940 : Strategies of Being)のカバーにも使われた。中国からやってきた無名の男は、ほんの小さな行為でも大きなインパクトの作品を生み出すことができると証明してみせたのだ。
それから二〇年以上が経った現在、一連の写真を改めて眺めると、また違った意味でぞっとする。シリーズのなかにはマンハッタン島の対岸から撮影された作品もあるのだが、そこには、二棟の世界貿易センタービルが大きく写り、空にはキノコ雲が上がっている。
撮影からわずか五年後、この巨大なタワーが煙を上げながら崩壊することなど、蔡は知る由もない。だからタワーが写っていることは、ただの偶然にすぎない。とはいえ、不吉な予言めいたこの作品は、時が経つほどに評価が高まることになる。
こうして蔡は、予定した一年が経つころには、日本には戻らない決心を固めた。
「アメリカでの展覧会のオファーがいっぱいありました。それに、中国のパスポートでは一度日本に戻ってしまうと、またアメリカに戻るのが大変だったので、そのまま残ることにしました」
そういう現実的な事情もあったものの、蔡はニューヨークが持つ自由闊達な空気も気に入ったと語る。一九九六年には、ギャラリーが立ち並ぶソーホーの近くに、「サイ・スタジオ」を設立。煉瓦造りの瀟洒(しょうしゃ)な建物のひと部屋で、初めてアシスタントの女性をひとり雇った。
ニューヨークに流れ着いた蔡國強という帆船に、アメリカの風は強く、強く吹き続けた。一九九六年、グッゲンハイム美術館ソーホー別館で発表した作品《龍が来た! 狼が来た! —チンギスハンの舟》は、ヒューゴ・ボス賞にノミネート。また翌年、ニューヨークのクイーンズ美術館では、アメリカ初となる美術館での個展も行われた。これにより、蔡はアメリカの美術界のメインストリームに躍り出た。
美術評論家でアートディレクターの清水敏男は、蔡の作品がアメリカで受け入れられた理由を、次のように説明した。清水は、水戸芸術館やのちの上海ビエンナーレ(二〇〇〇年)でキュレーターを務め、長きにわたり蔡と交流を続けるひとりだ。
「蔡さんの作品は、その背景を詳しく説明されなくても、共感できるところが大きい。直接(体や感覚に)響いてくるところがあります。アメリカは、色々な国や文化の人がいて、もともとバラバラです。例えばアメリカ映画で派手なアクションを多用するのは、文化の違いを超えた理解を得やすいからです。色々な背景や文化を持つ人がいて、みんなバラバラで違っていても、蔡さんの爆発作品は人間の根源的なところに響いてくるのです」
蔡の作品を受け入れたのはアメリカだけではなかった。同じころ、南アフリカ、イタリア、オーストラリア、日本など、異なる地域や大陸で展示を実現。アイデアが尽きることはなかったし、体力も気力も十分だった。蔡はかつて夢見た通り、ビッグフット(大きな足)で国境を跨(また)ぐように世界を旅するようになった。
忙しくなったものの、蔡はなるべく多くの時間を家族と過ごしたがったので、長女の文悠はときに学校を二週間も休まなければならなかった。文悠は、自身の手記で自分は美術館で育ったも同然だと書いている。
毎回のように美術館に連れて行かれることは、よくある〝子どもの職場見学デイ〟のようなものでした。私が知りえた職業といえば、アーティストやキュレーター、美術館のディレクターや技術者だけでした。こういった仕事は、子どもがイメージする「普通の職業」とは違いますが、そんなことには気がつきませんでした。自分は将来、お医者さんや弁護士、消防士や宇宙飛行士になれるかもしれない、という可能性にも気がつきませんでした。いやたぶん私は、毎朝目を覚まして同じ場所に通勤するというイメージすら持っていませんでした。 (『When You Make No Art』)
「蔡さん、頑張ってるみたいだなあ」と志賀や藤田は、ときどき蔡の話をした。普通ならばこのあたりで、「世界的アーティストといわき市民の交流の物語」は、思い出のアルバムにしまわれてもおかしくない。しかし、いわきの人々の心にはまだ蔡が生き続け、蔡がアメリカでどうしているかを知りたがった。そこで志賀と藤田は、不定期で『蔡國強通信』というニュースレターを出し、配ることにした。それを知ったとき、蔡はとても嬉しかったそうだ。
「私という〝船〟がいわきの港から出て、世界中のあちこちの港に行っている。いま、自分が海外でどういう感じかみんなに知ってもらいたい、いわきの方々にずっと遠くから見守ってほしいと思ってたから、(通信が)嬉しかった」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第八章はこちらからどうぞ。
書籍でお読みになりたい方はこちら↓からどうぞ。
空をゆく巨人 目次
プロローグ
はじめに
第一章 生まれながらの商売人 いわき・一九五〇年
第二章 風水を信じる町に生まれて 泉州・一九五七年
第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす サンフランシスコ・一九七六年
第四章 爆発する夢 泉州・一九七八年
第五章 ふたつの星が出会うとき 東京・一九八六年
第六章 時代の物語が始まった いわき・一九九三年
第七章 キノコ雲のある風景 ニューヨーク・一九九五年
第八章 最果ての地 レゾリュート ・一九九七年
第九章 氷上の再会 レゾリュート・一九九七年
第十章 旅人たち いわき・二〇〇四年
第十一章 私は信じたい ニューヨーク・二〇〇八年
第十二章 怒りの桜 いわき・二〇一一年
第十三章 龍が駆ける美術館 いわき・二〇一二年
第十四章 夜桜 いわき・二〇一五年
第十五章 空をゆく巨人 いわき・二〇一六年
エピローグ いわきの庭 ニュージャージー・二〇一七年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
