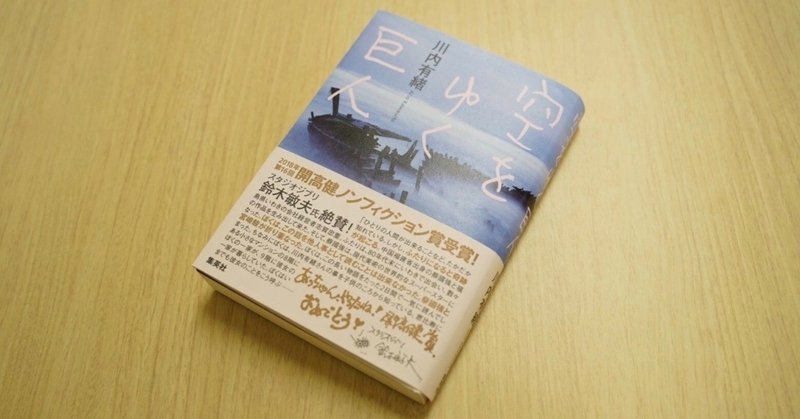
全文公開『空をゆく巨人』 第四章 爆発する夢
第16回 開高健ノンフィクション賞受賞作『空をゆく巨人』(集英社)をnoteで全文公開中。今回は第四章です。
第四章 爆発する夢(泉州・一九七八年)
自分だけの表現を探して
二〇代となった蔡もまた、ひとつの転機を迎えていた。荒波をゆく人生という船に同乗してくれる女性に出会ったのだ。名は呉紅虹(ウホンホン)。五〇代後半になったいまでも驚くほど美しい人だが、当時の美しさは群を抜いていたらしい。
「どうやって紅虹さんと知り合ったんですか」
ある夜、日本酒を飲みながら、蔡に聞いた。蔡は深酒はしないが、リラックスしてちびちびと飲む酒は好きなのだ。
「それはですねえ、私が二一歳、彼女が一七歳のときでした。彼女はよく外でスケッチをしていたんですね。でも、外にひとりでいると危ないから友人が私に『お前、一緒についていてあげたらどうか』と聞いてきたんですよ。でも、そのときは、ノーって断りました。『俺は世界に出るから女と知り合ってもしょうがない!』という気持ちだったので、断りました。でも、あとから気になって、友人に紹介を頼みました。友人は、あれ、興味がないんじゃなかったのか、って言いましたが、紹介してくれました」
実は、紅虹のほうは、以前から蔡のことを知っていたという。そのころの蔡はいくつかの映画に出演していて、そのなかで蔡の姿を見たことがあったのだ。
「映画では悪人の役で、最初は悪いやつだと思った」(紅虹)
ふたりが恋に落ちるのに時間はかからなかった。それからというもの、蔡は紅虹をどこにでも連れていき、蔡のアトリエは紅虹のアトリエにもなった。
このころ、美術をとりまく状況も変わりつつあった。泉州から遠く離れた北京の片隅では、それまで地下に潜んで活動していた若い前衛芸術家たちが、表舞台に出始めたのだ。
そのひとつが、一九七九年に誕生した中国初の前衛芸術集団「星星画会」。そのロマンチックな名には、ひとつの太陽だけが世界を照らす〝太陽の時代〟ではなく、〝ひとつひとつは小さくとも、個性的な無数の星々が輝く時代〟になるようにという思いがこめられている。のちに政治活動家となり、権力と闘うことになる現代美術家の艾未未(アイウェイウェイ)も若きメンバーのひとりだった。
しかし、当時の中国では、前衛芸術家が美術館やギャラリーで展示することはまず不可能だったので、あくまでも空き地でゲリラ的に展示するしかなかった。星星画会の誕生は、中国の現代美術の遠い夜明けを感じさせるものだったが、最終的には、メンバーの多くが海外に去ることになってしまった。
それでも、八〇年代に入ると、鄧小平が経済改革と対外開放を本格的に推し進め、大国の扉は大きく開かれ、美術の世界にも影響を与えるようになる。それまで中国ではほとんど存在しなかった「現代美術」を実践するグループがあちこちで結成された。中国にもいよいよ自由な表現の時代がやってくる、そんな空気がうっすらと漂い始めていた。
一九八一年、二三歳になった蔡は、上海演劇大学美術学部への進学を決め、紅虹と一緒に上海に向かった。ふたりがどういう風に暮らしていくのかと周囲は心配したが、蔡自身は気にしていなかった。
「みなさんは、将来私が本当に何ができるか分からなかったですね。私自身も分からなかったけど、私は仕事に就くことが決して私が楽しくやれることじゃないということ分かってましたから、そんなに心配してなかったです。でっかい世界に向かっていきたかったと思います。夢のない、闘う意味のない、そういう生き方はしたくなかったですよ」(『CHAI』二〇〇四年二月号)
大学で学んだのは、引き続き舞台美術だった。その後の人生を考えると、ここで学んだことは太い幹となり、葉をつけ、果実となる。
「みんなで素材やテーマについて話し合い、空間、時間、照明、見ている人の反応などについて考えます。プロポーザルをつくり、アイデアを発展させ、どうやってチームとして共同作業をするのかを学びます。演劇では、プロセス、提案、予算、制作、プレゼンテーションのすべてを把握することが求められます。そして何より大切なことは、劇場は〝時間〟を軸にしているということです。どうやって作品を時間軸のなかで見せるか。どうやって発展させ、物語を進めるか、どうやって観客と一体化するのか。すべては私の作品づくりの礎になりました」(『Cai Guo-Qiang』 Phaidon)
本格的に演劇を勉強したことで、蔡は新たな視点を獲得した。立体的に作品を見せること。止まった時間ではなく、流れゆく時間軸で見せること。観客に作品を「体験」「体感」させること。制作のプロセスを見せること。この世界のすべての場所が「劇場」になり、人でもモノでも事柄でも何もかもが作品になる——。
当時、多くの前衛芸術家や蔡の友人は、ヨーロッパやアメリカに強い憧れを持ち、西洋的な作品づくりがブームともいえる様相を呈していた。それに対して蔡は、あえてそういったムーブメントとは一定の距離を置いていたようだ。
考えてみると不思議だ。やっと自由な芸術活動をしようというグループが現れたというのに、なぜその輪に飛び込まなかったのだろう。
「中国の〝新しいアートシーン〟に対するちょっとした抵抗感がありました。あのころは誰もが西洋のアートに興味を持っていました。特にヨーゼフ・ボイスとかアンディ・ウォーホルとか」(前同)
アンディ・ウォーホルは、マリリン・モンローやマイケル・ジャクソン、キャンベル・スープの缶など、アメリカ文化のアイコンを使い、カラフルな作品に仕上げたポップアートの巨匠だ。
もうひとりのヨーゼフ・ボイスは、すべての人はアーティストであると考え、ひとりひとりがアートや創造活動に参加することによって未来の社会をつくり上げる「社会彫刻」という概念を構築したドイツ人である。環境や社会といったテーマをアートと関連づけ、実践することを重視し、作品《7000本の樫の木》ではドイツのカッセル市に樫の木を植樹するプロジェクトを行った。またアメリカの画廊のなかでコヨーテと一緒に一週間を過ごし、徐々に自分とコヨーテが一体化していく《私はアメリカが好き、アメリカも私が好き》という作品も有名である。しかし、そういった欧米発の新しい美術の動きは、蔡の心にはまるで響かなかった。
「ウォーホルのポップアートを見ても、自分の人生との間に広がる膨大な距離しか感じませんでした。ウォーホルの物質主義や商業主義への批判は中国にいる人間とは無関係でした。私たちは、当時ちょっとした品々を買うために長い行列をつくっていました。だから、ウォーホルの作品とは、何も対話すべきことがなかったんです。そして、ヨーゼフ・ボイスが発した環境への懸念もまた、当時の自分とは関係のないものでした。一歩家を出れば緑の山や魚を釣ったり泳いだりできる美しい水辺がありました。家の庭にも魚が泳ぐ池があり、動物や犬がいました。もちろん、その後の中国では物質主義や環境破壊が問題になっていくわけですが、当時は、それらのことは、〝いったい自分たちにどんな関係があるんだ?〟という感じでした」(前同)
そこで蔡と紅虹は、旅に出ることにした。遠い外国の作品に恋い焦がれるのではなく、自分の生まれ育った国の文化や歴史を知りたかった。文化も信仰も古いものはすべて破壊することしか許されなかった〝失われた世代〟に育った蔡は、そういった歴史や伝統文化を学ぶチャンスがなかったのだ。
一九八二年から八五年にかけて、夏になるたびにカバンに画材を詰め込んで、紅虹と長い旅をした。駅舎で眠り、ときには通行証を偽造し、ふたりはウルムチ在住の兄妹ということにして検問所を突破した。
チベットや灼熱の砂漠、シルクロードの街、仏教遺跡や壁画を見ながら、光と風が溢れるたくさんの油絵を描いた。出会った人々の姿、食事など、その心を動かされたすべてを描き、地元の人々にプレゼントすると、とても喜ばれた。
火薬で絵を破壊する
砂漠や山を歩き、旅をしたことで、蔡の作品の方向性は急カーブを描くように変化した。近隣の山で石や木の根を拾い、アトリエに戻ると、じっと見つめた。
自然は、人間にはコントロールできない——。
そう改めて感じていた。木々は大地に根を張り、強い風はすべてを吹き飛ばし、砂漠は生き物の痕跡を消し、宇宙の果ては想像できない。そういう、圧倒的な自然の力を作品に取り込みたかった。
蔡は太古の石刻(せっこく)や海岸の岩、樹の根などから直接拓本を取り、作品の一部にしてみた。自然界のものには、始まりも終わりもない。そこにはただ歴史の烙印(らくいん)と無限の生命力があると感じていた。次々と新たな作品が生まれた。しかし、まだ何かが足りないという感触も覚えていた。
ある日、蔡はふと思いつく。
そうだ、火薬はどうだろうか?
中国で発明された火薬は、ごく身近な素材で、しかもメッセージ性の強いものだった。泉州では、誰かが生まれても、結婚しても、亡くなっても爆竹の音が街角に鳴り響いた。人生のあらゆる祝福に使われる一方で、戦争や殺戮(さつりく)の道具でもあるという矛盾を孕(はら)んだ存在であることにも惹かれた。
そして近所の子どもたちは、学校から帰るとよく爆竹をつくり、家計を助けていたので手に入りやすかった。
試してみよう。
最初はキャンバスに向かってロケット花火を発射してみたが、結果はいまひとつだった。次に、火薬そのものをキャンバスの上に乗せ、火をつけてみた。
ボン! という激しい爆発が起こり、煙が部屋に充満した。キャンバスを見てみると、そこには火の痕跡がまざまざと残っていた。その不規則な黒い焦げ跡は、蔡の心をしっかりとつかんだ。
これだ。
「火薬は宇宙のエネルギーを象徴するものです。見えるものを使って見えないものを表現するのにふさわしかった。火薬は永遠と瞬間、時間と空間を曖昧にして、混沌をつくってくれるのです」
火薬の魅力について蔡はそうアーティスティックに説明するが、実はもっと切実でわかりやすい理由もあったようだ。
「自分の父親は真面目で、あまり大胆な性格ではなかった。私自身も父親と同じで、真面目でコントロールすることが好きでした。真面目なのは人間として悪くないのだけれど、アーティストとしてはあまりよくない。アーティストにはおかしい部分も必要です。だから、自分にはコントロールできないものが欲しかった。火薬は私を解放してくれるための起爆剤でした」
それまでの生き生きとした色彩は姿を消し、闇夜の疾風のごとく渦巻く黒が絵画の主役となった。
蔡は、それまでの自分の絵を破壊したかった。
コントロール不能な巨大な火のエネルギーで、絵をそして自分自身を生まれ変わらせたかった。炎と爆発のあとの不気味な暗黒、太古から引き継いだ光と闇にこそ、自分の未来があると信じた。それは、パブロ・ピカソが、サルバドール・ダリが、ジャクソン・ポロックが、その他の数え切れない数の芸術家が自分のそれまでのスタイルを捨て、覚悟を決めてキャンバスに向かい合った瞬間に似ていたかもしれない。
蔡は、ひたすら孤独な実験を繰り返した。ときに実験は予想を超える大爆発を引き起こした。誤ってキャンバスに引火してしまったときは、祖母がアトリエに飛んできた。
「おばあちゃんがすぐに足を拭くマットを濡らしてもってきて、すぐに火を消してくれました。それを見て、アーティストは火薬を点火するだけではなく、火を消すことも仕事なのだとわかりました」
最初のころは、花火をばらして使っていたが、コストがかかりすぎるので、爆竹工場に火薬を買いにいった。工場からの帰り道、胸に何キロという火薬を抱えて長距離バスに乗り込むと、他の乗客がタバコを吸い始め、ひどく緊張した。
万が一タバコの火が火薬に移ったら大爆発だ。そうしたら、自分も他の人々も粉々になって死ぬ——。
そんな危険な物だからこそ、その力に惹かれていた。こうして、蔡のアートの神髄ともいえる表現、火薬画がこの世に生まれた。
あの麗しき中国
話はそれるが、中国は私が人生で最初に訪れた異国である。「中国」と聞いただけで、いまでも懐かしさで胸が疼いてしまう。それは一九八七年の三月で、私は一五歳で中学校を卒業したばかりだった。
旅の目的は、日中の国交回復一五周年を記念して合唱曲を歌うこと。日本と中国の小学生を歌で交流させるというプログラムだった。外務省や国際交流基金が支援するようなオフィシャルな活動ではなく、公立小学校の保護者が中心となった泥臭い草の根活動だ。そして、活動の中心人物のひとりが、PTAの役員だった私の母だった。
きっかけは私の妹が小学三年生のとき、同級生の保護者に中国と縁の深い人がいたことだった。PTA活動などを通じてその人と親しくなった母や音楽の先生は、合唱団を中国に連れていこうと盛り上がったらしい。
彼らは二年以上をかけて準備を進め、子どもたちに中国語の歌を教え、中国側と様々な交渉を行い、寄付金や助成金をかき集めると、小学生や保護者、一〇〇人以上を連れて、北京に飛び立った。基本的には小学生向けのプログラムだったが、ピアノを弾くことができるという理由で私も参加することになった。私は、高校受験で希望の高校に入れず、何もかもに毒づきたい気分だったが、結果的にはそんなモヤモヤを吹き飛ばすには最高の一週間となった。
当時の北京は、まさに異郷だった。
空港から市内に入る道は広い泥の道で、土ぼこりが舞う並木道の向こうには地平線に沈む夕日が見えた。その鮮やかな赤さは、いまもくっきりと記憶に刻まれている。
翌日から私たちは、天安門広場や万里の長城、紫禁(しきん)城、小学校の校庭や音楽ホールなどに出向き、日本語の歌と中国語の歌を披露した。一五歳の私は、歴史が刻印された情緒ある風景に完全に心を奪われた。石造りの古い家々、立派な四合院(しごういん)、薄暗い夜の町、どこまでも続く万里の長城、そして毛沢東の巨大な肖像画。町ゆく男性の多くは人民服で、女性たちも作業着のような地味な服を着ていた。すべてが、映画のなかにトリップしたように美しく見えた。
私たちのバスが目的地の小学校に到着すると、真っ赤なスカーフを首に巻き、頬を赤く染めた子どもたちが「훑烈뻑迎!」と描かれた旗をちぎれるくらいに激しく振ってくれた。心が震えるような瞬間の連続で、私は旅や音楽、体験することの喜びを知った。
その傍で、大人たちが「あれって公安かしら」と心配そうに話していることも聞き逃さなかった。私たち一行が歩くあとには、必ず人民服の男性がついてきた。〝こうあん〟って何だろう? スパイみたいなものかなあ……。
とにかく、その七日間が、私の人生の航路を変えたように思う。行けもしない中国の辺境のガイドブックを何時間も眺め、中国人を見ると話しかけたくなった。
そんな三〇年前の中国行きの思い出を、蔡にも話したことがある。
「そうですかあ! そんな昔に中国に行ったんですか!」と蔡は笑顔になった。「あなたのお母さんは、とーっても強い人ですね!」
そして、一五歳の私が中国に行く四ヶ月前、奇遇にも二九歳の蔡は、入れ違いに日本に行く準備をしていた。
このころ、中国では私費留学が可能となり、大勢の若者がどっと海外に出た。蔡も友人の助けを借り、日本行きの学生ビザを取得した。
どうして日本を選んだのですか、と蔡に聞いた。
「日本を選んだわけではありません。選べなかったです。知り合いが日本の学校を紹介してくれたので、日本に来たんです」
その言葉には、日本に来たのはただの偶然だった、というニュアンスが読みとれた。どうやら彼は日本に長くとどまるつもりはなかったらしい。日本に行くことは、それまでのシルクロードなどの旅の延長線にすぎなかったという。
貯金もさしてなければ、仕事の目処も立っていなかった。
しかし、「銀座」という場所に行けば画廊が一〇〇〇も並んでいるらしいので、絵を売れば暮らしていけるだろうと考えていたそうだ。祖母の愛柑は、旅立つ蔡のために護符を用意してくれた。
出発の少し前、蔡は火薬と油彩で幅三メートルもある絵画作品をつくった。タイトルは《翳:庇護のための祈り》。かなり陰鬱な雰囲気の作品である。
キャンバスの左側には小型飛行機と柱時計が描かれ、空には黒と金色が入り交じった雲のようなものがたなびいている。時計の針が指すのは午前一一時二分。それは、アメリカのB29が長崎に原爆を投下した時間を表していた。飛行機の下には、骸骨(がいこつ)のような人影も見える。そして、キャンバスの右側に、亡霊のように浮かび上がる若い男は、蔡本人だ。
出発前の心境を表しているのかもしれないが、旅立ちの高揚感や明るい希望はまるで感じさせない。
一九八六年の冬、蔡と紅虹は「一〇〇〇の画廊」と「原爆」の国に向かった。のちに、蔡の親しい友人となる美術評論家の鷹見明彦は、来日したころの蔡の異邦人ぶりをこう表現する。
「日本の現代社会に関する情報もないままに昨日の世界からタイムマシーンでポストモダンな後期資本主義の渦中に降り立ったという状況が伝わってきた」(『美術手帖』一九九九年三月号)
蔡がタイムマシーンで降り立ったのは、バブル景気が到来する直前のギラギラした東京だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第五章は明日午前七時に公開します。
書籍でお読みになりたい方はこちらからどうぞ。
空をゆく巨人 目次
プロローグ
はじめに
第一章 生まれながらの商売人 いわき・一九五〇年
第二章 風水を信じる町に生まれて 泉州・一九五七年
第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす サンフランシスコ・一九七六年
第四章 爆発する夢 泉州・一九七八年
第五章 ふたつの星が出会うとき 東京・一九八六年
第六章 時代の物語が始まった いわき・一九九三年
第七章 キノコ雲のある風景 ニューヨーク・一九九五年
第八章 最果ての地 レゾリュート ・一九九七年
第九章 氷上の再会 レゾリュート・一九九七年
第十章 旅人たち いわき・二〇〇四年
第十一章 私は信じたい ニューヨーク・二〇〇八年
第十二章 怒りの桜 いわき・二〇一一年
第十三章 龍が駆ける美術館 いわき・二〇一二年
第十四章 夜桜 いわき・二〇一五年
第十五章 空をゆく巨人 いわき・二〇一六年
エピローグ いわきの庭 ニュージャージー・二〇一七年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
