
[投稿|トーク]小林健太「#photo」を巡って|小林健太×荒川徹×飯岡陸×大山光平(G/P gallery)


「#photo」Installation View(G/P gallery). Courtesy of G/P gallery, Tokyo
小林健太の個展「#photo」(G/P gallery)会場にてトークイベントが行われた。小林はインターネット世代、ストリート、シェアハウスである渋家などのキーワードをきっかけに話題に挙がることが多いが、今回のトークでは、ゲストである荒川徹氏からの「画像加工における工学的劣化」という問題提起をきっかけに小林の作品の可能性について批評的に議論する内容となった。構成の関係上掲載することができなかったが、トークのイントロダクションとして、G/P galleryディレクターの後藤繁雄氏より小林の作品について紹介が行われた。またそれ以外にも小林の作品をどのように位置付けるか、印刷とモニターの間でどのように解像度の変換が行われるか、また会場とのやりとりがあったが、構成上小林と荒川の対話を中心に掲載する。
image all rights ©Kenta Cobayashi
画像加工における工学的劣化

[fig.01]Amusing, #liquify , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo

[fig.02]Pink and Blue, #blur #sharpness , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo

[fig.03]Phone (God Scorpion), #smudge , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo
飯岡 今日はゲストとして、セザンヌやミニマリズムについて研究されている荒川徹さんをお呼びいたしました。最近では『現代思想』1月号にミニマリズムと建築についての論文を発表されています。小林君の作品は同時代的な語られ方をすることが多いのですが、もう少し広いパースペクティブで小林君の作品を捉えなおすということが必要なのではないかと思っております。本日はよろしくお願いします。
荒川 ありがとうございます。荒川徹と申します。小林さんは渋家出身と聞いております。渋家といったら、都会の渋谷のシェアハウスですよね。僕はそもそも今、田舎の一軒家に家族と住んでいまして。「逆」渋家ですよ!(笑)環境が全く違うので、どういうふうに論じたらいいかなと。でもとりあえず小林さんの技法のみに注目すると、ちゃんと考えられるんですよね。まずはですね、広いパースペクティブを求められているんですけれど、非常に狭い話をします(笑)。お話ししたいのは、端的に言ってしまうと、デジタル画像で加工すると必ず劣化するってことなんですね。もちろんすごい暗い写真を明るくしたりする場合に、元となっている画像よりもよく見えることはあるんです。ですが、それを一回やってしまうと、もとには戻らないんです。そういう加工していくほどに劣化していくプロセスを、劣化ではない方向で捉えているのが小林さんの方法論なんだろうなということを考えてみたいんです。
まずはじめに、写真っていうのは工学的に考えると射影(プロジェクション)されたものです。哲学の記号論の中では、指標(インデックス)、対象を指し示す記号としての特性を持つと言われてきました。現実に三角形ABCが立体としてあった場合、撮影行為を通して、小さいA’B’C’という二次元の画像に変わるんですね。現実が二次元の画像に変わる。例えばプロジェクターで画像を投影するときにイメージが台形になるように、三次元のものを二次元にすると形が変わるんです。しかし、その変化は物理的に厳密に法則化されているので、理論的にはその台形も補正できる。ところがそれを加工すると、全体の法則が変わるんです。物理的な相関関係が壊れてしまうわけです。圧縮されていないRAWデータという、情報量が豊かな形式があります。でもそれをjpgの形式でコンパクトにすると、色調の幅が減り、解像度が下がり劣化するんです。過剰に加工された写真というのは、美や自然に価値を置くような美学的な観点から見れば全く真逆の方向です。非常に人工的で、貧しいということになる。いわゆる芸術分野でも、Photoshopを使った画像加工っていうのは主に、加工の痕跡を排除して虚構をでっちあげるという方向に向かう。広告写真だったら、全く会っていない2人を1枚に収めたりしているわけです。そういう加工された画像を単なる劣化と捉えることのない可能性に導くことはできるのだろうか、という問いを立ててみたい。
小林さんの作品を見ていくと、一番特徴的なのはPhotoshopの指先ツールです。それを使うと筆跡みたいなのができるわけですよね。画像が液状化するみたいに、質が変化していくんですが、それが非常に絵画的な感じがする。元のソースを持ったまま、抽象性がつくられる。あと、ぼかした後に過剰にシャープをかけることを通じて、等高線のようなRGBのラインを炙り出す。等高線って普通は地図の山の高さとかを表現するものです。しかし小林さんの作品における等高線的なラインは、オリジナルの起伏がないから光学的な情報だけを頼りに立体化しているわけです。地図って、普通2枚以上の写真をステレオで撮って奥行き情報を出しているんです。でも、1枚の写真だけだったら完全に偽の等高線であって、全くオリジナルの光景には基づかない。オリジナルの現実には基づかないけれど画像のみによる立体感として出来ている。起源が現実ではなくて画像からのみ発生しているということです。また、そういったエフェクトを部分的にレイヤーで分けている画像もあります。つまり、複数の解像度と複数のモードがある画像ができるわけです。
ソース画像と加工

[fig.04]Moray, #smudge , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo

[fig.05]Denny’s, #smudge , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo

[fig.06]H&M, #smudge , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo
荒川 あくまで現実から出発するんだったら現実を再現する方向に向かう。でも、そうじゃないやり方って、いかようにも着地できる感じがあるんです。小林さんに聞いてみたいようなことって、例えば元画像からどんな要素をピックアップするか。加工と元の画像との間の関わりはどのようにあるのでしょうか?
小林 なんていうか、下にある意味性みたいなものを少しずつ消していくっていうか。ソースは、例えばH&Mのロゴや、デニーズの看板だったりするんですけど、元を知っている人はそれを想像することもできるけど、画面自体は抽象化している。
荒川 ありがちな落書きとして、まず目線を消すっていう像を打ち消す方向。あと政治家のポスターの鼻に画鋲で穴を開けるような、像をなぞる方向。そのどちらにも陥らないやり方というと、人物の形や書かれている文字に対してではなく、その人の体勢とかその場所とか画像として見えている全体を掴んでやることになりますよね。例えば本を見ている男性の、彼の姿勢[fig.04]。本を読むってすごくスタティックな行為をしているのにすごく動きが感じられる。目線を消しているんだけれども、単にそういう落書き的なものだけじゃない。このポーズ自体を動きとしてもう1回作り直すみたいなところもあるのかな、と思うんです。
小林 そういう感じは結構あるかもしれないですね。
飯岡 ピンク色の女性の写真[fig.02]で言うと、その上に重なる等高線の形態は、女性の耳の形と類似していて、響き合うになっていて。ソースとなる画像の形態に反応するように、加工が行われている。
荒川 あと、H&M、筆致がなんとなく「&」の形態を繰り返しているようなところもあって[fig.06]。小林さんが使われている「写真とコミュニケートする」っていう言葉は、写真を何かを読み取って何かを与えるといったようなものというよりは、写真全体のノリを掴む行為に近いのではないかと思います。要素を拾うっていうことも含めて、身体で写真と向き合って写真と応答する、っていうことになるんですかね。
小林 行為をバインドしたいという感じがあって。写真を撮るときの行為って、被写体とのコミュニケーションがあったり、構図を決めるために身体を動かしますよね。そういう動きと、写真を編集するときの速度感をすりあわせていくっていうか。そこでは写真とのコミュニケーションがあるんですよね。
荒川 写真において動きがどうやって判断されるかっていうと、基本は手ブレや動きのブレですよね。でも、男性の画像[fig.04]、右側がブレているんだけれど、このブレに頼りきっていない。この男性の右側をブレさせただけで編集を終わることもできたと思うんですよ。でもそこで、単に動きを付けて終わりというわけではないわけですよね。
シャッターを押す指、編集する指

[fig.07]Untitled, #smudge , 2015

[fig.08]Untitled, #smudge , 2015

[fig.09]Untitled, #smudge , 2015
小林 指が大事な気がしていて。写真って実際の行為は、いろいろ身体を動かすにしても、ボタンを押し込むっていうそれだけで、そのボタンを押し込むっていう行為と、出て来た画像との間に、動作的な分断がある。その感じが面白いと思っていて。一方編集では指先と、そこから延びる筆致に連続性があって。
飯岡 今回の展覧会では指が強調されているのではないかと思いました。小林君は筆致の終わりが絵画の筆のようになっているイメージ[fig.07, 08, 09]を作っているんですが、今回はそういったイメージは展覧会に展示されていない。今回の展覧会に出している作品っていうのは、筆致の終わりが丸くなっていて、指先ツールで操作したように見えるものに縛られている。もう少し飛躍して言うと、指先であると同時に紐でもあるのではないかと思っています。例えばH&Mの作品に対して感じるのは、紐の絡まりに似ているということです。紐と紐が重なって、重複によって情報量を増やしている。紐の絡まりのような解けなさを作っているのではないかと。
小林 それはレイヤーの概念を拡張した考えかも。Photoshopのレイヤーっていうのは、水平に積み重なっているので、階層がはっきりしていますけど。紐は部分的に階層構造になっているけど、はじっこは繋がっていて、伸ばせば一枚になる状態が生まれる。指先ツールの面白いところは、ぬるっと伸びていくっていうか、ベースとなったレイヤーと緩やかに繋がっている、その、半分浮き出て半分埋まっているみたいなところかもしれないですね。
飯岡 トークの始めに、写真が世界と相似関係にあることを記号論では指標(インデックス)と呼ぶという話がありました。C・S・パースが論じた、記号を指標(インデックス)と類似(イコン)、象徴(シンボル)に分けるという考え方ですよね。写真論でよく出てくるのは指標(インデックス)と類似(イコン)の対比です。指標(インデックス)に分類されるのは、写真やタイヤの跡のように物理的な痕跡として現実の世界と相似関係にあるもの。それに対して類似(イコン)に分類されるのは絵や地図など現実に「似ている」ものです。これは物理的な対応にはないんだけど、似ている、ということによって繋がりを持っている。小林君の作品は確かに指標(インデックス)の側面は劣化しているのですが、別の側面、類似(イコン)のレベルで別のものに似ているということが起こっているのではないかと思うんです。グーグルのトップページに自分の持っている画像を読み込ませると、それに似た画像を検索して見せてくれる画像検索という機能があります。これで部分的に小林君の作品の一部を検索をかけてみると、陶器や服の縫い目の、編み物、CDのレンズみたいな、構成物がたくさん出て来るんです。他にはタイヤのホイールのような金属の画像が出てきたり(実際に会場で検索して会場に見せる)。別の画像や構成物に似てくるっていうのも、ひとつの画像の情報が豊かになるということなのではないかと思うんです。
荒川 (google検索は)画像からパターンを拾って、自動認識して、出自が異なるけど、同じパターンを持った画像を見せてくるっていう。デジタル写真を引き伸ばすと、情報的にはタペストリーのようなギザギザした画像のレーンなわけですね。
飯岡 等高線みたいなイメージは、植物の細胞を顕微鏡で見たことを思い出したりして。結晶や壊れたCDディスクの表面みたいだなと。
小林 そうですね。手法は今の所大きく二種類に別れてて。ひとつは指先ツールみたいに直接触れて変形させる接触タイプと、非接触で、フィルターを過剰にかける、結晶みたいにほっとけば集まるような、現象タイプと呼んでいるもの。
画像編集における完成、写真における未完成

[fig.10]Orange Blind, #smudge , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo

[fig.11]Shopping Mall, #smudge , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo

[fig.12]Sleeping, #smudge #splay , 2016. Courtesy of G/P gallery, Tokyo
荒川 画像編集は終わりがないとか言われますよね。僕も画像編集することがあるんですが、どこでやめるかって、直感的なものですね。僕にとっての終わりは、画面が飽和したと考えるタイミングです。どこも死んでいないし、ひとつの新しいバランスができている。元の画像に依拠しない、新しいバランスができていると感じた瞬間に手を止める。つまり画像は編集を通す時点で必ず劣化してしまうんですが、新しいバランスが生まれると復活したように感じる。小林さんの場合、その復活の契機はどこにあるでしょうかね。
小林 イメージが結晶化する現象タイプは、特に劣化した画像が復活するって感じがありますね。例えば、小さなサイズの画像を大きな印画紙に印刷しようとすると劣化しちゃう。1ドットと印刷の一番小さい単位、インクの1粒みたいなものが対応しなくなる。そういう状況で現象タイプは特に生きてきて。データ上で画像を引き伸ばすとして、それがアンチエイリアスがかかるような設定だと、巨大にするほどイメージがぼけてくる。そこにシャープネスを何重にもかけると、今回展示した作品の、等高線の原型のようなディティールが浮かび上がってくるんですよね。そのディティールの最小単位を、印刷の最小単位と合わせることは可能で。それはまさに、劣化したデータから新しい生命というか、劣化したものではないものが出てくるような、蘇生のような感じがありますね。
編集の終わりどきに関してはですね。指先ツールで作業していて、最初はこう、写真の要素を引き延ばしていくんですけど。それを続けると画面が筆致に埋め尽くされていくんです。筆致から、筆致を産まなきゃいけなくなる瞬間がくる。そうなったときには、もう止めどきって感じがありますね。
あとは、未完成の写真ってどういう状態かなあというのを考えていて。絵画は塗り残しがあるみたいな、未完成であるっていうことが絵画言語として成立していると思うんです。写真はシャッターボタンを押すとあっという間に完成していて、普通はその中間というか、未完の状態にアクセスできない。これはもしかしたらデジタル特有の問題かもしれないですけど。そういう中で、僕が扱ってる写真において、未完成の状態はなんだろうって。編集によってそれを目指している感じはあるかもしれません。同じ写真をベースにしても、複数のバリエーションがあるんですけど。それは完成を目指していないからこそ可能になってるっていうか。
大山 最近小林の写真集の出版に向けてやり取りを何度もしているんだけれど、打ち合わせをするたびに彼の出してくる編集の印象が変わるんだよね。だからなかなかこれでオッケーっていう判断がむずかしいんだけど、その流動的な状態が非常に面白いなあって思っていて。 彼は日頃ブログを頻繁に更新していて、そのトップページはその度に変化している。一方で本は通常固定化された状態で提示する必要があるっていうことに改めて気づかされて。だから今回の本は拡張可能な本ということをテーマとして、ある意味未完成な状態を肯定した形にしたいと思ってる。イメージはもちろん、本やブログ、プリントという形態もアウトプットのバリエーションのひとつでしかなくて、それぞれが上書きされていく可能性を持って常にパラレルな状態を保っている。
荒川 つまり下書きから始まるんじゃなく、下書きになっていくっていうことですよね。
小林 そうです、そうそう。完成品しか手に入らない写真っていうものを未完成にするには、時間を遡らなくちゃいけなくて。それが結構面白いなあって。指先ツールで画像をゆがめていくのは特にそういう感覚があるような気がします。
荒川 その本来成立していったものを、もう一回移動しなおすというか、ずらすんですよね。極端な話をすると、小林さんの作品にはある意味「中身がない」っていうことなんですよ。これは良い言い方でね。肖像写真で、その人の内面を喚起したりするようなセッティングをどうするかとか、風景を見たときの記憶に迫るとか、全然そうじゃないんですよね。起源に戻らないで、写真というメディアでどうやってまた経験するかっていうことの方に進んでいるんですよね。
小林 トークが始まるまえに、荒川さんとiPhoneのカメラアプリでお互いの顔を入れ替えたりして遊んでたんですけど。それって別にもう、なにか被写体を正確に再現するみたいな目的はもうそのアプリにはなくて、この編集面白くね? みたいな。そこになにか表現があるわけでないっていうか。別に顔が入れ替わっていることに意味があるわけではなくて、ただそれが楽しいみたいな。それってなんかこう、テクノロジーと人間の関係の本質的な姿っていう感じがするんですよね。
荒川 初めて鏡を見たとき、みたいな。
小林 そう! その根源的な喜びって、初めて写真を撮ったときの喜びも同じですよね。ボタンを押したら目の前の光景が写るっていう、その喜び。
大山 これまでの写真はロラン・バルトが『明るい部屋』で述べたように「かつて、ここにあった」という現実世界のリプレゼンテーションだったわけだけど、小林にとって写真それ自体が現実の一部なんだよね。それがグラフィティーのウォールみたいな役割を持っていて、その上に書き加えていく対象になっている。画像の時点では物理的に存在しないから、その行為は光学的に劣化を促しているといえるんだけど、イメージとしては乗算だよね。そういった意味では、写真家の横田大輔もフィルムの物理的な劣化とイメージの乗算を同時に行っていて、デジタルとアナログで手法は全く違うけど、共通項を見出せる。
荒川 打ち合わせで小林さんと話していたときに、小林さんは、ゲルハルト・リヒターをプリクラと結び付けるというか、同一線上に乗せちゃうわけです。プリクラはコミュニケーションベースの(解像度が)貧しい行為だけれど、ゲルハルト・リヒターをPhotoshopでできるじゃん! みたいな事が、同一線上に乗ってることが、多分小林さんの特有の感覚なんだろうなと。ある種のB級的なもの、非常に解像度が粗くてコミュニケーションベースなものと、アートフォトグラフィーみたいな非常に完成されたものとのどっちとも言えないような感じ。後者だったら、筆のぼかしによる技法というのをいろんなバリエーションで試すのが今までのあり方だと思うんです。指先ツールなんて、Photoshopを使ったとき初めてやるようなことで普通、2週間ぐらい経つとやらなくなるんですよ。でもひとつの道を達成するみたいなやり方じゃない、むしろ最初写真を伝ってコミュニケートしたときの初期衝動を持ち続けている。
飯岡 作品に中身がないっていう話は、例えば絵画は、その絵画性を強調すればいいし、写真はその写真性を強調すればいいっていう所謂モダニズムの方向に進みがちだと思うんです。でも小林君の作品はそうはなっていない。複数のメディア、媒体の間にある差異を見せていくような感じ。
小林 そうだね。作品を作る上でもよくコラボレーションするんですよね。プログラマーやデザイナーといった、エンジニアと組んだとしても、自分の見えてるイメージを正確に実装してもらうっていうやり方ではない方法を探っていきたくて。自分っていうメディアを超えて、他の人との間にあるものを作っていくっていうか。
荒川 内面とか記憶みたいなものをベースに個人という主体を醸造させていくという完成主義とは全く違った方向があるべきだと思うんですね。写真のような表面をきっかけに全てが同時多発的に、コントロールの取れないようなやり方で共鳴するというか。
小林 そもそも写真が持っている速度感ってそういうものだって思っていて。メディアを限定しない、複製されたものである、っていう前提がある。だからこその流通の早さっていうのが写真の魅力だと思っていて。すごく力強い生命力があるなって。ネットが登場してから特に写真が、作家の手を離れて一人歩きしてるじゃないですか。タンブラーでリブログされたり、画像検索でどこかに行ったり、誰かが保存して自分のブログにあげたりする。元の文脈と違う文脈にすっと繋がっちゃったり、作者不明の状態で流通したりしちゃうみたいな状況がある。
作家性を超えたものとして筆致を考える
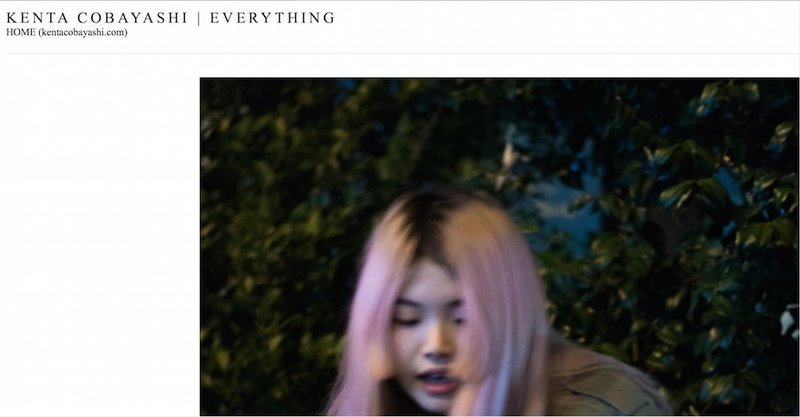
[fig.13]blog「everything」
小林 よくネットに上がってる写真で、右下とかに透かしでコピーライトが埋め込まれていることもありますけど。それの別の形態として、俺は筆致を埋め込んでいるんじゃないかなっていうのは思っていて。筆致っていうのは、サインみたいな感じで。絵画でも線に個人の人格が宿るみたいな考え方がありますし。俺オリジナルの筆跡っていうのが、そこに書き込まれるっていうような。半分幻想なんですけど、もしかしたら読み取れるのかもしれない、みたいな。
飯岡 普通のサインだったら、毎回自分の名前を書き込むっていうことになるんだろうけれど、小林君の場合っていうのは、反応みたいなものがサインになっている。サインっていうのは結局一個性のあるアーティスト個人が偉い、作家性の強調になるんですが、小林君の筆致には対象があって、それに対する反応からできている。
荒川 コピーとコピーが複数で起こっていて、ひとつに収束しないようにサインっていうものを考える可能性ってあると思うんですよ。要するに身元鑑定、身元同一するためではなくて、それはその中に偽装っていうものも含まれるかもしれないんだけれども、そういうものもOKってするような。もっと許容性のある形でサインっていうものを考えれば面白いんじゃないか。つまりオリジナルとコピーという関係ではない。コピーとコピーが干渉し合うような、そこにモワレを起こすようなやり方でオリジナリティ、サイン、アーティスト性というものを考えたらいいんじゃないかなと思うんですよね。
ヘルツォークが監督した洞窟壁画のドキュメンタリー映画があるのですが、面白いのは、最初熊が洞窟の壁に引っ搔き傷を残すんです。それを見た何千年後かの人間が動物の絵を描いて、それからまた五千年とか経ったあとに、別の人が動物の絵を重ねて描いたりする。つまり、今あるオリジナリティっていうのは、誰かが先にサインして終わりっていうような入れ方だけども、そうではない。何千年も超えて、人間と動物と、自然の形態がそれぞれのレイヤーに乗っかってしまうようなやり方で、作品を作りあげていく。それって現在のアイデンティティ概念っていうのを超越していますよね。例えば熊ががーって引っ掻いたときって、表現したいという意図ではなかったのかもしれない。でもそれを読み取った、あとの壁画を描いた人にとっては、それはもう表現だったわけですよね。
そういうやり方は小林健太っていう個人を超えて回収できないことも十分考えられるし、それが写真というメディア自体も超えていくということになりうるかもしれない。現代美術、あるいは近代美術をつくった作家性、作家がこれをやりましたという世界と、洞窟壁画の世界、ほとんどアイデンティティがないような世界の間で考えることがポイントだと思うんですね。どっちかに行き過ぎてもだめな気がする。全く個人性が排除されたものも、虚構だと思うんですね。なにか凄いものができたときっていうのは必ずひとり以上の天才がいる。チーム制作ですごいものができるっていうことは、大体天才がいるわけであって、完全に全く個人に依拠しないやり方で全く新しいものが立ち上がるっていうことはないだろうと思っているんですよ。だから、作家性に担保された個人を逃れた制作の在り方っていう経路があるし、それを指し示しているのかもしれないと思いました。
小林健太|COBAYASHI Kenta
1992年神奈川県生まれ。2015年東京造形大学卒業。東京で同世代のアーティストらと共同生活を送りながら、そこで撮影した写真を編集しブログに掲載している。5月に大山光平の運営する出版社NEWFAVEから、初の写真集『Everything_1』をリリース予定。巨大なZINEを様々なアーティストとコラボレーションして制作するMMGGZZNNプロジェクト主宰。主なグループ展に「Close to the Edge: New Photography from Japan」(MIYAKO YOSHINAGA、NY、2016年)「trans-tokyo / trans-photo」集美xアルル国際フォトフェスティバル(廈門、中国、2015年)、「The Devil May Care」(Noorderlicht Photogallery、フローニンゲン、オランダ、2015年)、「hypermateriality on photo」(G/P gallery Shinonome、東京、2015)、「The Exposed #7 」(G/P gallery Shinonome、東京、2014)など。
http://kentacobayashi.com/
荒川徹|ARAKAWA Toru
研究者・写真-映像制作。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。千葉商科大学、京都造形芸術大学通信教育部ほか非常勤講師。最近の論文に「「芸術」の終わり」(『現代思想』2016年1月号)、「ミニマリズムと写真」(『カメラのみぞ知る』ユミコチバアソシエイツほか、2015年)。作家として近年の参加展覧会に「カメラのみぞ知る」(タリオンギャラリー、2015年)。
飯岡陸|IIOKA Riku
1992年生まれ。東京芸術大学美術学部卒業、横浜国立大学都市イノベーション学府Y-GSC在籍。企画した主な展覧会に「EXPOSED#9 passing picture」(2015)、「Slipping Out of the Circuit 回路を抜け出して」(2015)。現在2016年夏に向けて次回展覧会を企画中。
大山光平|OYAMA Kohei
ZINEのオンラインプラットフォームparaperaを経て、出版レーベルNewfaveを設立。パリやロンドンなどのブックフェアに出展する他、展覧会やイベントの企画、執筆、ワークショップなどを行う。2012年に横田大輔と行ったZINEのワークショップで当時学生の小林健太と出会い、2014年にキュレーションしたグループ展「THE EXPOSED #7 」で初展示となる小林を起用。今春小林の作品集『EVERYTHING_1』をリリース(http://newfavebooks.com/everything1-kenta-cobayashi.html )。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
