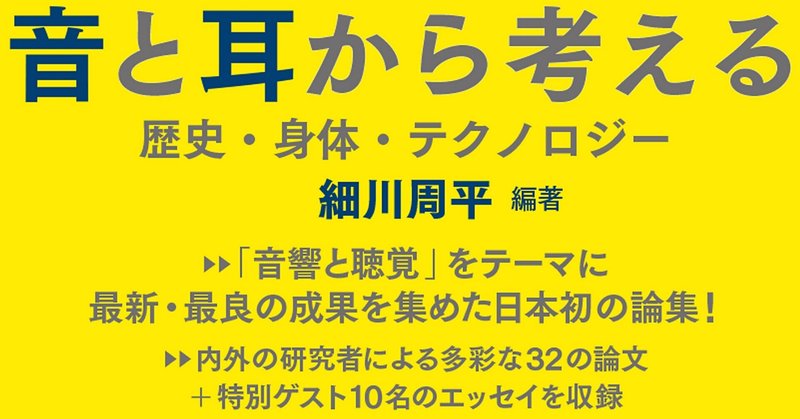
『音と耳から考える──歴史・身体・テクノロジー』から序文「音故知新 音と耳からの出発」細川周平|その8
第七部「ステレオの時代─聴く、録る、売る」は、日本でレコード盤とオーディオ装置が中産階級の生活に浸透した一九六〇年代から七〇年代に関する三つのモノグラフを集めている。その時代、ステレオはハイファイと並んで、オーディオ世界の輝けるキーワードだった。機械録音から電気録音へという三、四〇年前の転換期と同じく、新しい技術には反対者もいて、録音の音像に関する議論になった。またステレオ録音を可能にしたオープンリール式のテープレコーダーが家庭向けに開発されて、プライベート録音する趣味のサークルが生まれた(七〇年代のカセット・テープの発明はミニチュア化をさらに進めた)。最初の二編は聴く実践、録る実践に関するオーディオ評論家荻昌弘の活動を評価している。同時期にはステージ用の拡声装置が巨大化し、大音量・重低音が支持され、それに向いたダンス音楽、ディスコが生まれ、日本もその重要なマーケットだった。
福田(貴)論文は、荻の「ステレオ愛好者」としての顔を紹介している。彼はふたつのスピーカーの位相のずれが醸し出す「音の蜃気楼」を賛美し、否定論を完全に退けている。モノーラルの支持者には、ステレオの「立体感」は二台の映写機によるワイドスクリーン上映、シネラマと同じようなまがい物としか聴こえなかったのだが、荻は目をつぶり、純粋な聴覚体験のなかで「視覚的立体像」を想像した。福田は荻の耳が「自分自身でしかありえぬ音」を聴いていたと結論づけている。
金子論文は、荻の「生録応援者」としての顔を紹介している。七〇年代に携帯式のテープレコーダーが開発され、アマチュア録音のコンテストが開かれると、彼は現場の感情やユーモアを伝える作品に高い点を与えた。金子は「市民」という戦後民主主義の基礎概念が彼の一貫した評価基準だったと考えている。この二本の論考は荻だけでなく、オーディオ言説やアマチュアの録音実践を考え直すヒントになるだろう。技術開発に集中しがちな録音技術史に、利用の文脈についての考察を加えている。
テクノロジーを介した市民参加型の音楽コミュニティに関して、日高エッセイは短命に終わった録音担体、ミニディスクのファン世界に接近している。現在、骨董的な関心は、MD以前に主流を務めていたカセット・テープにも集まっていて、日高エッセイは参考になる点が多い。
輪島論文は、七〇年代に世界中に広まったディスコが、国際マーケットを意識したプロデューサーやゲートキーパー、ミュージシャンによってどのように現地化したのかについて論じている。日本製ディスコを売り込む際、「洋楽風を装っ」たり、「オリエンタル・タッチ」を加えたというエピソードは、洋楽と邦楽の境界が六〇年代のカバー・ポップスの時代以上に曖昧になっていたことを教えてくれる。洋楽の擬装から日本製の誇示へという流れから、著者は日本の業界内のディスコ・シーン、国際的ディスコ市場内の日本の位置を両耳的(ないしステレオフォニック)に見直している。(9に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
