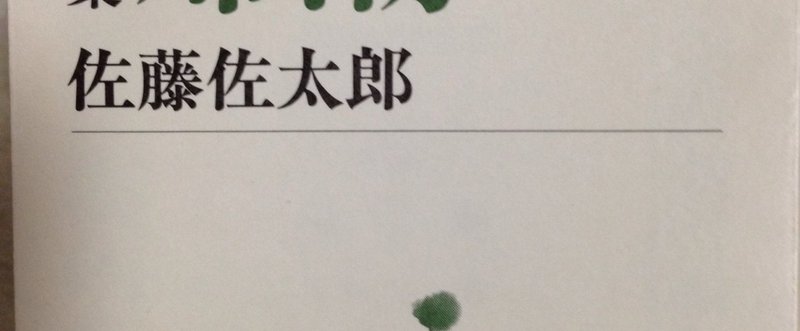
歌集を読む・その8
こんばんは。今日は古い歌集を扱おうとおもいます。佐藤佐太郎『帰潮』です。「きちょう」と読みます。1952年、第二書房刊行。第5歌集です。
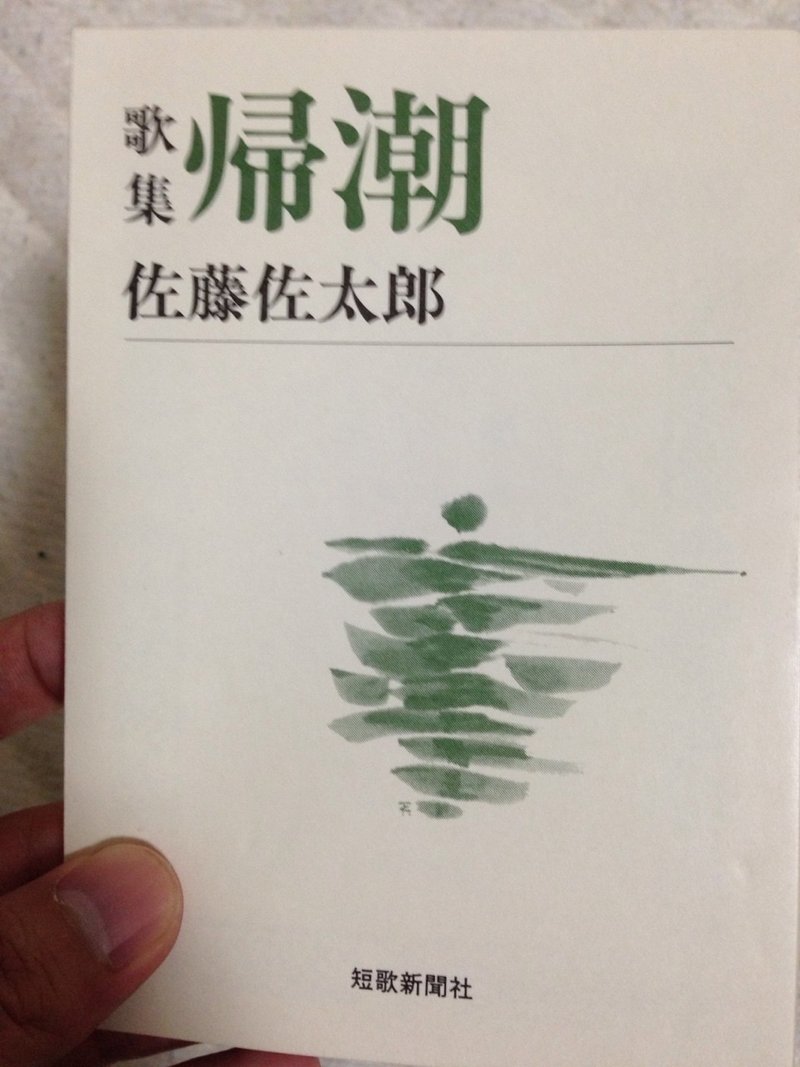
今回読むのは文庫版です。こちらは1992年、短歌新聞社刊行です。
佐藤佐太郎は1909年生まれ。 斎藤史と同じ年ですね。一つ上(1908年)に窪田章一郎、三つ下(1912年)に宮柊二。四つ下(1913年に高安国世、近藤芳美。ふむふむ。
※宮柊二、高安国世、近藤芳美の生年を勘違いして一つ下、二つ下と表記していましたが誤りだったので訂正しました。
この歌集は読売文学賞を受賞しています。「戦後の名歌集」と呼べる一冊なのでしょう。佐藤佐太郎はあとがきでかなりかっこいいことを言っています。
一般に表現は限定する事だといつてよいが、短歌に於いては、先づ感情生活の中から詩的感動を限定し、それを五句三十一音の形式に限定するのである。限定された直観像即ち詩的感動は、生のリズムとして意味に満ちてゐるけれども、その意味は概念的に抽象し証明することの出来ないものである。ただ何となく大切なかけがへのない感じとして胸中に置かれた生の核心である。このいはば意味なきものの意味に満ちた瞬間と断片の裂目から人間性の奥底とか生命のニュアンスとかいふものを見るのが抒情詩としての短歌である。
なんか硬質でかっこいい文章ですよね。「何となく大切なかけがへのない感じ」「意味なきものの意味」とか、わかる〜って感じです。
夕雲(ゆふぐも)の輝くごとき菊の花その比喩ひとつ抱いてねむる
佐太郎は茂吉の弟子だから、例のごとく「写生」とか「アララギ的」みたいな枠組みの中で語られたり印象つけられたりするんだけども、結構直喩でゴリッといくタイプだったりもする。そもそも写生が比喩や直喩、観念と対置して語られる概念でもないみたいですしね。
この歌は、菊の花が咲いているのを見て、それを夕雲が輝くみたいだと思った/思っているわけですね。そして、その比喩を心に抱きながら眠りへ落ちていく……と。これこそまさに「何となくかけがへのない感じ」ですね。「夕雲」がなんかいいな。輝き方に恩寵のようなものを感じられて、その比喩のおかげですこーしだけ安らかに眠れるような、そんなイメージで読みましたね。
さみだれのしげく降る時おぼろなる笹群(ささむら)みえて吾は居りたる
「笹群みえて吾は居りたる」、なかなかヤバい転換をしててスリリングですね。さみだれが高い密度で降っていて、おぼろに笹の群れが見えている、それまではちゃんと佐太郎視点で外を見るカメラだったのに、急に内省的に自分の存在の方へ目を向ける。
連結を終りし貨車はつぎつぎに伝はりてゆく連結の音
この歌とか、典型的な「助詞がテクい」系の歌ですよね。「貨車は」の「は」ね。よく見ると「連結を」の「を」もあやしい感じがする。ただ、こういうのってみんながあまりに褒めると、むやみやたらに助詞をねじりまくっとけばええやろみたいな理解を生んでしまいがちなので罪深いところではあります。
すごく文法上厳密に読んでいくと、「連結が終わった貨車」=「伝わっていく連結の音」である、という定義づけに読めますね。ただ、その定義づけ自体がけっこうアクロバティックだし、歌の色気が損なわれてしまうような感じもある。
「終る」も「伝はる」も自動詞ですよね。これが「終へる」「伝へる」だと恐らくだめなのでしょう。「貨車は」の「は」は、貨車を主題化している感じでしょうね。「は」を使うことで、貨車にフォーカスが当たる。
この歌の場合は、佐太郎の意識が、貨車の内部に代入されて、貨車と一体になったために、「終る」「伝はる」などの自動詞的な動詞が選択されている、と考えてみるのもいいかもしれません。
どちらにせよ、ある種のちぐはぐさが、「生命のニュアンス」の部分として響いている歌でしょうね。不安定な助詞、あるいは自動詞の使い方をしているんだけど、ここから言葉が動く気がしないというか。妙なバランスで立ってるジェンガみたいな。
かたむける月の光に照らされてわが庭のものみなたけ高し
秋分の日の電車にて床(ゆか)にさす光もともに運ばれて行く
みづからの光のごとき明るさをささげて咲けりくれなゐの薔薇(ばら)
佐太郎は光の歌がいいです。月光のパワーによって、「うおお、うちの庭のものみな丈が高ぇ!!」みたいなことを思ってる一首目。下の句の細かいリズム展開と、「だから何やねん」感がすきですねえ。
秋分の日の歌は、言わずも知れた名歌ですけれど、やはりこれは「光も」じゃないとだめで、「光と」だとナルシシズム全開になってしまうわけです。短歌という詩型のサイズ感にかっちり言葉の分量がはまってる感じ。何かとともに輸送される歌で、この歌のようなレベルで簡潔であり、しかし確かな味わいのある抒情を作るのはかなり難しいでしょうねえ。憧れるけれど。
薔薇の明るさを「光のごとき明るさ」と言っているのも、かなり攻めた表現だとおもうんですよね。ある意味何も言っていないし、陳腐に見える。でもこの歌キマってるんですよね。たとえば、「みづから」「ひかり」「あかるさ」「さけり」「くれない」と、kとrの子音の連続ですね。日本語ラップは母音で踏むけれど、短歌は(無意識レベルで)子音で踏んでることが多いのかもしれません。それがフレーズや一首の強度をつくる。もちろんこれだけじゃなくて「ささげて咲けり」とかも韻律的なフックになってますよね。佐太郎はこういう一首の意味以外の部分の構築がめちゃくちゃ上手いと個人的には感じていて、文語の中でもかなり読みやすいので、おすすめです。岩波文庫でも出てて手に入りやすいですし。
それでは今日はこんな感じで終わりましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
