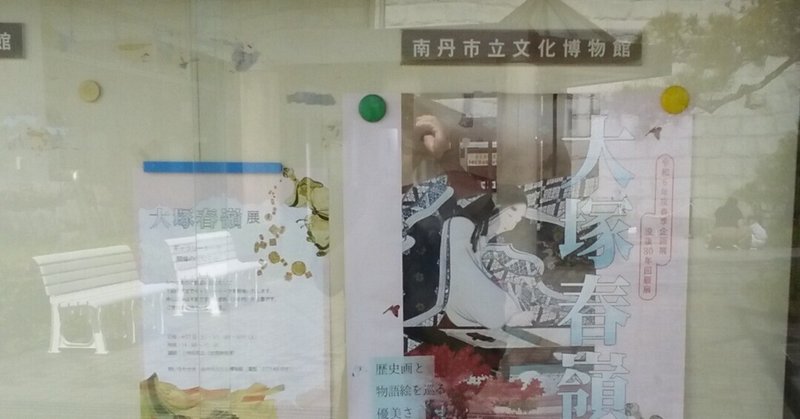
南丹市立文化博物館「大塚春嶺 没後80年回顧展」(-2024.5.12)
閲覧ありがとうございます。日本絵画一愛好家です。
晩春の過日、ほんの先日ですが、京都府南丹市の南丹市立文化博物館で絶賛開催中の「大塚春嶺 没後80年回顧展-歴史画と物語絵を巡る優美さ-」を拝覧して拝覧して参りました。
本展、上記の通り、本投稿の時点でも絶賛開催中の展覧会で、残り期間が短いですが、本年2024年4月6日から5月12日までの開催となっております。見出し画像が反射しまくってて申し訳ありません。
この回顧展、弊方、全く存じ上げておりませんでした。
それだけではなく、そもそも「大塚春嶺」先生のお名前すら存じ上げておりませんでした。
まず、南丹市立文化博物館のウェブサイトに僭越ながらリンクを張らせて頂きます。ただし、本記事の投稿時点では、同館のウェブサイトは更新されていない模様です。
また、南丹市立文化博物館の FACEBOOK と 旧Twitter現X では、本展の告知がなされております。僭越ながらリンクを張らせて頂きます。
明日4月6日(土)から南丹市立文化博物館春季企画展「大塚春嶺展-歴史画と物語絵をめぐる優美さ-」が開幕いたします(5/12まで)。本展は没後80年となった南丹市園部町出身の日本画家・大塚春嶺の画業を振り返るもので、これまで紹介されることのなかった作品を多数展示します。ご来館お待ちします。 pic.twitter.com/HRpl7xA54A
— 南丹市立文化博物館 (@nanpaku2006) April 5, 2024
弊方が本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」のことを存じ上げたのは、晩春の過日、大阪府池田市の池田市立歴史民俗資料館にて2024年3月20日から5月26日にかけて絶賛開催中の企画展「矢野橋村と石橋の芸術家たち」を拝覧しにお伺いしたときに、チラシ(フライヤー)が頒布されていたためです。
僭越ながら、同展チラシを弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

「大塚春嶺」?! 誰? 知らん?! 萌える!!!
という感じで、驚きつつも弊方オリジナルのナゾのヲタク三段論法(論法ではないですね、申し訳ありません)に基づいて、期日と開催ミュージアムを確認してお伺いしようと思いましたが、ここで再び驚きました。
南丹市立文化博物館?! それも4月6日から開催されてんの?! チェックしてたはずやのにぃぃぃ・・・、ぜんぜん気付いてへんかったぁぁぁ!!!
ということで、急遽、公私ともにスケジュールを調整して強引に本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」にお伺いすることにいたしました。
南丹市立文化博物館は、弊方、これまで何度もお伺いしたことがあります。JR嵯峨野線(山陰本線)のターミナル駅である園部駅が最寄り駅です。
駅前からバスは出ているようですが、徒歩で約30分くらいですので、弊方、当然のごとく歩きます。
園部駅は改札がひとつで、線路をまたぐ自由通路(コンコース)の両端に東出口と西出口があります。どちらから南丹市立文化博物館に向かっても、歩く距離はあまり変わらないような気がします。
園部駅の西出口側には天神山という山があって、この天神山の向こう側に文化ゾーンがあり、ここには、園部城址、園部公園、南丹市役所、園部高校、南丹市国際交流会館等が所在しており、この国際交流会館に隣接して南丹市立文化博物館が所在しています。なお、南丹市立文化博物館のすぐ隣が南丹市立中央図書館になっております。
弊方は、たいてい往路は園部駅の西出口から出て天神山の北側を通るルートを選択し、復路は天神山の南側を通って園部駅の東出口に至るルートを選択しています。深い理由はありません。
ということで、園部駅の西出口から国道9号線に沿って園部本町の交差点まで出て、そこから南側に曲がって南陽寺というお寺の前のT字路に至り、そこを曲がってどんつきのT字路まで進み左に曲がりますと、南丹市立中央図書館の前に出ます。
南丹市立中央図書館の正面を、僭越ながら弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を下記に掲載させて頂きます。ちなみにこの中央図書館前に「図書館前」バス停があります。

正面入口の向かって左側に本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」の看板が出ておりますね。でも、こちらは飽くまで中央図書館の入口です。看板の拡大写真を僭越ながら掲載させて頂きます。

同看板の下側に記載されておりますように、左奥にある細くて急な階段を上がると、南丹市立文化博物館の入口前に出ます。
あるいは、道路沿いに少し進むと階段または駐車場がありますので、そこを登ると公園になっております。ちなみにこの公園には、巨大なカワセミの像があります。写真撮り忘れましたが、かなり有名なようです。
巨大なカワセミさんの横には橋がかけられていて、その下にプールがあり、この橋を渡ると国際交流会館の正面に出まして、この国際交流会館の左側に文化博物館が隣接しております。
僭越ながら南丹市文化博物館の正面入口を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

南丹市立文化博物館内に入りますと、入口すぐに受付があり、こちらで入館料を支払って入館券を購入いたします。こちらの受付はミュージアムショップを兼ねています。
入口から見て右側が常設展入口で、左側はラウンジで、正面近いところに2階につながる階段があります。入口から階段にかけては吹き抜けとなっております。階段の下側にはトイレがあり、階段の裏手側にはエレベータがあります。
南丹市文化博物館の構造は、正面入口から見て1階左右に常設展示室があり、2階の企画展示室および特別展示室は正面左側のみにあり、1階の左右の常設展示室の間の廊下にエレベータが位置しているという感じです。
本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」は、2階の企画展示室および特別展示室に加えて、エレベータで降りてすぐの1階にある特集展示スペースと、ここにつながる先ほどのラウンジに亘っておりました。弊方が想像するよりも規模が大きいものでした。
本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」の展示構成は、下記のようになっておりました。
階段すぐの企画展示室の入口側
第1章「師との出会い、画家への道(習作時代・明治10~20年代)」
企画展示室の奥側
第2章「画壇開花期(明治25年頃~明治末)」
企画展示室から特別展示室の大部分
第3章「物語絵の展開期(明治末から大正時代)」
特別展示室の出口付近
第4章「能画の世界(大正時代)」
エレベータを下りた1階の特集展示スペースとラウンジ
第5章「故郷・園部での暮らし(大正末から昭和初期)」
さて、大塚春嶺先生については全く情報がない状態だったのですが、春嶺先生は南丹市園部町のご出身で、近代大阪画壇を代表する偉大なる画人、深田直城先生の門人であり、その後に、近代京都画壇を代表する画人であり、かつ幸野楳嶺四天王の一人でもある、谷口香嶠先生の門人でもいらしたそうです。
それにしても大塚春嶺先生の作品を見て弊方が思いましたところは、たいへん流麗な近代やまと絵、という所感でした。
端麗という表現もできるかと思うのですが、端麗には、姿かたちが整っている意味合いが強いのに対して、流麗は詩文の美しさを表現する場合に用いられるそうで、澱みのないという意味合いを含む言葉のようです。
絵画に澱みがないというのは、何か日本語的におかしな感じがするのですが、単に整った画面構成というだけではなく、何か言葉で表現しにくい麗しさがあるように思いました。飽くまで弊方私見です。
本年2024年1月13日から3月31日まで、東京都立川市のたましん美術館で開催されていた、近代やまと絵の旗手といってよいと思うのですが、偉大なる邨田丹陵先生の企画展「邨田丹陵 時代を描いたやまと絵師」を、調子に乗って前期後期2回も拝覧したのですが、その割には、未だに記事化して投稿していないのですが、邨田丹陵先生の作品を見たときにも、非常に格調高く麗しいと思ったのですが、大塚春嶺先生の作品は、邨田丹陵先生とは違う方向性で格調高く美しいと思いました。
これほどの方が全く無名なのはおかしいなぁ、と思いましたら、別に無名ではありませんでした。本展展覧会図録の第2章の総合解説から、僭越ながら次の通り引用させて頂きます。
春嶺が画壇で認められたことを示す最も早い記録は明治25年(1892)、古今名家新撰書画一覧の画家番付への掲載となっている。その2年後の明治27年、春嶺33歳の時、絵画共進会に出品した《女官弾琴》は二等褒状となり、「優美の状設色ノ間ニ現ハル」との講評を得ている。この頃には美しい歴史がを描ける画家として、広く知られるようになっていたことがわかる。
明治35年前後に画壇でのピークを迎え、歴史風俗が展覧会や日本美術協会などで幾つかの出品入選を確認できる。明治37年の『美術画報』には、入選した《大伴古麿語国威》が画像入りで掲載され、地名の作家で、国内有数の逸材との趣旨で紹介されている。
第15ページ第4-10行、同第13-17行
このように、大塚春嶺先生は、数々の展覧会で入選して注目されていた画人だったようです。
それでは、大塚春嶺先生の作品とはどのような感じなのかというと、館内は当然のごとく撮影禁止ですので、展示作品の写真はございません。
本展、先ほどの引用の通り、本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」では図録が制作されていただけでなく、グッズとして2種類のクリアファイルが制作され、絵葉書も10種類制作されて販売されておりました。
弊方、本展を拝覧してあまりにも感銘を受けましたので、めずらしく絵葉書も購入させて頂きました。クリアファイルは、いちおう自称コレクターなので、当然のごとく2種類とも購入させて頂きました。
そこで、クリアファイルといくつかの絵葉書を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を、僭越ながら掲載させて頂きます。
実は、本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」では、出陳作品の大半が、展示ケース内ではなく露出状態で展示されているという、めちゃくちゃ豪勢な展示状況でした。
第1章では、作品No.7-2「柴田勝家と木下藤吉之図」、No.7-6「小町踊り」、No.7-7「伊勢物語」、No.7-10「猿図」、No.7-9「富士之図」という粉本作品と、作品No.1-10「富士三保の松原図」という額装作品のみ展示ケース内での展示でした。
第2章では、作品No.2-8「三十六歌仙図」と、作品No.7-33「信実三十六歌仙之図の模写」という粉本作品のみ展示ケース内での展示でした。下記の絵葉書の作品(掛軸)は第2章で展示されておりました。

第3章では、作品No.3-5「春秋遊楽図屏風」という二曲一雙の大作が大きな壁面展示ケース内での展示であり、作品No.6-1「若葉(美術誌)」という深田直城先生を会頭とする結社「若葉会」の会誌資料、No.6-2「瑞穂春」という画帖作品が移動型の展示ケース内での展示でした。
これら以外の作品は、いずれも露出展示されておりました。下記のクリアファイルの作品(掛軸)は第3章で展示されておりました。

また、下記の絵葉書の作品(掛軸)も第3章で展示されておりました。

なお、第3章には、典型的な美人画作品も展示されていたのですが、これら美人画作品も素晴らしい作品でした。
第4章の能楽関係作品は、いずれも露出展示でした。
第5章では、作品No.5-1「小倉山屏風」という六曲一雙の大作屏風作品、作品No.5-8「琴棋書画図」という六曲一雙の大作屏風作品が、特集展示スペースの壁面展示ケース内の展示でした。
下記のクリアファイルの作品(掛軸)は、第5章でラウンジにおいて展示されておりました。

なお、作品No.1-1「酒造之図」、『美術画報』掲載の「大伴古麿語国威」は写真パネルであり、作品No.2-9「雲龍図」とNo.5-20「松図」は、タペストリーによる写真展示でした。
それにしても、これほどの才能をお持ちの大塚春嶺先生が現代において「無名」となってしまったのか、その理由の一つと思われる点について、僭越ながら本展図録から下記の通り引用させて頂きます。
文展以降は、展覧会の出展は確認されていない。特に大正以降は、徐々に画壇から離れ、注文に応じて画を描く職業画人としての生活を送った。すなわち大阪の船場派と呼ばれる画家の一人として認識されている。
第27ページ第17-21行
大塚春嶺先生は、展覧会への出展をされなくなり、基本的には「近代大阪画壇」の「職業画人」に移行された模様です。
とはいうものの、大阪中之島美術館において、昨年2023年に開館1周年記念特別展として開催されていた、近代大阪画壇の実質的に「初」の大規模展覧会といってよい「大阪の日本画」展には、大塚春嶺先生の作品の展示はありませんでした。図録でもお名前を確認することはできておりません。
師系から見れば、2021年に岡山県笠岡市の笠岡市立竹喬美術館で開催されておりました、特別展「歴史を旅する谷口香嶠」展は、谷口香嶠先生の個展/回顧展という位置づけなので、門人の方々に関する情報は少なかったのですが、もちろん大塚春嶺先生の作品は展示されておりませんでしたし、図録でもお名前を確認することができておりません。
それでは、近代やまと絵(大和絵)、あるいは、近代日本の歴史画という観点では、どうでしょう? ということで、弊方が古書で入手した、下記の近代やまと絵に関する網羅的な傾向を持つ展覧会/企画展の図録を確認しましたが、いずれも大塚春嶺先生のお名前は確認できませんでした。
「特別展 川辺御楯と近代大和絵の系譜」展
1994年、福岡県立美術館にて開催
「近代のやまと絵 古典美の再発見」展
1998年、岐阜県美術館にて開催
「明治神宮外苑創建80年記念特別展 小堀鞆音と近代日本画の系譜 勤皇の画家と「歴史画」の継承者たち」展
2006年、明治神宮文化館宝物展示室にて開催
大塚春嶺先生の画人としての立ち位置は、偉大なる上島鳳山先生に似ているのかもしれません。
上島鳳山先生は、岡山県笠岡市のご出身で大阪に出てこられて、北野恒富先生と並んで、近代大阪の美人画の大家と呼ばれ、「大阪の日本画」展でももちろん作品が展示されておりましたし、ご出身の笠岡市立竹喬美術館や、パトロン的存在であった住友家のゆかりの泉屋博古館(京都・東京)でも、展覧会が開催されたり作品が展示されたりしており、かなり有名でいらっしゃると思います。
それに比べても、大塚春嶺先生の情報が、何故これほど少ないのか、インターネットの安直な検索でもほとんど出てこないのか、よくわかりません。
そういう意味でも、本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」は、非常に貴重な激萌え展覧会であり、弊方、強く強く強くお勧めさせて頂きたいと思います。
・・・と思っておりましたら、以前、本館で購入させて頂いた「新園部町発足50周年記念 平成17年度周期特別展 園部ゆかりの画家たち」展図録に、大塚春嶺先生、めっちゃバッチリ掲載されておりました。
弊方が気付いてない(忘れてた)だけやったんかーい!!!
まことに申し訳ありません。当該図録を弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

それにしても、「園部ゆかりの画家たち」で紹介された画人の先生方の展覧会は、本展「大塚春嶺 没後80年回顧展」により全て開催されたということですね。
最後に、非常に印象的な作品をひとつ紹介させて頂きたいと思います。当該作品の絵葉書を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影したものを、僭越ながら下記に掲載させて頂きます。この作品は第3章での展示でした。

この作品は、ポスターやチラシ(フライヤー)、図録表紙にも採用されておりますが、紫式部(藤式部)先生が、源氏物語を執筆されるご様子を表した作品なのですが、何となく不思議な構図だと弊方思いました。
実は、弊方が本展にお伺いしたときに、おそらく本展のキュレーター(curator)を務められたと推測される先生が、来客と思しき方々に作品解説をされていました。
弊方、他の展覧会/企画展において何度か遭遇経験がありますが、たいていこういった来客は「行政の偉いひと」だと思うのですが、今回に限ってはどうも違うようで、専門分野の異なる研究者の方々のように推測されました。
もちろんギャラリートークではありませんので、ひそひそ解説されており、弊方も聞き耳を立てていないふりをしていたのですが、なにせ弊方以外にほとんどオーディエンスがおられないという独り占め状態だったため、ときどきお話し内容を把握できることがありました。
この作品に関しては、解説されていた先生が、とある能(謡曲)をテーマにしているのではないか、というご見解を示されていたのを、盗み聞き・・・やなくて、耳にすることができました。ただし、飽くまで私見とお断りになられており、展示解説にも図録にも、この点に関しては説明はありませんでした。
弊方も、盗み聞き・・・ではなくて、たまたま耳に入っただけなので、具体的な言及はいたしませんが、このご見解も受けて、改めてこの作品を拝見いたしました。
一般的の考えるベタな構図であれば、執筆活動をされる紫式部先生を画面下に、紅葉の枝を画面上に描くような配置になるんとちゃうやろか、と弊方思いました。
本作品を拝見して、否応なく最初に目に入ると思われる紫式部先生のお姿は、画面中央ではなく上側にシフトしており、それがために、見る者の視線は画面下の方に遷移するような感じです。
画面下の紅葉の枝は、下側が霞んでいるような描写になっておりますので、遠方から執筆中の紫式部先生を眺めているような感じも受けます。
そうすると、本作品では、「主役」のように見える紫式部先生の執筆活動が実は「主役」ではなく相対化され、別の「主題」が暗喩的に表現されているのでは?! と弊方妄想したいと思います。
構図的には全く違うのですが、暗喩的な表現としては、弊方の下記の投稿記事でヲタトークさせて頂いた、応挙先生の「唐美人図」に似たような印象を受けました。
いずれにせよ、本展、特に近代やまと絵、あるいは日本画の歴史画に強い興味をお持ちの方は、見逃すとぜったい損しまっせ!!! と一方的に申し上げておきたいと思います。
なお、弊方、南丹市文化博物館にはこれまで何度もお伺いしているのですが、同館と南丹市日吉町郷土資料館の共通キャラクター「どきタマちゃん」について全く存じ上げておりませんでした。
弊方、かわいらしい存在に目がないため、どきタマちゃんに喰いついてしまい、どきタマちゃんのクリアファイルも買うてしまいました。
僭越ながら、どきタマちゃんを紹介する画像から当該ウェブページ(PDF)にリンクを張らせて頂きます。

どきタマちゃんの相方である、親友の「ドバくん」もかわいらしいですね。
南丹市立文化博物館ウェブサイトによれば、どきタマちゃんグッズはたくさん発売されているようで、これから南丹市立文化博物館にお伺いする折には、どきタマちゃんのグッズを集めていきたいと思います。
速報的に短いめの記事にするつもりが、相変わらず長くなっており申し訳ありません。閲覧頂きましてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
