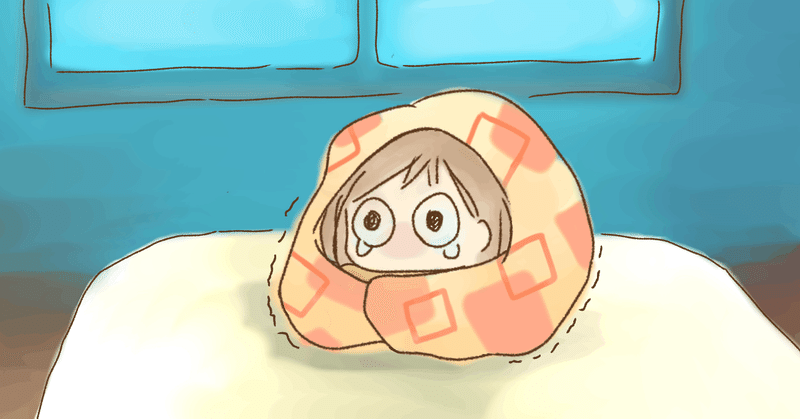
看護師が「患者さんを受け持つ」ことに感じる重圧。
みなさんこんにちは!
看護師ばんびです。
4月を迎え、あっという間に看護師6年目を迎えました。
特にコロナ禍になってからの4・5年目は、
日々のコロナ患者さんの増減に追われあっという間に過ぎ去ってしまいました…!
そんな中、「一度医療現場を離れて息抜きをしたい」
と考える同僚も多いなと感じています🤔
そこで、「看護師のどんなところにみんな辛さを感じるのだろう」
ということをよく考えてみています。
今日はその大きな原因の一つとわたしが考えることをお伝えします。
受け持ち看護師とフリー業務がある。
わたしは2020年4月から、コロナ病棟で働いています。
コロナ病棟の大きな特徴として
コロナの流行に合わせて患者数が増減したり
(数人の時のあれば満床となることも…!)
患者層が変化するということがあります。
(若い人が多い時もあれば、施設クラスターが多発して介護が必要な高齢者ばかりになることも…!)
初期は生活が自立している若い方が入院することもありましたが、
最近は高齢の方や酸素吸入が必要な方しか入院しないようになっています。
普通の病棟では、大体患者さんの人数や
どんな患者さんが入院しているかは大きな変化をしないので
数や患者層が変化するのは大きな特徴だと思います。
そして2022年4月現在は、
オミクロン株の流行による第6波が落ち着き、
新規感染者はまだまだいるものの、
入院している患者さんはだいぶ少なくなっています。
人数にして10人以下です。(満床だと42とかです!)
そんな中、
スタッフにも余裕ができるので、
患者さんを受けもたない、「フリー業務」という役割を作ることができています。
受け持ちとは
日勤であれば6〜7人程度、夜勤であれば12〜17人程度(人数は病棟や病院によります!)
の患者さんを担当します。
担当看護師は、
患者さんの入院した理由
今行っている治療やリハビリ
本日投与する薬剤
体調の変化
患者さんの困りごと
などさまざまな情報を収集し、
今日患者さんにどんな関わりを行うかを考え実行します。
フリー業務とは
患者さんの受け持ちをせず、
受け持ちをしている看護師さんのお助けマンとして、
採血
点滴の針の挿入
シャワー介助
ナースコール対応
その他頼まれごと何でも
を行います。
忙しい第6波の最中は、
看護師1人につき担当患者さんが9〜10人ということもざらにありましたが、
最近は患者さんが減っているので、フリー業務の役割を作れるというわけです!
フリー業務をして気づいた「受け持ち」の大変
このように久々にフリー業務をして思ったのが、
いかに「受け持つ」という責任感が看護師にとっての重圧となるか
ということです。
もちろん治療方針の決定の責任を持つのは医師です。
でも看護師は、長く患者さんと関わる分、
「自分のせいで患者さんが悪くなってしまったのではないか」
と思う可能性のある時間がとても長いです。
自分がミスをしてしまった時はもちろんそう思いますが、
そうでなくても
「異常を早く見抜けなかったら受け持ちの私の責任になる」
という不安を常に抱えています。(私の場合)
だから、休憩中も、家に帰ってからも心配なのです😢
もちろん、患者さんは看護師ひとりでみるのではなく、
病棟のスタッフみんなでみているので、
1人の責任ということはないのですが、
それがわかっていても自分の責任のように感じてしまいます。
大変だけどだからこそ…!
でも、この「責任感」が悪いことばかりというようには思いません。
患者さんに1人つき誰か1人のスタッフが
真剣にその人のことをみているからこそ、
わずかな患者さんの変化にも気づけるかもしれないと思います。
でも、特に新人のうちは
「責任感」と「チームの分担」の配分
がうまくできず、
責任感に押しつぶされそうになることも多々ありました。
もし、この文を新人の看護師さんが読んでくれていたら、
どうか1人で抱え込みすぎず、
怖いと感じるかもしれませんが、周りの先輩に相談してみてください。
あなたが患者さんのことを一生懸命思う気持ちは、
きっと伝わります😊✨
今回も長いブログとなってしまいましたが、
最後まで読んでくださりありがとうございました😌✨
少しでも心に残るものがあれば、いいねやフォローをしていただけるととっても励みになります!☺️
また、このようなわたし目線の医療の世界について、
毎日ラジオ配信やTwitterでの発信をしているので
聞いていただけると嬉しいです!🥺💕
リンクはこちら!👇
それでは、最後まで読んでくれたあなたの一日が、素敵な一日となりますように☺️✨✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
