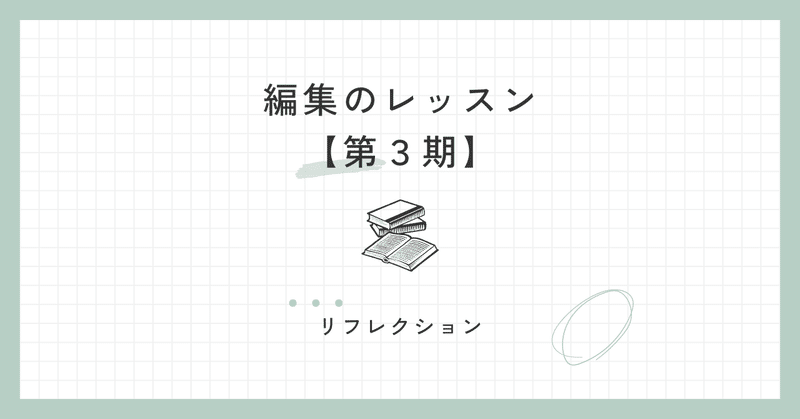
無計画と偶然を楽しむこと。(編集のレッスン【第3期】 リフレクション#1)
アーカイブ受講している「編集のレッスン[第3期]」について、個人的な学びのリフレクションとして記事を掲載しています。
(講座内容のまとめではありません。)
講座のテーマは「場の編集」。
「場の編集」とは?との問いには、ナビゲーターである「for Cities」の石川由佳子さんと杉田真理子さんらによる定義が示されています。
私たちの考える “場の編集”とは、その場所への「介入可能性を探っていくこと」だと思います。それは今その場所にあるものを、読み替えたり、作り替えたり、集めて異なる意味を作ったり、つなげて 新しい関係をつくったり、新しい視点を提供すること。メディアの編集も場の編集も基本の考え方は同じで、私たちは冊子の編集・デザインも場のデザインも、同じような姿勢で行っています。
上記のnoteは受講者募集記事のようですが、遅まきながら第1回講座を受講後に読みました。
内容がオーバーラップする部分もありつつ、初耳のこともあり学びが多く、非受講者の方にもおすすめです。
note記事を読む中で、目に留まった「偏愛」は関心の高いキーワードです。
杉田さん:あと、偏愛が強い人にも会ってみたいです。昨年、獅子舞を偏愛する人に出会ったんですが、彼は全国のいろんな祭りを見て、獅子舞を残していくためのまちの条件として道の広さや人的リソースなどを検証して、『獅子舞生息可能性都市』という本も出していました。話を聞いていたら、私たちが定義しているような「アーバニスト」と近しい活動で、都市のスケールを個人の視点から捉え直すという姿勢にもつながっている。そのような偏愛を持って活動している人、そこに都市的なアプローチを投入してみたい人は、きっと私たちと趣味が合うんじゃないかなと思います。
個人的なことですが、昨年まで福井県庁の観光セクションに在籍していました。
その時から、地域の「ホンモノ」とは何だろう、とモヤモヤしています。「福井には何もない」が口癖のようになっている我々が、心底「これぞ我が地域の一押し」と言えるものをそれぞれが持てるようになるには、どうすれば良いのか。
以前、手にした書籍では、地域文化の担い手である住民の真摯さが、それをホンモノたらしめているとの論が展開されていました。
たとえ、観光向けにアレンジされた地域の舞踊であっても、それを地域の文化に育て、つなげようとする真摯な気持ちがあれば、それをホンモノたらしめるというものです。
偏愛は、自分では止めることのできない対象への愛情。その熱量は、真摯さの源泉となるのではないでしょうか。
また、一見、たった一人の偏愛であったとしても、それを紐解くと、「あるある。そうだよね!」と地域内で共感し得る要素が埋め込まれているかもしれません。
そして、その「あるある」がともすると、一人の偏愛から地域の誇りや帰属意識に繋がりうるのでは、とぼんやりと考えています。
随分と脱線しましたが、偏愛についても今後の講義の中で触れていただけないかな、と期待が膨らみます。
さて、第1回目の講義では、これまでのお二人の活動やリサーチ手法をレクチャーいただきました。第2回の今回は吉田勝信さんが講師です。
吉田さんは山形県在住で、「採集者/デザイナー/プリンター」という不思議な肩書きをお持ちです。
採集は文字どおり、山に入ってキノコなどの採集のほか、郷土のお祭りなども採集の対象とのこと。採集した対象から地域を紐解きます。(吉田さんは民俗学のバックボーンがあるとのことです)
吉田さんが、「採集がデザインと印刷を下支えしている」とおっしゃられていました。それを象徴しているなと感じたのは、採集したものから顔料を作り用いている点です。
その顔料について語る場合、素材となった植物の採集地や地域での活用方法など、地域を文脈にせざるを得ません。
何気なくそこにあるものが顔料となることにより、「地域語り」の起点となる。
地域の色として、地元住民が語れるようになれば素敵なことではないかと感じたところです。
このようなアプローチも、読み替えや捉えなおしという点で、一種の「場への介入」であり、アーバニスト的振る舞いなのかも?などとの思いが、ふわりと頭をよぎりました。
さて、採集を英語で言い換えると「foraging」がしっくりくるとのことで、ガサゴソと薮をかき分けるイメージだそうです。
計画的に目的を遂行するのではなく、散策する過程そのものを楽しみ、偶然に見つけ出したものを愛でる。お話の中で、レヴィ=ストロースの名前も登場しましたが、ブリコラージュ的な姿勢が必要ということでしょうか。
キラキラしていなくても、ただ、そこにあるものに興味を持ち、じっくり味わう心持ちを大事にしたいところです。
