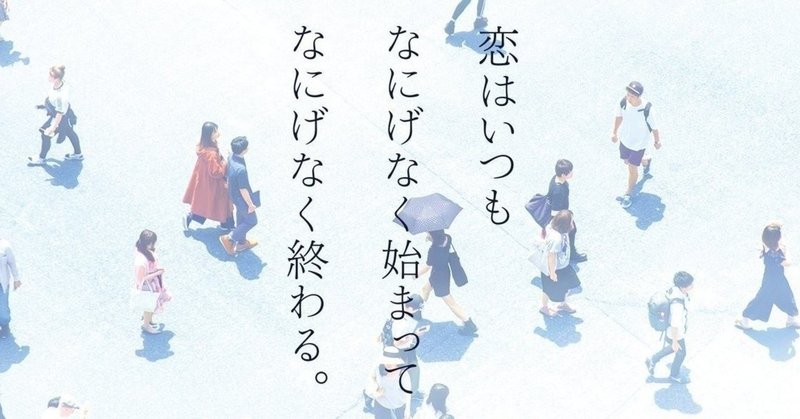
『恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。』全文公開⑥15歳年下の彼との恋
ヴァレンタインのチョコレートが街中で売られ始めた二月のまだ寒い夜。
私はダイナ・ショアがアンドレ・プレヴィンのピアノで『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』を歌っているレコードを棚から出した。
この曲は女性が愛する男性のことを歌う、こんな内容だ。
「ねえ。大好きな私のヴァレンタイン。ずっといて。
だってあなたさえいてくれれば、私にとっては毎日がヴァレンタインデイなんだから」
幸せいっぱいなのに、まるでこれからの二人の別れを予感しているかのような切ない歌だ。
この曲がかかると、扉が開き、近くの広告代理店に勤める松山さんという女性が入ってきた。松山さんは年齢は四十歳だが三十五歳くらいに見え、瞳は大きく、ほりの深い整った顔をしている。コートを脱ぐと、Vネックのオリーブ色の薄手のセーターのせいで、胸のふくらみと対照的な華奢な鎖骨がよくわかる。
彼女は私がすすめるまでもなく、カウンターの方にコツコツとヒールの音を響かせて歩き、真ん中の椅子に座ると、ゆっくりと足を組んだ。そして低くて艶のある声でこう話し始めた。
「今日は本当に疲れました。マスター、一条かおりのあのディズニーランドでのデート事件知ってますか? 一条かおり、ずっと恋愛スキャンダルなんてなかったのに、一般の男性とディズニーランドでデートしたらしいんです。相手の男性の素性が今ネットで詳しくさらされているんですけど、ホント普通のサラリーマンで高校の同級生らしいんです。どうして一条かおりが変装もしないであんな男性とデートしたんだろうってみんな大騒ぎで。
私、一条かおりが出てる口紅のCMの担当をしてて、口紅のイメージがどうなるかってもう心配で心配で、今までずっと働きっぱなしでした。でも、彼女も一人の女性なんですよね」
「ああ、私もその騒動、見ましたよ。私にはすごく素敵な男性に感じられましたがね。一条かおり、幸せになるんじゃないですか」
「そうですかね。私も疲れたのかチョコレートが食べたくなってしまって。たしかおいしいガトーショコラがありましたよね。ガトーショコラにあうお酒も一緒にいただけますか?」
「でしたらラムなんてどうでしょうか」
「ラムですか。『宝島』で海賊の船長が飲んでいたイメージしかないんですけど」
「ラムはカリブ海でよく作られているんです。だから海賊をイメージするんですかね?」
「カリブ海ってキューバとかジャマイカとかですか?」
「ええ。ラムは宗主国の人間が好むように作られるんです。例えばイギリスでは海軍がラムを消費するのでジャマイカでは海軍向けのパンチのきいたラムが作られます。
ハイチではフランス人が好むブランデーのような香りの華やかなラムが作られます。このハイチのラム、バルバンクールの十五年ものは世界中のいいバーには必ず置いてなくてはならないラムだと言われています。このバルバンクールでしたら、ガトーショコラにぴったりあいますよ」
「ハイチのラムとガトーショコラですか。試してみたいですね。それをいただきます」
私は香りをゆっくりと楽しめる大きなチューリップ形のグラスにバルバンクールを注ぎ、ガトーショコラと一緒に彼女の前に出した。
彼女はガトーショコラを少しだけ口に入れ、それからバルバンクールにそっと口をつけた。
「おいしいです。大人になってよかったって思うおいしさですね」
「大人になるっていいものですよね」
「大人かあ。マスター、私、今、四十歳なんです」
「え? そうなんですか。もっともっとお若く見えますよ」
「まあそうやってみんな言ってくれるんですけどね」
「いや、本当にそう思いますよ」
「ありがとうございます。でも、二十代の男性から見たら、オバサンですよね」
「ええと、どうしてですか?」
「私、二十五歳の男の子を好きになっちゃったんです」
「そうなんですか。ところで、結婚してから今までご主人以外の男性と何かあったことは? 松山さん、モテそうだからいろんなお誘いはありそうですよね」
「一応、派手な職種なんで、誘われることは何度かあったんですけど、私そんな気持ちにはまったくならなくて。たぶん恋愛体質じゃないと思うんです」
「そういう方、たまにいらっしゃいますね」
「でも、杉田くんは違ったんです。春に私の部署に入ってきたのを見たその瞬間から恋に落ちました。ああ、一目惚れってあるんだ、私もこんな風に誰かに恋をすることってあるんだ、って思いました。
今まで付き合った人って、基本的に向こうからすごく押してきて、デートのセッティングをこまめにやってくれたり、一生懸命プレゼントをくれたりしたから、まあそこまでしてくれるんならいいかって感じで付き合い始めるケースばかりだったんです。
だから私の方からこんな風に一方的に好きになるなんて自分でもびっくりしました。
でも彼は私の十五歳も年下なんです。
この気持ちはずっと隠そうと心に決めました。だいたい私は結婚しているわけですし、十五歳年下って、ほとんど自分の息子みたいな年です。向こうから見たら、本当に親戚のオバサンと同じような関係でしょ。途中からは『私、たぶんお母さんみたいな気持ちで杉田くんを見ているんだ。だから普通に上司として保護するような気持ちでいよう』と考えるようにしたのですが、やっぱりそういう気持ちじゃないんです。
女性として杉田くんと手をつないで街を歩きたいし、正直、あの杉田くんの腕の中に抱きしめてもらえたらどれだけ幸せだろうって思ってしまって……」
「その杉田くんとは食事なんかはされたんですか?」
「はい。出来るだけ仕事がからんでいるフリをして、二人っきりでいろんなところで食事をしました。
まだ若いからフレンチやちゃんとしたお寿司屋とかに行ったことなくて、そういうところでご馳走してあげると『松山さん、さすが大人だなあ』って毎回毎回、言うんです」
「杉田くんは松山さんの気持ちに気づいていたんでしょうか?」
「たぶん気づいていたと思います。私、絶対にそんな素振りは見せないようにしようと思ってたんですけど、彼といる時って『キャー!』とか『おいしい』とか普段は言わないような声ばかり出していたんです。バレていたはずです。
十月のことでした。私たちはチームで東京のハロウィンがどんな風に消費されているか調査することになりました。
杉田くんが『松山さん、僕の大学の時の友達がクラブを借切ってハロウィン・パーティを開くから一緒に行ってみませんか?』って提案してくれたんです。杉田くんとパーティに行けるなんて、夢のようでした。私は『行きましょう!』って答えました。それが間違いの始まりでした。
やっぱり仮装はしていった方がいいだろうなあって思ったのですが、私、世代的にそんなのしたことないから、よくわからなくて。東急ハンズで魔女の帽子とマントを買って、それをつけて日曜の夜に六本木で待ち合わせをしました。
ハロウィン当日の六本木は凝った仮装をした外国人や若者たちがたくさんいて混雑していました。その中から私に向かって手を振るゾンビがいました。杉田くんでした。杉田くん、いったい誰だかわからないくらい完璧なメイクでゾンビの格好をしていたんです。
パーティ会場のクラブの入り口に行くと、DJの音と、若い人たちの大騒ぎしている声が聞こえてきました。中に入ってみたら当然ですけど私以外の全員が若い人たちなんです。みんなアニメのキャラクターやナース、女豹やゾンビといった思い思いの自由な仮装をしていて、すごく楽しそうでした。ああ、今ってこんな感じなんだなあって実感しました。
私は、一人だけ気合いの入ってない東急ハンズの魔女の帽子とマントをつけているだけの、勘違いのきどったオバサンで、完全に浮いていました。
今までずっと自分は綺麗で若いんだって思ってたんですけど、やっぱり二十代の子たちとは全然違うんです。鏡にうつった自分を見るとやっぱりどう見てもオバサンでした。
杉田くんは友達がたくさんいました。みんなが『おお、スギタ、久しぶり!』って集まってくるんです。可愛い女の子もたくさんいました。たぶん杉田くん、学生時代すごくモテたんだってその時やっと気がつきました。みんな学生時代の思い出や新しい職場での話なんかですごく盛り上がっていました。
杉田くんはみんなに私を『会社の上司で、松山さん。あの一条かおりのCMを作ってるんだよ』って紹介してくれました。みんな『すごいですね』って口々に言ってくれたのですが、それ以上、会話が続かないんです。彼らとの共通の話題がなんにもないのに気がつきました。
『ちょっと飲み物取ってくる』って言って、杉田くんから離れました。
飲み物を取りに行っている途中でやっとあらためて会場の全体が見渡せました。そうかあ、杉田くんこんな派手な若い人たちの中心で人気があるんだなってわかってきました。私の会社に入るくらいだから当然なんですが、フレンチのワインのテイスティングで緊張していたくらいだからって軽く見ていたんです。
私、その若い人同士の雰囲気に戻っていけなくて、飲み物だけ持って、すみっこの方でしばらくパーティ会場を眺めていました。壁の花になるなんて生まれて初めてでした。私、ずっと自分は綺麗で若い方だって思ってましたから。
ああ、私、どうしてこんなところ来ちゃったんだろう、どうして若い人しか来ていないって気づかなかったんだろう、どうして四十歳なんて自分だけだって想像できなかったんだろうって後悔しました。
そしたら杉田くんが血相を変えて、私の方に飛んで来て『松山さん、どこに行っちゃったのかと捜しちゃいました。もしかして、あんまりこういうザワザワした雰囲気好きじゃないんですか? 一度ちょっと外に出ましょうか?』と言いました。
私は『杉田くん、ごめんね。私こんなオバサンで。これ飲んだら帰るね。杉田くんも恥ずかしいでしょ。こんなオバサンといるの』って言ったら杉田くんがその場で私を抱きしめてキスしてきたんです。
私、足がガクガクして、その場で杉田くんに身を任せてしまいそうになったんですけど、これは絶対にダメだと思って、唇を離して『杉田くん、オバサンをからかわないでよ』って言ったんです。
『からかうってどういう意味ですか? 僕、松山さんのことが大好きなんです』
『四十のオバサンに何言ってんの。冗談はやめてよ』
『僕、本気ですよ。松山さんがこれから旦那さんがいる家に帰ると思うだけで苦しいです。出来れば今日は松山さんを帰したくないし、出来れば松山さんを奪ってどこか遠くに逃げたい気持ちです』
その言葉で私は落ちてしまいました。その日から家には帰ってません。主人とは弁護士をはさんで離婚を協議中です」
そう言うと、松山さんはバルバンクールを流し込み、ガトーショコラを少し食べた。
私が何か言おうとすると松山さんはさえぎった。
「この恋がうまくいかないのは知っているんです。こういう関係も後一、二年続けばいい方だなって最初から知っているんです。杉田くんはいつか目が覚めて、また誰か他の若い女の子と恋を始めてその若い女の子と結婚すると思います。
そんなことはわかっているんです。でも私、今、杉田くんがいる部屋に帰って杉田くんに抱きしめられると心も身体も溶けて、女で良かったって思うんです。ここでこの人に出会えて良かったって思うんです。こんな幸せな気持ちになったの、人生で初めてなんです。この後一人ぼっちになっても、この思い出があれば一生後悔はしません」
そう言うと、財布を取り出した。
私のバーにはさっきからずっと、ダイナ・ショアが「ねえ、大好きな私のヴァレンタイン、ずっといて。だってあなたさえいてくれれば、私にとっては毎日がヴァレンタインデイなんだから」と歌い続けていた。
※
SNSでシェア等していただけると助かります。「もう早速、全部読みたい! 待てない!」という方、本、売ってます。こういう短い恋の話が、あと20個入ってます。冬の読書にいかがでしょうか? キンドルだと今、お安くなってます。ヴァレンタインのプレゼントにも最適です。好きなあの人に贈っちゃいましょう。
#ファーストデートの思い出 というハッシュタグで、あなたのファーストデートのあれこれを募集しています。是非。詳しくはこちら↓
サポートしたいと思ってくれた方、『結局、人の悩みは人間関係』を買っていただいた方が嬉しいです。それはもう持ってる、という方、お友達にプレゼントとかいかがでしょうか。
