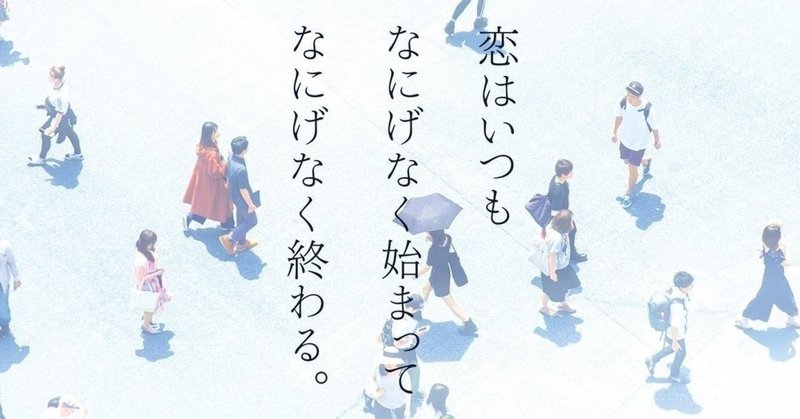
『恋はいつもなにげなく始まってなにげなく終わる。』全文公開②私を月に連れてって
私のバーには結婚を控えた交際中の男女がよく来る。渋谷の街で映画やライブを見た帰りに軽くバーで飲んでいこうかなという男女や、休日に買い物をして彼の家に向かう前に二、三杯バーで飲もうかなという男女だ。
そんな彼らはある日、「今度僕たち結婚するんです」とバーテンダーである私に告げる。バーテンダーとしては、一番嬉しい瞬間だ。どういうわけか、私も彼らの恋愛劇の脇役になっているような気がして、ハッピーエンドが近づくと「良かった」と思い、乾杯をしたくなる。
その後、そのカップルはしばらく私のバーには来ない。若い二人の新婚家庭を想像してほしい。二人で都会の暗いバーで飲むというシチュエーションは存在しない。しかし、数年後のある日、「お久しぶりです。今日は子供を実家に預けてきたんで」と言いながら来店してくれることもある。
秋も深まり始めた十月のある日、久しぶりに来店された男性もそんな一人だった。レコード会社に勤める藤原さんは二重の大きい瞳が印象的な男前で年齢は三十五歳。髪の毛は少し長めで真ん中で分けていて、グレーのポロシャツに紺色のジャケットをはおり、白いジーンズをあわせている。
「こんな風にカウンターで座って飲むのなんて本当に久しぶりです。マスター、今夜は三日月がすごく綺麗だったんで、なにか月に関したカクテルをいただけますか?」と藤原さんからリクエストがあった。
「では、あまり有名ではないカクテルですが、ムーン・ライトなんてどうでしょうか?」
「有名ではないんですね。月のカクテルってあまりないんですか?」
「そうですね。もっとあっていいはずなのに、私はこれしか知らないです。アポロのせいかもしれないですね」
「アポロのせいですか?」
「一九六九年にアポロが月に到着してからは、月への夢がなくなったのか、月に関する名曲が出てこなくなったと聞いたことがあります。カクテルの名前に月をつけるのも同時に流行らなくなったのだと想像します」
「面白いですね。じゃあ、そのムーン・ライト、いただけますか?」
私は冷凍庫からミキシング・グラスを出して氷を入れ、ヘネシーとチンザノ・ロッソを注ぎ、アンゴスチュラ・ビターズとシロップを足し、ステアした。
大ぶりのショートカクテル・グラスに注ぎ藤原さんの前に出して、ターンテーブルのレコードをアストラッド・ジルベルトの『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』が入ったレコードに替えた。
藤原さんはムーン・ライトを口に入れてこう言った。
「これが月の光の味なんですね。アルコールは強そうですが」
「古いスタイルの良いカクテルです」
「マスター、今かかっているの『私を月に連れてって』ですよね」
「よくご存じですね」
「このアストラッド・ジルベルトのレコード、僕の義理の父がくれた十二枚のレコードの中の一枚で、これをかけてちょっと素敵なことが起こったんです」
「十二枚のレコードをもらったんですか。それはいったいどういうことなんですか?」
「以前よく一緒に来てた僕の妻、覚えていますか?」
「お酒が好きで、音楽や映画にも詳しくて、とても素敵な方ですよね」
「ありがとうございます。その妻のお父さんがすごいコレクターなんです。妻の家にはお義父さん専用のオーディオ・ルームがあって、壁一面に一万枚くらいのレコードが並んでるんです」
「一万枚ってすごいですね。奥様の実家にはよく行かれるんですか?」
「ええ。結婚前には二カ月に一回、妻の家の食事に誘われました。彼女の家族はみんな料理をするのが大好きで、お義父さんとお義母さんと彼女と彼女の妹が四人でわいわい言いながら、夕食の用意をするんです。
料理は毎回、季節を感じるものというテーマが決まっていました。夏には夏野菜をたっぷり使ったもの、冬にはジビエにこだわってという風に、フレンチやイタリアンを中心に、中華やタイ料理のアレンジも加わって、とにかくどんなレストランよりも自由でおいしい料理が作られました。
そして、食事の時はとにかくみんなたくさん飲みます。ビールから始まって白ワイン赤ワイン、お義父さんもお義母さんも彼女も彼女の妹もたくさん飲んで、たくさんの話を僕たちはしました」
「楽しそうですね」
「食事が終わると僕も加わって、みんなで後片づけをしました。マスター、ちょっと酔っぱらって家族みんなで洗い物をするってすごく楽しいものなんです。さっきまで油やソースで汚れていたお皿が綺麗になって片づいていくのっていいものです。その後はお義父さんのオーディオ・ルームに集まりました。みんなこだわりのコーヒーや手作りのケーキ、とっておきのシングルモルトのウイスキーや話題のお店のチョコレートといった食後の楽しみを持ち寄って、好きなところに座りました。
お義父さんがかけるレコードには毎回テーマがあって、『今夜はフランク・シナトラの人生を振り返りながら、彼のレコードを聴いてみよう』とか、『今夜は一九六九年に発表されたレコードだけをたくさん聴き比べてみよう』って感じなんです」
「それは私も参加したいですね。仲が良さそうな家族ですね」
「そう思いますよね。僕も彼女に一度『本当に仲が良い素敵な家族だね』と言ったことがあるんです。彼女には『あなたが家に来る二カ月に一回だけのことなのよ。他の日はみんな忙しくて全然顔を合わせたりしないの。あなたの存在がみんなを繋げているの』って言われました」
「そんなものなんでしょうかね。その後、お二人は結婚されたんですよね」
「はい。彼女との結婚式の日に、彼女のお義父さんが僕にレコードを十二枚くれたんです。多分、どれもが発売当時に買ったものなんですが、お義父さんが大切にしていたことがひと目でわかる、とてもきれいなレコードで。
内容はビートルズやグレン・ミラー、『ティファニーで朝食を』のサントラと、このアストラッドのアルバムもあるし、まったくバラバラで、お礼の後の言葉に詰まってしまって」
「いったいどういうことなんでしょうか」
「お義父さんがこう言いました。
『このアルバム全部に、必ず一曲は〈月の曲〉が収録されているんだ。お願いがある。満月の日にはこのレコードのどれでも良いから一枚、うちの娘と一緒に聴いてくれないかな?』
その言葉を聞いて、レコードをゆっくりと見てみると、たしかにどのアルバムにも〈月の曲〉が収録されていました」
「ああ、そうでしたか」
「僕がそのレコードを眺めているとお義父さんがこう説明しました。
『結婚すれば喧嘩することもあるし、イヤなこともあると思う。でも、満月の夜にはレコードをかけて〈月の曲〉を聴くと決めたら、幸せな家庭が出来るかなと勝手に思って。まあ嫁の父の最初で最後のわがままを聞いてください』
僕はお義父さんに『ありがとうございます。もちろん、満月の夜には必ずお義父さんのレコードをかけて愛する彼女と聴きます』と伝えました」
「いいお義父さんですね。奥様とは今でも満月の夜にお義父さんのレコードを聴いているんですか?」
「もちろんです。このあいだ三歳の娘を連れて、満月の日にあわせてキャンプに行きました。誰もいない山奥で、お義父さんからもらったアストラッド・ジルベルトの『私を月に連れてって』をかけていたら、娘がそこで踊りだしたんです。親馬鹿なのかもしれませんが、月明かりの下で踊る娘の姿がとても幻想的で。思わず妻の手を取って、僕たちもたどたどしく一緒に踊ってしまいました」
「素敵な話ですね。アストラッド・ジルベルト、もう一度聴きましょうか」
「お願いします」
私のバーでは、アストラッドがずっと「私を月に連れてって」と歌い続けた。
※
SNSでシェア等していただけると助かります。「もう早速、全部読みたい! 待てない!」という方、本、売ってますよ。プレゼントにも最適です!
#ファーストデートの思い出 というハッシュタグで、あなたのファーストデートのあれこれを募集しています。是非。詳しくはこちら↓
サポートしたいと思ってくれた方、『結局、人の悩みは人間関係』を買っていただいた方が嬉しいです。それはもう持ってる、という方、お友達にプレゼントとかいかがでしょうか。
