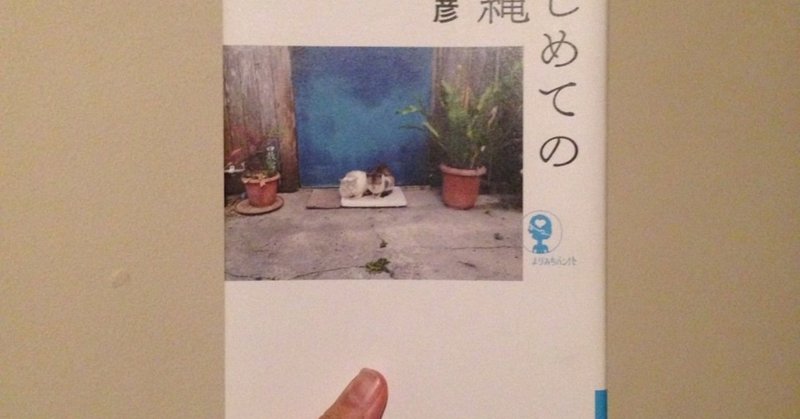
はじめての沖縄
私は沖縄を受け止めきれない。
高校卒業と同時に18歳で地元のいろいろをぜんぶ置いて、茨城の大学に進学した。
絶対に本土に行く、というつよい意思があったのは、沖縄の人間関係の狭さ、近さ、猥雑さが性に合わなかったからだ。
私個人としても「陽気でフレンドリーな沖縄人」のイメージとは程遠いし、
数少ない友人たちは好きだけれどその他大勢との距離感はうるさいくらいだし、眩しい直射日光の陰のようにひそんでいる基地問題もどうしたらいいのかわからないし、
きらいじゃないけど、思い入れはあるけど、沖縄とずっと一緒にはいられない、というような感覚はいまもある。
大学卒業後は、沖縄のニュースにも耳をふさいできた。
もう帰るつもりはないのだから、沖縄のことは沖縄にいる人が決めてくれ、と思っていた。
少しでも耳に入れたら泣いてしまいそうだった。
一方で、自分のルーツに触れたい気持ちもあった。1995年生まれの私は、復帰前も戦前も知らない。
小沼理さんの書評を読んで、これなら私にも読めるかもしれない、と感じたのが『はじめての沖縄』だ。
社会学者の岸政彦先生が、一般の、「ふつうの」うちなんちゅにインタビューして考えたこと、「沖縄について考えることについて、沖縄出身でない他者が考えたこと」が書かれてある。
Twitterを見ていて、岸さんが在沖米軍基地に反対していることは知っていたから、思い切り左に振った本だったらどぎまぎしちゃうな…という身構えは杞憂に終わった。
岸さんが大学の生徒を連れた沖縄実習の最中に、コザの海兵隊と口論するシーンがある。ひとしきり米軍が沖縄にしたことを批判した後に、岸さんは海兵隊にこう言っている。
でもな、俺はお前らマリーンは、好きだよ。お前もどうせ、大学の学費や、自分の家族の健康保険のために、ここに来てるんだろ。俺は基地は反対だけど、お前らひとりひとりは好きだよ。
声を上げて泣いてしまった。
後半では、政治的に真っ向から対立する人同士の交流も描かれている。
元県知事で基地の県外移設を求め続けた大田昌秀と、基地建設に大きく寄与した県内最大手ゼネコン・國場組の社長が、バーで親しげに語らう姿だ。
私はそのとき、沖縄の指導層の人びとの、左右の政治的対立を超えた結びつきを垣間見たような気がした。その場で私は、右も左も関係なく戦後の沖縄の人びとを引っ張ってきた人びとの、自負と、覚悟と、ある種の連帯感のようなものが存在するのを感じた。
これらのシーンは、私の愛する沖縄の象徴だ。
うるさいくらい親密で、ときには押し付けがましくさえもあるけれど、
ままならない立場を乗り越えて手を差し出せるやわらかさ。
相手や自分の正誤も美醜も引き受けて飲み込んで、笑って肩を組める豪胆さ。
そうだよ私は、そういう沖縄が好きだったんだ、と改めて思い出すことができた。
大学で私が属していたゼミでは時事問題を扱っていて、私はよく基地問題や米軍の事件事故を担当させられた。
担当教員は典型的な左派の元新聞記者で、私に沖縄を通して政権批判をさせたかったのだろうと思う。
はじめの頃は、話を聞いてもらえることに浅ましくも喜んで、私たちがどれだけ被害を受けてきたのかを意欲的に発表していた。
けれど、基地賛成派の友人や、沖縄の偏った報道批判などを見るにつれ、この被害者意識は正しいものなのか、と疑念が持ち上がるようになってきた。知れば知るほど、自分のポジショニングが曖昧になっていった。
卒業直前の最後のゼミでは、「沖縄の人も基地をどうしたらいいのかわからないけれど、基地に由来する事件事故が起こるのは悲しいです」というような、何も言っていないに等しい感想しか言えなくなってしまった。
自分の曖昧さに疲れて、もう何も言わないでおきたいと怠けていた私は、終章で岸さんが語ったことにいま揺らされている。
沖縄という対象をどのように語るにしても、沖縄というものに対する政治的態度、位置取り、理想化や相対化から自由になることは、とても難しいのだ。
基地に反対する声も、強まると基地内労働者や県内の特定自治体を非難することになる。沖縄も一枚岩ではないのだ。
一方で、そのような「基地に賛成する要素のある人びと」の声を掬い上げようとすると、基地推進派に利用されてしまう。
この難しさを指摘した上で、岸さんは「語らなければならない」と言う。
沖縄に限らず、そもそも私たちは、私たちの個人的な経験を交換できないようになっている。(中略)できることは、言語という、まったく個人的でないような公共的な道具を使って、おたがいに合理的に「理解」しあうことだけなのだ。
たとえその言葉というものが、あらゆる政治性から自由ではありえないとしても、私たちにできることは、まだあるはずだ。
なんの解決もしていないように見えるし、事実わかりやすい結論や解釈とは無縁の本だった。
でも、語ることをやめてはならない理由は理解できた。
私たちはどれほど近くに感じても一様に他人で、感情や経験を100%「わかる」ことはできないからこそ、
言葉で伝えなくてはいけなかった。
「言いたいことがあるなら言わなければ伝わらない」という簡単な話だ。
黙することは断絶を生む。
私があのゼミで言わなければいけなかったこと、言いたかったこと、「いろんな沖縄があるよ」ということを、
そしてそれを「曖昧でもそれぞれの立場から語らなければいけないよ」ということを、
至極ていねいに書いてくれている本だった。
もだもだと要点のない話しかできないかもしれない。情報もすべては追えない。私は偏った意見の持ち主だ。沖縄にいたときも基地の害はなく、比較的発展した南部の出だ。中北部の実態を知らない。家庭も困窮していない。大学まで出させてもらった。沖縄の中では、あからさまに強者の部類かもしれない。
この立場で、語る。
この立場で語るしか術がない。
だからなるだけ多くの、話者がいると心強いなあと、これまでの自分を棚に上げていまは思う。
こんなにめんどくさい本を書いてくれて、岸さんは本当に沖縄が好きなんだなと思った。心から、ありがとうございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
