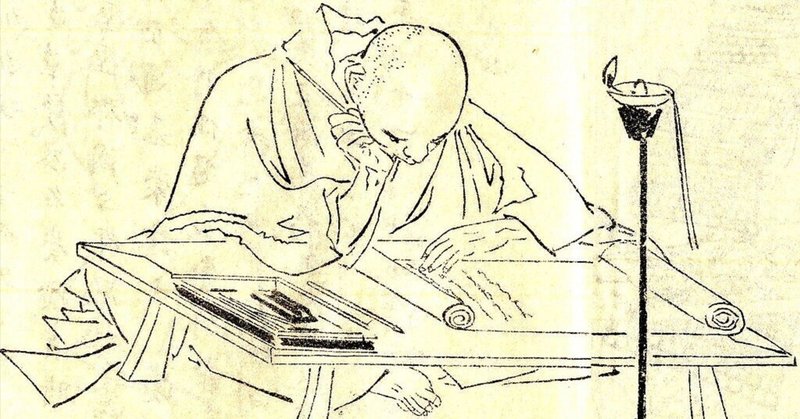
夏休みの読書感想文『徒然草』考 その4
ドナルド・キーン(英語: Donald Keene、1922年6月18日 - 2019年2月24日は、アメリカ合衆国出身の日本文学・日本学者、文芸評論家。コロンビア大学名誉教授。位階は従三位。
日本文化研究の第一人者であり、日本文学の世界的権威とされる。文芸評論家としても多くの著作がある。日本文化の欧米への紹介でも数多くの業績がある。ケンブリッジ大学、東北大学、杏林大学ほかから名誉博士。受賞歴は全米文芸評論家賞受賞ほか多数。2002年文化功労者。2008年文化勲章。著書に『百代の過客』(1984年)、『日本人の美意識』(1990年)、『日本文学の歴史』(全18巻、1976~1997年)など。
キーンさんは偉い。なんといっても「従三位」なんだから。「従三位」という位は律令制下では苗字の下に「朝臣」の姓を名乗ることができて、さらに名前の下に「卿」の敬称が付されたくらいだからね。なんせ兼好だって従五位下に過ぎないんだから。
そもそも「朝臣」って言えば。皇族以外の臣下の中で最も上の地位にあたるんだぜ。
そのキーンさんが『徒然草』と兼好について、こんなことを書いてるんだ。
その時代の雰囲気は、とても内省と評論に適していたとはいえない。当時の日本は、事実上、執権北条氏に支配されていたが、1331年に後醍醐天皇がその打倒を企図した。失敗して、翌年隠岐に流されるものの、1333年には脱出、都にもどって討幕を果たしている。こうした経過とそれに先立つ一連の事件は、知識層に大きな不安を生んだ。
しかし、この動乱の時代に書かれながら、『徒然草』の表面にはほとんど小波すらたっていない。困難な時代を嘆くでもなく、特定の勢力に肩入れするでもない。『徒然草』は時代を超えて意義をもちつづける作品であり、日本人の思索の様式の一つの典型を示している。という見解を示している。

日本文学の世界的権威にいちゃもんをつけて申し訳ないけど、僕は違うと思うんだよ。
「この動乱の時代に書かれながら、『徒然草』の表面にはほとんど小波すらたっていない」
ってっゆーてはるけど、兼好が『徒然草』に巧妙に隠したさざ波を、キーン先生が見落としたとしか考えられないなあ。
兼好はどこかの派閥に与することが危険極まりない動乱の世にあって、「もののあはれ」という体を取って痛烈に体制を批判し、力ある者の堕落を嘆いていると思うんだ。
卜部兼好って、そういう男やと思うのですよ僕は。
たとえば、『徒然草』に登場する人物の中に、ひときわ異彩を放つ日野資朝ていう人がいる。
日野資朝 1290年-1332年
卜部兼好 1283年-1350年
二人はほぼ同世代と言っていいよね。
鎌倉幕府の権勢揺るぎない時代、朝廷は割れていたんだよ。皇位争いに端を発し、大覚寺統と持妙院統に皇統が二分されたのはみんな知ってる思う。
両派は、その場しのぎ幕府の案を受け入れて、皇位を交互に継承することで危うい均衡を保っていたんだ。
そんな中、臣下であるはずの幕府が皇統を決めることに耐えられなくなった後醍醐天皇は、ついに倒幕を決意する。
日野資朝は後醍醐天皇に重用され、大覚寺統として倒幕計画の中心となった人物なんだよ。
けれど内部からの裏切りで、計画はあえなく潰えてしまう。
幕府の追求は苛烈極まりなく、後醍醐天皇にまでも詮議が及ぶかと思われたけど、日野資朝らが罪を一身に被って捕縛されたんだ。(1324年-正中の変)
首謀者として佐渡へ流された日野資朝は、幽閉7年の後、ふたたび起こった討幕計画に関わったとして流刑地佐渡で斬首されるんだ。
歴史に翻弄された悲運の男と言えるよね。
でも「悲運」などという感想は、歴史を俯瞰的に見ることができる現代人の勝手な感傷に過ぎないのかも知れないよ。
日野資朝は自らの義を貫き、そして嬉々として歴史に踊り、満足して散っていったたんじゃないかな。僕はそんな風に考えてます。
兼好が日野資朝を見る時の目は、いつもと少し違う気がするんだ。
「無常」とか「もののあはれ」というフィルターがかかっていない、素の兼好の目で見ていた気がするんだよ。すくなくとも隠遁者の目ではなかったように思う。
兼好も、出自からいえば日野資朝と同じ大覚寺統なんだ。それに兼好自身も若かりし頃は北面の武士として太刀を佩いていた男だからね。
かつて左兵衛佐卜部兼好と呼ばれた兼好の、眩しいものを見るような視線を感じるのだよ。
西大寺静然上人、腰屈まり、眉白く、まことに徳たけたる有様にて、内裏へ参られたりけるを、西園寺内大臣殿、「あな尊の気色や」とて、信仰の気色ありければ、資朝卿、これを見て、「年の寄りたるに候ふ」と申されけり。
後日に、尨犬のあさましく老いさらぼひて、毛剥げたるを曳かせて、「この気色尊く見えて候ふ」とて、内府へ参らせられたりけるとぞ。
(Be訳)
内大臣の西園寺実衡さんは、西大寺の静然上人の腰の曲がり具合や眉の白さを見て、いかにも徳の高そうな方だと感激したようで、
「何という尊いお姿だろう」
と感極まったように呟いたんだよね。
すると、それを聞いていた日野資朝は、
「はあ?年を取っとるだけですがな」
と言い放ったという。
はっきり物を言うんだよ、資朝君は。
後日資朝君は、老衰して毛が抜けた犬を連れて西園寺内大臣のもとに行き、「ほれ。この犬も尊く見えまっしゃろ」と言ったらしいんだ
ここで登場する西園寺実衡てのは資朝君と敵対する「持明院統」の人なんだ。兼好も日野資朝の破天荒さに喝采したんじゃないかな。
それにしても日野資朝君、内大臣など屁とも思っていないかのような愚弄ぶりだ。それほどまでに西園寺実衡は許せぬ存在だったのかも知れないね。
続く【第百五十三段」では資朝の美学のようなものが垣間見れるよ。
為兼大納言入道、召し捕られて、武士どもうち囲みて、六波羅へ率て行きければ、資朝卿、一条わたりにてこれを見て、「あな羨まし。世にあらん思い出、かくこそあらまほしけれ」とぞ言はれける。
(Be訳)
京極為兼大納言が捕まり、武士たちにとり囲まれながら六波羅探題に連れて行かれるところを一条大路で見た日野資朝は、
「いや、実に羨ましい。この世を生きた証として、最後はかくありたいものだ」
と言ったんだ。
京極為兼は政治家として抜きんでていたけど、苛烈な政治手法を政敵から疎んじられ、陥れられて六波羅に捕縛されたんだよ。
これは日野資朝、23歳の頃に起きた事件で、『徒然草』はこの事件から十数年後に執筆されている。その時すでに、日野資朝は佐渡に流されているので、兼好は過去に起きた事件を書いていることになる。
つまり、それほどまでに「日野資朝」の段を『徒然草』に加えたかったということなんじゃないかな。
兼好は資朝の「滅びの美学」のありように惹かれたのかも知れないけど、時世を考えると、結構ヤバいこと書いてるよね。
隠者となった兼好が、日野資朝の生き様に羨望と共感を感じていたと思わせるくだりだね。
従三位キーンの朝臣ドナルド卿は
「この動乱の時代に書かれながら、『徒然草』の表面にはほとんど小波すらたっていない。困難な時代を嘆くでもなく、特定の勢力に肩入れするでもない」
と言ったけど、兼好は日野資朝の死生観に胸をザワつかせ、体制に与する富める権力者を巧妙な筆致で痛罵している。
ことに、
その物に付きて、その物をつひやし損ふ物、数を知らずあり。身に蝨あり。家に鼠あり。国に賊あり。小人に財あり。君子に仁義あり。僧に法あり。
というくだりを読む時、そこに「穏者」や「もののあはれ」という枕詞では決してくくることのできない、体制や現世にスラリと太刀を抜く、本当の兼好を見る思いがするんだよ。
『徒然草』に小波すら立っていないってのは、ちょっと違うような気がするんだけどなあ。
卜部兼好。結構熱い男だぜ。
この段、しまい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
