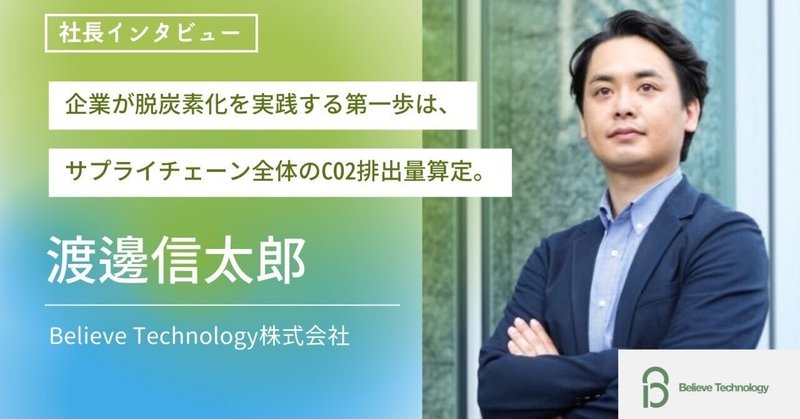
【代表インタビュー】渡邊信太郎が考える「脱炭素時代に企業が取り組むべき第一歩」
世界的に地球温暖化対策の取り組みとして脱炭素へと動き出している現代において、企業は何から始めればいいのか。多くの経営者や社内担当者がそのような疑問を抱えています。
今回は弊社代表の渡邊信太郎が考える「脱炭素時代に企業が取り組むべき第一歩」についてお伝えします。
ー Believe Technologyはどのような会社でしょうか
『脱炭素のハードルを下げて民主化する』というビジョンを掲げている会社です。
地球温暖化の問題に取り組むには、脱炭素化を進めていかなければなりません。しかしまだまだ多くのハードルがあると考えております。
我々はテクノロジーを適切に活用して脱炭素のハードルを下げ、誰もが当たり前に、簡単に、脱炭素に取り組める社会をつくっていきたいと思っております。
ー 企業が脱炭素経営に取り組む必要性やメリットは何でしょうか
企業というのは社会的な責任があるものです。事業活動は地球が正常に保たれてこそのものですが、現在は地球温暖化によってその状況が脅かされています。世界平均気温も産業革命前に比べて1.09度以上、場所によっては2度以上も上昇しています。
地球温暖化は社会全体で取り組むべき大きな課題であり、企業としても脱炭素に取り組む責任があります。
一方で、企業は社会に対して経済的価値も提供しなければなりません。簡単に言えば企業価値を上げ、利益を生み出していく必要があります。実はその点においても、脱炭素には価値が育ちつつあります。
例えば、企業が脱炭素に対して具体的にどういった活動に取り組んでいるかの情報を公開することで、投資家がESG投資の判断に活用をしたり、CO2排出の少ない製品が企業間で選ばれ始めているといった潮流があります。
企業が脱炭素に取り組むことは、様々な面で経済的なメリットを享受することができる時代がきています。
ESG投資とは、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)要素を重視・考慮した投資のこと。
ー 具体的にどのような事業を行っているのでしょうか
弊社が注力している事業は、企業のCO2排出量(スコープ1・2・3)算定支援です。
CO2排出量の計算というのは、脱炭素の第一歩目です。自社のCO2排出量を把握していなければ、削減活動を行ったところでどの程度減ったのかを定量化することができません。最終的に排出ゼロを目指すため、どれだけCO2を減らす必要があるのか、まずは自社の排出量を可視化する必要があります。
排出量の計算は、スコープ1・スコープ2.・スコープ3に分けて計算するのが一般的で、スコープ1・2・3を足し合わせた排出量が自社のサプライチェーン排出量となります。

Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)
引用:環境省/経済産業省
ただしここで問題は、スコープ1・2・3排出量をどういう算定方法で計算すればいいのか、企業の中でデータがないときにどのように算定すればいいかなど、計算のハードルが非常に高いという点です。特にスコープ3は難しいと言われていて、15個のカテゴリに分かれ、企業が自力で算定するには専門的な知識と算定工数が必要になってしまいます。
そこで我々のような専門家が入ってコンサルティングとしてご支援させていただくという事業となっています。
ー 企業の脱炭素を支援するサービスは複数あると思いますが、どういった違いがあるのでしょうか?
企業が排出量の算定をしようとするとき、3つの選択肢があります。
1つは自力で計算することです。
ただし知識が乏しい状態で算定をすると算定に漏れが出たり、誤った数値を算出してしまう可能性があります。
2つ目は弊社のようなコンサルティング会社に依頼することです。
弊社のようなコンサルティングサービスの強みとして、CO2排出量算定の柔軟性を重視している点があります。たとえば、お客様によっては「データを丸ごと渡すので計算してほしい」というケースもあれば、「一部自分達の手を動かしながら必要に応じたアドバイスがほしい」というケースもあります。
お客様がCO2排出量算定に対してどのような携わり方を希望されているのかをまずヒアリングし、お客様に合わせたご支援をすることが弊社の強みです。
特にスコープ3に言えることですが、CO2排出量の算出をするには、企業の総務の方やサスティナビリティ担当者の方が様々な部署からデータを集めなければなりません。調達部、経理部、物流部など多岐に渡ります。実作業を行うとなると各部署の方々にも協力をお願いしなければなりません。
その場合、弊社では社内向けのセミナーを実施していて、企業の各部署の方々にどのようなデータが必要なのか、そもそもなぜこの取り組みをしているのかといった等の話をすることで算定が円滑に進むよう支援しています。
また弊社では、スコープ1・2・3に特化して様々な業種・業態の算定支援を行っている実績がありますので、算定スキルの高さも自信を持ってお伝えできる部分です。
3つ目が排出量の計算をクラウドで計算するソフトウェアを利用することです。
企業の脱炭素を支援する企業様には、CO2排出量算定ソフトウェアを提供されるところもあります。ソフトウェアは必要なデータが揃っており、算定の知識があれば、誰でも便利に使いやすいため、「データがすべて集まっている」「算定方法が理解できている」といったケースではソフトウェアの活用がおすすめです。
ただしそもそも「算定方法がわからない」「どんなデータを集めればいいのかわからない」「いろんな部署からデータをどのように集めればいいのかわからない」「データがそもそもない」というお客様の場合は、我々のようなコンサルティングを活用していただくことで最適な支援ができます。
ー 実際にBelieve Technologyに脱炭素化のコンサルティングを依頼した場合、どのような流れになるのでしょうか?
基本的にオンラインでミーティングを実施させていただき、ご支援をさせていただきます。たとえばスコープ1・2のみの算定であれば、週1回あるいは2週に1回のミーティングを1ヶ月〜2ヶ月に渡り実施します。スコープ3まで含めた算定になると4ヶ月〜6ヶ月程度の期間をかけて支援いたします。
内容としては、スコープ1・2・3においてどういう活動量に対応すべきかということをリストアップすることから始まります。
スコープ1・2・3という考え方はGHGプロトコルという国際的な規格をもとにしたもので、GHGプロトコルが公式に出している算定のガイダンスマニュアルと、それをもとに国内の環境省/経済産業省が作成したガイドラインがあり、その2つで若干算定の範囲や使う係数が異なるケースがあります。
お客様の算定目的に応じてどの算定方法を選ぶべきかもアドバイスさせていただき、排出量の算定までご支援するという流れになります。
ー これまでに導入された企業からはどのような声がありましたか?
現在スコープ1・2・3排出量の算定に取り組む企業様からは、総じて「伴走してもらいながら算出に取り組めている」「算定作業を自社で行うよりも大きく作業を減らすことができた」といった声をいただいております。
また「CDP質問書に対する回答に利用できた」「TCFDの指標と目標に活用できた」という企業様もいます。
CDPとは、イギリスで設立された国際的な環境非営利団体(NGO)。CDPの署名機関投資家を代表して世界各国の企業や団体、自治体に質問書を送り、二酸化炭素排出量や気候変動への取り組みに関する情報開示を求める。CDPがつけるスコアは、投資家が企業に投資する基準の一つとして重視される。
TCFDとは、企業の気候変動への取り組みを具体的に開示することを推奨する国際的な組織。Task force on Climate-related Financial Disclosuresの略で、日本では「気候関連財務情報開示タスクフォース」と呼ばれる。近年は社会的意義や持続性の高い企業が評価されるようになり、財務諸表だけでは見えない企業の情報をTCFD提言で開示する重要性が高まっている。
弊社にご依頼いただければ、CO2排出量算定からCDP回答・TCFD対応の支援までワンストップで提供可能です。
利用企業様の声は弊社の公式サイトに詳しく掲載しているので、ぜひご覧ください。
ー最後に脱炭素化に興味を持っている企業様に伝えたいことはありますでしょうか
脱炭素を進める上では、まずは自社がどれだけCO2を排出しているかを把握しなければ、先に進むことができません。
弊社では様々なニーズに合わせたCO2排出量計算のご支援が可能です。脱炭素経営を始めたい企業様は、ぜひ弊社にご連絡をください。
Believe Technology株式会社
脱炭素のハードルとなっている部分を取り除き、誰もが簡単に、当たり前に取り組めるようにしていく『脱炭素の民主化』をビジョンに掲げ、プライム上場企業〜中小企業まで業種問わず幅広くスコープ1, 2, 3排出量算定代行、伴走の支援を実施。述べ200社以上を対象に、排出量算定に関するセミナーを開催。
〜スコープ1・2・3コンサルに関する見積もり依頼・ご相談は〜
HP:https://www.believe-technology.com/
メールアドレス:info@believe-technology.com
