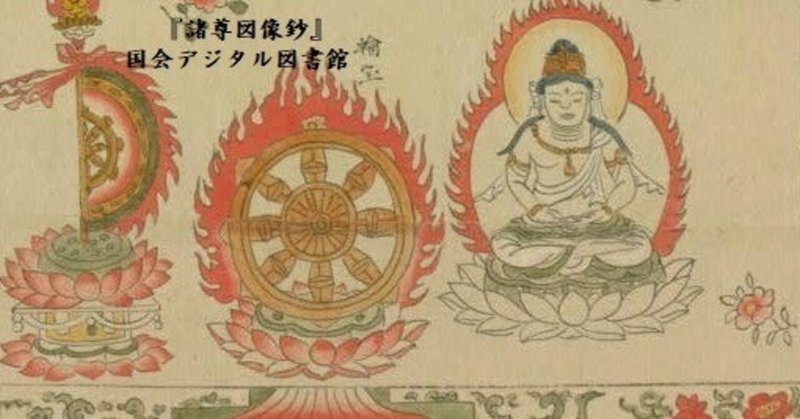
『法句経』(『ダンマパダ』)覚え書き②
法句166
以前の記事で『法句経』(『ダンマパダ』)の178番の詩偈を取り上げたが、今回は166番の句を取り上げてみたい。166番の文句は日常において指針となる言葉である。
まずは私がよく拝読する2冊の典籍の訳を引用する。
先ずは仏教学者にして浄土宗僧侶である荻原雲来博士の訳は、
他を利することは如何に重大なりとも、己を益することを廃(や)むべからず、己の本分を識りて恒に本分に専念なれ。
続いて仏教学者で曹洞宗僧侶の片山一良博士の訳は、
他者のために大事でも 自己の目的を失うなかれ
自己の目的をよく知って 自身の目的に専念すべし
大乗仏教では利他行を前面に押し出すが、ここでの釈尊は何はともあれ自己のやるべきことや本分にこそ専念すべきことを強調されておられる。もちろん他者のことはどうでもよいというような独善的な考え方ではなく、先ずは各自に与えられた役割や領分を全うせよとのこと、また他者の役割や領域にまで手を出して中途半端なことをすべきではないということであろう。
『正法眼蔵随聞記』に説かれる源頼朝公の態度
道元上人の法話録『正法眼蔵随聞記』には、源頼朝公が当に自己の本分に忠実なる態度を取った言行が記されており、我々に深い示唆を与えてくださっている。
また、お話の中で、こんなことをいわれた。
亡くなった鎌倉の右大将、源頼朝公が、兵衛佐(近衛武官次席)であったとき、ある日、綺麗びやかな晴れの儀式の宴があって、内大臣の側近に出仕していた。そのとき、ひとりの狼藉者があった。
そのとき大納言には、「あの者を取り抑えよ」とお言葉があった。
頼朝公は「六波羅にお命じ下さい。六波羅の清盛公は、平家の総指揮官であります」と答えた。
大納言は「しかし手近かに、お前という者がいるではないか」といったが、頼朝公は、「私は武人ではありますが、平家の侍を取りしまる立場の者ではありませぬ」といった。
この頼朝公の言葉は、立派である。このような心がけであったから、後に天下の支配者ともなったのである。いま仏道を学ぶ者も、このような心がけがなくてはならぬ。その立場になかったら、ひとを叱り取りしまるようなことをしてはならないのだ。
上記の逸話は我々の日常生活を営む上でも指針となるものである。
時折ニュースなどである人が公共の場において善意や正義感から他者の規則違反や迷惑行為を注意をした結果、逆上されて大怪我などしたなどということを見聞きするが、このような場合は頼朝公の行動を見習うべきではないかと思う次第である。善意や正義感を持っており、それを行動に移すことはことは大変素晴らしく立派であることは確かであるが、やはり各自の本分や領分を弁え、然るべき役目の人に伝え、その人物から取り締まってもらうようにすることが最善の方法であると考えられる。そうすれば自己防衛にもなり、遺恨を残さずにその後は自分の本分も勤めることができる。
釈尊は人類の教師 祖師は良き指導者
ブッダは「両足尊」とも称され、衆生の中で最も尊い存在であり教師であるのだから、仏教徒は世間で云われているような処世訓や人生訓に惑わされることなく、釈尊が説かれる法を頼りにする。釈尊は深遠な教えを説かれる一方で解りやすい処世訓も説かれるから、釈尊の処世訓こそを至心とする。
また仏教に身と心を奉げて生き抜かれた祖師方を良き指導者として敬い、遺してくださった教えを主軸として生活する。少なくとも仏教徒にとってはそれが価値あることであると私は考える。仏教徒は仏教を立脚地として生きることに尽きる。
荻原雲来博士いわく、
法句の内容は各章の題号にて察せらるるが如く、仏教の立脚地より日常道徳の基準を教へたるもの
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
